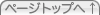意識変革の劇、Macbeth
—Gun Powder Plotをめぐって—
米田 拓男
Introduction
Macbethが執筆されたと考えられるのが1606年。今から遡ることちょうど400年前、ロンドンは、Gunpowder Plotの話題で持ち切りだった。そしてShakespeareは、事件を巡る一連の騒動を横目に見ながら、Macbethを執筆していた。
ある作品はそれが書かれた時代と無縁ではいられない。Macbethも例外ではない。Macbethという作品はどのような社会背景の下で書かれたのか、それを知ることで見えなかったものが見えてくるに違いない。本論では、Gunpowder PlotとShakespeareのMacbeth執筆の関係について探ってみる。
1. Gunpowder Plot
Gunpowder Plotは、1605年11月5日に起こった、カトリック教徒たちが弾圧を恐れて起こした、国会議事堂爆破未遂事件である。その時期は、ShakespeareがMacbethの構想を固めていた時期と、恐らく重なる。
この事件とMacbethの執筆ではどちらが早いか、様々な議論があるが、私見では、様々なテキストの内的要因から、Shakespeareは Macbethを、事件が最終的な決着を見たあとで完成したと思われる。例えば、Macbethの中には’equivocator’という言葉が何度か使われている。この言葉は、国会議事堂を爆破する陰謀のことを告白によって首謀者たちから知らされていながら、告白の内容を外に漏らすことは牧師という立場上許されないため、秘密にしておいたことを罪に問われたGarnet神父が、裁判の際に使った言葉だった。
「二枚舌」というテーマは、作品を構成する重要な要素のひとつである。PopeとColeridgeは、’equivocator’という言葉が現れる The Porter Sceneは後から書き加えられたのだと主張しているが、それは考えられないように思う。魔女が語る、劇冒頭の’foul and fair’というフレーズも、魔女がMacbethに「二枚舌」を使って騙すのも、’equivocation’というテーマと繋がる。このような作品の根幹に関わるテーマを後から付け足したとは考えづらい。Garnet神父の裁判が行われたのは1606年3月28日なので、初演はそれより確実に後だと思われる。事件の首謀者たちの中には、Shakespeareと同じWarwickshire出身の者もいたようだ。Shakespeareはことのほか、この事件に関心を寄せていたのではあるまいか。
個人的な印象からも、Macbethという劇は事件と繋がっているように思える。私がMacbethという芝居に抱く印象は、闇のイメージである。そのような印象は、次のような場面からもたらされる。Macbethは、Duncan殺害の前に、闇の中に短剣が浮かんでいるのを見る。Duncanは、闇の中で寝込みを襲われ殺害される。Banquoは暗い森の中で暗殺される。その時、ランタンが落ち、あたりが暗闇に包まれる。Macbeth夫人は夜の城内をさまよい歩く。そしてMacbethの独白には蝋燭が出てくる。
Out, out, brief candle,
Life’s but a walking shadow, (5.5.22-3)
消えろ、消えろ、束の間の灯火、
人生はたかが歩く影に過ぎない
深い闇を感じさせる独白である。
Macbethという劇の印象は、このような暗闇に包まれた、地下牢のようなものである。その暗闇は、Guy Fawkesたちが火薬をしかけた地下室の闇に通じるように思える。それは、Fawkesたちの闇の中の作業に通じる。独白に出てくる蝋燭は、火薬のイメージと結びつく。暗い想像力が働かされ、地下室で陰謀が企まれる。そのような暗い地下の思考から生み出されたと思えるような殺戮が、Macbethの舞台上でも展開される。
Fawkesたちの為したことは、明らかなテロ行為である。彼らはカトリック教徒の解放を求めてこのような手段に出たが、その思惑は裏目に出た。この事件以降、カトリックへの弾圧はいっそう激しいものとなったのだ。アメリカ社会で、9.11がイスラム教徒に対する差別意識を強めたように、当時のロンドンでも、カトリックに対する迫害がいっそう加速されたのは想像に難くない。この陰謀事件は、カトリックへの迫害を強めるために、プロテスタントの側が仕組んだのではないかと、陰謀説を主張する歴史家もいるくらいだ。
いずれにせよ、彼らの思惑は達成されず、Fawkesたちは逮捕され、処刑が決行されることになった。その処刑は凄惨を極めるものだった。事件の首謀者たちは、首をくくられ、内蔵を引き出され、馬で四裂きにされ、その首はロンドン・ブリッジにさらされた。
このような事件が起こり、それがこのような結末を迎えたことは、同時代の人々に強い衝撃をもたらしたはずだ。町に陰鬱な空気が漂ったのは間違いないだろう。Shakespeareは、血なまぐさい社会を背景に、血なまぐさい出来事を描いた。陰鬱な劇は、当時の陰鬱な社会状況の反映なのだ。
Shakespeareが事件に触発されて劇を書いているのは間違いないように思える。事件の詳細を知ると、劇中のいくつかの場面の印象がより鮮烈なものとなる。Henry N. PaulはThe Royal Play of Macbethの中で、Gunpowder Plotの主犯者たちの一人の青年について述べている。Paulは、1606年1月30日に処刑された一人の青年と、一幕で語られるCawdorの領主に関連があるという。
その青年、Everard Digbyは、清廉潔白な人物だった。James Iは地方を回っていた時に、この人物に出会った。そしてJamesは彼を高く評価し、騎士の称号を与えた。Digbyはそのような人物であったにも拘らず、事件の首謀者たちと接し、彼らに協力することを約束してしまう。Macbethの一幕四場に次のような台詞がある。Duncanは、Cawdorの領主に処刑の処分を下す。そして彼の死に様がそれに続く場面で語られる。
But I have spoke
With one that saw him die, who did report
That very frankly he confessed his treasons,
Implored your highness’ pardon, and set forth
A deep repentance. Nothing in his life
Became him like the leaving it. He died
As one that had been studied in his death,
To throw away the dearest thing he owed
As ’twere a careless trifle. (1.4.3-11)
しかし、
処刑を見た者には会いました。その話によれば、
彼は率直に反逆を認めて
陛下のお赦しを請い、
深い改悛の情を示したそうです。彼の生涯を通じ
その去り際ほど見事なものはなく、かねてから
死に方の稽古をしていた者のように
最も大切な物を
反古同然とばかり潔く投げ捨てたそうです。
Cawdorの領主は立派な最期を遂げる。Paulは、彼の死に際しての態度は、Digbyのものと重なるという。DigbyはCawdorの領主のように、自らの罪を悔い、祈り、死んでいった。PoulはShakespeareが彼の処刑を見た可能性を示唆する。このCawdorの領主のくだりは、モデルになった人物がいたことを想像すると、より生々しいものとして目に浮かんでくる。
事件と共鳴しているように感じられる箇所は他にもある。戦場から戻ってきたMacbethは、次のように言う。
So foul and fair a day I have not seen. (1.3.36)
ひどいのか良いのか、こんな日は初めてだ。
この台詞は何を意味しているのだろうか。何を指しているのか意味を取りにくい台詞である。’fair’は戦場における勝利であるだろうが、’foul’は戦場の残酷さを指しているのか、あるいは、天候を指しているのか、劇の中では意味が通りにくい。だが、これは、火薬陰謀事件が発覚した日を形容するのにまさに相応しいような言葉だ。つまり、あまりにおぞましい事件だったが、実現しなくて本当に幸運だった、と。
私がこの事件から連想してしまうのは、オウム真理教による地下鉄サリン事件からしばらく経って起きた、新宿で青酸カリの時限装置が発見された事件だ。事件そのものは未然に終わったが、あの出来事は人々を不安に陥れた。あれが成功していたらどうなっていただろうか。Shakespeareが私たちの同時代人だったら想像したに違いない。Shakespeareは、Macbethでまさにそれをやっているのだ。
Macbethは’nothing is, But what is not’「あるものはないものだけ」と言う(1.3.140-1)。実際には「何も」起こらなかった爆破事件。それは、Shakespeareの想像力を刺激し、彼に劇を書かせた。Fawkesたちがしかけた火薬は、実際には爆発しなかったが、Shakespeareの想像力の中では爆発したのだ。 Macbethは、実際には起こらなかった恐ろしい事件を、Shakespeareが想像力を使って具現化した劇なのである。
2. 犯行のシミュレーション
現実の地下室では不発に終わった火薬は、しかし、Shakespeareの想像力の中で爆発した。そして同時代の人々も、それが爆発していたらどのような恐ろしいことになったか想像せずにはいられなかったに違いない。実際には爆発しなかったが、それはShakespeareの、そして、ロンドンの人々の想像力の中では確実に爆発したのだ。現実世界では何も起こらなかったが、陰謀の発覚は社会に大きな不安をもたらした。事件は、人々の想像力の中に、何かを確実に胚胎させたのだ。
Macbethは次のように言う。
Present fears
Are less than horrible imaginings. (1.3.136-7)
現実に恐ろしいものを見るよりも
想像するほうがずっと恐ろしい。
想像力豊かなMacbethは、実際の恐怖よりもそれを想像する方が恐ろしいと言う。Shakespeareは正にその恐ろしいことをして、劇を書いている。爆発していたらどのようになったか、皆想像したと思う。実際に爆発してしまうよりも、それを想像する方が恐ろしい。Gunpowder Plotは、人々の想像力に訴えかける事件だったのだ。
事件で使用された火薬の量は、いったいどのくらいの威力のものだったのか。実際にそれが爆発していたら、どの程度の被害がもたらされたのだろうか。案外、本当に爆発していたら、それほど大きな被害がもたらされなかったかもしれない。地下室がひとつ吹き飛ぶだけで、事なきを得たかもしれない。爆発していた方が、実行犯たちの刑が軽くなっていた可能性だってあるかもしれない。政府がそこまで犯人探しに血眼になることもなかったかも知れない。人々が感じた恐怖が、彼らに残酷な処刑をもたらした。彼らは、市民の想像力が描き出した爆発の罪さえも背負わされてしまったのかもしれない。そして市民は、彼らが一般の人間とは根本的に異なる、悪魔的な人物たちだったのだと考え、処刑して胸を撫で下ろした。
しかし、ここで、市井の人々の想像力とShakespeareの想像力の間には、当然ながら、大きな開きがあった。Shakespeareは、決して Macbethを悪魔的な人物として描いていない。Macbethは悪党であるが、自分の悪事におののきながら悪を行う、Barbara Everettが言うところの、一種の’villain-hero’なのである(Everett 85)。
MacbethはDuncanを殺す前に、その行為の恐ろしさに恐れをなし、気持ちがくじけそうになる。
My thought, whose murder yet is but fantastical,
Shakes so my single state of man that function
Is smothered in surmise, (1.3.138-40)
心に浮かぶ殺人は、まだ空想に過ぎないのに
俺の五体を揺さぶり、
思っただけで体が利かなくなる。
Macbethはこれほど自分の行為に恐れを抱いている。そして悪事を重ねたあとになっても、その行為におののいている。
O, full of scorpions is my mind, dear wife! (3.2.36)
ああ、お前、俺の心はサソリでいっぱいだ!
Macbethは罪悪感に責めさいなまれている。そして彼は心の平安を求める。
To be thus is nothing,
But to be safely thus. (3.1.49-50)
こうしていても何にもならない、
心安らかにこうしているのでなければ。
Macbethは悪を自覚しているのだ。それはShakespeare作品の他の悪党とは大きく異なる点だ。Richard IIIのGlocesterは悪を自覚しているが、それを行うことに快感も覚えている。Macbethは快感を覚えていない。彼は自分の行為を恐れている。自分の行為を見たくないと言う。彼はDuncanの血に濡れた手を見て’they pluck out mine eyes’「この両手が俺の目玉をえぐり出す」と言う(2.2.62)。Macbethは苦しみながら悪を行うのだ。Macbethの残虐な行為を想像しながら執筆しているShakespeare自身、快感を感じていないだろう。この劇で描かれる犯罪は痛みを伴っており、重々しい。Duncanを殺す場面に悪を為す爽快感は微塵も無い。それは、IagoやEdmundとも全く異なる点である。
Macbethは自分がなそうとする行為を何度も想像してしまう。そして自らが為そうとしている行為に恐れを抱く。Harold Bloomは、Macbethは’a tragedy of the imagination’「想像力の悲劇」であると言っている(Bloom 517)。A. C. Bradleyも次のように言う。
Macbethのよい面は・・・道徳の理念や命令や禁止という率直な言
葉で 自らを語るというよりも、動揺や衝撃を与える映像の中に具体
化されている。ゆえに想像力が彼の最高の持ち味なのである。
この想像力は、Shakespeareの想像力にそのまま重なる。
Shakespeareは、MacbethによるDuncan殺害を、恐ろしいものとして描いている。Macbeth自身、その行為に恐ろしさを感じているが、それは執筆しているShakespeare自身が感じている恐怖心と同等のものだ。Macbethが、自分が為すことに恐れを抱きながら実行に移して行く過程は、Shakespeare自身が恐れを抱きながら、悪事を舞台上に描いていくそれと同等なのだ。つまり、Shakespeareは Macbethに感情移入しながら劇を執筆しているのだ。
Shakespeareは火薬陰謀事件を恐ろしいと思ったが、彼の想像力は自分がそのような犯罪を犯すことを想像せずにはいられなかった。事件の実行犯の中にShakespeareと同郷の者がいたことは、犯人の立場を想像する際の一助となったかもしれない。Paulは、次のように書く。
Clopton House, which was a rendezvous of the plotters, was
near Shakespeare’s land, and he had known several of these men
since childhood. (Paul 226)
Shakespeareが犯人たちの何人かを子供の頃から知っていたというのは、本当だろうか。それが真実であったのだとすれば、それは、Shakespeareが犯人たちに感情移入する大きな余地を与えたと言えるだろう。
Shakespeare自身はカトリックだったのか、プロテスタントだったのか。どちらであったとも、立場を表明していない。しかし、 Shakespeareの身近にカトリックがいた可能性はある。Shakespeareの父、John Shakespeareは、国教忌避者のリストに名前を連ねたことがある。さらには、彼はカトリックの信仰遺言書を残してもいる。それは18世紀に発見されて失われてしまったので、その真贋は今となっては判断するのは難しいが、Shakespeareの父がカトリックであった可能性はある。さらには Shakespeareの娘、Susannaも、Holy Trinity Churchの「不信心者」のリストに名前が載せられたことがある。Shakespeareの身内にカトリックがいた可能性があるのだ。
Shakespeareは反逆者Macbethを、ごく普通の道徳観を持つ、臆病な男として描いた。その男が魔女にたぶらかされる。Macbethの行いは残虐なものだが、観客はMacbethに感情移入せずにはいられない。そのように書かれている。Shakespeareが感情移入しながら、劇を書いている。Shakespeare自身、犯人たちがどのような心境で犯行に臨んだのか、作品の中でシミュレートしてみたかったのではないか。
次のMacbethの台詞からは、いかにもShakespeareらしい発想が垣間見られる。
To know my deed, ’twere best not know my self. (2.2.77)
やったことを思い出すくらいなら、自分を忘れている方がいい。
恐ろしい行為を行うには、別の人格が必要なのだ。Macbethは他人になりたいと願う。役者でもあったShakespeareらしい発想である。そして Shakespeare自身、劇を書いている時にはMacbethになりきっている。犯罪者になりきって台詞を書いている。自分自身では恐ろしくてできないようなことを別の人格を借りて、劇の中でやっているのである。
観客は、Macbethが悪事を働くに至る心情の変化を注意深く見守る。そして観ているうちに、Macbethの思考に巻き込まれていく。観客も Macbethとなって犯罪者の意識を体験する。恐ろしいと感じた事件を、主犯の側から想像する。Shakespeareによる反逆者の心境のシミュレーションを、追体験することになるのだ。
3. 御前公演
だが、このようにMacbethに共感を抱いてしまうような書き方をすることはある種の危険を伴う。何故なら、観客の中には、James Iがいたからである。そのような書き方をしては、Jamesを陥れようとした犯罪者を擁護することになりかねない。Macbethは御前公演として上演された可能性が高い。そのため、James Iが観客として想定されていた可能性がある。
Macbethの作中には、James Iへの胡麻すりと受け取られかねないような箇所が散見される。四幕一場では、Macbethが魔女たちと再会し、彼の前を八人の王の幻影が横切る。その際、八人目の王が鏡を掲げているが(F1のト書きではBanquoが鏡を持っていることになっているが、Macbethの台詞との間に矛盾が生じてしまうので、八人目の王に書き換えられるのが通例)、その鏡には、御前公演の際には、観劇しているJames Iの姿が映し出されたはずである。もう一つが四幕三場、Malcolmがイギリス王の奇跡を語る場面である。Malcolmは、王がその奇跡の力を子孫に伝えると聞いたと言う。
and ’tis spoken
To the succeeding royalty he leaves
The healing benediction. (4.3.156-8)
そして聞くところによると、
王はこの有難い治癒力をご子孫に
伝授なさるそうだ。
このイギリス王がどういった血筋の者なのか分からないが、Banquoの子孫として先の八人の王の幻影に名を連ねるJamesの血筋を、さらに讃えんとする意図が垣間見える。その血縁の誉れ高さを二重に持ち上げようとしているように感じられる。他にもMalcolmが軍勢を貸し出してくれるイギリス王を ‘Gracious England’と呼んで、ほめ讃える箇所がある。
Shakespeareは、さらに、材源の設定にも操作を加えている。Holinshedの『年代記』では、Macbethにも正当な王位継承権があり、見方によれば、Duncanこそ王位簒奪者ととれる。また、James Iの先祖であるBanquoも、王位への野心を持っていて、MacbethのDuncan殺しに加担したことになっている。Shakespeareはそれらの箇所を劇化にあたって割愛した。
これらの要素は、James Iのためのご機嫌取りと勘ぐられかねない。犯罪を悪人の側から描いた作品だから、慎重さを要したのだろうか。しかし、私には、ただひとりJamesが見ることを想定して、このような台詞を書いたのではないのではないかと思う。
私は当時のロンドンを、9.11以降のアメリカと重ねて想像してしまう。アメリカでは9.11以降、国民の間に国粋主義的な言動が目立つようになり、ブッシュの支持率が大きく上がった。Gunpowder Plot以降のロンドンでも同様のことが起こっていたのではないか。国教徒たちが、James Iのもとに結束を固めようとしていたのではないか。Macbethにこのような台詞が現れるのは、それが時代の空気を反映しているからなのではなかいか。観客もこのような台詞を喜んだからなのではないか。
当然、Macbethでは、最終的に悪は罰せられねばならない。Macbethは最期、Macduffに破れ、無惨な死を迎えることになる。ここではタンバレイン大王のように、悪を為して尚、生きながらえることは許されない。もしMacbethが死ななかったらどうなるか。Shakespeareはただでは済まなかっただろう。James Iの寵愛を失うことになったかもしれない。いや、それだけではなく、客席から石が飛んでくることにもなりかねなかった。9.11の事件を受けたヒステリックなアメリカ市民は、少しでもイスラムを擁護するようなことを発言したら、少しでもブッシュ政権に非があることを言おうものなら、その者に対して激しい非難を浴びせかけた。Macbethにこのような国威の高揚に繋がるような台詞が含まれているのは、Jamesの顔色を伺っているだけではなく、検閲を恐れていただけでもなく、社会的要請だったのではないか。
4. 観客との乖離
Macbethという劇は、後半に向かうに従って、だんだんと観客とMacbethの間に距離が出来て行く。Macbethは劇の中で殺戮を繰り返して行く。Duncanを殺した後は、Banquoを、そして次にはMacduffの夫人と息子を殺す。Shakespeare劇において、子殺しは重大な罪だ。それを犯した者は死を覚悟しなくてはならない。ここまで来ると、観客は、観客が生きるモラルの世界から、完全に別の次元へと連れて行かれる。罪の意識に責めさいなまれる以前のMacbethはもういない。彼は自分の恐怖の感覚が麻痺してきたと独白で語る。
I have almost forgot the taste of fears;
The time has been, my senses would have cooled
To hear a night-shriek and my fell of hair
Would at a dismal treatise rouse and stir
As life were in’t. I have supped full with horrors;
Direness familiar to my slaughterous thoughts
Cannot once start me. (5.5.9-15)
恐怖がどんな味なのか、ほとんど忘れてしまった。
かつては、闇を切り裂く悲鳴に
五感が凍り付き、凄まじい話には
髪の毛が根元から逆立って、生き物のように
うごめいたものだ。だが恐怖をしたたか舐めた今、
どんな恐ろしいことも人殺しの俺の胸には昔馴染みだ、
もうぎくりともしない。
Macduffが自分の妻と子供が殺されたことを告げられる四幕三場では、MalcolmとMacduffが、そしてMacduffに妻子の死を知らせに来たRossが加わって、Macbethに対する批判を繰り広げる。ここで観客は、それまで感情移入して付き合って来たMacbethを第三者の視点で眺めることになる。子供を殺してしまったMacbethに対して、観客はもはや以前ほど親近感を抱けなくなっている。
そしてMalcolmたちは、ここでMacbethに対して兵を挙げることを話し合う。Macbethに対して攻撃をしかける側から話が展開していく。 Macbethが何かに対してアクションをしかけるのではなく、しかけられる側に回る。能動から受動へと劇の中での立場が変わる。Macbethを攻める側に、観客の心情の重心が移行し始める。
そして彼らの奇襲は成功し、最後、Macbethは戦場で倒れる。しかし、その死は舞台上では描かれない。四大悲劇では、Hamlet、 Othello、Learの死は舞台上で描かれるが、Macbethの死は異なる。「女の腹から生まれた」Macduffに戦いを挑む決心を固めた Macbethは、二人で切り結び合いながら舞台から退場し、次の場面では、切り落とされた首として舞台に現れる(注1)。そしてその姿は事件首謀者たちの末路とも重なる。Macbethは逆臣の徒として、相応しい最期を遂げたのである。
ここに来てJames Iはほっと胸を撫で下ろしただろうか。スコットランドに失われていた秩序が回復して、劇は幕を閉じる。観客たちもその終わり方に納得するだろう。劇としては安定した終わり方だ。誰からも文句は出ないだろう。
Shakespeare作品には、問題を残しながら終わる劇は多いが(注2)、Macbethは何も問題を残さない。あまりに残らなさ過ぎるほどだ。誰の目にも明らかな逆臣の徒Macbethが打ち倒され、Malcolmが王位を継承して、全ての問題が解決して、劇は幕を閉じる。あまりにも完全な完結性。
Macbethが死んだ後は、何ももったいぶることなく、劇はあっさりと終わる。Shakespeareの中で、そして観客の中で、James Iの中で、この終わり方はあまりに当然のものだった。事件首謀者たちの末路がそうであったように、Macbethはここでこのような末路を辿らねばならなかったのであり、それは誰にとっても自明のものだったのだ。こうして事件へのルサンチマンを解消した観客は、気持ちよく劇場を後にすることができる訳だ。
5. Is the Time Free?
しかし、私は、Macduffが言う”The time is free”「世界は解放された」という言葉に違和感を覚える。
Hail, king, for so thou art. Behold where stands
Th’usurper’s cursed head. The time is free. (5.9.21-2)
国王万歳、もう、そうご挨拶できるのです。ご覧ください、
王位簒奪者の呪われた首です。世界は解放されました。
その劇の完結性にも拘らず、この台詞に感じる居心地の悪さは何だろうか。
観る者がこの台詞に違和感を感じるとすれば、それは、観客がMacbethに感情移入してきていることによる。Macbethの性格には残虐なことをしてもなお、感情移入を許すような余地がある。それはMacbeth自身が、自分が生きていては許されないことを理解しているからである。本人も死を避けられないと思っている。殺戮を繰り返し、戻ることのできない地点に到達してしまったMacbeth自身、それを自覚していて、川の比喩を使って心情を述べている。
I am in blood
Stepped in so far that should I wade no more,
Returning were as tedious as go o’er. (3.4.136-8)
血の川に
ここまで踏み込んだからには、たとえ渡りきれなくても
戻るのも億劫だ、先へいくしかない。
そして、愛情も友人も持てず、老いていく悲しさを語っている。
My way of life
Is fall’n into the sere, the yellow leaf,
And that which should accompany old age,
As honour, love, obedience, troops of friends,
I must not look to have; (5.3.22-6)
俺の人生は
黄ばんだ枯れ葉となって、散るのを待っている。
それなのに、老いの日々の伴侶、
例えば栄誉、愛、従順、それに多くの友など
何ひとつ持てる見込みはない。
ここまで来ると、Macbethはもう生きていても楽しくない。死だけが安らぎである。だから観客は最後、Macbethが、「女の腹から生まれた」Macduffに、自分が負けることを予感しながら挑んで行く気持ちをよく理解することができる。
Macbethに対峙したMacduffは言う。
Then yield thee coward,
And live to be the show and gaze o’the’time.
We’ll have thee, as our rarer monsters are,
Painted upon a pole and underwrit,
‘Here may you see the tyrant.’ (5.8.23-7)
それなら降参しろ、卑怯者、
生きながらえて世間のさらしものになれ。
世にも珍しい怪物なみに見世物にして、
柱に絵を描き、こう書いてやる、
「さあ、お立ち会い、暴君だよ」
ここでMacduffが言っていることは、Gunpowder Plotの実行犯たちが最後に受けた屈辱と同じものをMacbethに舐めさせるということである。実行犯たちの運命について、Paulは次のように書く。
Some were killed, and some were taken alive and sent up to London. The King’s Book (M2), explained that people wished to see them “as the rarest sort of monsters; fools to laugh at them; women and children to wonder, all the common people to gaze ” (Paul 230)
Macbethは、Gunpowder Plotの実行犯たちと同じ屈辱を味わいたくなかったのだ。そして勇敢な戦士として、勝ち目の無さそうな相手に立ち向かっていく。
Conclusion
Macbethを1606年に書くとはどのような行為だったのか。当時のロンドンは、Gunpowder Plotの話題で持ち切りだった。1606年1月30日には、本論でも触れたEverard Digbyら、事件の犯人たちの処刑が決行された。それからちょうど四百年。その時にレポートで彼らのことを取り上げているのもなんだか不思議な気がする。
ある作品は、それが生み出された時代と切り離すことはできない。その作品は、その時代に生み落とされたからこそ、価値があるのだ。作品が書かれた背景を知ると、作品の面白さが増す経験を味わうことができる。今回もそれは例外ではなかった。
Chapter 1 では事件の概要と、作品の成立時期について論じた。様々な内的要因から、テキストは事件が決着を見たあとで成立したと論じた。Macbethは、実際には起こらなかった恐ろしい事件を、Shakespeareが想像力を使って具現化した劇なのだと論じた。
Chapter 2 では、Shakespeareが描き出したMacbethの性格について論じた。Shakespeareは反逆者Macbethを、ごく普通の道徳観を持つ、臆病な男として描いた。Shakespeareはカトリックに親近感を抱いていた可能性があり、Macbethという作品は、Gunpowder Plotの主犯者たちがどのような心境で犯行に臨んだのかについての一種のシミュレーションだったのかも知れない。
Chapter 3 では、作中にJames Iへの胡麻すりと受け取られかねないような箇所が散見されることを指摘し、Gunpowder Plot以降のロンドンでも9.11以降のアメリカと同様のことが起こっていた可能性を指摘した。つまり、ロンドン市民の間に国粋主義的な言動が目立つようになり、James I を持ち上げているような台詞は、そのような時代の空気を反映しているのである。
Chapter 4 では、MacbethがMacduffの夫人と息子を殺す辺りから、Macbethと観客との間に距離ができていくことを指摘した。以降、観客は、それまで感情移入して付き合って来たMacbethを第三者の視点で眺めることになり、Macbethの切り落とされた首が舞台に登場するに及んで、その視点は事件首謀者たちの末路を眺める視点と重なるのだ。
Chapter 5 では、Macbethに感情移入してきた観客が”The time is free”という言葉に感じる違和感について論じた。劇の視点は、後半、Macbethから離れていくが、Macbethの性格には、残虐なことをしてもなお、観客に感情移入を許すような余地がある。Macbethが辿った、一人の反逆者としての末路は、当時の観客にとっては、つい最近見たのと良く似た光景だった。Macbethを観てしまった観客は、ロンドン・ブリッジに掲げられた首謀者たちの首を、以前と同じものとして眺めることは出来ない。 Macbethは、当時の観客に、意識変革をもたらす劇だったのだ。
このように見てくると、Shakespeareがいかに一人の劇作家として優れていたかが分かる。当時Macbethを書くのは、危険を伴う行為だった。もっと無難な題材ならいくらでもあった。しかし、Shakespeareはこの事件に関心を抱いた。事件に触発され、想像力が掻き立てられた。面白い劇が書けると思った。だから書きたいと思った。自然な欲求。作家なら誰しも、自分が面白いと思ったものを書きたいと思うはずだ。しかし、その表現者としての自然な欲求を、妨げる力もまた存在する。表現者は、時にそのような力と戦うことになる。時の権力に逆らうことなく、しかもおもねることなく、如何にして作家的欲求を充足させるか。ShakespeareがMacbethを執筆する際に選択した手法は、その二律背反する課題を達成するための最良の選択だったのである。
Notes
1. F1を見ると、ユExeunt fighting.ユというト書きによってMacbethとMacduffは一度舞台上から退場し、その次の行のト書きヤEnter Fighting, and Macbeth Slaine.ユで、二人が斬り結びながら舞台に再登場し、MacduffがMacbethを打ち倒すことになる。しかし、その後Macbethの亡骸を舞台から運び出さなくてはならなくなる。しかしそのことを示すト書きや台詞は存在しない。Macduffが引きずって行くのかも知れないし、 MacduffがMacbethに致命傷を負わせ、うめきながらMacbethが退場するのかも知れない。いずれにせよ、Macbethには Hamlet、Othello、Learに与えられていたような、死際の台詞は与えられていない。
2. 問題のある終わり方をする劇は、Shakespeare作品には多い。『冬物語』では、最期にハーマイオニが彫像の姿で現れ、生きていたことが発覚する。しかし、十六年間、宮廷のそばでポーライナに匿われていたというのは、現実的な話ではないし、そもそも、Shakespeareは、ポーライナがハーマイオニを匿うことにしたということを観客に告げていなかった。彼女たち、ハーマイオニとポーライナ、そしてShakespeareは、観客を、レオンティーズもろとも十六年間騙し続けるのである。話のあまりの唐突な展開についていけなくなる観客がいたかも知れない。『リア王』では、最期、リアがコーディリアの亡骸を抱きながら登場し、リアもその場で命を失う。その理不尽なコーディリアの死に観客が納得がいかないと思ったとしても無理は無い。『十二夜』では、シザーリオに恋いこがれていたオリヴィアが、セヴァスチャンと結婚することになるが、それで本当に良いのかといぶかる観客が出てもおかしくない。
参考文献
Bloom, Harold. Shakespeare: The Invention of the Human. New York:
Riverhead, 1998.
Coursen, Herbert R. Macbeth: A Guide to the Play.London: Greenwood,
1997.
Everett, Barbara. Young Hamlet: Essays on Shakespeare’s Tragedies.
Oxford: Clarendon, 1989.
今井 宏 編 『世界歴史大系 イギリス史 2 近世』 東京: 山川, 1990.
Ioppolo, Grace. Revising Shakespeare. London: Harvard UP, 1991.
川北 稔 編 『新版 世界各国史11 イギリス史』 東京: 山川, 1998.
森 護 『英国王室史話』 東京: 大修館, 1986.
Paul, Henry N. The Royal Play of Macbeth. New York: Octagon, 1971.
Shakesepare, William. The New Cambridge Shakespeare: Macbeth. Ed. A. R.
Braunmuller. Cambridge: Cambridge UP, 1997.
イアン・ウィルソン 『シェイクスピアの謎を解く』 訳: 安西 徹雄 東京: 河
出書房, 2000.
2008/05/02/21:13
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
ラファエルが語り、ダーウィンが読んだ天地創造
—『失楽園』第7巻をめぐって—
米田 拓男
Introduction
本論では、ミルトン『失楽園』第7巻を扱う。第7巻では、旧約聖書の「創世記」の冒頭にあたる天地創造が、ミルトンらしい壮大な筆致で綴られている。ミルトンはこの『失楽園』書くにあたって、聖書のauthorized versionを使用しているのは間違いのないところである。ミルトンは聖書という材源をどのように扱かっているのだろうか。私はその点に関心がある。本論では、ラファエルの語りに注目したい。
Chapter 1「ミルトンとシェイクスピア、その材源の差異」では、グリーンブラットの7つの「否認宣言」を手掛かりに、グリーンブラットの言うところの「社会エネルギー」という観点から、ミルトンとシェイクスピアの材源を比較し、両者の作品がどのような人々を対象として書かれたのかということについて考察する。
Chapter 2「ラファエルの語りについて」では、『失楽園』がラファエルの語りによって成立しているという点に焦点を当てて、第7巻の語りの構造について分析する。
Chapter 3「ダーウィンが読んだ『失楽園』」では、第7巻の天地創造の記述が、何故ダーウィン以降の私たちにとって読むに耐えるものとなっているのかという点について、ラファエルの語りを手掛かりに考察する。
Chapter 4「教育者としてのラファエル」では、第7巻に登場するラファエルが人間存在を賛美する台詞を、「存在の大きな鎖」、「雅量」、「高邁」といった言葉をキーワードに、ミルトンの『教育論』と絡めて論じる。
Chapter 1 ミルトンとシェイクスピア、その材源の差異
スティーブン・グリーンブラットは、文学作品は社会的エネルギーの磁場の中に存在するものであると説く。彼によると、一つの文学作品は、常に社会的エネルギーの影響を受けて成立し、そしてその作品自体が持つエネルギーが、今度は社会に影響を与えるのである。彼は、「文化的実践(つまりは文学作品)に内在する社会的エネルギーがいかに交渉され交換されるのか」という問いに答えるための第一段階として、次のような7つの「否認宣言」を行っている。
1 偉大な芸術のエネルギーの唯一の源泉として天才を持ち出すこと
はしない。
2 動機なき創造はあり得ない。
3 超越的、無時間的、不変的表現はあり得ない。
4 自立的な芸術作品はあり得ない。
5 源泉(〜から)と対象(〜のため)のない表現はあり得ない。
6 社会的エネルギーを持たない芸術はあり得ない。
7 社会的エネルギーの自然発生はあり得ない。
(グリーンブラット 22-23)
グリーンブラットは、シェイクスピアについて論じる過程においてこの7つの否認を行っているのだが、このことは『失楽園』にも当てはまる。一つずつ検証してみたい。(1)ミルトンは、『失楽園』という作品をある社会的背景のもとで(社会的エネルギーを受けて)書いた。イギリスでは1660年に、チャールズ二世が王位に就き、彼が望んでいなかった王政が11年振りに回復した。ミルトンは王政批判のためのパンフレットを多く書いたが、『失楽園』には、その反響と取れる詩行が散見される。(2)ミルトンは1652年に失明し、1658年には結婚生活わずか15ヶ月の妻と生後間もない女児を失うという立て続けの不幸に見舞われた。彼の個人的不幸は、『失楽園』の執筆と無縁ではあるまい。(3)『失楽園』という作品には、書いている当時の政治的見解、個人的な思いが込められているはずである。(4)ミルトンは『失楽園』を書くにあたって、材源として聖書の「創世記」を使用している。そのため彼は『失楽園』を、彼の内的想像力のみに頼って執筆した訳ではない。(5)ミルトンは『失楽園』を、ある程度読者を想定して執筆したはずである。第7巻には ‘fit audience find, though few’(31行)という一節があるが、これはミルトンが『失楽園』を執筆する時に想定していた読者像と重なるかも知れない。(6)ミルトンは1660年頃には『失楽園』をすでに口述を開始しており、1667年に出版した。『失楽園』には、永年に渡る執筆によって蓄積された、グリーンブラットが言うところの「エネルギー」が凝集しているはずである。(7)『失楽園』という作品が持つ「社会的エネルギー」は、政治的、個人的背景の影響を受けており、ある程度は「創世記」という材源から継承しているはずである。
ここでグリーンブラットを引用して私が確認しておきたかったことは、『失楽園』には材源がある、ということと、ミルトンは、何らかの読者を想定して『失楽園』を書いたはずだ、ということの2点である。ここで、シェイクスピア作品と『失楽園』を比較してみたい。まずは第1点目の、材源の違いについて考察する。シェイクスピアは、そのほとんどの作品で材源を用いている。私は過去に『ロミオとジュリエット』と『冬物語』の材源比較を試みたことがあるが、シェイクスピアの材源の扱いについて、その時私は両作品に共通性を見出だした。シェイクスピアは、アーサー・ブルックの物語詩『ロウミアスとジューリエット』(Tragical historye of Romeus and Juliet, 1562)を劇化するにあたって、様々な改変を施しているが、その時私が注目したのは、二人の喜劇的人物、乳母とマキューシオであった。ブルックの詩には、巻頭に ‘To Readers’ として、ここに描かれている恋人たちのように、後先考えずに行動すると身を破滅することになると、読者に対して警告している。そのことが象徴するように、ブルックの詩には全体的に若者たちへの戒めめいた説教臭が充満している。シェイクスピアは、二人の喜劇的人物に、多くの活躍の場を与え、猥雑な冗談を言わせることによって、材源にあった説教臭さを取り除いた。
『冬物語』は、シェイクスピアと同時代の作家ロバート・グリーン (Robert Greene, 1560?-1592) の『パンドスト』 (Pandosto, 1588) を下敷きにして書かれている。シェイクスピアによる『パンドスト』からの改変の最大のもの、それは物語の結末の付け方にある。『パンドスト』は『冬物語』と同じように、パーディタ(『パンドスト』ではフォーニア)とフロリゼル(ドラスツス)の結婚によって幕を閉じるが、リオンティーズ(パンドスト)が自殺することによって苦い後味を残す。ところがシェイクスピアは、『冬物語』においてリオンティーズを殺さず、かつその妻ハーマイオニも生きていたことにして、彫像を装って彼の前に現れる彫像の場を創作し、作品に救いを与えた。材源には、嫉妬深く自分勝手な男に罰が下されるという説教臭が残るのである。『パンドスト』の物語を読み終えた読者は、因果応報、というありがたい教訓を頂戴して本を閉じることになる。しかし、シェイクスピアの『冬物語』に、そのような教訓物語めいたニュアンスはない。
グリーンブラットは、「5 源泉(〜から)と対象(〜のため)のない表現はあり得ない」と言うが、シェイクスピアの作品を受容したのは、劇場の観客であった。観客は、いつの時代も、娯楽に教訓など求めない。一体、誰が、説教を聞きに劇場に足を運んで金を払うだろう。説教を聞きたいのなら教会にでも行った方がましである。シェイクスピアはそのことを良く知っていた。シェイクスピアは『ロミオとジュリエット』で、材源の長篇詩が持っていた説教臭さを見事に抜き取り、ロミオとジュリエットの悲劇を、情熱的な恋の物語として昇華させた。そして『冬物語』では、教訓めいた物語を許しの物語へと書き換えた。シェイクスピアが行ったことは、材源を対象のために書き換える作業だったと言える。
では、ミルトンはどのような材源をどのような対象のために書き換えたのか。ミルトンは聖書を材源として選んだ。当時のイギリスにおいて知らない人はいないアダムとイヴの楽園追放の物語を、である。ミルトンとシェイクスピアの場合とで大きく異なるのは、『失楽園』の読者は、予め材源を知っていることを想定して書かれている点である。シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』や『冬物語』は、その材源を観客が知っているものとして書かれてはいない。ミルトンは聖書を材源として選んだことで、シェイクスピアとは比べ物にならないくらい大きな制約を迫られることになったはずだ。『失楽園』は、読者に馴染みの深い物語を扱っているので、読者と作品の間に、シェイクスピアの場合には無い軋轢が生じることになる。第7巻は、殊にそれが強い巻である。ミルトンは、天地創造を聖書からあまりにもかけ離れたように書くことはできない。何故なら、読者は聖書の一番始めに出てくる天地創造の記述をいやと言うほど頭に刷り込まれているだろうからである。そこからあまりかけ離れれば、そのようなものは私が知っている天地創造ではないとして、読者が離れてしまうだろう。それでは、予め知っている物語を読むことによって、読者がミルトンに期待したものとは何であろうか。自分が知っている天地創造を読みたいのであれば、聖書を紐解けばよいだけの話だ。聖書の天地創造を知った上で、尚、天地創造の物語をミルトンに求めるものがあるとすれば、それは、自分が良く知っている、あのお馴染みの場面が、詩人の力によってどのように再現されているのかという興味に尽きる。そしてミルトンは、そのような読者の期待に見事に答えて見せている。例えば、次のような描写はその格好の例である。
Be gathered now ye waters under heaven
Into one place, and let dry land appear.
Immediately the mountains huge appear
Emergent, and their broad bare backs upheave
Into the clouds, their tops ascend the sky:
So high as heaved the tumid hills, so low
Down sunk a hollow bottom broad and deep,
Capacious bed of waters:
神はさらに言われた、
『汝ら、天の下なる滄海よ、一処に集れ、しかして、
乾ける土をして出現せしめよ!』と。すると巨大な山々が
忽然として姿を現わし、その広々とした裸の背を高く
雲の中にまで擡げた。頂上は屹然として大空に聳え立った。
盛り上がる山々が高くそそり立つにつれ、広く深く
窪んだ谷間が、下へ下へと沈んでゆき、滄海をたたえるのに
ふさわしい広漠たる海底となった。(283-289)
(以下、引用は平井訳を参照)
さすが詩人だと思うような、スケールの大きなSF的と言っても良い描写だ。この箇所は聖書では次のように書かれている。
神は言われた。
「天の下の水は一つ所に集れ。乾いた所が現れよ。」
そのようになった。(「創世記」 1章9節)
このような簡潔な描写を、ミルトンは聖書の中のわずかな記述を詩人の想像力で大きく膨らませているのである。だが、ミルトンの詩的修辞にはこれ以上深入りしない。本論では、この天地創造の場面がラファエルによる語りとして描かれていることに注目したい。次章以降では、ミルトンが聖書の物語を、聖書を熟知している読者のために書き換える際に行った改変のうち、このラファエルの語りについて具体的に論じていくことにする。
Chapter 2 ラファエルの語りについて
第7巻は、ミルトン自身の詩神への呼びかけ(invocation)によって幕をあける。それはホメロスやヴェルギリウスの叙事詩の形式を意識してのことであろう。invocationの中でミルトンは次のように言う。
Standing on earth, not rapt above the pole,
More safe I sing with mortal voice, unchanged
To hoarse or mute, though fallen on evil days,
On evil days though fallen, and evil tongues;
In darkness, and with dangers compassed round,
And solitude;
目も眩むような宇宙の極の上に立ってではなく、この
地上に立ってさらに安らかに、人間らしい声で歌いたいのだ。
たとえ悪しき日々に沈淪していても、—-たとえ悪しき日々と、
悪しき罵詈雑言の中に沈淪し、暗黒の中にあって危険に囲まれ
孤独に苛まれていようとも、声だけは荒立てることなく、また
黙することなく歌いたいのだ! (第7巻 25-28)
このように、ミルトンは闇の中で創作をしていくことを宣言しているが、それはさながら、渾沌の中で神が行う天地創造のようである。第7巻は全12巻に及ぶ『失楽園』の後半の最初の巻であり、invocationによって始まる。そして『失楽園』の後半は、旧約聖書の冒頭に相当する天地創造の描写から始まるのだ。新たな始まりを感じさせる巻である。新井氏は、この箇所が最初に書かれた可能性を示唆する。
ミルトンが『楽園の喪失』のどの部分から口述を開始したかというこ
とは、わかっていない。叙事詩は詩神への呼びかけで始るのが通例で
あるから、この作品のなかでなん度かあらわれるその種の呼びかけの
ひとつが、ミルトンの最初の口述部分となったかもしれない。
(中略)
第七巻の冒頭は王政復古前後の、かれじしんの逆境に言及しているこ
とからみて、個人的色彩のきわめて濃い詩行であるといえる。そして
この個人的色彩は、これらの部分が、あるいは全体の歌い出しの部分
(のひとつ)となっていたのかもしれないという推測をゆるすのであ
る。(新井 126-7)
第7巻は、このように、ミルトン自身の詩神への呼びかけで始まるが、ミルトンが直接天地創造を語る訳ではない。その役割はラファエルへ引き継がれる。アダムはラファエルに、自分たちがどのように誕生したのか、世界がどのように造られたのか知りたいと思い、ラファエルに話すようにせがむ。「神聖なる解説者よ (Devine interpreter)」とアダムはラファエルに語りかける(72行)。平井氏は、『アエネーイス』でメルクリウス(マーキュリ)がそう呼ばれているのを借りたらしいと述べている(平井 312)。この願いに答えて、ラファエルはアダムに語り始める。
This also thy request with caution asked
Obtain: though to recount almighty works
What words or tongue of seraph can suffice,
Or heart of man suffice to comprehend?
Yet what thou canst attain, which best may serve
To glorify the maker, and infer
Thee also happier, shall not be withheld
Thy hearing,
用心深くお前はわたしに頼んだが、その願いを聞き届けて
あげよう。それにしても、わたしのような熾天使のいかなる言葉、
いかなる舌が、全能の神の御業をよく語りえようか? また、
人間のいかなる心がよく理解しえようか? だが、それにも
かかわらず、もしお前が創造主を誉め讃えるのに役立ち、
お前をさらに幸多き者にするのに役立つのであれば、お前に
理解できる限り、そのことについて答えることを控えるべき
ではなかろうとわたしは思う。(第7巻 111-8)
こうしてラファエルは天地創造の場面をアダムに語り始める。
このように天地創造をラファエルの口からアダムに向かって語らせたということは、非常に重要な点であると思う。そしてラファエルの語る天地創造は、聖書のそれと異なる箇所が多くある。聖書における天地創造は次のように始まる。
初めに、神は天地を創造された。地は渾沌であって、闇が深淵の面に
あり、神の霊が水の面を動いていた。神は言われた。
「光あれ。」(「創世記」 1章1-3節)
このように「創世記」では、神自らが天地を創造する。それに対して、ラファエルが語る天地創造では、神の代わりに御子が天地創造に赴くことになる。御子は戦車に乗って渾沌へと向かう。
meanwhile the Son
On his great expedition now appeared,
Girt with omnipotence, with radiance crowned
Of majesty divine, sapience and love
Immense, and all his Rather in him shone.
About his chariot numberless were poured
Cherub and seraph, potentates and thrones,
And virtues, winged spirits, and chariots winged,
御子は大いなる遠征の途につこうとして、その姿を現わされた。
その腰には全能の力を帯び、その頭には神々しい威儀と
広大無辺の知恵と愛との輝きを、冠として着けておられた。
そして、父なる神のすべての光が御子のうちに輝いていた。
彼の乗られた戦車の周囲には、智天使、熾天使、能天使、
座天使、力天使その他の翼をもった夥しい数の天使たちと、
これまた翼をもった多くの戦車の群れが屯していた。
(第7巻 193-9)
このように、ミルトンは聖書には登場しない御子を天地創造の場面に登場させ、御子が渾沌へ向かって行く過程を詩人の想像力で余す所なく壮大に描いて行く。聖書の単純な記述をここまで膨らませるその描写に、ミルトンの詩才をはっきりと見て取ることができる。あるいは、この場合、ラファエルが詩人であると言うべきか。いずれにせよミルトンはこのように、聖書には登場しない御子を天地創造の場面に登場させた。『失楽園』の神にとって、御子は「言(ことば)」と同義であるようだ。
And thou my Word, begotten Son, by thee
This I perform, speak thou, and be it done:
My overshadowing spirit and might with thee
I send along, ride forth, and bid the deep
Within appointed bounds be heaven and earth,
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
So spake the almighty, and to what he spake
His Word, the filial Godhead, gave effect.
だが、汝わが子よ、わが「言」よ、わたしは汝によって
今言ったことを行いたい。言え、汝、さらばことは成就しよう!
すべてを覆う聖霊と能力とを、わたしは、汝につけて送る。
直ちに戦車を駆って行き、「渾沌」に命ずるがよい、定められた
境界内において天と地とをあらしめよ、と!
(中略)
全能者はそんな風に語られた。そして、その語られたことを、
彼の『言』である聖なる御子が実現し給うたのだ。
(第7巻 163-75)
「言」である御子が天地創造を行う。これは聖書の、ヨハネによる福音書の冒頭の記述を受けてのことだろう。
初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言
は、初めに神と共にあった。万物は言によって成った。成ったもの
で、言によらずに成ったものは何一つなかった。(1章1-3節)
神と共にあり、神そのものでもある「言」。一体それは何を意味しているのだろうか。ミルトンはそれを御子と解釈した。ギャラガーは、 ‘Creation in Genesis and in Paradise Lost’ で、ミルトンが聖書にある矛盾に対して論理的辻褄を合わせようと試みた可能性について論じている(Gallagher 197-9)。[1] ギャラガーは次のように言う。
Milton may have been more consumed with the lust of logic than
smit with the love of sacred song
ミルトンは、神聖な詩の情熱に取りつかれていたというよりも、論理
への欲望に心を奪われていたのかも知れない(Gallagher 199)
「言」である御子による天地創造も、ギャラガーが言うような、ミルトンによる聖書の論理的辻褄を合わせるための試みの一つだったのではないか。第7巻の天地創造の件で御子が天地創造を行うのは、最初の方だけである。ラファエルの語りにはすぐに御子は登場しなくなり、代わりに神が自ら天地創造を行う。御子の記述が最初だけですぐになくなってしまうのは、言と神と御子が一体であることを示しているのかも知れない。
ギャラガーは、同じ論文の中で、聖書のテキストが過去に改変されたことについて論じている。聖書に見られる矛盾を解消するために、聖書が改変されたことがあったのだ。ミルトンの『失楽園』は、ギャラガーが言うように、それらの矛盾を解消する、ミルトン版の「創世記」の校訂本であると言えるのかも知れない。しかしミルトンは、新しい聖書を作り出そうとした訳では無かったと思う。私は、ミルトンは聖書に書かれていることを尊重しながら『失楽園』の執筆に取り組んでいたと考える。ラファエルの語りという大枠を導入したことがそのことを示している。どういうことか。ここで一度、語りの枠組みを整理しておきたい。『失楽園』第7巻の複雑な語りの構造は、聖書の「創世記」のそれと比べれば一目瞭然である。以下は聖書の語りの構造である。
神による天地創造(Act)
↓
執筆者(Narrate)
↓
読者(Read)
聖書では天地創造の描写を、執筆者が読者に向けてそのまま記述する。次に揚げるのは、それに対する『失楽園』第7巻の語りの構造である。
神(Order)
↓
御子(Act)
↓
ラファエル(Narrate)
↓
アダム(Listen)
↓
ミルトン(Narrate)
↓
娘たち(Write)
↓
読者(Read)
神は「言」である御子に命じて天地創造を行った。ラファエルはその光景を見ていた。 [2] そしてラファエルは、自分が見たことをアダムに語る。そのラファエルの語りを、作者ミルトンは読者に向かって語りかけている訳だが、実際には口述筆記として、実の娘に語りかけることによって作品化したのである。さらには第7巻には、invocationとしてミルトン自身が語り手として登場する。語りの構造の中に、ラファエルとミルトンという二人の語り手がいるのだ。何故、ミルトンはこのような構造を用いたのか。
『失楽園』第7巻が語りの入れ子構造になっているのは、聖書という材源の性質にあるのではないか。「創世記」の天地創造の描写は、聖書の中でも広く人口に膾炙した箇所である。そのためミルトンにとっては、聖書からの改変に特に慎重にならざるを得ない箇所だったのではないだろうか。ミルトンは天地創造の過程をラファエルの語りを通して描くことによって、「これは私が知っている天地創造ではない」という予想される読者からの批判に対して、「これはラファエルが語る天地創造ですよ」と予めエクスキューズしているのだ。だがそれ以上に、自分の手で聖書を書き換えるという行為が、ミルトン自身にとって恐れ多いことだったからなのではないか。ミルトンがミルトン自身の声で「創世記」を語るのでは、はなはだ不遜な行為であると思われかねない。天地創造をする神をも創造してしまうことになるのだから。私は、ミルトンがこのような語りの入れ子構造を採用したことに、ミルトンの聖書に対する畏怖の念を感じる。聖書の冒頭を飾る天地創造の記述を、『失楽園』では第7巻目に持ってきたということも、叙述を「事件の中心から(in medias res)」始めるという叙事詩の慣例に従ったということもあるだろうが、一方で、ミルトンの聖書に対する控えめな態度を示しているようにも思える。第7巻に見られる複雑な語りの入れ子構造。聖書の中の広く知られた物語を叙事詩として語り直すためには、このような構造が必要だったのである。
Chapter 3 ダーウィンが読んだ『失楽園』
『失楽園』第7巻で、ラファエルはアダムに天地創造について語る。アダムを通じて、ラファエル、そしてミルトンは、私たちに天地創造について語ってくれる。ところが残念なことに、ダーウィニズムに犯されている私たち(少なくとも私)は、このような天地創造が実際に行われたとは考えない。アメリカでは、進化論を教えない学校もあるようだが、根本主義者(fundamentalist)でもない限り、現代を生きる者がここに書かれているような天地創造を、実在の出来事として受け取ることはないだろう。ミルトン自身は、果たして本当に天地創造を信じていたのだろうか。もちろんダーウィンは、ヴィクトリア朝時代の人間であるので、ミルトンの時代の人々は進化論のことなど知る由もなかった。『種の起原』の出版は1859年である。17世紀の人間ならいざ知らず、ダーウィン以後の現代を生きる私たちは、天地創造の記述をフィクションとしてしか読むことはできない。だが、ラファエルの語りが、ここでも有効に機能している。本章でも前章に引き続き、ラファエルの語りの機能について考察する。
聖書には多くの矛盾点があるが、「創世記」に二つの天地創造が描かれていることもその一つである。ヘブライ語で書かれた原典では、「神」は1章ではエローヒーム、2章ではヤーウェと記されている。そのため、「創世記」は1章と2章で作者が異なるのではないかという説がある。神学者のアームストロングは、「創世記」に二つの天地創造が描かれていることには意味があると考えている。彼女は次のように述べる。
編集者たちは、最初に二つの明らかに矛盾する創造物語を提示するこ
とによって、およそ一人の人間が神的心理の全体を包括することなど
できないのだという基本的な宗教的原理を例示していたのである。
(アームストロング 30)
また、アームストロングは次のようにも述べる。(エロヒストとは「創世記」の1章の執筆者、ヤーウィストは、2章の執筆者を指す。)
聖書の編集者たちは、二つの矛盾する創造物語を提供することによっ
て、J[エロヒスト]もP[ヤーウィスト]も虚構を書いたのだということ
を指摘していたのである。彼らは、新しい宇宙論的発見によって時代
遅れのものとされえないような、時代を超えた真理を提供したのであ
る。([]は筆者による)(アームストロング 31)
アームストロングは、聖書の編集者たちが二つの矛盾する創造物語を並列したことによって、聖書の天地創造の記述が普遍性を獲得したということを述べているが、ラファエルがアダムに語る次の台詞にも同じ効果がある。
Immediate are the acts of God, more swift
Than time or motion, but to human ears
Cannot without process of speech be told,
So told as earthly notion can receive.
そもそも、
神の御業というものは瞬時にして成るもので、時間や運動の
速さを凌ぐものなのだ。しかし、そのことは、諄々と
言葉をつらねて地上の者に分かるように説かないかぎり、
到底人間の耳に伝えることはできない。(第7巻 176-9)
ラファエルが言うことが正しければ、天地創造は7日間かかったのではなく、全てが一瞬のうちに行われたことになる。ラファエルはアダムが理解できるように人間界の事例に置き換えて、分かりやすく説明しているのだ。ラファエルは、第6巻で天上の戦争について説明する時にも同じことを言っている。
Thus measuring things in heavユn by things on earth
At thy request,
わたしは、お前の求めに応じて、地上の事柄を物差しにして、
天上の事柄を測りながら今まで話してきた
(第6巻 893-4行)
ギャラガーは、神が人間の創造を第6日目の最後に行うように、ミルトンが創造の順序を入れ替えたことについて論じているが(198)、このような台詞の前では、そのような議論は全て水泡に帰する他ない。このような台詞は、聖書に書いてあることは全てフィクションだという考え方に導きかねないが、実際、ミルトンはそのように考えていたのではないか。これらの台詞はさりげなく挿入されているように見えながら、実はミルトンの聖書批判であり、聖書解釈を表わしているのである。聖書には多くの矛盾点が存在するが、ラファエルがアダムに告げているこのような考え方—-つまり、聖書に書かれていることは全て、読者のために分かりやすく書き換えられたフィクションであるという考え方—-は、そのような矛盾に対する解釈の問題を一挙に解決することだろう。ミルトンが聖書をフィクションとして捉えていた可能性を示唆するこのラファエルの台詞は、とりもなおさず『失楽園』という作品のフィクション性を強調する。ミルトンは『失楽園』を紛うかたなきフィクションとして書いた。だからこそ、ダーウィン以降の私たちも楽しめるのだ。そして実は、当のダーウィンその人も、『失楽園』を楽しんだのである。ミルトン詩集は彼の愛読書の一つだった。
ここで重要となってくるのが、ビーグル号航海におともした二冊の本
を思い出すことである。このとき彼の想像力は最も敏感な時期にあっ
た。一冊はライエルの『地質学原理』。もう一冊、彼が『自伝』のな
かで、肌身離さずビーグル号からの長い陸地探検のあいだも持ち歩い
たと言っているその本が、ミルトン詩集であった。(ビア 56)
そして、ミルトンの『失楽園』は、ダーウィンの進化論の着想に貢献していたのである。
ダーウィンは、ミルトンのうちだす人間中心的宇宙観を転覆すること
に喜びを見出だすようになるのだが、それでもミルトンの言葉の世界
は、それが豊富や、密集や、特定の種の形成に対する、ダーウィン自
身の感覚と一致していたために、どれくらいが生き残りうるか、どれ
くらいが過去との共通性と連続性を保ちうるかを、ダーウィンにはっ
きり示した。ミルトンがダーウィンに深い想像の喜びを与え、それが
ダーウィンにとっては理解につながる手立てとなった。
(ビア 61)
ダーウィンによる進化論以後の私たちがミルトンの『失楽園』を楽しむことができるのは、ミルトン自身がそのフィクション性に自覚的だからである。ミルトンは、「創世記」というフィクションに書かれている天地創造の描写を、同じく「創世記」というフィクションに登場するアダムに、ラファエルの口からフィクションとして語らせる。『失楽園』で二重の語りの構造を用いたことは、作品のフィクション性を強める作用をもたらした。そしてそのことによって、『失楽園』は普遍性を獲得したのだ。叙事詩が持つこのような語りの形式は、グリーンブラット流に言うなら、作品が保存しているエネルギーを、時代を超えて伝達することに有効なのである。
Chapter 4 教育者としてのラファエル
『失楽園』第7巻511行に次のような記述がある。ラファエルは、天地創造をアダムに語る過程で、人間存在のことを次のように賛美する。
There wanted yet the master-work, the end
Of all yet done; a creature who not prone
And brute as other creatures, but endued
With sanctity of reason, might erect
His stature, and upright with front serene
Govern the rest, self-knowing, and from thence
Magnanimous to correspond with heaven,
But grateful to acknowledge whence his good
Descends, thither with heart and voice and eyes
Directed in devotion to adore
And worship God supreme, who made him chief
Of all his works:
既に造られた
すべてのものの目標である、最も重要なものが未だ造られては
いなかった、—-つまり、他の生きもののように常に下を見、
道理を弁えないのと違い、聖なる理性を与えられ、背を
のばして直立し、穏やかな額を真っ直ぐに保って他のものを
支配し、自らを知り、そして自らを知るがゆえに神と交わるに
ふさわしい高邁な心を持ち、しかも同時に自分のもつ一切の
善きものがどこから下賜されているのかを知り、感謝し、
しかして、慎んでその心と声と眼を天に向けてそそぎ、
自分を万物の長として造り給うたいと高き神を崇め、拝む
ところの者、—-これがまだ造られてはいなかったのだ。
(第7巻 505-516行)
この台詞の中で、ラファエルは人間のことを ‘master-work’、’Magnanimous to correspond with heaven’、’chief / Of all his works’と賛美する。このような人間を賛美する記述は、聖書における天地創造の記述には出て来ない。このような記述を、ミルトンは人間の創造の場面に書き加えたのである。何故、ミルトンはこの台詞を追加したのか。この台詞から、ラファエルの語りが持つもう一つの性質を明らかにしたい。
ラファエルはこの台詞の中で、人間存在を貴いものとして謳い上げているが、この台詞は私に『ハムレット』の’What a piece of work is a man’という台詞を即座に連想させる (2幕2場286行)。前後を含めて引用してみる。
近頃、どういうわけか何をやっても楽しくない。日課にしていた武術
などの稽古も全部やめてしまった。やけに気が滅入って、この地球と
いう見事な建造物も、海に突き出た崖っぷちにしか見えない。大空と
いう類いまれなあの天蓋、見ろ、あの素晴らしい頭上の広がり、燃え
立つ黄金をちりばめた絢爛豪華な天井、ああ、あの空でさえ濁った毒
気の集まりとしか思えないのだ。人間は造化の神の傑作だ、気高い理
性、無限の機能、形の素晴らしさ、動きの敏捷さ、天使のような行動
力、神さながらの理解力。世界の美の精髄、生きとし生けるものの鑑
—-だが、それが何だ、俺にとっては塵のかたまり。人間を見ても楽
しくない—-女だって同じだ。(強調筆者)
(松岡訳 2幕2場280-91)
ハムレットの人間賛美は、前後の文脈の中で読むと、そう簡単に喜ばしいものでないことはすぐに分かる。この台詞をどのように理解したらよいのだろう。高橋氏は次のように記す。
ルネサンスの人間賛歌の思想に基づいて人間を神に例える一方で、
「死を想え」(memento mori)の思想に捉えられ、ジレンマに陥る
ハムレット。(高橋 187)
高橋氏によると、この台詞はルネサンスの人間賛歌の思想に基づいていることになる。しかし、人間存在がいくら素晴らしいものであっても、ハムレットには人間が「塵の塊」に見える。それは、人間がいずれ死すべき存在であるからである。人間は素晴らしい。しかし、いつかは塵に帰る。素晴らしいが完璧なものではない。この議論に対してティリヤードは次のように書く。
この台詞は従来、ルネサンス・ヒューマニズムの偉大な英国的一例、
すなわち中世の厭世的禁欲主義に対する人間の尊厳の主張として取り
扱われてきた。だが実は、これはまったく純粋に中世的伝統の中にあ
る。つまり神の姿に似せて造られた人間の堕落以前の状態への、そし
て観念的にはまだ人間が取り戻しうるような状態への正統的賛歌を
シェイクスピア流に書いたものなのである。これはまたシェイクスピ
アが人間を、天使と動物の中間という伝統的な宇宙観に従った位置に
据えているという事実をも示している。(ティリヤード 4)
ティリヤードによれば、この台詞はルネサンス以前の中世的伝統の中にあるという。そして、まだ人間が取り戻しうる堕落以前の状態への正統的賛歌を。そのことを踏まえると、ハムレットは高橋氏が言うように人間が死すべき存在であることを嘆いているのではなく、人間の堕落を嘆いているのかも知れない。堕落以前の人間は貴いものだったが、堕落によって、人間存在は地に落ちた。男も女も、本来貴いものであったはずが、堕落している。「人間は造化の神の傑作だ」という時、ハムレットは、そのことを嘆いているのかも知れない。
ここでティリヤードが触れている、この人間を天使と動物の中間に位置する存在として秩序付けているのはthe Great Chain of Beingの考え方に基づく。ティリヤードによれば、十五世紀の法学者ジョン・フォーテスキューは、自然法に関するラテン語の著作の中で次のように記しているという。
「この秩序においては、熱いものが冷たいものと、乾いたものが湿っ
たものと、重いものが軽いものと、大きなものが小さなものと、高い
ものが低いものと、それぞれ調和している。この秩序においてはま
た、天上の王国では、ある天使が別な天使の上にという具合に次々と
序列をつけて配され、地上と空と海とでも、人間は人間同士、獣は
獣、はたまた鳥は鳥、魚は魚と、それぞれがそれぞれのあいだで序列
をつけられている。したがって、地上を這ういかなる虫でも、空高く
飛ぶいかなる魚でも、この秩序の鎖によって妙なる協和音のハーモ
ニーのうちに縛られないものはないのだ。罪人ばかりのすむ地獄だけ
がこの秩序に抱擁されることを拒み……。神は被造物の数と同じ数だ
けその区別を設けた。したがっていかなる被造物であっても、他のあ
らゆる被造物となんらかの点で異なり、そしてそれゆえに他のすべて
となんらかの点で上下の差別を持たないようなものは存在しない。こ
のようなわけで、最高位の天使から最下位の天使に至るまで、自分よ
りも上と下に天使がいないような者は絶対に存在しないし、人間から
最も下等な虫に至るまで、なんらかの点で別の被造物にまさり、かつ
なんらかの点で別の被造物に劣ることのないようなものも存在しな
い。すなわち、秩序の絆に包み込まれないようなものはないのであ
る。」(ティリヤード 49-50)
フォーテスキューは、全ての存在は序列によって秩序付けられているという。このような序列の中で、人間は、動物と天使の中間に位置すると考えられていた。ポウプ『人間論』の中にも同様の考え方が見られる。
まず最初に、天なる神と地上の人間とについて、我らの知っているも
のから判断する以外に、我らは何を判断し得るだろうか。
人間について我らが判断し参照するよすがは、この地上の彼の状態を
除いて何があるだろうか。たとい神が無数の世界に知られているとし
ても、我らは我らの世界に神をあとづける以外にないではないか。
茫漠たる空間を貫いて眺め、
数多の世界が重なり合って、一個の宇宙を形づくるのを見、
組織が組織の中に連なり、
いかなる惑星がいかなる太陽をめぐり、
いかに様々な存在が恒星の一つ一つに住むかを観察し得る者は、
神がなぜ我らをこのように造ったかを語り得るかも知れない。
然しこの世界を支え、結ぶものを始め、
強固な連絡、微妙な依存、正しい位置の関係などを、
広く行き渡る汝の魂は、果して見ぬいたことがあるだろうか。
部分が全体を包むことがあり得るだろうか。
すべてのものを一つに引き寄せ、引かれて支える偉大な鎖は、
神と汝とのいずれが、支えているのだろうか。(強調筆者)
(ポウプ 上田訳 154)
この中で、「すべてのものを一つに引き寄せ、引かれて支える偉大な鎖」というのは、同じことを指している。
ここで再び、本章の冒頭に揚げたラファエルの台詞に戻りたい。新井氏は、この台詞には、雅量(Magnanimity)の考えを見て取ることができると言う。
アダムは「きよき理性」[sanctity of reason]をさずかり、「寛やか
なる心」[Magnanimous]—-つまり「雅量」をもって神と交わり、節
制を尊びつつ、他を治める。これらの美徳は、[・・・・]明らかに
「貴族とおもだったジェントリー」にミルトンが求めた理想的人間像
である。つまり創造されたアダムの姿には、ミルトンの考える指導者
層の典型が見い出されるのである(この理想たるアダムが堕落し、悔
い改め、神に従順を誓うにいたる過程が、『楽園の喪失』のそのもの
のドラマである)。(新井 116)
第7巻の次にみる箇所にも、Magnanimityの考え方を見ることができると、新井氏は言う(108-116)。ミルトンは1659年に『教会問題における世俗権力』や『教会浄化の方法』といった冊子を公刊している。そのうち『自由共和国樹立の要諦』を、ミルトンは改訂し、三箇所に大きな加筆を行ったという。そのうちの第二の加筆部分で、ミルトンは、王政支持派を、神のみわざと人間の努力を評価しない怠けものとこきおろしている。彼は旧約聖書の「箴言」第6章6節以下の、「怠けものよ、アリのところへ行き、そのなすところを見て、知恵を得よ。アリは君侯なく、支持者なく、主人もないが、夏のうちに食物をそなえ、刈り入れのときに食糧を集める」ということばを引用している。ミルトンはその引用の後、さらに次のように付け加える。
アリは無分別、無制限の人びとにたいして、倹しき自制の民主政、あ
るいは共和国の範例となり、一人の専制君主による一支配体制下より
も、多くの勤勉にして平等なる人びとが未来をのぞみ、協議しあいつ
つ、安全に繁栄してゆく型となる
この加筆を行った一六六〇年の二月、三月頃、ミルトンは『失楽園』の口述を進めていた。ミルトンはこの改訂版『自由共和国樹立の要諦』に見られる主張を、詩的なかたちで『失楽園』のテキストの中に嵌め込んでいるかもしれないのである。第7巻の次の箇所が、アリ社会の部分に相対すると考えられる詩行である。
First crept
The parsimonious emmet, provident
Of future, in small room large heart enclosed,
Pattern of just equality perhaps
Hereafter, joined in her popular tribes
Of commonalty:
最初に匍い出したのは、用心深く
将来のことを考える、なりこそ小さいが大きな知恵を
内に秘めた、節約ずきの蟻であった。蟻は、恐らく今後、
やがては公正な平等の手本となるであろうが、この時も
種族全員をあげての共同体を営んでいた。(第7巻 484-8)
共和政の象徴とされたアリ社会の諸特徴の一切が、ここに出揃っていると新井氏は述べる。この箇所では ‘large heart’ という言葉が使われているが、この語は、ラファエルの人間賛美の台詞に出てくる ‘magnanimous’という語同様、「雅量(マグナニミティ)」の変形であると言える。このアリの創造は第6日目に行われた。そしてこの第6日目の最後の仕事として、神は人間を造るのである。そしてその際に、本章冒頭の一節が記されるのだ。
新井氏は、この雅量という概念はアリストテレスの『ニコマコス倫理学』以来、「王者の条件とされていた美徳」であると言う(新井 133)。『ニコマコス倫理学』を実際に見てみよう。第四巻、第三章「高邁、うぬぼれ、卑下」で、アリストテレスは次のように述べる。高邁(メガロプシューキアー)という言葉で表わされているのが、雅量に相当する概念であろう。
高邁な人とは、自分自身のことを大きな事柄に値すると見なしてお
り、また現に値する人だと考えられる。なぜなら、自分にその価値が
ないのにそんなふうに思っているのは愚かな人であるが、徳をそなえ
ている者で愚かな人や、無分別な人というのは、だれもいないからで
ある。だから、高邁な人とは、今述べられた人を指している。という
のは、自分が小さな事柄に値し、しかも自分自身のことをそのような
ものにしか値しないと見なしているような人は、節制のある人では
あっても、高邁な人ではないからである。すなわち、高邁とは偉大さ
に存するのであって、それはちょうどまた美しさが、大きな身体に認
められれるのに対し、小さな人たちというのは、上品で均整がとれて
いても、美しいとは言えないのと同様である。
(アリストテレス 164-5)
アリストテレスは、「高邁とは偉大さに存する」と言う。高邁、つまり雅量は、偉大さと結びついている。
神は人間を偉大なものとして造ったのである。ラファエルはアダムに向かって、人間、つまり目の前にいるアダムの偉大さを謳い上げる。何故、ミルトンはラファエルにそのようなことをさせたのだろうか。その理由は、この作品が叙事詩であることに求められるかも知れない。英雄的人物が主人公であることは、叙事詩の特徴の一つだからだ。新井氏は次のように述べる。
第一に、叙事詩はそもそも民族の苦難と栄光を語るものであるから、
それは集団的な性格をもつ。第二に、民族の統一精神を象徴する人格
を「範例(モデル)」としてうたいあげる。だからことばも(ラテン
語ではなく)各地方、各国々のことばを用いることが多く、内容もナ
ショナリズムの色彩がつよい。第三に詩人と聴衆とは過去の歴史を共
通に想起することができる関係にある。第四に民族の美徳を代表する
「範例」的人物がうたわれるいじょう、作品は教育的目的をになっ
た。第五として、主人公が苦難の旅路をへて目的地に達するという、
いわば「探究」の形式をもつ。これが「誘惑とたたかう霊魂の巡礼」
の主題をかたちづくることが多かった。第六に、叙事詩は時間的・空
間的知識の「要約」でなければならなかった。さいごに、叙事詩人は
みずからが倫理的高潔を主張できる人物であることが求められた。
(強調筆者)(新井 124-5)
2番目に揚げられている「民族の統一精神を象徴する人格」とは、アダムとイヴをおいて他にない。『失楽園』が叙事詩である以上、ミルトンはアダムとイヴの人格を「範例(モデル)」として歌い上げなくてはならない。ラファエルの人間賛美の台詞は、そのような叙事詩というジャンルの要請によるものなのかも知れない。そして4番目に揚げられているように、アダムとイヴという「範例」的人物が謳われることによって、『失楽園』は「教育的目的」を担うことにもなった。
ミルトンは『教育論』の中で次のように記す。
学問の目的は、神を正しく知ることができるようになって、わたした
ちの最初の親が犯した堕罪を回復することである。その知識によっ
て、神を愛し神にならい、できうるかぎり神に近いものとなるため
に、わたしたちの魂に真の美徳を有せしめて、それが信仰という天か
らの恵みと結合して最高の完全を形成することである。ところが、わ
たしたちの理解力というものは、この肉体にあっては目に見えるもの
にしか及ばない。したがって、目に見える、より程度の低い被造物を
順序正しく研究することで得られるほど明らかには、神と目に見えな
い事がらを知る知識には到達できないのであるから、賢明なる教育に
おいても、必然的にこれと同じ方法がとられるべきである。
(ミルトン 11-12)
ミルトンは、学問の目的を「神を正しく知ることができるようになって、わたしたちの最初の親が犯した堕罪を回復すること」にあると述べる。「目に見える、より程度の低い被造物を順序正しく研究する」という記述からは、ミルトンが明らかに ‘the Great Chain of Being’の概念を意識していることを表している。ミルトンにとっての学問とは、「神を正しく知」り、「神を愛し」、「できうる限り神に近いものとなる」こと、つまり、「存在の大きな鎖」の序列をできるだけ上に上って行き、神に近づくことなのである。そしてここでも雅量の概念が表れる。ミルトンは、教育を次のように定義する。
わたしは、平時にも戦時にも、私的であれ公的であれ、すべての職務
を正しく、巧みに、気高くやりとげるように人を訓練するところのも
のを、完全至高の教育であると呼ぶ。(強調筆者)
(ミルトン 16)
「すべての職務を正しく、巧みに、気高くやりとげる」ような人とはアリストテレスが言う「高邁(メガロプシューキアー)」に通じる人をも指すのであろう。しかし、新井氏は、アリストテレスの雅量と。ミルトンの雅量には違いがあると言う。
アリストテレスのいう雅量は人間そのものの偉大性の概念であって、
政治指導者に求められる資質である。それにたいしてミルトンのいう
雅量は、具体的に旧新約聖書に出る、アブラハム、サムエル、ヨブ、
キリスト、パウロなど神への信従をとおした諸人物にたいして、神の
側からあたえられた尊厳をさしていうことばである。アリストテレス
のいう「雅量」が人間中心的概念であるとすれば、ミルトンのそれは
いわば神中心的概念であるということができるであろう。
(新井 72)
ここに至って、ミルトンが考える雅量、ミルトンが認識していた ‘the Great Chain of Being’のイメージが具体的に見えてくるような気がする。ミルトンは地球上の全ての生き物の頂点に君臨する者としてではなく、神、そして天使の下位に存在する者として人間を捉えていたのである。
ミルトンは、人間を神の下で気高く教育したいという意識があった。そしてそのような試みの成果として、私たちは『失楽園』という書物を持っている。ラファエルは第7巻において、アダムに天地創造について語るが、ラファエルはアダムの教育者なのだ。ラファエルはアダムに向かって次のように言う。
such commission from above
I have received, to answer thy desire
Of knowledge within bounds:
一定の限界内での知識を
えたいというお前の欲望に応ずるのが、わたしが天から
受けてきた使命でもある。(118-20)
そしてラファエルは、アダムが「すべての職務を正しく、巧みに、気高くやりとげるように」教育を施す。その過程で、人間賛美の台詞が出てくるのである。しかし私は、ラファエルのその言葉に、ハムレットが人間を賛美する時と同様、アイロニカルな響きを聞き取らざるを得ない。何故ならラファエルは、アダムがこの後ラファエルを裏切り、サタン扮する蛇によって堕落させられるのを知っているからだ。ラファエルは、アダムが堕落することになるのを神から聞いてすでに知っているのだ。全てが徒労に帰すのを知った上で、なおかつラファエルはアダムに教育を施す。となれば、ラファエルのこの言葉には、アダムに対して、人間は貴いものなのだから、誘惑に負けてくれるなという思いが込められていると考えるべきであろう。ミルトンがこのような語りを書いた背景には、そのような思いが込められているのではないか。ミルトン自身が口述筆記をしている時、ミルトンはラファエルがアダムに言い聞かせるようにして語ったのだ。
ここで再び、グリーンブラットの7つの「否認宣言」を思い出したい。ここに来て明確になったことがある。それは、(5)ミルトンは「創世記」を材源として、聖書を予め知っている人々、つまりアダムがやがて堕落することを知っている人々に対して『失楽園』の第6巻を書いた。(2)そしてその動機は読者を教育することにあったのだ。
最後に、先に引用した『教育論』からの一節を、再び引用する愚をお許しいただきたい。
学問の目的は、神を正しく知ることができるようになって、わたし
たちの最初の親が犯した堕罪を回復することである。その知識によっ
て、神を愛し神にならい、できうるかぎり神に近いものとなるため
に、わたしたちの魂に真の美徳を有せしめて、それが信仰という天か
らの恵みと結合して最高の完全を形成することである。ところが、わ
たしたちの理解力というものは、この肉体にあっては目に見えるもの
にしか及ばない。したがって、目に見える、より程度の低い被造物を
順序正しく研究することで得られるほど明らかには、神と目に見えな
い事がらを知る知識には到達できないのであるから、賢明なる教育に
おいても、必然的にこれと同じ方法がとられるべきである。
(ミルトン 11-12)
ラファエルは「わたしたちの最初の親」たるアダムに教育を施す。ミルトンは「私たちの理解力と言うものは、この肉体にあっては目に見えるものにしか及ばない」という。そのためミルトンは、天地創造を人間にも分かるような形で語り直した。ミルトンは第7巻で「目に見える、より程度の低い被造物を順序正しく」描写している。ミルトンは、それが、「神と目に見えない事がらを知る知識」に到達するために有効な教育法であると記す。まさにこの通りの方法で、ラファエルはアダムに教育を施す。しかし、それは失敗することが運命付けられている。神は天使たちの教育に、サタンという存在を生み出すことにより失敗した。その天使たちの一人、ラファエルは、アダムに対する教育に堕落を阻止することができず失敗することになる。そしてミルトンは『失楽園』という一冊の書物を通じて私たちに教育を施す。それは果たして成功しているのだろうか。だが、それが成功するかしないかが問題なのではない。ラファエルは、アダムが堕落することを承知の上で、アダムを教育する。ミルトンも、人間が「最初の親が犯した堕罪を回復する」ことができないと分かっていても教育を辞めなかっただろうからだ。
Conclusion
本論では、ミルトン『失楽園』第7巻について、ラファエルの語りに注目して論じた。第7巻では、旧約聖書の「創世記」の冒頭にあたる天地創造が、ミルトンらしい壮大な筆致で綴られている。ミルトンは聖書という材源をどのように扱かっているのか。私はその点に関心があった。
Chapter 1「ミルトンとシェイクスピア、その材源の差異」では、グリーンブラットの7つの「否認宣言」を手掛かりに、グリーンブラットの言うところの「社会エネルギー」という観点から、『失楽園』とシェイクスピア『ロミオとジュリエット』、『冬物語』の材源を比較した。ミルトンとシェイクスピアの場合とで大きく異なるのは、『失楽園』の読者は、予め材源を知っていることを想定して書かれている点である。天地創造をラファエルの語りによって描いたことは、ミルトンが聖書の物語を、聖書を熟知している読者のために書き換える際に行った改変の中で特に重要なものであることを指摘した。
Chapter 2「ラファエルの語りについて」では、『失楽園』がラファエルの語りによって成立しているという点に焦点を当てて、第7巻の語りの構造について分析した。ミルトンがミルトン自身の声で「創世記」を語るのでは、はなはだ不遜な行為であると思われかねない。何故なら、天地創造をする神をも創造してしまうことになるからである。聖書の中の広く知られた物語を叙事詩として語り直すためには、ラファエルの語りによる入れ子構造が必要だったのである。
Chapter 3「ダーウィンが読んだ『失楽園』」では、第7巻の天地創造の記述が、何故ダーウィン以降の私たちにとって読むに耐えるものとなっているのかという点について、ラファエルの語りを手掛かりに考察した。ラファエルはアダムが理解できるように、天上界の出来事を人間界の事例に置き換えて、分かりやすく説明しているのだと言う。ミルトンは、「創世記」というフィクションに書かれている天地創造の描写を、同じく「創世記」というフィクションに登場するアダムに、ラファエルの口からフィクションとして語らせる。『失楽園』で二重の語りの構造を用いたことは、作品のフィクション性を強める作用をもたらした。ダーウィンの進化論以後の私たちがミルトンの『失楽園』を楽しむことができるのは、ミルトン自身がそのフィクション性に自覚的だからである。
Chapter 4「教育者としてのラファエル」では、第7巻に登場するラファエルが人間存在を賛美する台詞を、「存在の大きな鎖」、「雅量」、「高邁」といった言葉をキーワードに、ミルトンの『教育論』と絡めて論じた。ラファエルは、天地創造をアダムに語る過程で、人間存在のことを’master -work’、’Magnanimous to correspond with heaven’、’chief / Of all his works’と賛美する。この台詞は、Great Chain of Beingや雅量(Magnanimity)、さらにはアリストテレスが『ニコマコス倫理学』の中で論じている高邁(メガロプシューキアー)といった考え方と結びつく。
ミルトンは『教育論』の中で、学問の目的を「神を正しく知」り、「神を愛し」、「できうる限り神に近いものとなる」ことにあると述べる。つまり、ミルトンにとっての学問とは、「存在の大きな鎖」の序列をできるだけ上に上って行き、神に近づくことなのである。ミルトンは「私たちの理解力と言うものは、この肉体にあっては目に見えるものにしか及ばない」という。そのためミルトンは、天地創造を人間にも分かるような形で語り直した。ミルトンは「目に見える、より程度の低い被造物を順序正しく研究する」ことが、「神と目に見えない事がらを知る知識」に到達するために有効な教育法であると記す。第7巻におけるラファエルは、まさにこの通りの方法で「わたしたちの最初の親」たるアダムに教育を施す。そしてミルトンは『失楽園』という一冊の書物を通じて、同時に私たち読者にも教育を施しているのだ。
Afterward
本論執筆中に、入院していた祖父の容態が悪化し、亡くなった。僕はお通夜、そして告別式に出席している間、ずっとある違和感を抱き続けていた。それは一昨年に亡くなられた倉本先生の告別式の時にも感じたことである。例えばそれは、斎場で流れているシンセサイザーの電子的な音楽に、段取り然とした斎場の係員に、テレビのワイドショーで芸能人の死が報じられる際に耳にするような女性アナウンスに感じた。そしてコンピューター制御の火葬場。火葬場の内装がひんやりと冷たい。冷たく光る御影石の床、蛍光灯の白い光。床にはゴミ一つ落ちていない。ガラス張りの自動ドアからは外の駐車場が目に入る。何の装飾も施されていないのは、宗教的に無色でありたいという思惑があってのことなのかも知れない。そして最後、駅員のようないでたちの係員の手によって祖父の遺骨は骨壷の中に収められた。僕にはこれらの光景が、悪趣味な儀式の一部に思われる瞬間がいくつもあった。システマティックに管理された、悪趣味な儀式。日本人の行き着く先がこのような光景であるとは、僕には哀しすぎる。
日本に必要なのは、ミルトン的教育だ。日本は宗教的基盤が脆弱に過ぎる。しかし近ごろでは、宗教というと、イメージが悪い。日本で宗教というと、オウムやアルカイダといった狂信的な宗教集団と結びつきやすい。そのような日本の宗教的な基盤の薄さが、葬儀に露呈している。
僕は以前、カトリックの葬儀にも参列したことがある。僕はどこの宗教にも属していないが、小中学校、高校と、ボーイスカウトに入っており、10年間カトリックの教会に通っていた。だからミサにも数えきれないほど参加したし、クリスマス・パーティにも毎年参加していた。その頃、スカウトの仲間の一人が、病気で亡くなるということがあった。葬儀は教会で執り行われ、僕は仲間のスカウトと共に礼拝に参列した。礼拝は教会の礼拝堂で執り行われ、オルガンの音が静かな流れる礼拝堂で、僕は敬虔な気持になった。
何も西洋の宗教が、日本の宗教より優れていると言いたいのではない。明治の近代化以降、さらには敗戦後のGHQによる統治を経て、日本人は日本の文化、伝統の多くを捨ててきた。それが問題だと言いたいのだ。それは言葉にも言えることである。明治以降、あるいは特に敗戦以降、日本語はそのボキャブラリーが物凄く少なくなった。日本語の語彙の貧しさは、文部科学省が認定している人名に使用できる漢字に、昨年まで「林檎」という漢字が含まれていなかったことが示している。
日本人は伝統を全て切り捨ててきてしまったのだ。それが無機質な火葬場と、告別式にかかるシンセサイザーの音楽が象徴している。無機質な斎場でのシンセサイザーの音楽と、礼拝堂でのオルガンの音。全ては高度成長のため。経済的発展のため。経済的発展のために多くのものを犠牲にしてきたのだ。
物質的に豊かになっていく過程では、無機質な火葬場は、近未来的なテクノロジーの反映として、豊かさとして人々の目に映ったのかもしれない。だが、そのような経済的発展を謳歌していない今の日本では、寒々しく映るばかりである。
日本において現在『失楽園』がそれほど読まれていないとしたら、『失楽園』が、読者が聖書を読んでいることを想定して書かれているからではないか。ミルトンは第7巻31行で、’fit audience (find,) though few’と書いている。日本ではまさに少ない読者になってしまっているのかも知れないが、僕はミルトンが『失楽園』を少ない読者に向かって書いたとは思わない。日本で『失楽園』が読まれないとするなら、それは恐らく日本の宗教的貧しさに根ざしているのである。問題は根深い。
このような日本が宗教的な深みに到達する時が果たしてくるだろうか。そう考える時、僕は、堕落するアダムに説教するラファエルの気持が少しだけ分かったような気になる。僕が今後行っていく活動、例えばいま大学院で文学を研究しているようなことによって、そのような日本の文化的土壌を少しでも豊かなものとすることに貢献できたら、と切に願う。
Notes
[1] ミルトンのテキストも改訂されてきた。中にはリチャード・ベントリー(Richard Bentry, 1662-1742)といったような古典学者が、ミルトンが没して五十年後に、主観的な解釈によって改訂するような事態も起きた。それは次の箇所に表れているという。
彼は思索と勇気を表わすために、
彼女は柔和と魅惑的な優美を表わすために、
彼は神のみのために、彼女は彼の内なる神のために造られた。
(第4巻 297-99)
佐野氏は次のように述べる。
とりわけ299行(He for God only, she for God in him)について、
古典学者リチャード・ベントリーは一七三二年に編んだ『失楽園』の
注釈で、「どの版でも見過ごされてきた誤り。作者は[彼は神のみの
ために、彼女は神と彼のために造られた He for God only, she for
God AND him]と書いていた」と主張した。ベントリーの大胆な改訂
は、女性の男性への依存・従属感を取り除こうとするもので、ミルト
ン批判というよりは、ミルトンを批判から救おうとしたものなのかも
しれない。(佐野 4)
[2] しかし、どうやら、ラファエルは6日目は、天地創造に付き合っていないようだ。
実を言うと、わたしは
あの日には偶々留守をしていた。大部隊で方形の陣を固め
(これがわれわれに課せられた命令だった)、暗澹たる未知の
旅に出、はるか彼方の地獄の門に向かって遠征していた。
神が御業を行っておられる間に、スパイや敵が一人でも
そこから抜け出さないように監視するのが、われわれの任務で
あった。(第8巻 229-35)
ということは、ラファエルは6日目に関しては他の天使、あるいは神から聞いたことになる。
Works Cited
新井 明 『人と思想134 ミルトン』 東京: 清水書院, 1997.
アリストテレス 『ニコマコス倫理学』 朴 一功 訳 京都: 京都大学学術
出版者, 2002.
カレン・アームストロング 『楽園を遠く離れて 「創世記」を読みなお
す』 高尾 利数 訳 東京: 柏書房, 1997.
ジリアン・ビア 『ダーウィンの衝撃』 渡部 ちあき・松井 優子 訳 東
京: 工作舎, 1998.
Gallagher, Philip J. ‘Creation in Genesis and in Paradise Lost.’ Milton
Studies. 163-204.
スティーブン・グリーンブラット 『シェイクスピアにおける交渉』 酒
井 正志 訳 東京: 法政大学出版局, 1995.
The Holy Bible: A Reprint of the Edition of 1611. Oxford: Oxford UP,
1985.
共同訳聖書実行委員会 『聖書 新共同訳』 東京: 日本聖書教会,
1987.
Milton, John. Paradise Lost. 2nd ed. Ed. Alastair Fowler. London:
Addison Wesley Longman, 1998.
—–. 『教育論』 私市 元宏・黒田 健二郎 訳 東京: 未来社, 1984.
—–. 『失楽園(下)』 平井 正穂 訳 東京:岩波書店, 1981.
アレグザンダー・ポウプ 『人間論』 上田 勤 訳 『世界名詩集大成9
イギリス篇 I 』 加納 秀夫 訳者代表 東京: 平凡社, 1959.
佐野 弘子 「ミルトンの女性観・結婚観をめぐる批評」 『神、男、そ
して女 ミルトンの『失楽園』を読む』 辻 裕子・佐野 弘子 編 東
京: 英宝社, 1997. 3-18.
Shakespeare, William. Hamlet, Prince of Denmark Updated Edition. Ed.
Philip Edwards. Cambridge: Cambridge UP, 2003.
—–. 『ハムレット』 松岡 和子 訳 東京: 筑摩書房, 1996.
高橋 康也・河合 祥一郎 註 シェイクスピア 著 『大修館シェイクスピ
ア双書 ハムレット』 東京: 大修館書店, 2001. 84-387.
E・M・W・ティリヤード 『エリザベス朝の世界像』 磯田 光一・玉泉
八州男・清水 徹朗 訳 東京: 筑摩書房, 1992.
Works Consulted
新井 明 『ミルトンとその周辺』 東京: 彩流社, 1995.
新井 明・野呂 有子 編 『摂理をしるべとしてムミルトン研究会記念論文
集』 東京: リ−ベル出版, 2003.
圓月 勝博・小野 功生・中山 理・箭川 修 『挑発するミルトンム『パラダ
イス・ロスト』と現代批評』 東京: 彩流社, 1995.
ヴィクター・ローランド・ゴールド 他 編 『聖書から差別表現をなくす
試行版 新訳聖書・詩編(英語・日本語)』 上沢 伸子 他 訳 東京:
DHC,1999.
平井 正穂 『イギリス文学論集』 東京: 研究者出版,1998.
白鳥 正孝 『ミルトンの思想-『失楽園』を中心に』 東京: 鷹書房弓プ
レス, 2001.
武村 早苗 『ミルトン研究』 東京: リ−ベル出版, 2003.
宇都宮 秀和 『文学と神学の間—ミルトン・言語・聖書解釈をめぐって
—』 東京: 近代文芸社, 2000.
2008/05/02/21:12
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
エリザベス朝時代の復讐劇
シェイクスピア『ハムレット』とトマス・キッド『スペインの悲劇』の比較
Elizabethan Revenge Plays
A Critical Comparison of Hamlet and The Spanish Tragedy
米田 拓男
序
本論で私は、イギリス演劇史における特に復讐劇という視点から、シェイクスピア(William Shakespeare, 1564-1616)の『ハムレット』(Hamlet, ca.1600)という作品がどのような状況の下で書かれたのかを、トマス・キッド(Thomas Kyd, 1558-1594)の『スペインの悲劇』(The Spanish Tragedy, 1587)と比較することによって考察してみたいと思う。そもそも何故、当時多くの復讐劇が書かれた中で、『ハムレット』だけがこれほどまでに上演されることになったのだろう。もちろん、『ハムレット』が優れた作品であることは言うまでもない。そうでなければ、『ハムレット』がグローブ座で初演されてから優に400年以上が経過している現在においてなお、これほど上演され、かつ読まれ続けているはずはない。『ハムレット』が優れた作品であると口にするのは容易い。だが、何故『ハムレット』だけが、という疑問を解くためには、当時のイギリス演劇の状況を考えなくてはならない。同時代の他の作品と比較してみなければ、『ハムレット』という作品が持つ真の価値というものは分からないだろう。
『ハムレット』という作品は、シェイクスピアの想像力によってのみ純粋培養されてこの世に生み落とされた訳ではない。『ハムレット』には材源が存在し、物語の筋の大部分をそれに負っている。なるほど確かにシェイクスピアは、材源であるサクソやベルフォレにはない亡霊や劇中劇といった要素を劇中に新たに導入してはいる。しかしそれらは、『ハムレット』が書かれる以前に、すでにトマス・キッドが『スペインの悲劇』で使用したモチーフだった。『ハムレット』という作品が、歴史から隔絶した真空状態で書かれた訳ではない以上、『ハムレット』がどのような先行作品の遺産を有効利用して書かれているのかということを考察するのには意味があるはずだ。それなくしては、『ハムレット』の価値を本当に理解したことにはならない。シェイクスピアはどのような素材をどのように料理したのか。本論における私の最大の関心はそこにある。
第一章では、エリザベス朝で復讐劇が誕生する過程について論じ、『スペインの悲劇』や『ハムレット』が書かれるに至った背景を説明する。第二章では、『スペインの悲劇』と『ハムレット』の共通点を列挙し、その影響関係について考察する。第三章から以下の三章では、第二章で指摘した、『スペインの悲劇』と『ハムレット』に見られる共通点のうち、「亡霊」(第三章)、「劇中劇」(第四章)、「狂気」(第五章)の三つの要素に焦点を当て、それぞれ一つずつ取り上げて論じたいと思う。果たして『ハムレット』は、『スペインの悲劇』から何ものかを継承しているのだろうか。また、継承しているとしたら『ハムレット』の独自性はどこにあるのか。本論は、その影響関係を、イギリス演劇史における復讐劇の系譜という視点から考察するものである。
第一章 イギリスにおける復讐劇の誕生
本章では、イギリスに復讐劇が現れ、『スペインの悲劇』と『ハムレット』が書かれるに到った背景について見たい。両作に直接的な影響関係はあったのだろうか。つまり、シェイクスピアの『ハムレット』は『スペインの悲劇』の影響下に書かれたと言うことはできるのだろうか。
16 世紀後半のエリザベス朝から、続くジェイムズ一世の時代に、イギリスでは復讐劇が大流行した。それは、ジャスパー・ヘイウッド(Jasper Heywood, 1535-1598)がセネカ(Seneca, ca.4 BC-65 AD)の悲劇を英訳したのを機に始まった。ラテン語から英訳されたセネカの戯曲は、人々に広く読まれるようになり、この時期に書かれた悲劇はその影響を受けることになった。そのため必然的に、この時代の悲劇には復讐がモチーフとして多く取り入れられた。例えば、1558-61年には、セネカの『テュエステス』(Thyestes)が翻訳された。これは、自分の女房を誘惑したとして、その男(実弟)の子供を殺し、その肉を料理して男に食べさせるという、アトレウス一家の悲劇を描いた話で、シェイクスピアの『タイタス・アンドロニカス』(Titus Andronicus, ca.1589)の種本のひとつと看做されている。[1] それと前後してセネカの『トロアス』(Troades)と『怒れるヘラクレス』(Hercules furens)が出版された。1561年には、セネカの影響色濃い、親子間の復讐を扱った、一般に英語による最初の悲劇と看做されている『ゴーボダック』(Gorboduc)が書かれた。[2] 1566年には、セネカの『アガメムノンの悲劇』(Agamemnon)が英訳され、ジョン・ピカリング(John Pickering, 1544-96)はそれを種本として『ホレステス』(Horestes)(1567年)を書いた。[3] 他にトマス・プレストン(Thomas Preston, 1537-98)『カンビュセス』(Cambises, 1569)と恐らくリチャード・バウワー(Richard Bower, d.1561)によって書かれた『アピウスとヴァージニア』(Appius and Virginia, ca.1567)も、『ホレステス』と同様に寓意を用いた道徳的インタールードであり、セネカの流血悲劇を思わせる題材を扱っている(中村 125)。そして、1581年には、『セネカの悲劇十篇』(Seneca’s Tragedies)が『ゴーボダック』の作者の一人であるトマス・ノートンの編集によって出版された。
だが、これらセネカの、あるいは、セネカ風の悲劇と、『スペインの悲劇』との間には、大きな差異があった。セネカの劇は、恐らく朗読用、あるいは読書の目的ために書かれている。『ゴーボダック』や『ホレステス』なども、いわゆる書斎劇(closet drama)として書かれた。こういった作品では、残酷な場面がすべて登場人物の台詞によって語られ、決して舞台上で展開されることはない。だが、キッドは、そういった場面を実際に舞台の上に再現してみせた。『スペインの悲劇』は、イギリスにおいて、初めて舞台上で殺人が描かれた作品なのだ。それは、当時、とても斬新なものだった。
『スペインの悲劇』の初演がいつだったか、はっきりしたことはわかっていないが、1587年頃とする説が有力である。[4] また、その年かあくる年にはクリストファー・マーロウ(Christopher Marlowe, 1564-1593)の『タンバレイン大王』(Tamburlaine the Great, 1590)が初演されたようだ。[5] 『スペインの悲劇』は、1592年の四つ折り版から、1633年の四つ折り版に至るまで、現存するテキストだけでも十版を重ねた(佐野 3)。そのことから、当時大変な人気を獲得していたことがうかがえる。
エリザベス朝の人々は、血の気の多い享楽を求めていた。熊いじめ、牡牛いじめなどといった見せ物は、いつも大変に人気があったし、絞首刑、斬首刑、八裂きの刑などの処刑には、たくさんの見物人が群がった。そのような背景も、『スペインの悲劇』に続く復讐劇の流行と無縁ではないだろう。ロンドン市当局は、市内に公開劇場を建設することを許さなかったが、この時期の演劇を、ピューリタンが支配していた市当局が気に入らなかったのも、当然だったと言えるかもしれない。結局、1642年に、ロンドン市郊外にあった全ての劇場は、議会によって閉鎖されてしまう。
『スペインの悲劇』の成功を受けて、その後クリストファー・マーロウが『マルタ島のユダヤ人』(The Famous Tragedy of the Rich Jew of Malta, 1589)を書く。そして、それと同じ頃、シェイクスピアは『タイタス・アンドロニカス』を書いた。[6] シェイクスピアは、『タイタス・アンドロニカス』を書くにあたって、セネカの劇に影響を受けながらも、キッドが『スペインの悲劇』でそうしたように、セネカでは描かれなかった残酷な場面を、実際に舞台上に再現した。1600年頃、『ハムレット』とほぼ同時期には、ジョン・マーストン(John Marston, 1576-1634)が、『アントニオの復讐』(Antonio’s Revenge)を書いた。[7] 『アントニオの復讐』は、『スペインの悲劇』が切り開いた復讐劇を、さらに残酷化したと言える作品である。そして、1601年に、シェイクスピアの『ハムレット』が登場する。[8]
以上が、イギリスに復讐劇が誕生してから『ハムレット』が書かれるまでのおおよその過程である。消失した作品もあるだろうが、数としてそれほど多くはない。そのことから言えるのは、『ハムレット』がイギリスにおける「復讐劇の伝統」に基づいて書かれたというのが、誤解であるということだ。『ハムレット』が当時流行していた復讐劇の伝統を利用していたという記述をしばしば目にすることがある。[9] しかし『ハムレット』は、イギリスの復讐劇の伝統の中から生み出されたものではない。河合祥一郎が次のように指摘しているように、むしろ、その後に続く復讐劇の伝統を作り出した作品なのである。
フレッドソン・バワーズは名著『エリザベス朝の復讐悲劇』の中で、真に「復讐悲劇」と呼べる一連の人気エリザベス朝悲劇の流れはキッドの『スペインの悲劇』から始まると言明しているが、『スペインの悲劇』上演の1589 年頃から『ハムレット』上演の1601年頃までに書かれた復讐劇の数が少ないことを鑑みても、『ハムレット』が「復讐劇の伝統」の中で書かれたものではないことがわかる。むしろ『ハムレット』はその後に続々と書かれた復讐悲劇の原型なのであって、「復讐劇の伝統」とはむしろ『スペインの悲劇』や『ハムレット』を嚆矢として生まれ始めたものなのだ(河合 148)。
『ハムレット』以前に書かれた復讐をモチーフとした作品、つまり「復讐劇」は、先に挙げた通りであるが、舞台用に書かれた「復讐悲劇」ということになると、『スペインの悲劇』と『タイタス・アンドロニカス』くらいしかない。『スペインの悲劇』以降に書かれた「復讐劇」には『タンバレイン大王』や『アントニオの復讐』があるが、主人公が生き残るので悲劇には当てはまらない。『ハムレット』以前に書かれた「復讐悲劇」の数がそれほど多くなかったという事実は、両作品の近似をより強く印象づける。次章で述べるように、両作品には偶然とは言えないほどの多くの類似点があるのだ。
トマス・キッドはセネカの影響下に、『スペインの悲劇』という独自の復讐劇を生み出した。そしてシェイクスピアは恐らく当時、画期的に目新しい芝居だった『スペインの悲劇』の影響の下に、『ハムレット』を書いた。その『スペインの悲劇』初演から『ハムレット』初演に至る十数年間に作られた復讐劇の型が、その後、シリル・ターナー(Cyril Tourneur, ca.1575-1626)や、ジョン・ウェブスター(John Webster, 1580-1630)といった劇作家たちの作品に受け継がれていったのである。
第二章 『スペインの悲劇』と『ハムレット』に見られる共通点
『ハムレット』には、『スペインの悲劇』の影響を受けて書かれたことを伺わせるような、多くの類似点がある。[10] 以下にその共通点と、差異を列挙してみたいと思う。
1、復讐劇である、ということ。そしてその復讐は、復讐者よりも身分の高い者に対して果たされるということ。『ハムレット』と『アントニオの復讐』は、王子から王への、『スペインの悲劇』と『タイタス・アンドロニカス』は、家臣から王への復讐であり、いずれにおいても、国王に対して復讐が果たされる。
2、肉親の情に基づく復讐。子の死に対する父親の復讐(『スペインの悲劇』、『タイタス・アンドロニカス』)、あるいは、父の死に対する子の復讐(『アントニオの復讐』、『ハムレット』)。
3、亡霊が登場する(『スペインの悲劇』、『マルタ島のユダヤ人』、『アントニオの復讐』、『ハムレット』)。
4、殺人が秘密にされていること(『スペインの悲劇』、『ハムレット』)。
5、狂気。復讐へと向かう過程で、復讐者は、狂気を装おう(『スペインの悲劇』、『タイタス・アンドロニカス』、『アントニオの復讐』、『ハムレット』)。
6、ホレイショという名前の主要人物が登場する(『スペインの悲劇』、『ハムレット』)
7、禁じられた恋のモチーフ。『スペインの悲劇』では、プリンセス(ベル=インペリア)と家臣の息子(ホレイショ)の恋であるのに対して、『ハムレット』では、プリンス(ハムレット)と家臣の娘(オフィーリア)の恋。
8、芝居好きな主人公(『スペインの悲劇』、『ハムレット』)。
9、劇中劇を伴う(『スペインの悲劇』、『ハムレット』)。
10、復讐を果たした直後に主人公が死ぬこと(『スペインの悲劇』、『タイタス・アンドロニカス』、『ハムレット』)。[11]
両作品にはこのように多くの共通点があるが、『ハムレット』と『スペインの悲劇』の繋がりは、ここに揚げたような作中の諸要素に留まらない。『スペインの悲劇』の作者トマス・キッドは、シェイクスピアの『ハムレット』の種本であると考えられている、『原ハムレット』(Ur-Hamlet)の作者であるとも言われているのだ。『原ハムレット』とは、シェイクスピアの『ハムレット』が初演されたと推定されている1600-1年以前に上演されていたらしい『ハムレット』と呼ばれる作品で、いくつかの記録以外、その存在は確認されていない。ハロルド・ブルーム(Harold Bloom)は、『原ハムレット』はシェイクスピア自身が書いたものであると論じており、[12] イアン・ウィルソン(Ian Wilson)も同様の考えを示唆している。ウィルソンは次のように記す。
一般的な見方としては、この『原ハムレット』の作者はトマス・キッドで、彼の最大のヒット作、『スペインの悲劇』と同種の劇と考えられているが、シェイクスピアの同僚の役者ケンプ、ブライアンなどの一座が、かつて1586 年、ハムレットのエルシノア城を訪れたことを想起すれば、この古い劇を書いたのは若いシェイクスピア自身で(この旧作は存在しないが)1599年から 1600年になって全面的に改訂し、この時期の彼にふさわしい成熟した作品に仕上げたということも、キッド説と同様、十分ありうることではないだろうか。
(ウィルソン 619)
シェイクスピアは1585年の段階で、息子をHamnetと名付けている。そのことも考え合わせると、シェイクスピアがその頃から劇作品としての『ハムレット』を構想しており、『スペインの悲劇』の成功に影響されつつ劇の構想を発展させていったという可能性もあり得なくはない。[13] 一方、ウィリアム・エンプソン(William Empson)は『原ハムレット』をもとにキッドが書き上げたのが『スペインの悲劇』だったと考えている(Empson 69)。ハロルド・ジェンキンズ(Harold Jenkins)も同意見である(Jenkins 97-101)。
『原ハムレット』を書いたのが誰か、今となっては知る由もないが、いずれにせよ、『ハムレット』が、12世紀末のデンマークの歴史家で詩人のサクソ=グラマティカス(Saxo Grammaticus)が書いた年代記『デンマーク史』(Historiae Danicae)を材源としているのは間違い無い。サクソの年代記は1514年に初めて印刷され、その後フランスで、ベルフォレ(Francois de Belleforest)がフランス語に翻訳した。そのフランスでの出版が、1570年である。そしてそれが英訳されたのは、1608年なので、英訳をシェイクスピアが参照したことはあり得ない。[14] しかし、シェイクスピアが、間接的にせよ、サクソに材源を負っていることは確かだ。何故なら『ハムレット』は、その物語の大筋をサクソと共有しているからだ。言うまでもなく、『ハムレット』の材源は、『スペインの悲劇』ではなく、サクソの年代記である。そして、シェイクスピアはその年代記に、いくつかの大きな変更を加えている。以下に揚げたのは、New Cambridge版『ハムレット』の編者フィリップ・エドワーズによる、サクソの年代記から『ハムレット』に加えられた変更点のリストである。そのまま書き出してみる。
『ハムレット』に見られる最も重要な変更点は、以下の通りである。
1、殺人が秘密のものとなった。
2、亡霊がハムレットに、殺人があったことを告げ、復讐するように言う。
3、レアティーズとフォーティンブラスが登場する。
4、オフィーリアの役が大きくなり、重要なものとなった。
5、役者たちと、彼らが上演する劇が登場する。
6、ハムレットは、王を殺す時に死ぬ。(Edwards 2)
これらの改変箇所を、『スペインの悲劇』と比べてみたい。このうち、3番目と4番目は、『ハムレット』の登場人物に関するものなので除外するが、[15] それ以外の、1、2、5、6番は、全て、『スペインの悲劇』と共通する要素である。『スペインの悲劇』では、ホレイショの殺人は隠されており(1)、亡霊が登場し復讐の神に復讐を懇願し(2)、ヒエロニモやベル=インペリアたちによって演じられる劇中劇が導入され(5)、復讐者は復讐を遂げる時に死ぬ(6)。この四つの要素は、サクソの材源に加えられた改変であるが、このように全て『スペインの悲劇』に含まれている。このことを鑑みると、サクソの年代記に、『スペインの悲劇』に見られるいくつかの重要な要素が加えられたものが『ハムレット』であると、ひとまず言うことが可能だろう。
次章からの三章では、本章で指摘した、『スペインの悲劇』と『ハムレット』に見られる共通点について、「亡霊」(第三章)、「劇中劇」(第四章)、「狂気」(第五章)にそれぞれ焦点を当てて、具体的に論じたいと思う。『スペインの悲劇』と共通する要素が、『ハムレット』ではどのように扱われているのだろうか。それを比較することによって、『ハムレット』の独自性を明らかにしていきたい。
第三章 亡霊
この章では、「亡霊」に焦点を当てて、『スペインの悲劇』と『ハムレット』を具体的に比較する。『スペインの悲劇』でも『ハムレット』でも、劇の冒頭に亡霊が登場する。今幕を開けたばかりの劇は、彼ら亡霊のために果たされる復讐の過程を描いていくこととなる。つまり、物語が始まる以前に肝心な殺人行為は行われているのだ。しかし、両作品では、その復讐の性質に差異がある。『ハムレット』の場合は、ハムレットは劇の冒頭に登場する亡霊に促され、復讐に赴くことになる。しかし、『スペインの悲劇』の場合はそうではない。『スペインの悲劇』では、冒頭に登場するアンドレアの亡霊は、物語の主人公であるヒエロニモに直接働きかけることはできない。アンドレアは、自分の命を奪ったバルサザーに対する復讐を誓うが、彼は、ギリシア悲劇のコロスのように、ヒエロニモが息子ホレイショのために復讐を遂げるのを、ただ傍観していることしかできないのである。[16] 『スペインの悲劇』では、バルサザーへの二重の復讐が描かれている。アンドレアの、自らを殺害されたことに対する復讐と、ヒエロニモの、息子が殺されたことに対する復讐である。そして物語は後者の復讐を軸に進展し、前者の復讐が、物語の本筋に影響を与えることはない。アンドレアの復讐は、ヒエロニモの復讐が果たされる時に、副次的に果たされることになる。
シェイクスピアは、『ハムレット』にサクソの年代記にない亡霊を登場させたが、物語が始まる以前のこの殺人について、ある改変を行っている。前章で揚げたフィリップ・エドワーズのリストの1 番目にあるように、殺人を秘密のものにしたのである。復讐劇における復讐は、遅延させられねばならない。何故なら、復讐こそが究極的な目的である復讐劇においては、復讐が果たされれば、劇が終わってしまうからである。そのため作者は、復讐をいかに遅らせるか、ということに知恵を絞ることになる。シェイクスピアが前王ハムレットの殺害を秘密のものとしたことは、サクソの復讐物語に、ミステリーの要素を加味することとなった。『スペインの悲劇』でも、ホレイショの殺害の真相は、隠されている。これは、復讐の遅延のための知恵なのである。観客は、主人公と共に事件の真相に近づいていく。『スペインの悲劇』と『ハムレット』で、作者は、現代の推理小説と同じテクニックを用いているのだ。
そのテクニックを見てみよう。『スペインの悲劇』では、ホレイショの殺害の真相は、ヒエロニモのもとに、まず、ベル=インペリアの手紙によって告げられる。殺害されたホレイショの恋人であったベル=インペリアが、肉親の情に背いて、兄とポルトガル王子を告発し、ヒエロニモに復讐を促す。『ハムレット』においては、隠された殺人に関する最初の情報は、亡霊によってもたらされる。ハムレットは、目の前で実の父親の亡霊に事の真相を明かされ、クローディアスに復讐を果たすよう請われるのだ。しかし、用心深いヒエロニモとハムレットは、にわかにそれ(ヒエロニモはベル=インペリアからの手紙、ハムレットは亡霊の言葉)を信じることができない。そのため両者は、しばらく様子を伺うことになる。
『スペインの悲劇』において、隠された殺人が真実であったことの確信をヒエロニモにもたらすのは、ホレイショ殺害を手伝った手下ペドリンガーノが、主人のロレンゾーに宛てて書いた手紙である。手紙によって真相を知ったヒエロニモは、ベル=インペリアからの手紙が真実を告げていたことを知る。ヒエロニモは、物語の中盤を過ぎたところで、初めて復讐を心に誓うことになる。『ハムレット』の場合はどうだろうか。『ハムレット』では、ミステリーが解きあかされていく段階で、これよりももっと複雑な手続きが踏まれている。『スペインの悲劇』においてヒエロニモは、事件の真相を、手紙を受け取ることによって偶然知ることになる。それに対してハムレットは、亡霊の言っていることが正しいのか確かめるために、自ら積極的に行動に出ることになる。王の面前で、その罪を告発するような内容の劇を上演しようと試みるのである。『スペインの悲劇』では、ホレイショの殺人は、舞台上で描かれているので観客はそれを目撃しているが、『ハムレット』においては、前王の殺害は亡霊の台詞の中でしか描かれない。そのため、『ハムレット』の観客は、『スペインの悲劇』の観客と異なり、事件の真相を知ることができない。観客は、ハムレットと一緒になって、謎を解きあかしていくことになるのだ。
ヒエロニモは、ベル=インペリアからの手紙を信じることができなかったが、それは、その手紙は直接ベル=インペリアから貰ったものではなかったので、ヒエロニモを陥れるための罠である可能性があったからだ。それでは、『ハムレット』ではどうか。ハムレットが亡霊の言葉を信じることができないのは、キリスト教の教義に関わる問題である。カトリック信仰においては、幽霊は煉獄からやってくる死者の霊であると考えられる。それに対して、プロテスタントでは、幽霊は悪魔の手先と考えられる。『ハムレット』が書かれた当時のイギリスは、宗教的に不安定な時期にあった。カトリックを信奉したヘンリー七世によって開かれたテューダー朝のイギリスは、次代のヘンリー八世に到り、離婚問題をきっかけにイギリス国教会が作られ、王室はプロテスタントを奉じるようになる。しかし次代メアリ一世によって、一転、カトリックへの反動政策が急進的に押し進められ、エリザベス一世の時代に、再びプロテスタントが国教となった。『ハムレット』は、イギリスがこのような一連の宗教的な混乱を、ようやくくぐり抜けた時代に書かれた作品である。もちろん、『ハムレット』の物語の舞台は12 世紀のデンマークであると設定されてはいる。しかし、12世紀には存在しなかったはずのウィッテンバーグ大学(1502年創立)が作中に登場したり、 1600年頃のロンドンの劇場の状況を反映した台詞があったりと、シェイクスピアが具体的に頭の中に思い描いていたのは彼が生きていたイギリスに近い。『ハムレット』が上演された当時のイギリスの観客にとっては、亡霊を死者の霊と見るか、悪魔の手先と見るかといった判断は、デリケートな問題を孕んでいた。そのような時代にあって、ハムレットは、亡霊が本物の父親の霊であるのか、ハムレットを陥れようとする悪魔の手先なのか、見極めることができない。この点において、『ハムレット』は、ミステリーとして高度なクオリティを誇ることになる。『アントニオの復讐』にも、ハムレットと同様に、父親の亡霊が息子を復讐へと駆り立てるために姿を現すが、アントニオは、亡霊の言うことをつゆにも疑わず、復讐へと赴く。そこでは『ハムレット』にあるようなミステリーが生成することはない。
さらに、ハムレット自身は、クローディアスが前王を殺害したという客観的な証拠を、結局、最後まで手に入れることができないのだ。『スペインの悲劇』では、亡霊が最後に登場し、復讐が果たされたことを観客の前で確認する。しかし『ハムレット』では、亡霊は居室の場以降登場しない。観客は、クローディアスが自らの罪を告白するのを聞いているので、クローディアスの罪を疑うことはないが、ハムレット自身は、「ねずみ取り」の上演の際、クローディアスが慌ただしく席を立ったという事以外、クローディアスの罪を確信する客観的な証拠を得ることはない。『ハムレット』の最後に亡霊が登場しないことは、『ハムレット』が持つ、ミステリーとしての効果を高めることに貢献している。
シェイクスピアは、『スペインの悲劇』でコロス的な役割を演じていたに過ぎなかった亡霊を直接物語に絡ませて、高度なミステリーをつくり出した。その結果、『スペインの悲劇』のヒエロニモに比べて、ハムレットの逡巡が、遥かにスリリングなものになったと言えるだろう。
第四章 劇中劇
本章では「劇中劇」を中心に、引き続き両作品の比較を試みたい。『スペインの悲劇』と『ハムレット』に登場する二人の復讐者、ヒエロニモとハムレットは、ともに芝居好きな人物として描かれている。ヒエロニモは、若い時分に劇を書いていたと言う。「私は若いころ一所懸命、ものにもならない詩劇を書きましてね。」(キッド 49)ハムレットは、旅回りの役者たちの前で、演劇論をぶってみたり台詞を暗唱してみせたりする(第2幕第2場、第3幕第2場)。そして二人とも、復讐の目的のために芝居の上演を企画する。ただ上演するだけではない。二人とも、芝居の台本の作成に関わっているのだ。ヒエロニモが上演する劇は、昔、ヒエロニモ自身が書いた悲劇であり、ハムレットは、上演する芝居「ねずみ取り」に、自分が考えた台詞を十五、六行、付け加えるように言う(第2幕第2場531行)。このような劇中劇の導入は、この二つの作品に、複雑な劇構造をもたらすこととなった。
その構造を『スペインの悲劇』から見ていきたい。『スペインの悲劇』では、冒頭に亡霊のコロスが登場し、劇中で展開されていく出来事を、亡霊が観客と共に見守っていくというフレームが示される。これから物語の中で展開される出来事を、亡霊たちが見、さらにそれを観客が見ることになる。そして、劇の最後にも亡霊たちが登場し、彼らが物語の幕を引く。『スペインの悲劇』は、劇全体が、亡霊のコロスの視点という大枠の中に、すっぽりと収まっている。亡霊たちは、最初と最後だけでなく、劇の合間にも度々登場し、そのフレームを確認する。
そのような入れ子構造の中に、終幕、ヒエロニモが劇を上演することによって、さらにもう一つの入れ子構造が加えられる。劇中劇の登場人物たち(パシャ、パーシダ、エラスタス、ソリマン)がいて、それをヒエロニモたちが演じている。そしてその演技を、スペイン王たちが見ていて、その光景を見守る亡霊たちがいて、さらに私たち観客がそれを観ているのである。
劇中劇の登場人物(パシャ、パーシダ、エラスタス、ソリマン)
↑
ヒエロニモ、ベル=インペリア、ロレンゾー、バルサザー (act)
↑
スペイン王、ポルトガル王たち (see)
↑
アンドレアの亡霊、復讐の霊 (see)
↑
観客 (see)
劇中劇の中で復讐を遂げたヒエロニモは、最後、観客であるスペイン王たちに向かって語りかける。
皆さん方はたぶん、いまの芝居はただの絵空ごとだ、俳優たちもふつうの悲劇役者と同じことをしただけだと、お考えでしょう。(中略)すぐまた息を吹き返して立ち上がり、あすの観客を楽しませるのだ、と。でもいま、それはあてはまらないのです。ちがうのです、王様方。
(キッド 48)
確かに、劇中劇の芝居を演じる、バルサザーやロレンゾーやベル=インペリアという役の人物たちは、物語の中では本当に死ぬ。しかし、もちろん、彼らは俳優によって演じられているのである。そして当然ながら、これらの人物を演じる俳優たちは、本当に死ぬわけではない。つまり、ヒエロニモたちが使う剣は、彼らが属する劇の次元では本物の剣であるが、観客が属している現実世界の次元では、舞台上の小道具に過ぎない。喜志哲雄は以下のように記す。
よほど血のめぐりの悪い観客でなければ、ハイエローニモーの台詞は芝居の嘘にわざと観客の注意を引きつける効果をもっていることを悟るに違いない。これは、あることを語りながら、同時にそれが虚偽であることを認めている台詞なのである。(喜志 24)
氏は、『スペインの悲劇』にこのような劇構造が取り入れられたことによって、芝居の嘘が強調される結果になったと指摘する。このことは、これが、舞台上で初めて殺人が描かれた劇であることと、関係があるように思える。『スペインの悲劇』は、ローレンス・スターン(Laurence Sterne, 1713-68)の『トリストラム・シャンディ』(The Life and Opinions of Tristram Shandy, 1759 -67)のように、それが語られているメディアそのものに強く意識的な芝居である。スターンが『トリストラム・シャンディ』を書いたのは、イギリスの近代小説がようやく完成した頃である。『スペインの悲劇』は、イギリス中世の聖史劇、道徳劇の時代を経て、ようやく演劇が大衆のものとなった時期に書かれた。ある表現手段の黎明期にそのメディアに自覚的な作品が登場するということは興味深い。いずれにせよ、この劇は舞台上で殺人を描く初めての作品だったため、キッドは、芝居というメディアに対して、極度に意識的にならざるを得なかったのではないだろうか。
では、『ハムレット』でシェイクスピアは、どのように劇中劇を使用しているのだろう。もうキッドと同じ手は使えまい。シェイクスピアは『ハムレット』で、『スペインの悲劇』の応用/発展型ともいえる劇中劇の使い方をしている。だが、『ハムレット』の劇中劇の場面を見る前に、ここで『ハムレット』第2 幕第2場443-509行の、旅回りの役者たちがトロイ落城の台詞を語る場面を見たい。役者たちがエルシノア城に到着して、ハムレットの前にやってくる。ハムレットは、彼が気に入っているアイネーアスがダイドーに語る、トロイア陥落の場面の台詞を暗唱し始める。そしてその途中で、台詞は役者1に引き継がれる。ハリー・レヴィン(Harry Levin)は、The Question of Hamletの中の一章で、このハムレットと役者が語る台詞を細かく分析している(Levin 138-164)。その中でレヴィンは、この語りが持つ、複雑な入れ子構造について触れている。『ハムレット』では、劇中劇の場だけでなく、ここでも複雑な入れ子構造が使用されている。順番に見ていきたい。まず、父アキレウスの仇を討とうと、トロイア王プライアムに斬り掛かる復讐者ピラスがいる。そしてその戦いをプライアムの妻ヘキュバが見ている。さらに、それを天上から神々が見下ろしている。そのことをアイネーアスがダイドーに語っているのである。そして、その語りを、ハムレットと役者が語っており、その光景を、ポローニアスをはじめとした周りにいる者たちが見ている。そして最後に、それを私たち観客が見ているのだ。図にすると以下のようになる。
ピラス→プライアム(kill)
↑
ヘキュバ(see)
↑
神々(see)
↑
アイネーアス→ダイドー(narrate)
↑
ハムレットと役者1(act)
↑
ポローニアスたち(see)
↑
観客(see)
このように、この語りは複雑な入れ子構造を持っているが、それは、次に見る劇中劇の場面にも当てはまる。同様に、順を追って説明したい。まず、劇中劇の中の登場人物たち、王と王妃、ルシアーナスがいる。そして、その役を演じている旅回りの役者たちがいる。そしてこの場に招かれ、観劇しているクローディアスとガートルードがおり、ハムレットは、その二人が芝居を観る様を観察している。そして、それだけに留まらず、後ろの陰で、ハムレットに頼まれたホレイショが、それを見張っている。さらには、この場面には登場しないが、プライアムに斬り掛かるピラスを神々が見ていたのと同様に、ハムレットの父親の亡霊がこの場を煉獄から見ているかもしれない。そしてそれを、私たち観客が観ているのだ。まとめると以下のようになる。
劇中劇
↑
役者たち (act)
↑
王と王妃 (see)
↑
ハムレット (see)
↑
ホレイショ (see)
↑
亡霊 (see)
↑
観客 (see)
『ハムレット』の劇中劇は、入れ子構造としてはトロイ落城の語り(player’s speech)ほど複雑ではない。だが、この劇中劇をさらに複雑なものにしているもう一つの要素がある。それは、場面の焦点の問題である。『スペインの悲劇』の劇中劇の場では、場面の焦点、つまり、観客が一番意識を向けている場所は、ヒエロニモたちが演じている劇中劇の舞台上にあった。その光景を傍観しているスペイン王たちや、亡霊たちに観客の意識が集中することはない。また、先のplayer’s speechにおいても、途中、ポローニアスやハムレットが言葉を差し挟むことはあるが、場面の焦点は、あくまで台詞を語っているハムレットや、役者にある。この場面で観客は、台詞を語っているハムレットや役者に意識を集中しているはずだ。ところが、『ハムレット』の劇中劇の場では、場面の焦点は、実は劇中劇の舞台上にはない。観客の意識が集中するのは、演じられている劇中劇の舞台上ではなく、むしろ、それを観ている王と王妃であり、二人を観察しているハムレットの方である。シェイクスピアもそのための工夫をしているように思われる。ここで演じられている劇中劇の王と王妃の台詞では、観客の意識を強く引くような表現は、故意に避けられている。古めかしい擬古文で語られており、語られている内容には、特別、目を引くようなアクションもない。ここでは、明らかに劇中劇より、それを観ているハムレットたちの方に焦点がある。
キッドは『スペインの悲劇』のクライマックスにおいて、演劇というメディアそのものを吟味し直すような、先鋭的な劇中劇を使用した。シェイクスピアは物語の中盤で、観客の焦点を「ねずみ取り」の劇そのものから、それを観る登場人物たちへとずらすことによって、劇中劇を背景的に用いた。『ハムレット』におけるこのような劇中劇の使用は、『スペインの悲劇』がなかったら存在し得なかっただろう。シェイクスピアは『ハムレット』において、『スペインの悲劇』の劇中劇の場で学んだものを、応用/発展させたと言えるのではないか。前章と本章で扱った「亡霊」、「劇中劇」という二つの要素は、サクソの年代記には見られないものである。シェイクスピアは「亡霊」と「劇中劇」という二つの大きな道具立てを、『スペインの悲劇』から継承しながらも、大きく発展させて、独自のものとしたのである。
第五章 狂気
本章では『ハムレット』と『スペインの悲劇』の共通点のうち、「狂気」について考察したい。ヒエロニモとハムレットは共に復讐者であり、復讐に至る過程で狂気を装うことになる。だが何も復讐劇における狂気は『スペインの悲劇』と『ハムレット』に限った話ではない。『タイタス・アンドロニカス』のタイタスや『アントニオの復讐』のアントニオも、同様に狂気を装う。狂気には、悪の犠牲者としての、また同時に悪の告発者としてのイメージがある。主人公の怒りが狂気として発現するのだ。狂気は、セネカの劇にも見られる、古典的ともいえる復讐者のイメージである。『ハムレット』の材源となったサクソの物語でも、アムレスは、狂気を装う。
そして彼は偽りの愚かさを装い、知性が完全に欠けている振りをした。この狡猾な策略は、彼の知性を隠しただけでなく、彼の身の安全を確保することにもなった。(Saxo 103)
復讐劇の主人公たちは、何故、狂気を身に纏わなくてはならないのだろうか。もちろんそれは、復讐を達成するために相手を油断させるための一つの手段である。しかし、ハムレットとヒエロニモには、狂気を演じているという範囲を超えて、本物の狂気に取り付かれてしまったと思えるようなところがある。それは例えば、次のような箇所である。『スペインの悲劇』における、ヒエロニモが、息子を失った老人を失った息子ホレイショと間違える場面や(第3幕第13場)、『ハムレット』における居室の場で、ハムレットが、ガートルードに詰め寄り、ポローニアスを刺し殺し、亡霊を見るような箇所である(第3幕第4場)。
二人は何故、狂気の縁にまで向かわなくてはならなかったのだろうか。さらには何故、復讐者は伝統的に狂気を纏うことになるのか。そのことについて考えるにあたって、アリストテレスによる悲劇の定義について見ておきたい。アリストテレスは『詩学』の中で、悲劇を次のように定義している。
悲劇とは、一定の大きさをそなえ完結した高貴な行為、の再現(ミメーシス)であり、快い効果をあたえる言葉を使用し、しかも作品の部分部分によってそれぞれの媒体を別々に用い、叙述によってではなく、行為する人物たちによっておこなわれ、あわれみとおそれを通じて、そのような感情の浄化(カタルシス)を達成するものである。
(アリストテレース 34)
アリストテレスによれば、悲劇とは、一定の大きさをそなえ完結した「高貴な」行為の再現でなくてはならない。復讐劇においては、この「高貴な」という箇所が問題を孕むことになる。ハムレットは、そしてヒエロニモは、果たして高貴であるといえるのだろうか。
西欧において復讐者とは、本来的に犯罪者と同義である。何故なら、キリスト教では復讐は認められていないからだ。聖書「ローマの信徒への手紙」第12章第19節には、次のようにある。
愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。「『復讐はわたしのすること、わたしが報復する』と主は言われる」
復讐劇の主人公は、それをアリストテレスが言うような悲劇として成立させるためには、高貴な状態を保ったまま、復讐を成し遂げなければならないという、二律背反した課題を背負うことになるのだ。[17] シェイクスピアとキッドがアリストテレスを気にしていたと言うつもりはないが、復讐劇の主人公が伝統的に狂気を纏ってきたのは、ひとつには主人公である復讐者に、悲劇の主人公としての高貴さが必要だったからではないか。悲劇の主人公としての高貴さを幾分かでも保つためには、狂気が必要だったのだ。つまり、気が狂っていれば、それは本人の理性とは関係のない行為ということになるので、悪の行為が容認される素地を作ることになるのだ。もちろん、エリザベス朝演劇には、『リチャード三世』や、『タンバレイン大王』といった、悪人を悪人として描いて観客を楽しませる劇は存在した。しかし、復讐劇における悪人は、復讐される者としてすでに存在している(例えば、クローディアスや、ロレンゾー、バルサザーなど)。復讐者は、復讐を達成するまでは犯罪者ではない。悪に立ち向かう正義が、復讐を達成する瞬間に悪人になるのだ。その時に観客の共感を引き離さないためには、工夫が必要になる。
『ハムレット』にも、そのような、復讐者=犯罪者となるハムレットから、観客の共感を引き離さないようにする作者の意図を垣間見ることができる。『ハムレット』には、ハムレットが悪の側に近付く瞬間がいくつかある。それは例えば、次のような箇所である。ハムレットは第五独白で次のように言う。
夜もふけた、いまこそ魔女どもがうごめき出し、
墓が口を開いて地獄の毒気をこの世に吹きこむ時刻。
いまならおれも人の生き血をすすり、昼日中には
目にするだけでふるえおののくような残忍な所業を
やってのけることもできよう。(第3幕第2場349-353行)
もうひとつの例は、クローディアスが自らの罪を告白する祈りの場で語られる第六独白からのものである。その独白の中でハムレットは、クローディアスをきちんと地獄にたたき落とすために、今は復讐するのをやめておこうと言う。
やつが飲んだくれて
眠りほうけるときもあろう、怒りにわれを失うとき、
あるいは邪淫の床に快楽をむさぼるときもあろう、
賭博にふけるとき、ののしりあうとき、いつでもいい、
救いようのない罪業にうつつを抜かすときこそ
やつを突き落としてやる、その踵が天を蹴り、
その魂が地獄へとまっさかさま、たちまち地獄の
どす黒さに染まるように。(第3幕第3場89-95行)
この独白は、ジョンソン博士(Samuel Johnson, 1709-1784)をはじめとする18世紀の批評家たちに、「恐ろしすぎて、読むのも口にするのも憚られる」と、衝撃を与えたらしい(野島 191)。これら二つの独白は「ネズミ取り」の成功によって、ハムレットが強い興奮状態にある時に語られるものだ。ワトソンは、ここには「示唆に富むパターン」があるという。「ハムレットが自らを復讐者であると明確に認識する際には、シェイクスピアは彼を何らかの感情的な緊張状態に置いている」という(ワトソン 70)。ポローニアスの刺殺についても同様のことが言える。居室の場において、ハムレットは明らかに冷静さを失っている。シェイクスピアは、ハムレットの冷静さを失わせ狂気に近付けることによって、ハムレットから悲劇の主人公に足る高貴さを完全に失わせてしまわないように気を配っている。
このように狂気の縁に追い詰められながら、復讐劇における復讐者たちは、最終的に見事に復讐を果たす。復讐劇の主人公たちは復讐を遂げて、ついには犯罪者となる。そして、死を迎える。復讐劇が悲劇としての「高貴さ」を獲得するために、復讐者は、復讐が達成された暁には必然的に死ななければならないのだ。
ここで、ヒエロニモとハムレットの、復讐から死に至る過程を検証してみたい。ハムレットは、フェンシングの試合でレアティーズの毒を塗られた剣に傷ついた後、その剣でクローディアスを刺し、突発的に復讐を果たす。まさに激情にかられた形で。それに対しヒエロニモは、冷静に計画を練り、その計画通りに復讐を達成する。その計画は、狂気とは対極にある理性によって生み出されたものだ。そしてヒエロニモは、劇中劇によって復讐を遂げた後、カスティールを刺し殺し、その後、自らの手によって命を断つ。ヒエロニモはこのように、復讐を遂げた後にもさらに罪を重ねるのだ。カスティールは一見罪のないように見えるし、[18] 自殺もまた神に禁じられた行為である。二人を比較してみると、観客の目にはハムレットの方が高貴さをとどめているように映るはずだ。
『スペインの悲劇』以外の復讐劇における復讐者たちと比較してみても、ハムレットの方が、相対的に高貴さをとどめているといえる。『アントニオの復讐』や『タイタス・アンドロニカス』では、復讐者が、その復讐の一環として相手の子を殺している。特にアントニオは、罪の無い子供を亡霊に言われるがままに殺していて、その残虐な行為は高貴さとはほど遠い。おまけにアントニオは、復讐を遂げた後で死ぬこともない。突発的に復讐を果たした瞬間に死を遂げるハムレットの方が遥かに高貴に見え、その分、『ハムレット』は、アリストテレスが理想とする悲劇に近いと言える。
だがそれは、復讐者に限らない。『ハムレット』では、復讐される者にまでいくらかの「高貴さ」が付与されているのだ。復讐される者、つまりは悪人であるクローディアスは、自分の罪を罪として認識している。クローディアスは、自らが犯した罪が邪悪なものであることを傍白によって語る。
いまのことば、おれの良心をきびしく鞭うつわ!
きれいに化粧された娼婦の顔は、化粧がきれいなのであって
実は醜い、だがそれ以上だ、美しいことばで
飾り立てられたおれの行為の醜さは。
ああ、なんという重荷!(第3幕第1場50-54行)
また、祈りの場で、クローディアスは、自らの罪を語る。
おお、この罪の悪臭、天にも達しよう。
人類最初の罪、兄弟殺しを犯したこの身、
どうしていまさら祈ることができよう。
祈りたいと思う心はいくら強くとも、
それを上まわる罪の重さに押しつぶされる。(第3幕第3場36-40行)
無論、これは真の悔悛ではない。何故ならクローディアスは、ハムレットの独白の後、この場の最後で、自らの祈りが心を伴わないものであったことを告白しているからだ(第3 幕第3場97-8行)。だが紛れもなく、クローディアスは良心の呵責に苦しんでいる。このように『ハムレット』には、悪人の中にある善の側面までもが描かれているのだ。それに対して、『スペインの悲劇』のロレンゾーもバルサザーも、決して反省することはない。『タイタス・アンドロニカス』には、アーロンを筆頭に、タモーラやサターナイナス、残酷なタモーラの息子たちディミートリアスとカイロン等、悪の権化といった役柄が多数登場するが、彼らは決して自らの罪を省みることはない。さらに復讐者タイタスも、劇の冒頭でタモーラの子供を生け贄として殺し、自分に逆らった息子ミューシャスを自ら剣で刺し殺しているが、それに対する反省の色を見せることはない。『アントニオの復讐』におけるピエーロも同様である。彼は、全く同情の余地のない、悪の化身のように描かれている。そのような人間味のない悪党たちによる残虐な行為は、観客の感情移入を妨げることになり得る。もちろん打倒さるべき悪党に観客が感情移入する必要などないのかもしれないが、何はともあれ、『ハムレット』のクローディアスには観客が共感する幾許かの余地がある。クローディアスは間違いなく、他の復讐劇の悪役に比べて、遥かに人間的に描かれている。エリオット(Thomas Stearns Eliot, 1888-1965)は、クローディアスに見られるそのような人間性を評価している。[19] 『スペインの悲劇』におけるキッドの人間観察は、ここまでの深みには到達していない。『ハムレット』が『スペインの悲劇』に比べて圧倒的に上演されている最大の理由は、このような人間観察の複雑さにあるのだと思う。
結論
第一章では、『ハムレット』が書かれるに到るイギリス演劇史の流れを、復讐劇という視点から概観した。エリザベス朝時代のイギリスでは、16 世紀後半から、セネカの影響を受けて復讐劇が書かれるようになった。『スペインの悲劇』は、それまで舞台上で描かれることのなかった殺人を直接観客の目の前で描いた、当時としては画期的な芝居だった。『ハムレット』でも『スペインの悲劇』同様、殺人は舞台上で行われる。そのような芝居の先行作品の数が少ないことから、『ハムレット』は、恐らく『スペインの悲劇』の直接的な影響下にある。シェイクスピアは『ハムレット』で、『スペインの悲劇』で切り開かれた新しい芝居のスタイルを継承し、発展させた。1587年頃に『スペインの悲劇』が初演されてから、1600-1年に『ハムレット』が初演されるまでの16 世紀末の十数年の間に、その後17世紀に多く書かれることになる「復讐悲劇」の型が作られたのである。
第二章では、まず『ハムレット』と『スペインの悲劇』の共通点を列挙した。それから、『ハムレット』の材源であるサクソの年代記に、シェイクスピアが新たに付け足した要素を示した。材源には無い、シェイクスピアが新たに『ハムレット』に付け加えた、「劇中劇」、「亡霊」、「殺人が秘密にされていること」などといった要素は、その重要なものの多くが『スペインの悲劇』に含まれている。従って、サクソの年代記に、『スペインの悲劇』に含まれているいくつかの重要な要素を加えたものが『ハムレット』であると言うことが可能である。
第三章から第五章にかけては、『ハムレット』と『スペインの悲劇』を具体的に三つの共通点に焦点を当てて比較することにより、『ハムレット』の独自性を明らかにしようとした。第三章では、「亡霊」について考察した。シェイクスピアは『ハムレット』で、『スペインの悲劇』でコロス的な役割を演じていたに過ぎなかった亡霊を直接物語に絡ませることによって、より豊かな物語を作り出してみせた。また、サクソの年代記では先王の殺害は公のものとなっていたのに対して、『ハムレット』では先王ハムレットの殺害が隠されたものとなり、物語にミステリーの要素が加味されることになった。さらにそのミステリーは、亡霊に対するキリスト教の教義の問題と結びついたことによって、一層高度なものとなった。
第四章では、両作品で使用されている「劇中劇」の構造についてそれぞれ例を示し、分析した。キッドは『スペインの悲劇』で劇というメディアそのものを吟味し直すようなやり方で劇中劇を使用した。それに対して、シェイクスピアクスイクスピアは、『スペインの悲劇』で学んだについてそれぞれ分析は、観客の焦点を上演されている劇中劇からそれを観ている登場人物たちへずらすことによって、劇中劇を場面の背景として使用した。シェイクスピアは、『スペインの悲劇』があったからこそ、このような劇中劇の使い方ができたのではないか。『ハムレット』の劇中劇の場は、『スペインの悲劇』の応用/発展型と言えるだろう。第三章と第四章で扱った「亡霊」、「劇中劇」という二つの要素は、サクソの年代記には見られないものである。この二章による分析から、シェイクスピアは「亡霊」と「劇中劇」という二つの大きな道具立てを『スペインの悲劇』から継承しながらも、大きく発展させて、独自のものとしていることが分かる。
第五章で扱ったのは、「狂気」である。「狂気」は、サクソやベルフォレの材源に見られる要素であるのみならず、セネカの悲劇、さらに、同時代の他の復讐劇、『アントニオの復讐』、『タイタス・アンドロニカス』でも用いられている要素であり、復讐劇というジャンルと密接に結びついた問題である。本章では、復讐劇をアリストテレスが理想とする悲劇の必要条件であるミメーシス(一定の大きさをそなえ完結した高貴な行為の再現)に近付けるために、狂気が欠くべからざる要素であることについて考察した。そして、ヒエロニモよりもハムレットの方が、アリストテレスが理想としている悲劇の主人公に相応しいと論じた。さらにその「高貴さ」は、シェイクスピアの『ハムレット』では悪人にまで付与されており、その人間観察の複雑さによって、『ハムレット』は復讐劇という一ジャンルを超越し得たのだと結論づけた。
これら三つの視点からの分析により、私の中で、『ハムレット』という作品が他の復讐劇に比べて現在も広く上演され続けている理由がかなり鮮明になった。その最も重要な理由は、第五章で扱ったように、人間の描き方にある。『スペインの悲劇』を含め、同時代の復讐劇における人間観察は、『ハムレット』ほどの深みには到達していない。16世紀フランスの人文主義者モンテーニュ(Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592)は、その著作『随想録』(Essais, 1580-1588)の中で、人間は本来的に、様々の相反する要素を同時に抱えた存在で、刻々と変わり行く存在であるとくり返し説いているが、シェイクスピアは『ハムレット』の登場人物を、まさにそのような者として描いた。[20] そのことは、『ハムレット』という作品の全体像を捕らえ難いものにしたかもしれない。だが、それによって『ハムレット』は、以後作られることになるあまたある復讐劇を突き放し、イギリス演劇史のみならず、世界文学の中で、特別な地位を獲得するに至ったのだ。
『スペインの悲劇』から『ハムレット』に到る16 世紀最後の十数年間に確立した「復讐悲劇」の伝統は、この後シリル・ターナーやジョン・ウェブスターといった劇作家たちに受け継がれ、1642年にロンドンの全ての劇場が閉鎖されるまで、隆盛を誇ることになる。その中にあって『ハムレット』は、「復讐悲劇」というジャンルを切り開いた作品であったと同時に、ジャンルを越えた作品となった。
引用文献
アリストテレース・ホラーティウス 『詩学・詩論』 松本 仁助・岡道男 訳
東京: 岩波書店 1997.
Bloom, Harold. Shakespeare: The Invention of the Human. New York:
Riverhead Books, 1998.
Edwards, Philip. Introduction. The New Cambridge Shakespeare: Hamlet,
Prince of Denmark: Updated Edition. By William Shakespeare. Ed.
Philip Edwards. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 1-82.
Empson, William. ‘The Spanish Tragedy’ Elizabethan Drama. Ed. Ralph J.
Kaufmann. London: Oxford University Press, 1961.
Erne, Lukas. Beyond the Spanish Tragedy: A Study of the Works of
Thomas Kyd. Manchester and New York: Manchester University Press,
2001.
Farley-Hills, David, ed. Critical Responses to Hamlet 1600-1790. New
York: AMS Press, 1997.
Jenkins, Harold. Introduction. The Arden Edition of the Works of William
Shakespeare: Hamlet. By William Shakespeare. Ed.Harold Jenkins.
London: Thomson Learning, 1982. 1-159.
河合 祥一郎 「復讐」 『シェイクスピア・ハンドブック』 高橋康也 編
東京: 新書館 1994. 148.
喜志 哲雄 『英米演劇入門』 東京: 研究社 2003.
トマス・キッド 『スペインの悲劇』 村上 淑郎 訳 『エリザベス朝演劇集』
小津 次郎・小田島 雄志 編 東京: 筑摩書房 1974. 5-52.
共同訳聖書実行委員会 『聖書 新共同訳』 東京: 日本聖書教会 1987.
Levin, Harry. The Question of Hamlet. New York: Oxford University Press,
1959.
村上 淑郎 著者代表 『エリザベス朝演劇 —小津次郎先生追悼論文集—』
東京: 英宝社 1991.
中村 哲子 「総論2. インタールードの主題と特色」 『イギリス中世・
チューダー朝演劇事典』 松田 隆美 編 東京: 慶應義塾大学出版会
1998. 115-132
野崎 睦美 解説 『タイタス・アンドロニカス』 ウィリアム・シェイクス
ピア 作 小田島 雄志 訳 東京: 白水社 1983.181-194.
野島 秀勝 脚注 『ハムレット シェイクスピア作』 ウィリアム・シェイ
クスピア 作 野島 秀勝 訳 東京: 岩波書店 2002. 11-325.
奥田 宏子 「67. 『ホレステス』 Horestes」 『イギリス中世・チューダー
朝演劇事典』 松田 隆美 編 東京: 慶應義塾大学出版会 1998.
オウィディウス 『変身物語(上)』 中村 善也 訳 東京: 岩波書店 1981.
佐野 隆弥 「『スペインの悲劇』一五九二から一六〇二年へ」 『エリザベス
朝の復讐悲劇』 石田 久 著者代表 東京: 英宝社 1997. 3-27.
Saxo Gramaticus. “Hamlet from the Historia Dania.” Trans. Oliver Elton.
The Sources of Hamlet. Ed. Sir Israel Gollancz. London: Frank Cass
and Company Limited, 1967. 93-163.
高橋 康也・河合 祥一郎 解説 『大修館シェイクスピア双書 ハムレット』
ウィリアム・シェイクスピア 作 東京: 大修館書店 2001. 3-53.
G. J. ワトソン 『演劇概論—ソフォクレスからピンターまで』 佐久間 康夫
訳 東京: 北星堂書店 1990.
イアン・ウィルソン 『シェイクスピアの謎を解く』 安西 徹雄訳 東京:
河出書房 2000.
[1] 『タイタス・アンドロニカス』のもうひとつの種本として考えられているのが、オウィディウス(Ovidius, 43 BC-AD 17)の『変身物語』(Metamorphoses, AD 8)第六巻の中の、『テレウスとプロクネとピロメラ』である。これは、妹ピロメラを夫テレウスに陵辱されたプロクネが、その復讐として、自分と夫との間の子を殺害し、夫に食べさせるという話である。(オウィディウス 241-254)シェイクスピアは、『変身物語』の中の多くのエピソードを、自作の中でモチーフとして使っている。
[2] 作者はトマス・ノートン(Thomas Norton, 1532-84)とトマス・サックヴィル(Thomas Sackville, 1536-1608)。
[3] 『ホレステス』はセネカを種本としてはいるが、ローマを題材にした他のセネカ風の悲劇と異なり、ギリシャから素材をとっていて、喜劇仕立てとなっている(奥田 306)。
[4]ルーカス・アーン(Lukas Erne)は、最新の『スペインの悲劇』の研究書、Beyond the Spanish Tragedy (2001)の中で、『スペインの悲劇』の初演は、1587年が有力としている(Erne 58)。
[5]アーンはBeyond the Spanish Tragedyにおいて、マーロウの『タンバレイン大王』と、『マルタ島のユダヤ人』に、キッドの影響を見ることができると記している(Erne 58)。これは、二人が共同で生活していたということを考えると、当然であろう。
[6]『タイタス・アンドロニカス』の初演がいつかは分かっていない。1594 年に第1四つ折り本が出版されたが、1592年から94年にかけて、イギリスでは疫病が猛威を振るい、ロンドンの劇場は閉鎖された。そのため、初演はそれ以前の1590年前後と考えられる。この作品も『スペインの悲劇』同様、人気を博したようだ(野崎 182-185)。
[7] 『ハムレット』と『アントニオの復讐』は、どちらが先行作か、議論が分かれている。『アントニオの復讐』の影響下に『ハムレット』が書かれたとする説と、『ハムレット』影響下に『アントニオの復讐』が書かれたとする説がある。New Cambridge版の編者フィリップ・エドワーズ(Philip Edwards)は、『ハムレット』が先行すると考えている(Edwards 7)。
[8] 『ハムレット』の初演の年代については諸説ある。第2幕第2場にある劇場戦争への言及から、従来は1601年とする説が有力であったが、最近の研究では1600年とする説もある(高橋 21-26)。
[9] 例えばG・J・ワトソン(G. J. Watson)は、「当時極端に人気を博していたジャンルである復讐劇の伝統」とか、「『ハムレット』が復讐劇の慣行を利用しているのは事実だが」などと記している(ワトソン 68)。
[10]リチャード・バーベッジ(Richard Burbage, ca.1570-1619)の死に捧げられた哀歌から、ハムレットと『スペインの悲劇』の主役ヒエロニモは、バーベッジによって演じられたことが分かる(Farley-Hills 9)。そのことは、ハムレットとヒエロニモには、共通する要素があるということを示してはいまいか。
[11] 『アントニオの復讐』、『マルタ島のユダヤ人』は、復讐劇でありながらも、主人公は死なない。尚、ハムレットの材源であるサクソの物語でも、ハムレットは復讐を果たした後も長い間生き続ける。ここでは、「復讐劇」と「復讐悲劇」を分けて考えている。『ハムレット』以前に書かれた「復讐悲劇」ということになると、『スペインの悲劇』と『タイタス・アンドロニカス』くらいしかない。その後書かれた「復讐悲劇」としては、『復讐者の悲劇』(Revenger’s Tragedy)、『モルフィ公爵夫人』(The Duchess of Malfi, 1612-14)などがある。
[12] ハロルド・ブルームは次のように記す。「私は、シェイクスピアは、1587-89年頃の初期の版から、ストラトフォードに引退する頃まで、『ハムレット』を書き直し続けたのだと考えている」。(Bloom 391)
[13] 『原ハムレット』が、シェイクスピアが書いたものであるとすると、『ハムレット』について触れられている最も古い記録が1589年のものなので、シェイクスピアの劇作活動、最初期の習作であると考えられる。
[14] ハムレットの物語を収めたベルフォレの『悲話集』(Histoires Tragiques, 1570)が、1608年以前に英訳されていたと主張する研究者もいる。
[15] リストの4番目の、オフィーリアのキャラクターの拡大は、『スペインの悲劇』に見られる、ホレイショと、ベル=インペリアの禁じられた恋のモチーフの『ハムレット』への導入と言えないこともない。
[16]クリストファー・マーロウの『マルタ島のユダヤ人』でも、冒頭にマキャベリの亡霊が登場する。亡霊は、権謀術数を用いて金をかき集めているユダヤ人の悲劇をこれからお目にかけるという序詞を述べて退場する。亡霊は、以後、登場せず、物語には関わらない。
[17]後年のシリル・ターナーの『無神論者の悲劇』(The Atheist’s Tragedy, 1611)では、亡霊は主人公に復讐をしないように命じる。「フランスへ帰れ、お前の老いた父親は死に、お前は殺人により灰嫡されたのだ。忍耐を持ち事の成就を持て、復讐は王の王たる神に任せよ」『ハムレット』や、『アントニオの復讐』で描かれた亡霊のイメージを逆手に取った設定といえよう。
[18] 村上淑郎はカスティールを刺し殺すことは不自然ではないと、ヒエロニモの心情を擁護している(村上 21)。
[19]志賀直哉も、人間的なクローディアスに感情移入したからこそ、『クローディアスの日記』を書いたのだろう。
[20] シェイクスピアはモンテーニュの『随想録』の一節を、『テンペスト』の中で借用している。そのことから、シェイクスピアがモンテーニュを読んでいたことは、「まったく疑問の余地がない」(ウィルソン 499)。ジョン・フロリオ(John Florio, 1553-1625)の手になる英訳が出版されたのは、『ハムレット』のQ1が出版されたのと同じ1603年である。ジョン・フロリオは、シェイクスピアのパトロンであった第三代サウサンプトン伯ヘンリー・リズリー(Henry Riseley, 1573-1624)のイタリア語の家庭教師でもあり、シェイクスピアと親しかったのではないかという説もある。『ハムレット』にモンテーニュの影響があるのかどうかは謎である。
2008/05/02/21:11
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
道化、英雄、人
—ミルトン『失楽園』のサタンについて—
米田 拓男
はじめに
ミルトンの『失楽園』に登場するサタンは、様々な受け取られ方をされてきた。サタンこそが『失楽園』における真の英雄であるという主張から、サタンは一種の道化に過ぎないという見解まで、その幅は極端なまでに広い。私自身は、『失楽園』を読み、サタンが持つ人間らしさに惹かれる。そして何故ミルトンはサタンに人間らしさを賦与したのかが気にかかる。そこで私は、本論において、今までなされてきた様々なサタンの解釈について考察し、サタンに人間らしさが賦与された理由を探ってみることにしたい。章構成は以下のようになっている。
第一章 道化か英雄か&mdash様々なサタン像—
第二章 ミルトンの分身としてのサタン
第三章 物語における悪役としてのサタン
第四章 堕落した人間の原型としてのサタン
第一章では、道化から、英雄までの幅広いサタン像について紹介する。第二章では、サタンとミルトンの主張が重なっている箇所があることから、ミルトンとサタンを同一視するサタニストの主張について考察したい。第三章では、物語においての悪の必要性について考え、サタンに崇高さが賦与された理由を探る。第四章では、サタンを堕落した人間の原型として考え、アダムとイヴと比較し、サタンの人間らしさの源泉を探り、サタンをサタンたらしめている問題について指摘する。
本論は、サタンについての様々な解釈を考察することを通じて、サタンに見られる人間らしさの理由を解明することを目的とする。
第一章 道化か英雄か&mdash様々なサタン像&mdash
ミルトンの『失楽園』に登場するサタンは、受け取り手に様々な解釈をされてきた。サタンこそが『失楽園』における真の英雄であるという主張から、サタンは一種の道化に過ぎないという見解まで、その幅は広い。これほど受け取られ方に幅があるキャラクターも珍しい。ここでは、様々な人々のサタンの解釈を見たい。
まず、サタンを英雄視する意見から見る。ウィリアム・ブレイクは、『天国と地獄との結婚』において次のように記す。
これミルトンが天使達及び神のことを叙する時活気なき理由である。
そして悪魔及び地獄の叙述の躍如たるは彼が真の詩人であり、しらず
しらず悪魔の仲間入りをしていたためである。
(ブレイク 128)[1]
ブレイクにとっては『失楽園』における天使達の描写は、退屈なものであったようだ。そして、それに反してサタンの描写は、大変に魅力的なものに映っていたらしい。ブレイクの他にも十九世紀の詩人や作家たちの中には、コールリッジやバイロン、ハズリット、シェリーなど、ミルトンのサタンを英雄視する者が多かった。パーシー・ビッシュ・シェリーにおいては、ミルトンのサタンは、道徳的にも神より優れた存在だった。
一道徳存在としてミルトンのセイタンは神より遥かに秀れている。敵
対し、苦しみながらも自らが良しと見る何らかの目的にじっと耐える
存在が、確実不動の勝利に安穏とあぐらをかきながら、敵にこの上な
く暴虐な復讐を企てる存在より秀れていて当然なのだ。この復讐は、
よく誤解されるように敵を悔い改めさせようとする意図とは無縁にし
て……敵を追いつめ、更なる苦悶を蒙らせようという公然たる意図の
もとに行われるのである。(リンク 296)
パリでは、詩人ボードレールが日記に次のように書き綴った。
私は美の、私の美の定義を発見した。それは激しく、そして悲哀に満
ちたものである。……敵対なきところに、この美は考えられない。…
…男性的なこの美の完全この上ない典型は、ミルトンが表現しようと
した魔王セイタンだと、考えざるをえないのだ。(リンク 297)
これらの記述から、ミルトンが描いたサタンに心酔する、若き詩人たちの姿を垣間見ることができる。
このようにサタンを英雄視する主張がある一方で、サタンを道化として考える見解もある。野呂有子氏は論文「道化としてのサタン、サルマシウスそしてチャールズ一世」の中で、サタンがイヴを誘惑する際、蛇に変身する前に一度、蛙になっていることに着目し、ミルトンはアリストパネスの喜劇『蛙』から道化的なイメージを継承しているのだと論じている(新井2003 60-5)。
何故、サタンの受け止められ方にはこれ程の差異が生じるのだろうか。ロマン派の詩人たちはサタンを英雄的だと言ったが、それは具体的にどの辺りを指しているのだろうか。それは、恐らく次のような箇所だ。第二巻において天上での戦いに破れた堕天使たちは、サタンを囲んで神への復讐策を模索する。そして神が造った、人間という新しい種族を堕落させることで、神に復讐を果そうということに決める。渾沌界を通って人間のいる楽園に赴くことには危険が伴う。だがサタンは、自分ひとりでやってのけようと言うのである。
わが戦友諸君、
全体にかかわる一大事として提案され決定されたことを、それが
単に困難であり危険だという理由だけで、もしわたしが敢えて
自ら引き受けないとするならば、わたしは、栄光に包まれ
武威に輝くこの王座を、そしてこの帝王としての権威を、
全く虚しくするものといわなければならぬ! (中略)
ことわっておくが、わたしは、この度のこの遠征に、余人の参加を
許さない」。こう言って、地獄の王は立ち上がり、一同に返事の
余裕を与えなかった。(第二巻 444-9、465-6)
サタンのこのような態度は、ルネサンス期に一般的であった「高い身分には義務がともなう」という考え方、’noblesse oblige’に基づいたものと見る事ができるという。(新井1980 259)そして、サタンはただ一人で旅立つ。この場面に見るサタンは確かに英雄的と言える。
サタンはつねに未来のことを考え、計画を立て、自ら率先して行動していく。神がその子に油を注いだ日に反乱を計画し、夜中に反乱軍を集結させ、神の軍勢に戦いを挑む。一日目には戦いに破れた後すぐに会議を開き大砲を作ることを提案し、彼の部下たちにすぐに仕事にかからせる。最終的に天上における戦いでは敗北し地獄に落とされることになるが、意識を回復するとすぐに神への復讐策を模索し、人間を堕落させるために楽園へと赴くのだ。藤井治彦氏は次のように記す。
セイタンは、つねに計画し、つねにその計画を行動に移す者である。
彼はつねに目標に向かって急いでいる。その姿は、それだけ切り離し
て眺めるならば、美徳を備えているように見える。セイタンは、ある
意味では、真面目なのであり、勤勉なのである。
(平井1974 280-1)
確かにサタンは、行動力に溢れ英雄的な魅力を備えている。
しかしミルトンは、果たして本当にサタンを英雄として描いたのだろうか。私はそう言い切ることに戸惑いを覚える。私がそう言い切ることができない理由は、第六巻と第十巻におけるサタンの相次ぐ敗北の描写にある。ここでのサタンの扱いは、英雄というよりは道化のそれと言った方が適切であるように思える。例えば、第六巻で描かれる天上での戦いで、サタンは、一日目には堕天使の軍勢から寝返ったアブデルを相手に強気に勝利を宣言するが、その後すぐに打ち負かされる。二日目には、ミカエルに威勢よく啖呵をきって立ち向かうが、結局、自分の方が傷付き味方の天使たちに運び去られていく。そして三日目には、神が御子を戦場へ遣わし、御子が堕天使の軍勢をもろとも地獄へと突き落とすが、この時サタンは登場さえしない。第十巻でサタンがイヴを誘惑する場面では、サタンがイヴを誘惑した後、サタンは巨竜に、堕天使たちは蛇に変身させられる。サタンの最後を描写する次の箇所は特に滑稽である。
そう言ったあと、恐らく自分の耳を聾するばかりの満堂の
喝采と賞賛の声が忽ちあがるものと思い、期待に胸をふくらませ、
暫時佇立していた。ところが、意外にも、四方八方から彼の耳を
襲ってきたものは、無数の舌、舌、舌から洩れてくる不気味な
しゅっしゅっという声であった!(第十巻 504-8)
確かにサタンは、第一巻と第二巻においては英雄的と呼ぶことはできる。しかし、『失楽園』に英雄的に登場したサタンは、最終的に道化的な扱いにまで貶められる。第六巻、十巻でのサタンの退場は、サタンの視点に立つ読者にとっては、アンチ・クライマックス的であると言わざるを得ない。もしミルトンが本当にサタンを英雄として描いていたとするなら、サタンの幕引きはこのようなものにならなかったはずだ。だが、そうかと言って、サタンが道化のバリエーションであると言い切ることも私にはできない。私はサタンを道化とも、英雄とも考えない。その両方の性質を合わせ持った、アンビバレントな存在であると考えたい。
第二章 ミルトンの分身としてのサタン
前章で、私は、サタンが道化的な要素と英雄的な要素を合わせ持ったアンビバレントな存在であると結論付けたが、私にはサタンの描写が、悪魔というにはあまりに人間的であると感じられる。それは、第六巻で傷付いたサタンが仲間に盾に乗せて運ばれていくところや、楽園にいる人間たちを羨む次のような台詞の中で強く感じる。
なんという憎むべき光景だ! なんという他人の心を
苛む光景だ! こうやって、この二人は、幸多きエデンの園の
中にありながらさらに幸多き園ともいえる、その固い抱擁の
世界に沈湎し、祝福につぐ祝福を心ゆくばかり味わうことができる。
しかるに、わたしは地獄に投げ込まれている–そこには喜悦も
愛もなく、永劫に充たされない恐ろしい欲望の苦しみが(それも
それに劣らぬ多くの責苦の一つにすぎないのだが)あるだけだ。
(第四巻 505-11)
ミルトンの描くサタンには、何故このような人間らしさが賦与されているのだろう。
サタンの人間らしさは、ことによれば、ミルトン自身に起因するのかもしれない。前章で、ブレイクが「悪魔及び地獄の叙述の躍如たるは彼が真の詩人であり、しらずしらず悪魔の仲間入りをしていたためである」と書いたことについて触れたが、ミルトンがサタンの仲間入りをしていたというのみならず、ミルトン自身とサタンを同一視する議論が存在する。つまり、サタンはミルトンの分身であるとする解釈である。だからこそ、サタンをいきいきと描写することができたのであるという訳だ。そのようにミルトンとサタンの類似に異常な関心と興味を寄せる者のことを「サタニスト」(Satanists)と呼び、その意見に反発する者を「アンティサタニスト」(anti-Satanist)と呼ぶこともあるという。(田中 100)
事実、サタンの語りの中には、ミルトンの主張と重なるように思える箇所がある。それは例えば次のような箇所だ。
座天使よ、主天使よ、権天使よ、力天使よ、しかして
能天使よ!わたしはお前たちにこのように呼びかける、ただし、
この厳めしい称号がただ単なる空しい肩書きでないとしての
話だ!というのは、神の命によって、今や或る者が
すべての権力を我が物顔に独占し、油を注がれし王という
名の下に、われわれの光彩を尽く奪い去ってしまったからだ。
(中略)我々が未だかつて
行ったこともない跪座の礼、つまり平身低頭して拝むという
あの醜悪な礼を、われわれから受けようとここへやって来る
彼を迎えるのには、どんな新しい恭啓の礼を工夫すべきかを
相談するためなのだ!一人の者に対してさえ過分の礼なのに、
況やその者と、今広く宣示されているその姿であるもう一人とに
対し、二重に拝礼するなどとはもっての他だ!
(第五巻 772-7、780-4)
William Kolbrenerは、論文’Milton’s Warring Angels’の中で、この語りでサタンは、ミルトン自身がReadie and Easie Wayで王政批判を行ったのと同じレトリックを使って、御子が天上において首位についたことを批判していると記す(Kolbrener 148)。一六六〇年に、イギリスではチャールズ二世が王位につき、十一年振りに王政が回復した。ミルトンは、キリスト教的共和国の実現を夢見ており、王政の回復には批判的な立場に立っていた。Readie and Easie Wayというのは王政批判のパンフレットであり、そのパンフレットの中の王政批判と同じレトリックをサタンが使っているというのだ。
だが、ミルトンの反君主制主義を主張する言葉と、サタンの御子に対する言葉の間には相違がある。ミルトンが提唱していたキリスト教的共和国というものは、人が人の上に立つことなどできない、ということだと理解する。つまり、人の上に立つ者は神一人で十分であると。サタンも御子の首位を批判するが、サタンの場合は、御子を引きずり降ろした後、自分が自らその座に座ろうと企んでいる。ここにサタンとミルトンの主張の決定的な相違がある。サタンはミルトンが使用したのと同じレトリックを用いているが、その本質は全く異なっている。だから私には、ミルトンとサタンの主張を同一視することはできないと思う。
それに、次のような見解もある。
『偶像破壊者』、『第一弁護論』、及び『第二弁護論』におけるミル
トンの敵対者たちの多様なイメージが『楽園の喪失』における大いな
る敵対者サタンの像に収斂している (新井2003 55)
ここで説明されていることは、先に述べたことと全く逆のことである。つまり、サタンは王政を批判するミルトン自身を反映しているのではなく、ミルトンと政治的に敵対していた相手側を反映しているというのである。こうしてみると、サタンとミルトンを同一視するのはいささか性急な議論のような気がして来る。
だが、次の主張は、一面の真実を含んでいるように思う。
この作品中のサタンや人祖の苦悩は同時にそのままこの作品執筆当時
のミルトン自身の苦悩であったと考えてよいと思う。つまりサタンや
人祖の追放を聖書の物語に則って詩化しようとした時、ミルトンはそ
の時の自分自身のエグザイル感をサタンや人祖のエグザイルの苦悩に
仮託して表現しようとした(長澤 73)
ミルトンは一六五二年に失明し、一六五八年には、結婚生活わずか十五ヶ月の妻と生後間もない女児を失うという立て続けの不幸に見舞われた。そして、一六六〇年に望んでいなかった王政が回復した。『失楽園』の出版は一六六七年だが、一六六〇年には、ミルトンはすでに口述を開始していたという。それを考えると、サタンにミルトン自身の感情が反映されているのは当然と言えば当然である。また、サタンのみならず追放の身となるアダムやイヴにも、ミルトンが心情的に託したものがあったとしてもおかしくはない。
だが、たとえミルトンがサタンに何らかの心情を仮託していたとしても、サタンは敗北する運命にあった。そして、ミルトンは実際にサタンを敗北させた。もしミルトンがサタンに自分の心情を託していたとしたら、そこには深いアイロニーが伴っていることになる。そのようなアイロニーを込めて、ミルトンはサタンを彼自身と重ね合わせていたのかも知れない。真相は知る由もないので、ここではサタンに弱さや嫉妬、苦悩といった人間的な性格が賦与されているということだけを確認して、議論を次に進めたいと思う。
第三章 物語における悪役としてのサタン
Neil ForsythはThe Satanic Epicの中で、叙事詩の古典やキリスト教の神話、プロテスタントの神学者や聖書を除けば、ミルトンのサタンに最も大きな影響を与えているものは演劇の伝統であると述べている。[2] 『失楽園』はもともと、叙事詩ではなく五幕構成の劇作品として構想されていた。それは正義、慈悲、勤勉、無知といった、寓意的な登場人物が出てくる中世の道徳劇を意識した作品だったようだ。[3] 中世の道徳劇には悪魔も頻繁に登場したようだが、その悪魔というのは「毛むくじゃらの悪魔が口に爆竹をくわえて、舞台を吠えまわる」といったようなもので、クリストファー・マーロウの『フォースタス博士』に登場する悪魔も当時、そのように演出されていたようだ。(村上 28)『失楽園』には『フォースタス博士』からの影響が指摘されている詩行がいくつかあるが、殊に悪魔の造形に限っては影響されていないようである。ミルトンは『失楽園』において、独自の悪魔像を追求したといえそうだ。『失楽園』は構想上、叙事詩となる前に一篇の劇作品であった訳だが、芝居には悪役というものが必要不可欠なものだ。『オセロー』にはイアーゴーが、『ハムレット』にはクローディアスという悪役が必要であった。悪役がその劇の成否を決めることも多い。ミルトンの創造したサタンは、劇場で観客の要求に応えることも十分にできうる、魅力を持った悪役である。
ミルトンは、そのような悪を描くことで何を伝えようとしたのだろう。その答えは第一巻の冒頭にある。
願わくば、このいと高き大いなる主題にふさわしく、
永遠の摂理を説き、神の配慮の正しきを、人々に
証明することを、私に得させ給わらんことを!(第一巻 24-6)
ミルトンはこの叙事詩で、神の配慮の正しさを描き出そうとしたのだ。だが、善を伝えるための物語にどうしてサタンが必要だったのだろうか。それは、悪が無いところでは善を描くことはできないからであるし、悪がいなければ、また、物語も生まれ得ないからである。つまり、サタンは、神の正しさを描くための必要悪だったのだ。
善という概念それ自体を、単独で表象するのは非常に困難である。何故なら、神に匹敵するような、最高の位にある善を表わすことのできる言葉を、人間は持ち合わせていないからである。そのため、善を描くためには比較対象となる悪が必要不可欠なのだ。悪によって善が知られる。もっと言えば、悪が善を規定する、と言うこともできよう。ミルトンは、善なる神を表象する必要上、サタンを表象しなくてはならなかった。神を描くためには悪魔が必要だったのである。そして、ミルトンが描き出さんとした善なる神は、人間にとって量り知れない大きさと深さを持つ、最高の位に位置する概念であった。だから、そのような大きな力を持つ神を描くためには、大きな力を持つサタンが必要だったのだ。『失楽園』におけるサタンの存在意義はそこにある。ミルトンは『失楽園』で巨大な善と悪を描こうとした。そしてその結果、善も悪も崇高な性質を帯びてしまったのだ。つまり、物語の要請で巨大な悪を描こうとしたら、悪もまた崇高なものとなってしまった。田中勉氏は、次のように記す。
(ミルトンは)人間精神に宿る絶対者、最高存在者としての神の観念
が包含する属性のことごとくに対立する邪悪をセイタンに表現しよう
としたが、あらゆる邪悪を邪悪たらしめる自己原因としての悪の実体
は、余りに大きく深くて、それを表徴するに足る概念は一つだにミル
トンの精神に存在しなかったのである。(中略)要するに、ミルトン
はキリスト者としてあらゆる悪の自己原因である悪の本体という、人
間の表徴力を越えた実体の描写を試みたために失敗したと言ってよ
い。(田中 106)
ミルトンが描くサタンに、私はそれ程邪悪な印象を受けない。確かに、田中氏が言うように、ミルトンが巨大で邪悪な悪を描くつもりでサタンを造型したのだとすれば、その試みは失敗に終わったのかもしれない。しかし、ミルトンのサタンは、悪の中に崇高さという善なる要素を兼ね備えることによって、『失楽園』という物語における一つの魅力的な登場人物となり得た。性格描写が複雑なものとなり、悪役として奥行きを備えることになった。
例えば、次のような箇所に、サタンの悪役としての複雑さが認められる。
ああ、それにしてもなぜあのようなことを? 神はあのような
仕返しをわたしから受ける謂われはなかった。わたしをあれほど
輝ける者として造り、恩恵を施しこそすれ、いささかも咎める
ことをされなかった。求められた奉仕にしろ辛くはなかった。
神に賛美を捧げることは、辛いどころか全く易々たる恩返し
であり、感謝を捧げることも全く当然なことであった!
(第四巻 43-8行)
サタンは楽園に到達し、いざ人間を堕落させて神への復讐を果たそうとする段になって、自分の行いを後悔し、このように逡巡する。サタンは、神に恩恵を与えられたことを正しく認識している。サタンは自分の過ちを認め、神に反逆したことを後悔しながらも悪を選ぶ。そして、アダムとイヴに哀れみを感じながらも、復讐のために彼らを滅ぼす決意を固める。
この二人を見ていると、
わたしの心は驚嘆の念に充たされ、ともすれば愛情さえ覚える。
それほど、神の姿が彼らの姿のうちに生き生きと輝いている、
それほど、彼らに形を与え給うた者の手がその形に美しさを
注ぎ込んでいる! ああ、気高き二人よ!(第四巻 363-7行)
これらの台詞は、悪の化身のものというには、あまりに人間的な響きを持っている。
サタンにこのような台詞を語らせることで、ミルトンのサタンは複雑さを増す。『ハムレット』のクローディアスにも自分の犯した罪を認め、自分の邪悪さを認識していることを示す独白があるが、そのような多面性を賦与することは、登場人物に奥行きを与えることになる。悪の中に善なる要素を描きこむことは、受け手に混乱や誤解を与えることにもなりかねない。だが、そのキャラクターだけに留まらず、作品自体に複雑さと奥行きを与える結果をもたらす。そして、受け手に、そのキャラクターに感情移入する余地をも与える。サタンに、崇高さや人間臭い感情が賦与されているからこそ、ブレイクやシェリー、ボードレールといった詩人たちは、サタンに感情移入したのである。
ブレイクは、西欧の絵画の伝統では獣的で醜悪な者として表現されることの多い悪魔を、どこからどう見ても人間にしか見えないような、一糸纏わぬ姿で両手を高く揚げるサタンの水彩画を描いている(図版1参照)。この絵は、ブレイクが、ミルトンが描いたサタンの本質を、さすがにサタンに共鳴したものであるだけあって、上手く捉えてみせたものであると思う。

図版1 ウィリアム・ブレイク『サタンが反逆天使に呼びかける』
ミルトンの『失楽園』のための版画下絵の水彩。(リンク 91)
第四章 堕落した人間の原型としてのサタン
これまでの章で、サタンの造形に見られる人間らしさについて様々触れてきたが、何故、サタンにそのような人間らしさが賦与されねばならなかったのだろうか。
一つには、善や悪というのは、観念だけではあまりに大きすぎて手にあまるので、人間の姿を借りて表現するのが、受け取り手とイメージを共有するのにもっとも有効であったということが言えるだろう。ラファエルは第六巻で次のように語っている。
わたしは今言語に絶する云々と言ったが、天使の
言葉をもってしてもそれを語るのは難しく、地上で見られる
いかなるものに譬えたら、このような神の如き力と力との極限に
近い激突を、人間の想像力に訴えたらよいのか分からないからだ。
(第六巻 297-300行)
ラファエルはアダムに向かって天上の戦闘の激しさを語っているが、天上界を知らぬ者にそれをそのまま伝えることはできないので、地上のものに置き換えて話をしているのだと言う。だから、他の箇所でも話の合間で、「壮大無比な事象を卑近な事象に譬えて表わすとしての話だが」と断ったりしている(第四巻 310-1行)。
作者ミルトンもまたラファエルと同じように、サタンを描くに当たって、巨大な悪を表現するために人間らしい性格を与えたとは言えまいか。読者に伝わりやすいように、人間らしい姿を借りてきたのではないか。人間が持つ想像力というのは、見たことのないものに対しては、なかなか有効に働かないものである。ギリシア神話やローマ神話には、多くの異形の者たちが登場するが、『失楽園』をそのようなものとして描いた場合、「神の配慮の正しさ」を伝えるという当初の目的を達成するためには障害となったことだろう。人間に善という概念を分かりやすく伝えるために、聖書にキリストが必要であったのも同様であるかも知れない。そしてその人物の思考に、第二章で述べたように、人間の一つのモデルとして一番勝手知ったる自分自身の考えが流れ込んでいたとしても、つまり、サタンにミルトン自身の思考が反映されていたとしても、何ら不思議は無い。
だが私は、ミルトンがサタンを人間的に描かなくてはならなかった最大の理由は、ミルトンがサタンを、堕落した人間の原型として描いたことにあると思っている。人間とサタンは、両者とも神によって造られた被造物で、共に罪を犯し、追放の憂き目に会う。
両者にはそのように重要な共通点があるが、最初に挙げておきたいのが、両者ともに、神によって自由意志を与えられているということである。自由意志とは、神が被造物に対して与えた、その者に自分自身の選択で自由に振る舞うことを許す特権である。その権利があるからこそ、被造物は、己の裁量で自由に振る舞うことができるのだ。つまり、一言で言えば、それは、堕落する権利である。サタンも人間も、この自由意志を誕生した瞬間から与えられていた。そして両者ともその権利を行使し、堕落に至るのである。第四巻で、サタンは自分自身に呼びかける。
お前こそ
呪わるべきだ。神の意志に反して、お前は今当然悔いているものを
自分の意志で選んだからだ。(第四巻 71-73行)
サタンは、自分が罪を犯したことを後悔しており、自分など呪われて当然であると考えている。この語りから、サタンは自分の意志で、罪を犯したことを理解していることが分かる。つまり、サタンは、神に与えられた自由意志を理解しているのだ。そして、その上で罪を犯した。
サタンも人間も罪を犯すが、両者が犯す罪は同じ性質のものである。それはどのような罪なのか。彼らの犯した罪は、七つの大罪のうち、傲慢である。それは、被造物が、創造主である神を、創造主であると認めるのを止める事である。神がサタン(正確に言えば、サタンと呼ばれる前のルシファー)と人間を創造した。そしてサタンは神に反逆し、人間は、神の言い付けを破り、知恵の木の実を食べた。被造物が、創造主を創造主であると認めることを止める、そのことがキリスト教的な罪の始まり、つまり原罪なのである。[4]
両者が罪を犯すことになった、その動機にも共通点がある。サタンが神に反逆した理由は、御子に対する嫉妬であった。そして、人間の堕落に関しては、イヴが堕落したのはサタンにそそのかされたからだが、アダムが果実を口にしたのは、己の欲望に負けたからだ。下の箇所がそれを説明している。
彼は狐疑逡巡することなく、かねて持っていた己の善き知識に
逆らってその果実を食べた、—-惑わされたからでなく彼女の女と
しての魅力に愚かにも負けたからに他ならなかった。
(第九巻 997-9行)
アダムは、イヴの魅力に抗うことができず、罪を犯した。サタンも人間も、それを悪だと判断する能力を有していたにも拘らず、己のうちの欲望に打ち勝つことができずに罪を犯したのだ。
平井正穂氏は、アダムとイヴが罪を犯したことが「堕落 (The Fall)」であるのに対して、サタンが罪を犯したことは「原堕落 (Ur-Fall)」であると記している(平井1998 26)。この指摘は正鵜を得ていると思う。サタンと人間にはこれだけの共通項がある。サタンは、堕落した人間の原型と言えるのではないか。つまり、原罪を背負った人間の原型であると。私は、ミルトンは、サタンをそのように描いていると思う。そのため、サタンに人間的な性質が備わることとなったのだ。
さて、サタンと人間は、罪を犯した後、サタンは天上界から、人間は楽園から、共に放逐される。以下に挙げるのは『失楽園』最後の詩行である。
彼らは、ふりかえり、ほんの今先まで
自分たち二人の幸福な住処の地であった楽園の東にあたる
あたりをじっと見つめた。(中略)彼らの目からはおのずから
涙があふれ落ちた。しかし、すぐにそれを拭った。
世界が、—-そうだ、安住の地を求め選ぶべき世界が、今や
彼らの眼前に広々と横たわっていた。そして、摂理が彼らの
導き手であった。二人は手に手をとって、漂泊の足どりも
緩やかに、エデンを通って二人だけの寂しい路を辿っていった。
(第十二巻 640-9行)
こうしてアダムとイヴは、楽園を追放されて旅立っていく。ここでも、サタンと二人を重ね合わせることができる。アダムとイヴの旅立ちは、第一章で取り上げた、天上での戦いに敗れたサタンが単身、人間を陥れるために楽園へと赴く姿と重なる。新井明氏は次のように述べる。
アダムの旅立ちを描写するときに、作品の最後まで読みきたった読者
としては、第二巻において感じたと同様のヒロイックな雰囲気を、こ
こに感じないわけにはいかない。ミルトンはおそらく、アダムのヒロ
イズムを主張するという目的からだけでも、旅ゆくサタンの英雄性を
強調しないわけにはいかなかったのである。
(新井1980 259)
両者のヒロイズムには確かに共通した雰囲気を感じ取ることができる。
長澤順治氏は以下に挙げるように、ミルトンは、サタンと人間の追放を似たように描いており、そのため、サタンの追放には人間らしい苦悩がもたらされ、読者もその苦悩に共感することができると述べる。
ミルトンはサタンを始めとする堕天使の群れを人間と同じような次元
で扱っている。つまり良心や選択の自由がずっとのこされているもの
のように描いている。だからそのための堕天使の人間臭に満ちたエグ
ザイルの苦悩は、そのまま人間的に共感できるものがある。
(長澤 76)
だが、実際は異なるのだ。人間は神によって見放されてはいない。第三巻で、神は、人間たちはサタンにたぶらかされて堕落したのであるから、恩寵を与える意向であることを宣言する。第六巻において、アブデルがサタンに告げる言葉が示唆的である。
隷属とは、今汝の部下が汝に仕えているように、
愚かなる者に仕える、或は己より価値高き者に叛逆した者に
仕える、ということだ。しかも、汝自身、自由な身どころか
自分自身の奴隷になっているではないか。(強調筆者)
(第六巻 178-81行)
アブデルは、サタンに告げる。お前はもはや「自由」ではなく、「自分自身の奴隷」に過ぎないと。ここでいう「自由」とは自由意志に他ならない。つまり、堕落する自由である。サタンは自由を失った。何故なら、すでに堕落してしまったからである。一度神の恩寵から離れたものには、もはや原罪を犯す自由、つまり、神の意志に逆らう自由は無いのだ。サタンは、堕ちる自由を失った。そして、「自分自身の奴隷」となった。サタンは自分自身の「内なる地獄」に捕われたのだ。
恐怖と疑惑が千々に乱れた思いを翻弄し、彼の
内なる地獄を底の底から揺り動かした。彼は自分の内部に、
自分の身の周辺に、常に地獄を持っており、たとえ
場所が変っても自分自身から抜け出せないのと同じく、
地獄からは一歩も抜け出せないからだ。(強調筆者)
(第四巻 19-23行)
この詩行は、クリストファー・マーロウ『フォースタス博士』の次の台詞と共鳴している。
地獄に境界はなく、一定の場所に限られてはいない。
われらのおるところすなわち地獄、
地獄あるところすなわちわれらの永劫の住まいなのだ。(二幕一場)
地獄とはサタンの外部にあるものではなく、サタンがいる所が地獄なのである。つまり、サタンは、永久に「内なる地獄」から逃れることはできない。サタン自身、空間としての地獄がそれを認識する内面と関係していることを理解している。次の引用は、サタンが天上での戦闘に敗れた後、地獄で語るものである。
心というものは、それ自身
一つの独自の世界なのだ、—-地獄を天国に変え、天国を地獄に
変えうるものなのだ。 [5] (第一巻 253-255行)
サタンは堕天使たちを前にして、今、彼らは地獄にいるが、気持ち次第で、その地獄は天国に変るのだと、彼らを鼓舞する。しかし、彼は地獄から逃れることはできない。楽園へと向かうサタンはそのことに気付く。
どこへ逃げようが、そこに地獄がある!
いや、わたし自身が地獄だ! (第四巻 75-6行)
ここに堕落後のサタンと人間との大きな差異がある。人間たちは堕落した後も、第三巻で神が語っているように、神の恩寵の下にいる。何故なら、人間たちはサタンにそそのかされて堕落したからである。しかしサタンは神の恩寵の下にいない。何故ならサタンは自分の心に芽生えたラファエルへの嫉妬によって、自ら堕落したからである。「内なる地獄」とはそのことを表わしている。つまり、「地獄」とは、神の恩寵の届かない場所のことを意味しているのだ。この「内なる地獄」、つまり神の恩寵の下にいないことが、サタンを、道化や英雄、ミルトン自身、アダム、イヴ等と分かち、サタンをサタンたらしめている。
結び
私は、本論において、今までなされてきて様々なサタンの解釈について考察し、サタンに人間らしさが賦与された理由を探ってきた。
第一章では、道化から、英雄までの幅広いサタン像について紹介した。サタンには確かに英雄的な側面があるが、第六巻、十巻でのサタンの退場を考えると、ミルトンが本当にサタンを英雄として描いていたかどうかは疑わしい。私は、サタンが道化的な要素と英雄的な要素を合わせ持ったアンビバレントな存在であると結論付けた。
第二章では、サタンとミルトンの主張が重なっている箇所があることから、ミルトンとサタンを同一視するサタニストの主張について考察した。サタンは、ミルトンが使用したのと同じレトリックを用いているが、その本質は全く異なっている。そのため私は、ミルトンとサタンの主張を同一視することはできないと考えた。だがサタンには、ミルトンと共有したかもしれない、弱さや嫉妬、苦悩といった、人間的な性格が賦与されているということを確認した。
第三章では、物語においての悪の必要性について考え、サタンに崇高さが賦与された理由を探った。ミルトンは、『失楽園』で、神の配慮の正しさを描き出そうとしたが、善を描くためには、サタンという悪役が必要だった。そして、ミルトンが、巨大な善と悪を描こうとした結果、善も悪も崇高な性質を帯びることになった。サタンは、悪の中に崇高さという善なる要素を兼ね備えており、複雑で奥行きのある悪役となった。
第四章では、サタンを、堕落した人間の原型として考え、アダムとイーヴと比較し、サタンの人間らしさの源泉を探った。人間とサタンは、両者とも神によって造られた被造物で、共に罪を犯し、追放の憂き目に会う。私は、サタンは、原罪を背負った人間の原型であると結論付けた。そのため、サタンに人間的な性質が備わることとなったのだ。しかし、サタンには堕落したアダムやイヴと異なる決定的な違いがある。サタンは、ラファエルへの嫉妬にかられ、自ら堕落する。そうしてサタンは、神の恩寵から離れ、「内なる地獄」に捕われることになるが、この「内なる地獄」こそが、サタンをサタンたらしめている要素であると論じた。
私は本論において、サタンに人間らしさが賦与された理由を探って来た。その理由は、従来論じられて来たように、サタンが道化として描かれているからでも、英雄として描かれているからでもない。あるいは、ミルトンが自分を投影してサタンの性格を造形したからでもない。私は、その理由は、サタンが堕落した人間の原型として描かれていることにあるのだと考える。そして、ミルトンにとってサタンとは、中世道徳劇に登場したよな爆竹を加えた毛むくじゃらの化け物といったような、異形のものを指すのではなく、「内なる地獄」に捕われているもの、つまり神の恩寵を離れ、永久に地獄に捕われ続けるものを指すのである。
引用文献
新井 明 『ミルトンの世界—-叙事詩性の軌跡』 東京: 研究社 1980.
新井 明・野呂 有子 編 『摂理をしるべとしてムミルトン研究会記念論文集』
東京: リーベル出版 2003.
Blake, William. Blake’s Poetry and Designs. Ed. Mary Lynn Johnson and
John E. Grant. New York and London: W. W. Norton & Company,
1979.
ウィリアム・ブレイク 『ブレイク詩集』 土居 光知 訳 東京: 平凡社 1995. Forsyth, Neil. The Satanic Epic. New Jersey: Princeton University Press,
2003.
平井 正穂 編 『ミルトンとその時代』 東京: 研究社 1974.
—– 『イギリス文学論集』 東京: 研究者 1998.
Kolbrener, William. Milton’s Warring Angels. Cambridge: Cambridge
University Press, 1997.
ルーサー・リンク 『悪魔』 高山 宏 訳 東京: 研究社 1995.
ミルトン 『失楽園』 平井 正穂 訳 東京: 岩波書店 1981.
長澤 順治 『ミルトンと急進思想 英国革命期の正統と異端』 東京: 沖積舎
1997.
村上 淑郎 著者代表 『エリザベス朝演劇—-小津次郎先生追悼論文集—-』 東京:
英宝社 1991.
小津 次郎・小田島 雄志 編著 『エリザベス朝演劇集』 東京: 筑摩書房
1974.
田中 勉 『ミルトン新考』 東京: 松柏社 1971.
辻 裕子・佐野 弘子 編 『神、男、そして女 ミルトンの『失楽園』を読
む』東京: 英宝社 1997.
参考文献
新井 明 『ミルトン論考』 東京: 中教出版 1979.
—- 編 『ミルトンとその光芒』 東京: 金星堂 1992.
—- 『ミルトンとその周辺』 東京: 彩流社 1995.
—- 『ミルトン 人と思想134』 東京: 清水書院 1997.
圓月 勝博 他 『挑発するミルトン—-『パラダイス・ロスト』と現代批評』
東京: 彩流社 1995.
Jasper, David. and Stephen Prickett. ed. The Bible and Literature;
A Reader. Oxford and Massachusetts; Blackwell Publishers, 1999,
越智文雄博士喜寿記念論文集編集委員会 『ミルトンム詩と思想』 東京:
山口書店 1986.
Milton, John. Paradise Lost. 2nd ed. Ed. Fowler, Alastair. London:
Addison Wesley Longman Limited, 1998.
ミルトン 『ミルトン詩集』 才野 重雄 編注 東京: 篠崎書林 1976.
才野 重雄 『ミルトンの生涯』 東京: 研究社 1982.
武村 早苗 『ミルトン研究』 東京: リーベル出版 2003.
註
[1] The reason Milton wrote in fetters when he wrote of Angels & God, and at liberty when of Devils & Hell, is because he was a true Poet and of the Devil’s party without knowing it. (Blake 88)
[2] Apart from classical epic and Christian myth, apart from Reformation theologians and their biblical proof-texts, the most important influence on Milton’s Satan was the dramatic tradition. (Forsyth 60)
[3] The early sketches in the Trinity Manuscript for what became Paradise Lost, when he was still thinking of it as a tragedy not an epic, show Milton thinking along the lines of the medieval morality plays (which, unlike the mysteries, continued to lead a half-life well into the seventeeth century): he peoples his draft with allegorical characters like Justice, Mercie, Labour, Ignorance. These jottings, which are also reminiscent of Greek tragedy in their use of the chorus and their five-act structure, are usually dated to 1640-42 According to Edward Phillips Milton’s nephew, he was still thinking of a tragedy a few years later (”several Years before the Poem was begun”), and Phillips even quotes the first ten lines of Satan’s Niphates speech as having been ”designed for the very beginning of the said Tragedy.” (Forsyth 60)
[4] メアリ・シェリーは、失楽園を意識して『フランケンシュタイン』を書いた。(辻 170)この物語に登場する怪物は、『失楽園』のサタンのように、創造主である科学者の意志に抗して世界を彷徨うことになる。
[5] 平井正穂氏は訳注に次のように記す。「天国と地獄のいわば外在性ともいえるものを否定し、内在性を強調する考えは、十七世紀の無神論者の主張したところであった。この考えは勿論ストア派の思想まで遡ることができる。しかし、ルネサンスの人々にとっては魅力的なものと思われたことは間違いない。」(ミルトン 333)
2008/05/02/21:10
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
ガートルードとアルカージナ
—シェイクスピア『ハムレット』とチェーホフ『かもめ』の比較—
米田 拓男
Introduction
本論では、シェイクスピアの『ハムレット』とチェーホフの『かもめ』の二作品を比較する。『ハムレット』と『かもめ』には、多くの共通点がある。両作品とも、主人公は新しい恋人(夫)を持った母親に対して愛情と憤りの入り交じった複雑な感情を抱き、恋に思い悩み、決意を持って行動を起こすことができない。二作品とも中断される劇中劇を含み、主人公の死によって幕を閉じる。作中でチェーホフは『ハムレット』からの台詞を引用してさえいる。『かもめ』の劇構造が『ハムレット』に似通っているとは、しばしば指摘されるところである。(佐々木 一八〇頁)
そのように多くの共通点を持つ二作品だが、その作品の形式には大きな相違がある。その相違は、対照的であると言ってもいいほどのものである。本論では、『ハムレット』のガートルードと『かもめ』のアルカージナという二人の登場人物を比較したい。Chapter 1では、ガートルードとアルカージナの性格を比較して論じながら、チェーホフとシェイクスピアの相違を、リアリズムと非リアリズムという点に求める。Chapter 2では、リアリズムと非リアリズムという観点からさらに前進して、作者と作中人物における主観性と客観性について議論を展開する。本論は、ガートルードとアルカージナという二人の作中人物を通して、最終的にシェイクスピアとチェーホフという二人の作家の違いを浮き彫りにすることを目的とする。
Chapter 1 リアリズムと非リアリズム
『ハムレット』においても『かもめ』においても、主人公とその母親との関係が、物語の展開の上で、主人公の内面における葛藤の焦点となっている。本論では、特にアルカージナとガートルードの台詞に注目し、シェイクスピアとチェーホフという二人の劇作家それぞれの特徴について論じたいと思う。そのための手続きとして、母親と息子が二人きりになって話を交わす、それぞれの作品にとって唯一の場面を比較することにしたい。『ハムレット』第三幕第四場の居室の場と、『かもめ』第三幕でトレープレフが母親に自分の頭に包帯を巻いてくれとせがむ場面である。
まず、『ハムレット』の方から見てみたい。王の御前での劇中劇の上演後、ハムレットはガートルードの部屋に来るように言われ、母親の部屋に赴く。そしてハムレットは部屋に入るなり、母親に対して強い調子で当たる。身の危険を感じたガートルードは人の助けを求め、それに応じて壁掛けの後ろに隠れていたポローニアスも助けを求める。ハムレットは彼を刺し殺す。その後、ハムレットはさらに母親に強い口調で言いつのる。そしてガートルードが答える。
王妃 私がなにをしたというのです、
おまえにそのような口のきき方をされるとは?
ハムレット あなたがしたことは、女のつつしみ深さに泥をぬり、
貞淑の美徳を偽善者呼ばわりすることだ、
汚れない愛の額からバラの冠を奪いとり、
そのかわりに売笑婦の烙印を押すことだ、
結婚の誓いを踏みにじり、博打うちの
空約束にすることだ、ああ、あなたがしたことは、
夫婦の約束からその魂を抜き去り、神に誓ったことばを
たわごとの羅列にすることだ。そのために、
天も憤りに顔を赤らめ、堅い大地も悲しみに
ふるえおののいているのです。
王妃 なんのことです、いったい、
のっけからそのようにどなりつけるようなこととは?
ハムレット ごらんなさい、この絵を、それから
これを、二人の兄弟の絵姿だ。
どうです、このお顔に宿る気品は、
太陽神アポロの巻き毛、主神ジュピターの額、
三軍を叱咤激励する軍神マルスのまなざし、
天を摩する山頂におり立ったばかりの
使神マーキュリーの立ち姿、
神々が天下にむかって、これこそ
人間のなかの人間、男のなかの男と
知らしむるために印を押した契約書、母上、
これがあなたの夫であった人だ。
(『ハムレット』第三幕第四場四一〜六四行)
ここでハムレットは、語気を荒げて、母親に対して挑むような強い口調で言いつのっていく。その語りかけには、一方的で、母親に意見を差し挟ませないような、断固とした調子がある。ガートルードは、ハムレットが一方的にたたみかける合間に、一言、二言、口を挟むだけである。ガートルードはハムレットに対して強く出ることができない。ここに見られる二人の関係は、一方が、もう一方の不正を容赦なく糾弾するというものだ。
続いて、『かもめ』のトレープレフとアルカージナの対話を見てみたい。第二幕が幕を閉じた後、トレープレフは拳銃で自殺を謀る。そして、第三幕が幕を開けた時、トレープレフは、自殺に失敗し、頭に傷を受け、包帯を巻いて登場する。この場面でトレープレフは、先のハムレットと同様に、自分の母親に向かって、母親の恋人がいかに彼女にとって相応しくないかを説いてみせる。
トレープレフ 包帯かえてくれる、ママ? ママは上手だから。
アルカージナ (薬品棚からヨードホルムと包帯を取り出す)それは
そうと、ドクターは遅いわね。
トレープレフ 十時にくるって約束したのに、もう十二時だ。
アルカージナ おすわり。(彼の頭の包帯をとる)まるでターバンを巻
いた人みたい。昨日勝手口にきただれかが聞いてたよ。おまえはど
この国の人かって。でも、もうほとんどなおったわ。あとほんのち
ょっと。(彼の頭にキスする)私がいなくなってからまたピストルを
おもちゃにしたりしないわね?
トレープレフ しないよ、ママ。あのときはぼく、とてつもなく絶
望して、自分をおさえきれなくなったんだ。もう二度とあんなまね
はしない。(彼女の手にキスする)
(中略)
ここ何日か、ぼくは子供のころみたいにママが好きで好きでたまら
なかった。僕にはママしかいないんだ。それなのにどうして、どう
してあんな男がぼくたちの間に入りこむんだい?
アルカージナ コンスタンチン、おまえにはあの人のことがわかっ
てないんだよ。あの人は最高の人格者で……。
トレープレフ その最高の人格者がぼくに決闘を申しこまれそうだ
と知ると卑怯者の正体をあらわしたじゃないか。逃げ出すんだから
な。恥っさらしめが、こそこそと!
アルカージナ なにをばかな! 私があの人に頼んで発つことにし
たんだよ。そりゃあおまえは私たちの関係を不愉快に思うかもしれ
ない。でもおまえだってもう一人前の知性はもっているだろう、だ
ったら私の自由を尊重してほしいわ。
(『かもめ』第三幕九七〜九九頁)
ハムレットもトレープレフも、母親に対してエディプス・コンプレックス的な屈折した愛情を抱いているといえるが、1ここでのトレープレフの振る舞いは、エディプス・コンプレックスというより、むしろ幼児返りといった方が相応しい。トレープレフは二十五歳という設定になっているが、とてもそうは思えない。彼は母親の前で、だだをこねる子供と化している。そのようなトレープレフと比べれば、ハムレットの方が遥かに理性的である。例えば次のような場面。ハムレットは自分の母親に会いに行く直前に、次のように決意を表明する。
だが待て、まず母上のもとへ。
ああ、それには人の心を失ってはならぬ、けっして
この固い胸に母親殺しのネロの魂を入りこませてはならぬ。
きびしくはあっても、子としての情愛は忘れないぞ。
短剣のようなことばは用いても、用いるのはことばだけだ、
その点、舌と心はおたがいに裏切りあってほしい。
舌がどのように激しく母上を責め立てようと、心よ、
そのことばを実行に移す責めだけは負うなよ。
(『ハムレット』第三幕第二場三八七〜三九四行)
「子としての情愛」。ハムレットは、母親の自分に対する愛情を問う前に、自分の母親に対する愛情を問う。トレープレフは決してそのような認識に至ることはない。『ハムレット』の例では、その場のイニシアティヴをハムレットがとっているが、『かもめ』では、場のイニシアティヴは母親のアルカージナに握られている。トレープレフは、母親に断固たる調子で語ることができず、到底母親を説得できそうにない。この二つの場面を比べてみると、『ハムレット』では、息子の方が母親よりキャラクターが強く、『かもめ』では、息子より母親の方がキャラクターが強い。言い換えれば、ガートルードの方がより受動的で、アルカージナの方がより能動的であるといえる。
この二作品における母親像は、その性格描写において、赴きがだいぶ違うのが判るだろう。そして、この二人の性格において、決定的に違うことがある。先の場面で、アルカージナは、トレープレフの批判に対してきつく言い返す。そもそもアルカージナは口が悪く、息子に対してもあけすけに批判し、露骨に冷淡な態度をとったりする。それに比べて、ガートルードはハムレットに対して、冷淡な態度をとったり、罵倒するようなことはない。一見すると、ガートルードの方が息子に対して理解がありそうに見える。しかし、実際は、アルカージナの方が息子の気持を理解していて、ガートルードの方が息子の気持を理解していない。
先の引用の中で、ガートルードは、言いつのるハムレットに対して、「私がなにをしたというのです、おまえにそのような口のきき方をされるとは?」であるとか、「なんのことです、いったい、のっけからそのようにどなりつけるようなこととは?」と疑問を呈する。どうやら、ガートルードは、ハムレットが何を言わんとしているのか、この段階で分かっていないようなのだ。先に引用した引用の直前には、もっとひどいことを言っている。
ハムレット まあ、まあ、おすわりなさい、動いてはなりませぬ。
いま、鏡を見せてあげましょう、あなたの心の奥底を
とくとごらんになるのです、それまではどこへも行かせませぬ。
王妃 なにをするのです? まさか私を殺すつもりでは?
だれか、だれか、助けて。
(『ハムレット』第三幕第四場十八〜二二行)
ガートルードは、ハムレットの母親に対する愛情を察していないどころか、実の息子に殺されるのではないかと思っているのだ。この誤解は、あまりに酷すぎると思う。この場面の息子に対する理解のなさから判断すると、ガートルードはとても聡明な人物とはいい難い。そもそも彼女は、自分の夫が不審な死を遂げ、それから間もない内に、夫を殺した男と少しも怪しむことなく結婚したのである。ハムレットの母親に対する憤りも判るような気がしてくる。ハムレットはガートルードの鈍感さをなじっているのだ。次の引用でガートルードは、そうやって言いつのられて、やっとのことでハムレットの言わんとしていることを飲み込む。
王妃 ああ、ハムレット、もうなにも言わないで。
おまえは私の目を心の奥底にむけさせる、
そしてそこに見えるのは、どす黒いしみ、
洗っても落ちはしまい。
ハムレット ああ、落ちるものですか。
脂ぎった汗くさい寝床のなかで、欲情にただれた
日々を送っている以上。抱いて抱かれる
その相手は汚らわしい豚—-
王妃 お願い、もうやめて。
おまえのことばは短剣のようにこの耳を刺す。
もうなにも言わないで、ハムレット。
(『ハムレット』第三幕第四場九〇〜九九行)
ガートルードのこのような鈍感さが、ハムレットの悲劇の源泉になったと言うことも可能だろう。そして、ガートルードが自らの内に邪な心が宿っていることを認識するこの言葉が、『かもめ』の中で引用されているのである。『かもめ』は、トレープレフが書いた戯曲を、母親とその愛人の前で上演する劇中劇の場面から始まる。そしてその場面のトレープレフとアルカージナの対話は、『ハムレット』の今の場面からの引用で始まる。
アルカージナ (トレープレフに)「ここへおいで、ハムレット、母の
そばへ」ねえ、いつはじまるの?
トレープレフ もうすぐだよ。辛抱して。
アルカージナ 「ああ、ハムレット、もうなにも言わないで。
おまえは私の目を心の奥底に向けさせる、
そしてそこに見えるのは、どす黒いしみ、
洗っても落ちはしまい」
トレープレフ 「ああ、落ちるものですか。
脂ぎった汗くさい寝床の中で、欲情にただれた
日々を送っている以上。抱いて抱かれる
その相手は汚らわしい豚……」
(『かもめ』二七〜二八頁)
この二つの台詞は、言っている言葉は同じだが、その意味合いは全く違うものになっている。ガートルードが言う時、この台詞はガートルードの鈍感さを暴露する。しかし、アルカージナが言う場合には、それとは全く逆のものを示す結果となる。この場面で先に『ハムレット』の台詞を引用してみせるのは、アルカージナの方だ。アルカージナは自分の息子をハムレットに見立てる。ということはつまり、アルカージナは、トレープレフが自分と愛人の関係に嫉妬していることを理解しているのだ。だからこそ『ハムレット』を引き合いに出しているのだ。そして、母親が始めた『ハムレット』ごっこに付き合うトレープレフもまた、母親が自分の気持を分かっている、ということを理解するだろう。実は、アルカージナは、ガートルードに比べて遥かに敏感であり、聡明である。アルカージナの感性が豊であることは、トレープレフによっても語られている。
まぎれもなく才能があって、頭もよくて、小説を読んで泣くことも
できる。ネクラーソフの詩を全部暗誦することだってできる。病人
の世話をさせたらまさに天使だ。
(『かもめ』十四頁)
トレープレフは、母親の感受性を評価している。彼は、感性の鋭い母親の自作への評価を恐れてさえいる。アルカージナは決して鈍感な母親ではない。しかし、だからこそ余計に厄介であると言うこともできる。アルカージナは、「おまえは私の目を心の奥底に向けさせる、そしてそこに見えるのは、どす黒いしみ、洗っても落ちはしまい」というハムレットの台詞を、ユーモアを持って言っている。実にしたたかな母親、ずぶとい神経の持ち主である。彼女が本当に自分の心にどす黒いしみがあると思っているのかといえば、露にも思っていない。全くの冗談として言っている。むしろ、トレープレフがそう思っているのだろうと悟って、自らガートルードを演じてやっている訳だ。それに対してトレープレフの「ああ、落ちるものですか。脂ぎった汗くさい寝床の中で、欲情にただれた日々を送っている以上。抱いて抱かれるその相手は汚らわしい豚……」という台詞の返答には、彼の本音が込められているように思える。アルカージナの方が、トレープレフよりも一枚も二枚も上手である。アルカージナは、ガートルードより遥かにトレープレフの気持を理解しているといえる。しかし、それだからこそ、ガートルードより質の悪い母親であると言うこともできる。アルカージナは、息子の気持を分かっていると思いこんでいたが、しかし、息子の絶望が、自らを死に追いやるほど強烈なものだとは思っていない。だから、息子に思っていることをそのまま言ってしまう。女優でまわりからちやほやされているから、人に気を使い慣れていないということもあるかもしれないが、息子のことを想っているのに、きつく当たってしまう。以下に挙げる引用は、先に挙げた、トレープレフが、頭に包帯を巻いてもらいながら、母親の愛人トリゴーリンのことを批判する引用に続く場面である。息子の愛人への批判に対して母親が答える。
アルカージナ じゃあおまえはなんなのよ? このデカダン!
トレープレフ さっさとあんたの大事な劇場にもどってくだらない三
流芝居に出るがいい!
アルカージナ そんな芝居に出たことなんて一度もないわよ! 私の
ことに口出ししないで! くだらないコント一つ書けないくせに!
この小売り商人! そう——キエフの商人! 居候!
トレープレフ けちんぼ!
アルカージナ ボロッかす!
トレープレフは腰をおろし、静かに泣く。
人間の屑! (興奮して少し歩きまわる)泣かないで。泣くことは
ないよ……。(泣く)泣いちゃだめ……。(彼の額、頬、頭にキスす
る)ね、おまえ、許して……いけない母さんを。ふしあわせな母さ
んを。
トレープレフ これだけはわかって! ぼくはなにもかもなくしてし
まった。あの人はぼくを愛していない、ぼくはもうなにも書けない
……ぼくの希望はみんなこわれた……。
アルカージナ そんなに気を落とさないで……なにもかもうまくいく
わ。あの人を連れて行くから——そしたらあの子もまたおまえを愛
してくれるでしょう。(彼の涙をふいてやる)さ、もうおしまい。こ
れで仲なおりよ。
トレープレフ (母の両手にキスする)うん、ママ。
(『かもめ』一〇〇〜一〇二頁)
アルカージナは、つい一時の感情に流されて息子にきつく当たるが、息子が泣き始めると、情愛のこもった態度をとるようになる。そして、自分はトリゴーリンを連れて立ち去るから、再びニーナの愛を取り戻せるようになるだろうと言う。アルカージナは、トレープレフの恋人のニーナが、アルカージナの愛人トリゴーリンに好意を抱いているのを感じ取っており、トレープレフがそのことを気にしているということまで気付いている。なんという感受性の豊かさだろう。それゆえにこの物語の結末は悲壮なものとなる。ことによると、アルカージナがあまりに感受性が豊かであるがゆえに、息子をあまやかしてしまったのかもしれない。
このように見てくると、アルカージナの性格描写の方がガートルードより遥かに生々しくて多彩であるように思える。それに比べると、ガートルードの性格描写が、平面的で、奥行きのないものに感じられてしまうことは否めない。2居室の場においても、ガートルードはハムレットの非難に対して、ただの一言も自己を弁護しようとしない。ガートルードは終始受け身の姿勢で、ハムレットの非難を受け入れるのである。『ハムレット』作中全体においてもガートルードは一貫して受け身である。自己を主張することがない。ハムレットに、いつまでも亡き父を憐んでいるのをやめるように言うのも、ウィッテンベルク大学に行かずデンマークに滞在するよう頼むのも、クローディアスの意向に追従して言っているように読むこともできる。
『ハムレット』の第四幕第七場に、ガートルードが、川で溺れるオフィーリアの情景を語る場面がある。この場面は、何故ガートルードは溺れているオフィーリアを見ていながら、助けようとしなかったのかと、議論のかまびすしい箇所であるが、あの語りを成立させているのは、ガートルードの受動性だ。実際に彼女がオフィーリアが溺れて行くところを見ていたとは思わないが、彼女の語りに観客が違和感を抱かずに済むのは、ガートルードの受動的な性格に負うところが大きい。アルカージナが同じように語るところを想像できるだろうか? 否、できない。アルカージナが同じ台詞を吐くとき、観客はそれこそ何故助けなかったのかと、違和感を抱くことになるだろう。アルカージナは、その台詞を語るには、あまりに地に足がつきすぎている。その台詞を語るには、彼女の性格描写は現実的すぎる。シェイクスピアが描いたガートルードは、あまり現実的に描くと成立しなくなるタイプのキャラクターなのだ。リアリズムと非リアリズム。この対照がチェーホフとシェイクスピアを比較した時に見えてくる最大の特色といえるだろう。
Chapter 2 客観と主観
そして、そのリアリズムと非リアリズムという区別は、客観と主観という区別に置き換えることができると思う。チェーホフは、客観的に、主観的に行動する人物たちを描き、シェイクスピアは、主観的に、客観的に行動する人物たちを描いている。どういうことか詳しく説明したい。まず、チェーホフは、今見てきたように現実主義的なスタイルで執筆をする。アルカージナがあたかもそこに実在しているかのように描く。その現実らしさは、チェーホフによる冷静な観察眼によってもたらされる。チェーホフは、人間の対話の複雑さをそのまま舞台上に再現しようとする。登場人物たちは、時に、言い淀んだり、言いやめたり、言い換えたりしながら自分の言葉を語っていく。そのためチェーホフの登場人物は、主観的に行動しているように見える。チェーホフは、客観的な観察に基づいて、主観的に行動しているように見える人物を作り出しているのだ。それに対して、シェイクスピアは、もう少し観客に分かりやすいように様式化する。ブランク・ヴァースを使用して、その人物の身分を表わしたり、会話の量を調整して、重要な人物には長い台詞を与え、その人物に観客の意識を集中させるように工夫する。そしてそのことは時に、登場人物の現実らしさを害うことにもなる。先のガートルードの語りがよい例である。あの場面でのガートルードは、本来の役を離れて、観客へオフィーリアの最後を伝えるための語り手として機能している。シェイクスピアは、主観的に人工の手も加えつつ、客観的に行動する人物たちを描いている。つまり、シェイクスピアの作品に出て来る登場人物たちは、皆、役者なのだ。シェイクスピア作品の登場人物たちは、観客に見られていることを意識して行動している。
俳優にとっては、チェーホフの自然主義的な芝居の方が、必然的に負担が大きくなる。シェイクスピア劇では、私は、悲しい、といえばそれは本当に悲しいことなのだ。しかし、チェーホフの芝居ではそうはいかない。チェーホフ劇の登場人物が、私は悲しい、と言っても、それが本当に悲しいという保証はないのだ。彼はもしかしたら、実はとても嬉しいのかもしれないし、あるいは楽しそうに振る舞っていても、本当に楽しいのかどうかわからない。私たちの日常生活と同じように。シェイクスピアの登場人物の感情の動きは、チェーホフに比べれば直線的であるといえる。チェーホフの場合は、感情が、さまよい、立ち止まり、たゆたう。チェーホフ劇の登場人物たちの台詞は、本当の感情を覆い隠したり遠回しに表現したりしている。役者たちは、表面的に台本にある台詞を頼りに、その人物が本当はどう思っているのかを読み取らなくてはならない。そして舞台上でその感情を辿り、追体験しなくてはならないのだ。私は悲しいと言って、大声で泣き叫べば、知らず感情移入して、涙を流せる。それはそれほど大変な作業ではない。しかし、楽しい風を装って、心で泣くというのは至難のわざである。チェーホフの方が、このように二重三重に屈折している。それは、私たちの日常の反映でもある。私たちもそのように屈折して生きているのである。
しかし、チェーホフが書いたその後の作品に比べれば、『かもめ』はまだシェイクスピアのような従来的な劇作に近い。『かもめ』の中には、拳銃が発射されるという非日常的な場面が二度もあり、主人公の死が描かれ、またリアリズム演劇には馴染まない、伝統的な演劇手法である独白や傍白も、何箇所かで使われている。独白や傍白と言うのは、それぞれのキャラクターが各々の主観的な考えを述べるものだ。しかし、日常に生きる私たちは独白や傍白を語ることはない。独白や傍白と言うのは、その人物が自分の考えを主観的に語っているようでありながら、実は、極めて客観的に自分を認識しながら語る、自意識の強い語りなのだ。
『かもめ』に出て来る傍白を見てみよう。アルカージナが、トリゴーリンが自分のもとを去るのを思い留まらせようとする場面である。アルカージナが言う。
あなたの価値を理解できるのは私だけ、あなたに真実を語る
のも私だけなのよ、私の大事な、すばらしい人……いっしょに発つ
わね? ね? 私を棄てたりしないわね……?
トリゴーリン おれには自分の意志というものがない……一度だっ
て自分の意志を通したことがない……(中略)一瞬たりともきみの
目の届かないところに行かせるんじゃないよ。
アルカージナ (ひとりごと)これでこの人も私のもの。(なにご
ともなかったかのように、けろっとして)残りたいなら残ってもい
いのよ。
(『かもめ』一〇七〜一〇八頁)
この傍白は、彼女が心の内で思っていることであるわけだが、チェーホフのような自然主義的な作風の中では特に、内面を自ら語るという行為は、観客にアルカージナの自意識を強く感じさせる結果をもたらす。それは、女優であるアルカージナというキャラクターには相応しいかもしれない。しかし、役者が傍白を語った段階で、観客は自分達が芝居を見ているのだという現実に引き戻されてしまう。このような、明らかに独り言とは言えない独白や傍白は、その芝居の虚構性を強調する結果となり、チェーホフのような自然主義的な作風の中では明らかに浮く。そのため、チェーホフは『かもめ』以降の作品では独白や傍白をほとんど使用しなくなるである。
チェーホフはこの作品以降、より写実主義的、現実主義的な方向性を深めていく。シェイクスピアは、ハムレットに「芝居というものは、昔もいまも、いわば自然にたいして鏡をかかげ、善はその美点を、悪はその愚かさを示し、時代の様相をあるがままにくっきりとうつし出すことを目指しているのだ」と言わせているが、(『ハムレット』第三幕第二場十九〜二三行)チェーホフの執筆方法は、まさに「自然に鏡をかかげる」ような方法であり、ハムレットが語る理想的な演劇手法に当てはまるのではないか。
一方シェイクスピアは、ハムレットにそのように語らせておきながら、後期ロマンス劇に至って、それとは反対の方向へ向かっていった。否、シェイクスピアの自然観が変化した、と言った方が正しいのかもしれない。シェイクスピアは『冬物語』を執筆するにあたって、「時」のコーラスや、熊を舞台上に登場させたり、彫像が動き出すといった自然主義的な演劇から遠ざからざるをえないような趣向を凝らしたが、恐らくシェイクスピアは、作為を持って、作為的な改変を行っていた。シェイクスピアが自らそのことを表明しているととれる台詞がある。
ポリクシニーズ 娘さん、どういうわけで
あの花をさげすむのだな?
パーディタ あの赤と白とのまだら模様は、
偉大な造化の自然に人工の手が加わってできたもの、
と聞いておりますので。
ポリクシニーズ それはそうかもしれぬ。だが、
なんらかの手を加えて自然がよりよくなるとすれば、
その手を生み出すのも自然なのだ。したがって、
自然にたいして加えたとあなたの言うその人工の手も、
実は自然の生み出す手に支配されているのだ。いいかな、
野育ちの幹に育ちのいい若枝を嫁入らせることによって、
卑しい木に高貴な子を宿らせることがあるだろう、
これは自然のたりないところを補う、と言うより、
すっかり変えてしまう人工の手だ、しかし実は
その人工の手そのものが自然なのだ。
(『冬物語』第四幕第四場八五〜九七行)
シェイクスピアはこの時点では、自然に人工の手を加えることも、大きな目で見れば自然の一部であると考えていたかのようである。ここに僕は、シェイクスピアの達観した演劇/芸術観を見る。彼の中では、もはや自然と人工は相対するものではなくなっていたのだろう。
これまで見てきたように、シェイクスピアの『ハムレット』と、チェーホフの『かもめ』は多くの接点を持っているが、両者の指向する方向には大きな違いがあった。シェイクスピアとチェーホフは、それぞれ『ハムレット』と『かもめ』を執筆した後、それぞれの劇作手法を突き詰めていき、全く逆の方向へと進んでいったのである。『ハムレット』と『かもめ』はそのような、対極的な志向を持った二人の作家の創作の軌跡が、一瞬だけ交わった交点となっている作品と捉えることができるだろう。
Conclusion
本論では、ガートルードとアルカージナを比較しつつ、シェイクスピアとチェーホフの作家性の違いについて論じた。
Chapter 1では、それぞれの戯曲中、唯一母親と息子が語り合う場面である、『ハムレット』の居室の場と『かもめ』の第三幕に焦点を合わせた。そして二人を比較していく内に、一見子供のことなんか何も考えていないように見えたアルカージナが、思いの外、トレープレフのことを思い遣っていることが明らかになった。また、アルカージナに対してガートルードはあまりに受動的であるが、その受動性は、ガートルードが溺れるオフィーリアについて語る場面では有効に働いていることについて論じた。また、ガートルードはアルカージナのように現実的に描くと成立しなくなる可能性があることについて言及した。そして、チェーホフとシェイクスピアの劇作術はリアリズムと非リアリズムという対照的な特色に負っていると結論づけた。
Chapter 2では、リアリズムと非リアリズムという観点からさらに前進して、作者と作中人物における主観性と客観性について議論を展開した。チェーホフは、客観的に、主観的に行動する登場人物を描き、シェイクスピアは、主観的に、客観的に行動する登場人物を描いているのである。そしてそのキャラクターの特質の違いが、実際に俳優が演じる時にどのような違いとなって表れるのか考察した。そしてシェイクスピアとチェーホフがそれぞれ『ハムレット』と『かもめ』を書き上げた後、各々、全く逆の方向へと進んでいき、自分の劇作手法を突き詰めていったと論じた。
自分の専門はイギリス演劇ということもあり、英米以外の国の劇作品を丁寧に読み込んだことがなかったが、今回レポートを書くにあたって『かもめ』を何度もじっくりと読んでみて、新鮮な感動があった。そして夢中になってメモをとり続けるうち、いつしかそのメモが膨大な量になり、まとめるのに苦労した。実は、もう一本レポートが書けるほどの材料があり、本レポートのChapter 3としてそれを展開したかったのだが、今回そこまで行くことができずに非常に残念だ。いつか、そのメモを活用して、チェーホフとシェイクスピアで悲劇/喜劇論を書きたい。
今回、シェイクスピアの比較対象としてチェーホフを選んで正解だった。シェイクスピアに関して、いくつかいままで思いもよらなかったようなアイデアを思いついた。ガートルードの溺れゆくオフィーリアについての語りを成立させるためには、現実主義的な人物造形が不適切であるという点や、シェイクスピアは主観的に、客観的に行動する人物を描いているという点などがそれだ。それ以外の思わぬ副作用としては、今回アルカージナとガートルードを比較したことで、ガートルードがなんとも人間味を欠いた人物に見えてきてしまったことだ。これならハムレットが憤るのも無理はない、そう実感してしまった。しかし、そう結論を下すのはまだ早い。何故なら、ジョン・アップダイクの小説を一年以上前に読んだ時に、人間的で魅力的なガートルード像に触れた気がしたからだ。ガートルードに関しては、いずれ再び考察したいと思う。
引用文献
佐々木 基一 『私のチェーホフ』 東京: 講談社 1990.
ウィリアム・シェイクスピア 『ハムレット』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1983.
ウィリアム・シェイクスピア 『冬物語』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1983.
アントン・チェーホフ 『かもめ』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1998.
※『ハムレット』と『冬物語』の行数は、それぞれArden版とOxford版によっている。
参考文献
ジョン・アップダイク 『ガートルードとクローディアス』 訳者 河合 祥一郎
東京: 白水社 2002.
アントン・チェーホフ 『桜の園』 訳者 小野 理子
東京: 岩波書店 1998.
アントン・チェーホフ 『三人姉妹』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1999.
アントン・チェーホフ 『ワーニャ伯父さん』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1999.
G・J・ワトソン 『演劇概論』 訳者 佐久間 康夫
東京: 北星堂書店 1990.
Notes
1 『かもめ』の第三幕に、医師のメドヴェジェンコが、「こんな謎々がありましたね—-朝は四本足、昼は二本足、夕方は三本足……」と言う場面がある。(『かもめ』九五頁)これは、ソポクレスの『オイディプス王』でスフィンクスがオイディプスに出す謎かけである。チェーホフはフロイトのエディプス・コンプレックスを踏まえてこの台詞を書いたのだろうか? しかし、フロイトがエディプス・コンプレックスについて論じた『夢判断』の出版は一九〇〇年であり、チェーホフが『かもめ』を執筆したのは一八九五年である。単なる偶然に過ぎないのか、それとも時代の最先端を行く精神分析に言及したのだろうか。医師であったチェーホフには、精神分析に興味を抱いていた可能性も十分あり得ると思う。
2 ジョン・アップダイクは、『ガートルードとクローディアス』という小説を書き、ガートルードが、犯罪のことなどなにも知らないまま、従順に、懸命に、目の前にいる人を愛する女性であるという解釈を豊かに肉付けしてみせている。
2008/05/02/21:09
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
『冬物語』の「時」の勝利
—ロバート・グリーン『パンドスト』との比較—
米田拓男
Introduction
シェイクスピアの『冬物語』は、シェイクスピアと同時代の作家ロバート・グリーン (Robert Greene, 1560?-1592) の小説『パンドスト』 (Pandosto, 1588) を下敷きにして書かれている。シェイクスピアが用いたのは、言葉遣いなどの共通点からみて、一五八八年版、あるいは一五九二年版のうちいずれかだろうと考えられている。(『冬物語』 217)『冬物語』には、プロットのみならず、グリーンの表現をそのまま使っている箇所もあり、グリーンの『パンドスト』に負うところは大きい。
本レポートでは、『冬物語』と『パンドスト』の比較を行う。材源比較をしてみたいと思ったそもそものきっかけは、この両作品の副題が、共に『時の勝利』 (The Triumph of Time) であることによる。私は以前から、シェイクスピアが、『パンドスト』を元に戯曲を執筆するにあたって、結末を大きく変えたことを知っていた。シェイクスピアのリオンティーズに相当する人物は、『パンドスト』では自ら命を絶ち、悲劇的な末路を辿ることになる。一方、シェイクスピアのリオンティーズは、自分が死に追いやったと信じていたハーマイオニが生きて目の前に蘇り、過去の罪を許される。何故、副題を同じくしながらこうも結末が変わるのか。その理由を知りたいと思った。
二作品には舞台となっているシチリアとボヘミアが入れ替わっているなど、[i]多くの相違点があるが、以下のSection で、具体的な例を挙げていくつかの相違点について論じたい。そして、二作品を比較することにより、シェイクスピアの『冬物語』の執筆の狙いはどこにあるのか、二作品に共通する主要テーマである「時」の性質の違いはどのようなものなのかを明確にすることを目的とする。
Section1 リオンティーズの嫉妬
シェイクスピアの『冬物語』のリオンティーズは、物語の冒頭で、全く突然に激しい嫉妬にかられるように見える。Sir Arthur Quiller-Couch氏は、「これは常に、当然のように、批評家たちの眉をひそめさせてきた」と書いている。[ii]以下は、リオンティーズが初めてその嫉妬心を表明する独白である。
リオンティーズ (傍白)あれの熱心さは
度がすぎる。友情の交換も度がすぎると情欲の交換となる。
この胸騒ぎはなんだ、心臓が踊り騒いでいるが、それは
喜びのためではない、喜びではない。あの歓待ぶりはどうだ、
無邪気な顔をよそおうのも、無遠慮にふるまうのも、
やさしい心からの、ゆたかな胸のうちからのものであって、
女主人にふさわしいことかもしれぬ、それは認めよう。
だが、ほら、あのように手のひらにふれ、指をつねるのは、
そして鏡にでもむかうように作り笑いを浮かべ、獲物を追う
角笛のような溜息をつくのは、ああ、あのような歓待ぶりは
気に入らぬ、寝とられ亭主のしるしである角をはやすのは
まっぴらだ。(『冬物語』 1.2.107-118)
この独白の前に描かれている、ハーマイオニがポリクシニーズに滞在を延期してもらうように頼む場面だけをリオンティーズの嫉妬の根拠とすると、リオンティーズの嫉妬は確かにあまりに唐突なものに思える。それに対して、『パンドスト』では、ハーマイオニ(『パンドスト』作中ではベラリア)とポリクシニーズ(同じくイギスツス)の仲がことさらに親密であることが説明されている。
ベラリア[ハーマイオニ]は、イギスツス[ポリクシニーズ]のなかにもろもろのすぐれた性質に飾られた王者らしい豊かな精神を認め、イギスツスは、彼女のなかに淑やかで親切な性質を見出したので、ふたりの愛情はいつとはなく結ばれ、お互いはなれていることができないほどになった。で、パンドストが緊急の国務にたずさわっていて、イギスツスと席を同じくすることができないときには、ベラリアが彼といっしょに庭園を散歩したり、またそこで、ふたりだけの雅びたたのしいもてないごとのうちに時を過しては、ふたりとも満足するのであった。両者のあいだにこういう習慣がつづいているとき、パンドストの胸には、ある暗い感情が入りこんで、さまざまな疑念に彼を駆り立てたのである。(『パンドスト』 25-6)
この描写を見ると、『パンドスト』でのリオンティーズの嫉妬は、十分根拠があるように思える。シェイクスピアは、『パンドスト』に見られる、このようなリオンティーズが疑念をつのらせていく過程をばっさりと切り捨てた。その理由として、Hallett Smith氏は、「彼(シェイクスピア)は、『オセロー』で嫉妬が心に芽生える過程を描き切ったので、他の芝居でそれを芝居にする必要がなかったのだ」と書いている。[iii]『オセロー』では、嫉妬が人の心にいかに形成されていくかということを描くのに、まるまる一本の戯曲を必要とした。レオンティーズの嫉妬が物語の発端に過ぎない『冬物語』で、嫉妬をつのらせていく過程を描いたとしても、『オセロー』には及ぶまい。それでカットしたのだ。シェイクスピアの関心は他のところにあった。
Nevill Coghill氏は、「レオンティーズは、シェイクスピアが参照している材源の話のように、長い期間に渡り嫉妬して」いたのであって、ここで突然嫉妬心を燃え上がらせたのではないと書く。[iv]私もNevill氏の意見に賛同したい。リオンティーズは、物語が始まる前からポリクシニーズとハーマイオニの関係を怪しんでいたのだ。私は、リオンティーズは二人の関係を確かめたくて、ポリクシニーズの滞在を引き延ばそうとしているのだと思う。だからハーマイオニに故意にポリクシニーズに滞在を引き延ばしてもらうように頼むのだ。
しかし、残念なことに、先に引用したリオンティーズの独白をそのような文脈で読むことはできない。リオンティーズは独白の中で「この胸騒ぎはなんだ」と言う。まるで、今初めて二人の仲を怪しみ始めたような口ぶりなのだ。この齟齬をどのように理解したらよいのだろう。私はここで、『ハムレット』の第三独白を引き合いに出して考えたい。第二幕第二場でハムレットは旅回りの役者たちと話を交わす。そして別れ際に、明日の晩に『ゴンザーゴー殺し』を、台詞を追加して上演してもらいたい旨を伝える。ハムレットは、その直後に第三独白を語る。その独白の中で、ハムレットは、芝居をうってクローディアスが本当に父を殺したのか確認しようと、今まさに思いついたかのように語る。
そうだ、よく聞く話だが、罪を犯したものが
芝居を見ているうちに、舞台の真実に魂をうたれ、
たちまち悪事いっさいを白状することがあるという。
(中略)
あの役者たちには、
叔父の前で、父上の殺害に似た話を
演じさせよう。(『ハムレット』 2.2.584-592)
これを一体どう考えたら良いのか。アーデン版の編者Harold Jenkins氏は、それだけでは説明がつかないとしながらも、Dover Wilson氏の、ハムレットの独白は、彼の心の中にすでに感じたことを表現しているのだとする理論を紹介している。(Jenkins 273)高橋康也氏と河合祥一郎氏による大修館シェイクスピア双書の註では、「役者を見たとき閃いた考えがここでようやく表現されたと解釈すべきであろう。独白の占める想像的な時空間は、リアリズムあるいは古典主義的な時計の針の動きから自由である」と記されている。(高橋 209)
リオンティーズの独白も、この『ハムレット』の第三独白と同じように考えれば良いのではないか。リオンティーズの独白は、彼がリアルタイムで考えていることだけを述べているものではなく、ポリクシニーズが滞在していた九ヶ月の月日の間に思っていたことをも内在しているのだ。シェイクスピアは観客にリオンティーズの心情の変化を理解してもらうために、ここで一度整理して独白によって語らせているのだ。
Section2 時間の省略
シェイクスピアが、リオンティーズが嫉妬心をつのらせていく過程を切り捨てたもう一つの理由として、時間の短縮ということが挙げられる。シェイクスピアは材源の物語を芝居にするにあたって、大胆といえるほどの時間の圧縮を行うことがよくある。『ロミオとジュリエット』の場合は、材源であるアーサー・ブルックの長篇詩で九ヶ月に渡る物語を四日間に圧縮した。『オセロー』では、オセローとデズデモーナの長期に渡る結婚生活を一昼夜半に凝縮した。『冬物語』でも、リオンティーズの嫉妬の過程以外に、多くの時間の省略が行われている。
シェイクスピアの『冬物語』では、ハーマイオニは登場した時から妊娠している。
侍女1 ねえ、王子様、
お母様のおなかは日一日と丸くおなりでしょう、
私たちが新しい王子様にお仕えすることになるのも
もうすぐです。(『冬物語』 2.1.15-16)
それに対して、『パンドスト』ではハーマイオニ(ベラリア)は、リオンティーズに貞節を疑われ投獄された後、獄中で妊娠していることに気付く。そして獄中で出産するのだ。そのため原作では、獄中で数カ月経過しているはずである。ポリクシニーズ(イギスツス)が何ヶ月滞在していたのかは判らないが、九ヶ月である必要は無い。『冬物語』では、ポリクシニーズはシチリアに九ヶ月滞在していることになっているが、私には、一国の王が親睦のために滞在する期間としてはいささか長すぎるように感じられる。シェイクスピアの作意が感じられる部分である。
シェイクスピアは、パーディタの成長の過程も切り捨てた。『パンドスト』では、幼少のパーディタ(フォーニア)が、七歳、十歳と成長していく過程が描かれている。
夫婦ともその子が大好きになったが、子どもは年を重ねるにつれていよいよ美しくなっていった。羊飼いは毎晩帰宅すると、その子を膝にのせ、歌を聞かせたり、踊らせたり、おしゃべりをしたりで、子どもも物を言うようになり、彼を父(とう)、彼女を母(まあ)、と呼びはじめた。(『パンドスト』 56)
それに対して、シェイクスピアは擬人化した語り手としての「時」を登場させ、十六年の時を一挙に経過させてしまう。
また、『冬物語』のパーディタとフロリゼルは、登場した時から相思相愛の仲である。
フロリゼル このような草花を身につけていると、きみのからだは
どこもかしこも生き生きと見える。羊飼いの娘ではない、
四月のはじめに姿を見せる花の女神フローラだ、きみは。
この毛刈り祭りというのはかわいらしい神々の饗宴のようだ、
そしてきみはその女王なのだ。
パーディタ まあ、王子様ったら。(『冬物語』 4.4.1-5)
しかし、『パンドスト』では、二人が初めて出逢う場面が描かれている。パーディタ(フォーニア)を初めて見たフロリゼル(ドラスツス)は、心ではパーディタの美しさに惹かれながらも、その気持を自ら否定しようとする。
非の打ちようのないフォーニアが、彼の愛情をはげしく燃え立たせたために、気持も大きくかわり、感情も改まったように感じて、こんな変化を生んだ恋を呪い、こんな選択をしたがるわが心の卑しさを咎めるのであった。が、こうした思いも、とるに足りない感情にすぎないものであって、自分の好き勝手に抛り出せるものだと考え、自分を魅惑した魔女を避けようと、彼は乗馬に拍車を当てると、この美しい羊飼い女に別れを告げた。(『パンドスト』 63)
シェイクスピアはこのような、十分劇的な場面となりうる箇所をあっさりと棄てている。
これらの改変からは、「時」のコーラスの導入がその最もたる例であるが、シェイクスピアの作意が感じられる。シェイクスピアは、「人間なんて、十六から二十三までの年がなきゃあいいんだ」(3.3.58 -9)と言って登場する羊飼いのように、気に入らない場面を片っ端から切り落としてしまったのだろうか。否。これらの改変により、余分なものが削ぎ落とされている分、リオンティーズの嫉妬や、フロリゼルとパーディタの愛といったものが、純化されていると考えることができるのではないか。シェイクスピアは、作為を持って、作為的な改変を行ったのだ。シェイクスピアが自らそのことを表明しているととれる台詞がある。
ポリクシニーズ 娘さん、どういうわけで
あの花をさげすむのだな?
パーディタ あの赤と白とのまだら模様は、
偉大な造化の自然に人工の手が加わってできたもの、
と聞いておりますので。
ポリクシニーズ それはそうかもしれぬ。だが、
なんらかの手を加えて自然がよりよくなるとすれば、
その手を生み出すのも自然なのだ。したがって、
自然にたいして加えたとあなたの言うその人工の手も、
実は自然の生み出す手に支配されているのだ。いいかな、
野育ちの幹に育ちのいい若枝を嫁入らせることによって、
卑しい木に高貴な子を宿らせることがあるだろう、
これは自然のたりないところを補う、と言うより、
すっかり変えてしまう人工の手だ、しかし実は
その人工の手そのものが自然なのだ。(『冬物語』 4.4.85-97)
かつてシェイクスピアは、ハムレットに「芝居というものは、昔もいまも、いわば自然にたいして鏡をかかげ、善はその美点を、悪はその愚かさを示し、時代の様相をあるがままにくっきりとうつし出すことを目指しているのだ」と言わせた。(『ハムレット』 3.2.19-23)シェイクスピアは今では、自然に人工の手を加えることも、大きな目で見れば自然の一部であると考えているかのようである。[v]ここに私は、シェイクスピアの達観した演劇/芸術観を見る。彼の中では、もはや自然と人工は相対するものではなくなっていたのだろう。
Section3 彫像の場
シェイクスピアによる『パンドスト』からの改変の最大のもの、それは物語の結末の付け方にある。『パンドスト』も『冬物語』と同じようにパーディタ(フォーニア)とフロリゼル(ドラスツス)の結婚によって幕を閉じるが、リオンティーズ(パンドスト)が自殺することによって苦い後味を残す。
イギスツス[ポリクシニーズ]はこのめでたい出来ごとを聞くと、息子[フロリゼル]の幸運を大いによろこび、ふたりの若い恋人たちには絶え間ないよろこびであったが、時を移さず結婚の賀宴を張ったのであった。終わるやいなや、パンドスト[リオンティーズ]は、彼が最初に朋友イギスツスを裏切った次第、彼の嫉妬がベラリア [ハーマイオニ]の死因となった経緯、また自然の掟にそむいて彼がわが娘に欲情を抱いた経過を思い出して絶対絶命の想いに駆られ、鬱病におち入り、この喜劇を悲劇の大団円で締めくくろうと、われとわが身を滅ぼしたのであった。(『パンドスト』 105)
それに対して『冬物語』では、リオンティーズの目の前で自分が死に追いやったと思っていたハーマイオニが彫像から蘇る。
ロバート・グリーンの『パンドスト』は、当時、大変人気のあった作品だったという。(『冬物語』 217)ということは、『パンドスト』と同じ結末を予測しながら観ていた観客が沢山いたということを意味する。そうであるならば、シェイクスピアによるエンディングの改変は、大きな衝撃だったはずだ。Nevill Coghill氏は、彫像の場で観客にハーマイオニの死を信じさせるために、シェイクスピアがそのステージ・クラフトに独自の工夫を施したことを論じているが(Coghill 39-40)、『パンドスト』の話が一般に流布していた当時の観客にとっては、それはより有効に働いたことだろう。
現実的に考えれば、ポーライナがハーマイオニを十六年間も匿っておき、その間、葬儀も済ませることはちょっとあり得そうにない。最後にハーマイオニが復活する場面が、それまでの展開から一見つながらないように思えるのは、シェイクスピアが原作の最後を改変していることに起因しているのではないか。だが、現実らしさを犠牲にし、観客に多少の違和感を感じさせてしまったとしても、シェイクスピアは最後をハッピー・エンドに書き換えたかったのだ。
思えば、シェイクスピアによる『パンドスト』からの改変箇所には明るく、喜劇的で、ポジティヴな要素が多い。威勢のいいおばさんといった風情のポーライナや、劇に喜劇的な要素を加味しているオートリカス、羊飼いの息子の道化は、シェイクスピアの創作である。シェイクスピアは『ロミオとジュリエット』を書く際にも、乳母とマキューシオという喜劇的な人物を大きく書き換えている。さらには、熊や時を舞台上に登場させるといった趣向も、前半の悲劇的な展開から喜劇へ転換する際の、蝶番の役割を担っていると考えることができる。原作へのこれらポジティヴな要素の追加は、物語の印象を大きく変えることになった。その際たるものがエンディングの変更である。しかし、エンディングの変更は、物語の印象を大きく変えたというにとどまらない。『パンドスト』も『冬物語』も、副題は共に『時の勝利』である。エンディングの変更は、この「時の勝利」の意味をも変えることになった。
『パンドスト』における「時の勝利」とは、パンドストに対する「時の勝利」を意味する。つまり、悪いものは「時」によって、結局裁かれる、ということ。『パンドスト』の物語を読み終えた読者は、因果応報、というありがたい教訓を頂戴して本を閉じることになる。しかし、シェイクスピアの「時の勝利」に、そのような教訓めいたニュアンスはない。では、シェイクスピアの『冬物語』における「時の勝利」とは、どのようなものか。シェイクスピアは、自分の妻や子供たちを死に追いやろうとしたリオンティーズに対して、許しを与える。「時」が人の罪を許す。『冬物語』の「時」は、そのようなものとして描かれている。人の弱さをも受け入れる「時」。この「時」寛容さは、前のSectionで述べた、人工をも受け入れる自然、という自然の寛容さに符合しているように思える。
観客は、いつの時代も、娯楽に教訓など求めない。一体、誰が、説教を聞きに劇場に足を運んで金を払うだろう。説教を聞きたいのなら教会にでも行った方がましである。シェイクスピアはそのことを良く知っていた。『パンドスト』の教訓めいた物語から許しの物語へ。シェイクスピアは『ロミオとジュリエット』でも、材源の長篇詩が持っていた説教臭さを見事に抜き取り、ロミオとジュリエットの悲劇を、情熱的な恋の物語として昇華させた。
『冬物語』の副題としての『時の勝利』とは、なんとも心憎いタイトルだ。『冬物語』の「時」は、悪をも許す。そしてその寛容さにおいて「時」は勝利しているのだ。『パンドスト』よりも懐の大きい「時」。より寛容な「時」。『冬物語』の「時」は、『パンドスト』の「時」に勝利している。
引用文献
Adelman, Janet. ‘Masculine Authority and the Maternal Body in The Winter’s Tale.’
Coghill, Nevil. ‘Six Points of Stage-Craft in the Winter’s Tale.’
ロバート・グリーン 『パンドスト王・いかさま案内他』 訳者 多田 幸蔵
東京: 北星堂書店 1972.
Shakespeare, William. The Arden Shakespeare Hamlet. Ed. Harold Jenkins. California: Methuen And Co. Ltd, 1982.
ウィリアム・シェイクスピア 『ハムレット』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1983.
ウィリアム・シェイクスピア 『ハムレット』 編者 高橋康成・河合祥一郎
東京: 大修館書店 2001.
ウィリアム・シェイクスピア 『冬物語』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1983.
Smith, Hallett. Shakespeare’s Romances. California: The Huntington Library, 1972.
※『ハムレット』と『冬物語』の行数は、それぞれArden版とOxford版によっている。
参考文献
Bloom, Harold. ed. Modern Critical Interpretations The Winter’s Tale. New York: Chelsea House, 1987.
Sanders, Wilbur. Harvester New Critical Introductions to Shakespeare The Winter’s Tale. Sussex: The Harvester Press Limited, 1987.
Shakespeare, William. The Oxford Shakespeare The Winter’s Tale. Ed. Stephen Orgel. New York: Oxford University Press, 1996.
Notes
[i] ここでしばしば、ボヘミアには海岸が無いということが問題となる。蒲池美鶴氏は、白水Uブックスの解説にシェイクスピアは「原作のボヘミアとシチリアをわざわざ入れ替え、「ボヘミアの海岸」などという実際にはありえない場所をつくり出した」(『冬物語』 217)と、書いているが、原作中にもボヘミアの海岸はしっかり登場する。
市の裏門からこっそり、すばやく出て行ったので、誰にも疑われず海岸についたからである。そこでは、さかんにののしりながらボヘミヤに別れを告げて上船した。(『パンドスト』 34)
船員たちは、ボヘミヤの海岸を発見すると、かくも恐ろしい嵐から逃れおおせたよろこびに、祝砲をうち出すのであった。(『パンドスト』 90)
港が、パンドストの宮廷のあるボヘミアの首都にあるものだ、と船員に聞くと、ドラスツスは悲しくなりはじめた。(『パンドスト』 90)
[ii] ‘This has always and rightly offended the critics.’ (Coghill 31)
[iii] ‘Shakespeare changed all this, because he had fully portrayed the growth of jealousy in Othello and had no need to dramatize it in another play.’ (Smith 102)
[iv] ‘It is clear that Leontes, as in the source-story which Shakespeare was following, has long since been jealous and is angling now (as he admits later) with his sardonic amphibologies, to catch Polixenes in the trap of invitation to prolong his stay, before he can escape to Bohemia and be safe.’ (Coghill 33)
[v] フェミニズム批評のJanet Adelman女史は、論文 ‘Masculine Authority and the Maternal Body in The Winter’s Tale’ の中で、『冬物語』の中で「造化の神を欺く」という言葉が使われていることを根拠に、この芝居は芸術家ジュリオ・ロマーノの「人工的な作品を決定的に否定」していると書いているが、(Adelman )私にはそうは思えない。語り手「紳士3」のただの強調に思える。以下、その箇所からの引用。
紳士3 いや、姫君がポーリーナ様ご所蔵の母上の彫像のことをお聞きになり——それはイタリアの巨匠ジューリオ・ロマーノが長い歳月をかけて製作し、やっとこのほど完成したものだが、ロマーノ自身、自分の作品に息を吹きこむ永遠の力が与えられていたら、造化の神を欺いてそのまねをしたいと言っているほど、ハーマイオニ様そっくりのハーマイオニ様の像だという。(『冬物語』 5.2.92-98)(下線筆者)
2008/05/02/21:08
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
Shakespeare時代の舞台照明
米田 拓男
Introduction
本論では、William Shakespeare(1564-1616)が劇作を行っていた十六世紀末から、十七世紀初頭にかけての、劇場における照明効果について論じる。Shakespeareが劇作を行っていた時期には、彼の作品は大きく分けて三種類の劇場で上演されていた。一つ目はthe Globe theaterに代表されるような屋外劇場。二つ目がHampton CourtやWhitehallなどといった宮廷での上演。そして三つ目は当時出来たばかりのBlackfriarsといった屋内劇場である。各Chapterごとにそれぞれの劇場での照明効果について、具体的にShakespeareの作品と関連付けながら論じて行きたい。
Chapter 1 屋外劇場
Shakespeare時代の劇場といえば、屋外劇場が一般的であり、Shakespeareが所属していた劇団、the Lord Chamberlain’s menもthe Globe theatreという屋外劇場を所有していた。屋外劇場の舞台空間における主要な光源は、当然ながら、太陽からの自然光であり、上演は、日照時間や天候といった自然条件に左右された。1 そのため、十六世紀末の屋外劇場では昼に上演されるのが一般的だった。2 屋外劇場でも、松明やロウソクなどの人工照明が用いられることはあったが、それは主に芝居の中で使われる小道具としてであった。
残されている様々な記録から判断すると、シェイクスピアの時代、十六世紀末から十七世紀初頭にかけての屋外劇場での開演時間は、午後二時から四時くらいであったようだ。3 以下に挙げたのは、十六世紀末のロンドンでの日の入り時刻である。
Sunset Times in London, 1598 (Old-Style Dates)
|
1st |
7th |
14th |
22nd |
28th |
| January |
3:57 |
4:06 |
4:14 |
4:27 |
4:37 |
| February |
4:46 |
4:51 |
5:10 |
5:26 |
5:38 |
| March |
5:40 |
5:52 |
6:06 |
6:20 |
6:24 |
| April |
6:24 |
6:54 |
7:06 |
7:21 |
7:31 |
| May |
7:37 |
7:45 |
7:55 |
8:04 |
8:09 |
| June |
8:11 |
8:14 |
8:15 |
8:13 |
8:09 |
| July |
8:06 |
8:01 |
7:53 |
7:40 |
7:30 |
| August |
7:13 |
7:13 |
7:00 |
6:44 |
6:33 |
| September |
6:26 |
6:14 |
5:58 |
5:44 |
5:33 |
| October |
5:26 |
5:14 |
5:00 |
4:45 |
4:34 |
| November |
4:27 |
4:17 |
4:07 |
3:57 |
3:51 |
| December |
3:48 |
3:46 |
3:45 |
3:48 |
3:52 |
(Graves 70)
この表では、縦の列が月を表し、横の列が月の日にちを表している。
当時の芝居の上演時間は大体三時間程度だったようだ。4 すると、表の十六世紀末の開演時間は二時から四時なので、芝居が終わるころは夕方だったはずである。開演時刻を仮に午後二時ちょうどで、上演時間がぴったり三時間だったとする。その場合、上演終了時刻は午後5時ちょうどということになる。そうなると、芝居が終わる時間が日没を過ぎるのは、十月十四日から、二月七日あたりまでの四ヶ月間ということになる。あるいは、もしもその開演時間が三時であったならば、上演終了が午後六時ということになり、一年のうちの半分(九月の半ばから、三月の半ばまで)が、芝居が終わるころには日没を過ぎていたことになる。
このような日照時間の変化は、作品の上演にも影響を与えていた筈だ。ジョン・ウェブスターの『モルフィー公爵夫人』のタイトルページには“with diverse things . . . that the length of the Play would not beare in the Presentment”「その芝居の最初から最後までの全てが実際に上演された訳ではなかったようだ」という記述が見られる。そこからGravesは、早い日の入り時刻が芝居を削った主要な理由の一つであったのではないかと主張している。(Graves 84)
このように当時の芝居作りは、自然環境に左右さる側面があった。しかし、それが芝居の中で劇的な効果をあげたかもしれない場面がある。Shakespeareの『ロミオとジュリエット』の五幕三場、パリスがジュリエットの眠る墓地へやってくる場面である。
パリス 松明をよこせ。向こうへ行っていろ。
いや、松明は消してくれ、人に見られたくない。
(『ロミオとジュリエット』5.3.1-2)
パリスが松明を持った小姓とともに登場し、小姓に松明の火を消させて暗闇の中に身を隠す。そこへ松明をバルサザーに持たせ、ロミオが登場するのだ。『ロミオとジュリエット』は、あたりが夕闇に包まれた当時の屋外劇場で劇的なクライマックスを迎えただろう。この場面では、Shakespeareは日没という自然現象までをも舞台演出として考慮して、劇作をしていたのかもしれない。
Chapter 2 宮廷での上演
Shakespeareの作品は当時、屋外劇場のみならず、余興として宮廷においても上演された。例えば、一六〇二年二月二日には『十二夜』がHampton Courtで上演された記録が残っている。Shakespeareの所属する劇団が屋内劇場the Blackfriarsを所有するのは一六〇九年である。しかし、それ以前の一五九四から一六〇八年の間に、まだ屋内劇場がほとんどなかった時期に、少なくとも九十三の屋内での上演の記録が残されているという。(Graves 196) それらの宮廷での芝居やマスクの上演は、夜の十時頃から始まり、深夜の一時半や二時にまで及んだらしい。ある司祭などは、一六一八年一月十七日のBen JonsonのPleasure Reconciled to Virtueの上演が深夜にまで及び、くたびれ果てて家路についたことを日記に書き残している。(Graves 158-9)
そういった宮廷での上演が夜に行われていた以上、自然光を舞台に取り入れることはできない。それでは具体的にどのような照明機具が用いられていたのだろうか。記録によると、宮廷での上演に使われた主要な照明機具は、branchと呼ばれる燭台であったようだ。それはホールの天上からシャンデリアのように吊るされていて、Shakespeareが所属していたthe Lord Chamberlain’s menが上演していた一五八三年のウィンザーのホールには、二十六の小さなbranchと三つの大きなbranchが備えられていたようだ。(Graves 160-1)そしてそれぞれのbranchには、一五七六から八八年頃にかけては、合計百四十一本のロウソクが載っていたという。ロウソクの数はその後増えていき、一六一一年に『テンペスト』と『冬物語』が上演された時には、ひとつのbranchに最低でも百八十本のロウソクが載せられていた。(Graves 163)
この屋内上演での照明機具の発達も、実際の芝居の上演になにかしらの影響を与えた筈だ。『リア王』はthe Globe theatreで上演されていた時、同時にWhitehall でも上演されていた。Whetehallでは自然光は使われておらず、薄明かりの中で上演された。Whitehall は、天上にたくさんのロウソクが吊られている。嵐の中、荒野でリアが天に向かって嘆く場面では、観客は、the Globe theatreのような屋外劇場で見るものと全く違うものを見ていたはずである。Gravesは人の力の及ばない自然を前にした、リアの無力感よりも、闇さえコントロールする、人間の人工的な制御の力を強調することになるのではないかと主張している。
Chapter 3 the Blackfriars
Shakespeareの所属しているthe Lord Chamberlain’s Menは、一六〇八年にthe King’s Menとして新たなスタートを切り、the Globe theatreに次ぐ第二の私設劇場the Blackfriarsを購入した。 (Campbell 765) the Brackfriars は屋内劇場で、窓から取り入れる自然光と人工的なロウソクの光とを併用していた。また、the Blackfriearsは冬にだけ使われていた。冬のthe Globe theatreは冷え込むため、代わりにthe Blackfriarsを使用していたようだ。
そこでの上演時間は、現存する、近隣の住民の枢密院への苦情の手紙から、二時から五時頃までだったと推定できる。5 また同じ時期に女王Henrietta Mariaが楽しみのために夜にも上演していたという記録も残されているようだが、GravesはBlackfriarsでの夜の上演は特別な例であったと主張している。(graves 128)
the Blackfriarsでの上演は主に昼に行われていたので、自然光を舞台照明に使うことが出来た。一六〇六年にThomas DekkerはThe Seven Deadlie Sinns of Londonの中で、典型的なロンドンの日暮れを屋内劇場の喩えを使って描写している。
“all the Citty lookt like a private Playhouse, when the windowes are clapt downe, as if some Nocturnal, or dismall Tragedy were presently to be acted before all the Tradesmen.” (Graves 132)
「街の全景はまるで窓が閉められている時の屋内劇場のように見える。あたかもあの夜の劇(nocturnal)や、陰鬱な悲劇が、いままさに商人たちの前で上演されているかのように。」
この文章は、日中でのいくつかの屋内劇場での上演では、窓を閉めて外の光が入らないようにしていたことを示唆している。さらには、窓を開けていれば入って来る光をわざと入らないようにしていたことを示しているので、屋内劇場での照明効果は、単に舞台上にあるものを視覚的に見えやすくするためだけではなく、芝居の審美的な価値を高めるためにも使われていたことが分かる。この文章はまた、コメディーやロマンスなど、他のジャンルの芝居を上演する時には窓を開けていた可能性があることをも強く示唆している筈だ。
G. E. Bentleyは、一九四八年に発表した“Shakespeare and the Blackfriars Theatre”という論文の中で、Shakespeareは後期のロマンス劇と呼ばれる作品群を、このthe Blackfriarsで上演することを強く意識して書いたのではないかと主張した。(Campbell 790) 彼は、Shakespeareがロマンス劇を書くことで、the Blackfriarsの新しい観客を楽しませる方法を模索していたのだと考えた。6 実際、Shakespeareには『冬物語』というロマンス劇がある。そのタイトルは、冬にだけ使用されていたthe Blackfriarsで上演するのにうってつけのように思える。
そしてその数年後、Alfred HarbageがBentleyの研究を踏まえて、Shakespeare and the Rival Traditions (New York, 1952)を書き、ロマンス劇とそれ以前の作品の作風の違いは、屋内と屋外、どちらの劇場で上演することを意図して書かれたかに起因するのではないかと指摘した。BentleyもHarbageも共に、劇場の物理的な構造が、ある程度までそこで上演される芝居の形式や意味を規定してしまうと考えた。(graves 5) ジェームズ一世時代の屋内劇場という新しい舞台空間と、そこに集まるより洗練された観客の嗜好が、そこで演じる役者や劇作家に変化することを求めたのだろう。
Conclusion
Shakespeareの作品は現代においては聖典として扱われている。上演の際にも、英語を母国語とする人々が台詞を削除することはあるが、書き換えることはまずありえない。本レポートでは、Shakespeareの時代の照明を、劇場の種類ごとに見ていきながら、聖典として、不動のものとして扱われているShakespeare作品が、劇場の物理的な環境に大きく影響されて書かれたことについて論じた。
Chapter 1では、『ロミオとジュリエット』が屋外劇場での日の入りを意識して書かれた可能性について。Chapter 2では、恐らくは屋外劇場で上演することを意図して書かれた『リア王』が、宮廷で上演された時に生じたはずの違和感について。Chapter 3では、the Blackfriarsという新しい舞台空間がShakespeareにロマンス劇の作品群を書かせた可能性についてそれぞれ論じた。
今回のレポートは、R. B. GravesのLighting the Shakespearean Stage 1567-1642にその多くを負っている。この書物は当時の舞台空間について、照明という一つの側面から徹底的に論じたもので、とても興味深く読んだ。本レポートでも引用しているような、当時の演劇界の上演状況を忍ばせる記述を読むのは大きな楽しみであった。
引用文献
Campbell, Oscar James, ed. The Reader’s Encyclopedia of
Shakespeare New York: Thomas Y, Crowell Company,
1966.
Graves, R. B. Lighting the Shakespearean Stage 1567-1642.
U. S. A.: Southern Illinois University
Press, 1999.
Shakespeare, William. Romeo and Juliet. Trans. Kazuko
Matsuoka. Tokyo: Chikumashobo, 1996.
Notes
1 その自然環境は、屋外での上演に適したものではなかったかもしれない。Gravesは、 ‘London is not famous for its sunshine, and what evidence we have indicates that the weather in Shakespeare’s time was rather worse than it is now’ 「ロンドンは自然光に恵まれているとはいえず、現在ある証拠がシェイクスピア時代の天候は、現在よりだいぶ悪かったことを示している」と論じている。(Graves 84)
2 フィリップ・ヘンズローの日記に、the Admiral’s menによる夜の上演の記録が一つだけ残されている。“lent vnto the company when they fyrst played dido at nyght the some of thirtishillynges wch wasse the 8 of Jenewary 159[8].” (Graves 80) (下線筆者)しかし、Gravesは、それは特殊な例であったと考えている。
3 Looking at the whole period, we can say with confidence only that the public playhouses usually began performances anywhere from 2 P.M. to 4 P.M. Chronologically speaking, the times recorded before 1594 refer most often to around 4 P.M., at the turn of the century perhaps more towards 2 P.M., and closer to 3 P.M. some fifteen years later. (Graves 80)
4 Although the “two hours’ traffic” of the stage from the prologue to Romeo and Juliet is often quoted normatively, it is likely that most full entertainments at the public playhouses lasted closer to three hours. (Graves 82)
5 In a letter to the Privy Council, neighbors protested that “multitudes of Coaches” clogged the streets and disrupted business “almost everie daie in the winter tyme . . . from one or twoe of the clock till sixe att night, which beinge the tyme alsoe most vsuall for Christenings and burialls and afternoones service.” Certainly the play did not last from 1 to 6 P.M.; it must have required at least an hour before and after the performance for the coaches to push through the traffic. (Graves 127-128)(下線筆者) ‘almost everie daie in the winter tyme’という記述からもthe Blackfriarsが冬にだけ使用されていたことが分かる。そしてその後に続いて、「一時か二時頃から午後六時まで、あたかも洗礼式や、葬式、あるいは午後の兵役、労働のように喧しい」ということが書いてある。一時から六時頃までいつもうるさかったという記述から、観客の入場と退場の時間を考えれば、 the Blackfriarsでの上演時間は二時から五時頃だったことが推定できる。
6 Gravesによれば、Blackfriarsは冬にだけ使われていたらしい。 ‘For although some hall playhouses were used only in the winter (the King’s men’s Blackfriars, for instance), Salisbury Court has left behind records of a number of summertime plays’ (Graves 130) Shakespeareはthe Blackfriarsを念頭に置いて『冬物語』を書いたのかもしれない。
2008/05/02/21:06
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
Burbage as Hamlet
Takuo Yoneda
Introduction
Richard Burbage was the most famous actor in Shakespeare’s time. He played Hamlet throughout his acting career and, as this discussion demonstrates influenced Shakespeare’s writing Hamlet more than critics have been willing to admit. In the first section I will bring forward evidence on the production of Burbage’s Hamlet from extant documents and compare these documents with the three different early versions of the play. Because Hamlet’s age is different in each text, I will argue that Burbage’s age and his growth in playing the part of Hamlet influenced key revisions in these early versions.
In the second section I will compare the Second Quarto with the First Folio. And I will argue that Shakespeare intended to rewrite Hamlet.
In the third section I will discuss the relationship between Shakespeare’s Hamlet and the non-extant Ur-Hamlet that critics have forwarded as a possible source of the play. And I will examine the possibility that Burbage played the lead in Ur-Hamlet.
Section 1 Burbage in Hamlet
At the beginning of the 1623 First Folio of Shakespeare’s work, there is a list of ‘the principal actors in all these plays.’ (Campbell 229) William Shakespeare’s (1564-1616) name is at the head of the list. He acted in his own plays and other playwright’s plays. Legend goes that he played the ghost of Hamlet’s father and the old servant Adam in As You Like It (ca.1600). He was a playwright, an actor and, at the same time, a stockholder of the Globe theatre.
Richard Burbage’s name appears next to Shakespeare. He was a star actor of the Lord Chamberlain’s Men and the King’s Men. He also had stock in the Globe theatre. His father, James Burbage (1530 or 1531-1597), built the first public playhouse in London in 1576, the Curtain Theatre. And his brother, Cuthbert Burbage (1566-1636), moved the playhouse to the south bank of the Thames in 1599 and called it the Globe Theatre. Hamlet was written in ca.1600.[i] So the first production of Hamlet would have likely taken place in the Globe Theatre. At the time it appears that Shakespeare was 36 years old and Burbage was 29 years old.[ii]
It also appears that Burbage played Hamlet. Following is the quotation from an extant elegy for the death of Richard Burbage.
He’s gone and with him what a world are dead,
Which he revived, to be revived so.
No more young Hamlet, old Hieronimo,
Kind Lear, the grieved Moor, and more beside,
That lived in him, have now for ever died. 5
Oft have I seen him leap into the grave,
Suiting the person, which he seemed to have,
Of a sad lover, with so true an eye
That there I would have sworn he meant to die;
Oft have I seen him play this part in jest, 10
So lively that Spectators and the rest
Of his sad crew, whilst he but seemed to bleed,
Amazed, thought even then he died indeed. (emphasis added)
From A Funeral Elegy on the Death of Richard Burbage
March, 1618 (Farley-Hills 9)
This elegy points out clearly that he acted Hamlet, Hieronimo in The Spanish Tragedy (1582-92), King Lear and Othello. Moreover, this elegy also hints of a production of Burbage’s Hamlet.
Oft have I seen him leap into the grave,
Suiting the person, which he seemed to have,
Of a sad lover, with so true an eye
That there I would have sworn he meant to die; (6-9)
You may call these lines one excellent theatrical note. This elegy tells the most detailed report giving us a glimpse of what the play was like to its first audience. The ‘young’ Hamlet as the ‘sad lover’ leaped into the grave of Ophelia. The reference, also, to his “true eye” echoes Hamlet’s amazement at the ability of visiting players to feign sorrow.
The reference to ‘young’ Hamlet suggests that Elizabethan audience regarded Shakespeare’s Hamlet as a younger man than most current editions of the play indicate. David Scott Kastan says the description of Hamlet as ‘young Hamlet’, may have been “regular in use,” and it gives us “a valuable suggestion as to something vital in the tragedy that we have now largely lost” (Kastan 244).[iii]
[This point may not be necessary in the end, let’s see] Another then current description of the play offers us another clue about how the Hamlet was performed. Following is a quotation from Diaphantus (1604) by Anthony Scoloker.
Puts off his clothes, his shirt he only wears,
Much like mad Hamlet; (Wilson 1935, 97)
These lines tell us about Hamlet’s appearance. This costume style clearly remains for us as a stage-effect of our time.
Then, what kind of appearance did Burbage have? A key to solve the question is in the text of Hamlet. There are notorious lines [in which version?] that may mention the appearance of Hamlet.
Queen. He’s fat and scant of breath.
Here, Hamlet, take my napkin rub thy brows.
The Queen carouses to thy fortune, Hamlet. (5.2.290)
John Dover Wilson writes as follows.
The notion that “fat” refers to the hypothetical corpulence of Burbage is absurd on the face of it; for, if the player was actually growing over-stout for the part of “young Hamlet” in 1601, the last thing Shakespeare would do would be to draw attention to the fact. (Wilson 1935, 284)
On the other hand, Shouichirou Kawai argues that ‘fat’ was used as good epithet. According to Kawai, ‘fat’ stood for French ‘embonpoint,’ in other words, lusty plumness (Takahashi 379). So he insists that this ‘fat’ implied Burbage’s good physique. Harold Jenkins also mentions this ‘fat’ in his longer notes for the Arden Edition.
The precise meaning of this word is difficult to establish. But few now see in it an allusion to the actor’s corpulence, any more than in the ‘thirty years’ since Hamlet’s birth a reflection of Burbage’s age. (Jenkins 568)
Jenkins denies the possibility that the ‘fat’ reflected Burbage’s fatness, but he accepts that it related with his age. If these hypotheses had been true, Shakespeare might change the lines according to each actor.
Hamlet has three substantive texts: the First Quarto (Q1) (1603), the Second Quarto (Q2) (1604) and the First Folio (F) (1623). George Ian Duthie argues Q1 was based on some actors’ ‘memorial reconstruction’ (Takahashi 18). One or more actors who appeared in Hamlet likely reconstructed the text by memory. Q2 published as ‘the true and perfect Coppie’ (Jenkins 36) within 5 years after in the first performance of Hamlet. This text probably represents foul papers. And after Shakespeare’s death F was published. Presumably, it represents the play as it was performed during his lifetime, perhaps with his own cuts and alterations. F is also based on foul papers and earlier quartos. Though there are many differences between these three texts, it should be noted that the settings of Hamlet’s age are different in each text. Followings are the lines in the Gravedigger’s Scene. Hamlet asks gravedigger.
How long hast thou been grave-maker?
Grave. Of all the days i’th year I came to’t that day that
our last King Hamlet o’ercame Fortinbras.
Ham. How long is that since?
Grave. Cannot you tell that? Every fool can tell that. It was that very day that young Hamlet was bourn (5.1.138-43)
And a little farther on the gravedigger says ‘I have been sexton here, man and boy, thirty years’ (156-7). Judging from these lines, Hamlet should be 30 years old in F. In Q2 Hamlet should be 19 years old.[iv] And in Q1 Hamlet should be more than 12 years old because there is no reference to the sexton’s thirty years at his job. The gravedigger says that Yorick who took care of Hamlet in early boyhood had been in the grave for a ‘dozen’ years.
Today, Shakespeare’s texts have been treated canonized. Shakespearean actors and directors are bounded by the text. You can cut and move lines and scenes but cannot rewrite a line by Shakespeare. But when Shakespeare was alive, his texts were not treated with such reverence. Shakespeare himself apparently flexibly rewrote his own text. There existed interaction between Shakespeare and his actors and audience. So it is certainly likely possible that Shakespeare rewrote and revised his texts frequently using feedback from actors and audience . These revisions, moreover, may have occurred to suit the practical needs of the commercial stage rather than as a self-conscious attempt to pen immortal verse.
Section 2[v] Young Hamlet and Adult Hamlet
Hamlet’s age is different in each version of the play: Q1, Q2 and F. Given a bit of cross-referencing, it seems likely that Shakespeare could have rewritten the character of Hamlet to accommodate Burbage as he began to age. It is also likely that Shakespeare rewrote certain elements of Hamlet’s behavior and deeds to fit his age of his actor rather than his fictional character. I will compare Q2 with F because both of them were thought to be based on foul papers. The character of Hamlet in F is more mature than the Hamlet of Q2. For example, before the fencing match with Laertes Hamlet apologizes to Laertes after Gertrude asks him to do so (through the character of the ‘Lord’) in Q2.
Lord. The Queen desires you to use some gentle entertainment to Laertes before you fall to play.
Ham. She well instructs me. (5.2.202-4)
On the contrary, the Lord doesn’t enter in F. And Hamlet apologizes to Laertes on without being prompted by his mother.
But I am very sorry, good Horatio,
That to Laertes I forgot myself;
For by the image of my cause I see
The portraiture of his. I’ll court his favours. (5.1.75-78)
{need to comment briefly on the meaning of this quotation. This suggests Hamlet’s maturity.
The following is another example. As soon as Rosencrantz and Guildenstern meet Hamlet, he demands the cause of their coming to Elsinore in Q2. However, only in F, Hamlet talks comfortably with them for a while (2.2.239-69) before he demands their cause in coming. This sequence also suggests Hamlet’s maturity.[vi] In the following passage Hamlet [from which versions?] speak to Guildenstern.
What have you,
my good friends, deserved at the hands of Fortune that she sends you to prison hither?
Guild. Prison, my lord?
Ham. Denmark’s a prison.
Ros. Then is the world one.
Ham. A goodly one, in which there are many confines, wards, and dungeons, Denmark being one o’th’ worst. (2.2.240-247)
Hamlet says ‘I will not sort you with the rest of my servants,’ moreover, he even uses the word ‘friendship’ in F.
Ham. No such matter. I will not sort you with the rest of my servants; for, to speak to you like an honest man, I am most dreadfully attended. But in the beaten way of friendship, what make you at Elsinore? (2.2.239-70)
The next example also suggests Hamlet’s maturity. Hamlet represents his hostility toward Rosencrantz and Guildenstern straight in Q2. (3.4.204-12)
Let it work;
For ’tis the sport to have the enginer
Hoist with his own petard, and’t shall go hard
But I will delve one yard below their mines
And blow them at the moon. (3.4.207-11)
However these lines are omitted in F. [I’m not sure I understand, here] Similarly, Hamlet’s reaction toward Rosencrantz and Guildenstern’s death is different between Q2 and F. In the following lines Horatio, speaking to Hamlet, confirms Rosencrantz and Guildenstern’s death.
Hor. So Guildenstern and Rosencrantz to to’t.
Ham. Why, man, they did make love to this employment.
They are not near my conscience, their defeat
Does by their own insinuation grow. (emphasis added) (5.2.56-9)
The line 57 is omitted in Q2. F’s Hamlet seems more rational. Shakespeare also omitted the whole of the seventh soliloquy.
The imminent death of twenty thousand men
That, for a fantasy and trick of fame,
Go to their graves like beds, fight for a plot
Whereon the numbers cannot try the cause,
Which is not tomb enough and continent
To hide the slain? O, from this time forth
My thoughts be bloody or be nothing worth. (4.4.60-66)
In this soliloquy Hamlet sees the march of Fortinbras’ army and determines to revenge his father’s death. These lines fit a short-tempered youth. This omission answers the intention to mature Hamlet’s character. The following is the last example.
But I am very sorry, good Horatio,
That to Laertes I forgot myself;
For by the image of my cause I see
The portraiture of his. I’ll court his favours.
But sure the bravery of his grief did put me
Into a tow’ring passion. (5.2.75-80)
In these lines Hamlet repents of his rude attitude toward Laertes. These lines are only in F. Though Harold Jenkins wrote that ‘The absence of these lines from Q2 is difficult to explain except as an accidental omission’ (Jenkins 398), this omission is also fit for the effect of creating a Hamlet who is more mature.
Burbage probably played Hamlet all his life.[vii] If this is true, he played Hamlet until he was 48 years old. F was published in 1623 after Shakespeare’s death. Burbage was 45 years old when Shakespeare died in 1616. There is a possibility that Shakespeare continued to rewrite Hamlet until his death. I think that Shakespeare rewrote Hamlet because Burbage’s actual age [became not to fit the setting of Hamlet’s age.] He is also regarded as the first actor who played King Lear. He was 35 years old in 1606, the year of the first appearance of the play. Indeed, Burbage must have been a great actor. But it seems to me that it’s more difficult to play a younger character than an older character especially in tragedy. This may make the actor susceptible to ridicule.
There is some evidence that suggests F reflects a production of the time. In the Gravedigger’s Scene Hamlet receives the skull of Yorick.
Ham. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest, of most excellent fancy. (5.1.178)
In F there is an additional line ‘Let me see’ before ‘Alas.’ This addition seems to reflect an actual production. The next example is in the last scene of Hamlet. Hamlet dies right after the line ‘the rest is silence’ in Q2. But F also has an additional line in this part. F’s Hamlet dies with the groan ‘O, o, o, o’ after the line ‘rest is silence.’ These additional lines ought to reflect the actual production. These alterations might have been the parts of Burbage’s ad libs. So all these things considered, it is not an exaggeration to say that the difference of Hamlet’s age in each version reflects Burbage’s actual age.
Section 3 Burbage in Ur-Hamlet
I mentioned that Hamlet’s age is different in Q1, Q2 and F in the last chapter. And I assumed that Shakespeare revised Hamlet’s age in relationship to Burbage’s actual age. Nevertheless, there remains a mystery. In the First Folio, Hamlet is 30 years old. However, there are many descriptions “as being young,” including the reference to “young Hamlet” (1.1.170; 5.1.142), Hamlet’s “youth” (1.3.7; 1.5.38; 3.1.159) or Hamlet being “young” (1.3.124; 1.5.16; 4.1.19). Why did Shakespeare retain Hamlet as a university student? If Shakespeare changed Hamlet’s age in relationship to Burbage’s age, he could also change other settings of Hamlet. I think there is a gap between the setting of Hamlet’s age and his image.[viii]
The image of ‘young Hamlet’ might have been inherited from Ur-Hamlet. Ur-Hamlet is the name given to the lost play believed to have been the direct source of Hamlet. Shakespeare’s Hamlet was first performed circa 1600. But there is some evidence that proves Hamlet existed before 1600. Q1 was published in 1603. The more Shakespeare’s Hamlet was editionalized, the wider the gap between the setting of Hamlet’s age and his image became. So Q1 provided the narrowest gap. Some critics suggest that there are some remnants of Ur-Hamlet in Q1.[ix] Q1’s Hamlet was more than 12 years old. Consequently, Hamlet in Ur-Hamlet also might have been young.
There are three extant records that suggest Hamlet was staged before 1600. References to Ur-Hamlet first appeared in 1589. Thomas Nashe (1567-1601) wrote about Hamlet in the preface of Robert Greene’s (ca. 1558-92) prose poem Menaphon (1589). This poem contains an allusion that Hamlet had “handfulls of tragical speaches.” Harold Jenkins argues that judging from the description of “kiddle in Aesop,” the Hamlet was written by Thomas Kyd. (Jenkins 83)
The second appearance of Ur-Hamlet was in 1594. Philip Henslowe’s (?-1616) diary records 10 days of performances in 1594 by Shakespeare’s company, the Chamberlain’s Men, in combination with Alleyn and the Admiral’s Men, the rival company to the Chamberlain’s Men, at the Newington Butts theatre. The theatre at Newington was probably at least partly under the control of Henslowe. He was a theatre owner and manager of the Admiral’s Men that mainly performed at the Rose. Below is the list from his diary.
In the name of god Amen begininge at Newington my Lord Admeralle men & my Lorde Chamberlen men As ffolowethe 1594.
June 3[5?] Heaster & Asheweros viijs.
4[6?] the Jewe of Malta xs.
5[7?] Andronicous xijs.
6[8?] Cutlacke xjs.
8[10?] ne Bellendon xvijs.
9[11?] Hamlet viijs.
10[12?] Heaster vs.
11[13?] the Tamyne of A Shrowe ixs.
12[14?] Andronicous vijs.
13[15?] the Jewe iiijs.
(Campbell 583)
There is the title of Hamlet with an account of ‘viijs’. This means that the receipts for this performance were ‘mere’ 8 shillings. This ‘suggests that the play had been on the boards for some time and was no longer popular.’ (Campbell 925)
The third appearance of Ur-Hamlet was in 1596. Thomas Lodge (1558?-1625) wrote that he saw Hamlet at the Theatre in Wit’s Misery and the World’s Madness (1596). He alludes to ‘what seems to have been a notorious feature, the pale-vizarded ‘ghost who cried so miserably at the Theatre, like an oysterwife, Hamlet, revenge’.’ (Jenkins 82-3)
What theatre company did give a performance of Ur-Hamlet? From Henslowe’s diary we can know the Lord Chamberlain’s Men or the Admiral’s Men performed Ur-Hamlet. Lodge mentioned that Ur-Hamlet was performed at the Theatre. It was the home of the Chamberlain’s Men up to 1596. (Campbell 925-6) These facts indicate that Ur-Hamlet was the property of the Lord Chamberlain’s Men. Moreover, Richard Burbage was star actor of the Lord Chamberlain’s Men, and he organized the company himself. Though we don’t know for certain who wrote the Ur-Hamlet, it is possible that Burbage played the leading character of the play.
The following is the first record that suggests Burbage belonged to the Lord Chamberlain’s Men.
He and his colleagues, now the Lord Chamberlain’s Men, resumed acting in 1594, and performed twice at court in the Christmas season. Three of their leaders signed a receipt for £20 – Richard Burbage, William Kempe, and Shakespeare. . . . The receipt proves that by 1594 he had won a prominent place in his company. (Grazia 5)
Burbage was roughly 23 years old at this time. Burbage’s father, James Burbage, was an actor and builder of the Theatre. He was a person of influence in the theatrical circle. So Richard Burbage might have played major part from the beginning of his career. The following is the other example that suggests Burbage’s earliest career.
He [Richard Burbage] is first officially mentioned in extant records of the 1590 dispute over the Theatre. A direction in the “plot” of the anonymous Dead Man’s Fortune, given by the Admiral’s men about 1590/1, reads “Burbage a messenger.” The plot of Richard Tarlton’s Seven Deadly Sins (1590/1) casts “R Burbadg” in the two important roles of Gorbuduc and Terens, (Campbell 88)
It seems that Burbage already played major role when he was 19 years old. If this hypothesis is true, Richard Burbage was 25 years old in 1596, the year of the third Ur-Hamlet appearance, and was 23 years old when Ur-Hamlet secondarily appeared in 1594. And in 1589, the year of the first appearance of Ur-Hamlet, He was 18 years old. The age corresponds with the image of “young Hamlet.”
Conclusion
In Section 1 extant documents were presented as examples of production during Shakespeare’s time. An example suggested that Burbage’s Hamlet was more energetic than he is in most current productions. Hamlet’s age is different in each text: Q1, Q2 and F. I suggested the possibility that Shakespeare rewrote the character of Hamlet according to Burbage’s actual age. In Section 2 Q2 is compared with F with the conclusion that F’s Hamlet was more mature in F than in Q2. In Section 3 I pointed out the gap between the setting of Hamlet’s age and his image. And I forwarded the probability that the image of ‘young Hamlet’ was derived from Ur-Hamlet. Then I investigated the possibility that Burbage played the leading character of Ur-Hamlet.
If all these hypotheses were true, Hamlet might have been a synonym for Richard Burbage. Shakespeare might have written Hamlet for Burbage and Burbage alone. In the shadow of the historical monument of literature there was the most talented actor of the age.
Works Cited
Campbell, Oscar James, ed. The Reader’s Encyclopedia of
Shakespeare. New York: Thomas Y, Crowell Company,
1966.
Farley-Hills, David, ed. Critical Responses to Hamlet 1600-
1790. New York: AMS Press, 1997.
Grazia, Margreta de, and Stanley Wells, eds. The Cambridge
Companion to Shakespeare. Cambridge: Cambridge
University Press, 2001.
Ingram, William. The Business of Playing: The Beginnings of the
Adult Professional Theater in Elizabethan London. New
York: Cornell University Press, 1992.
Kastan, David Scott. ed. Critical Essays on Shakespeare’s
Hamlet. New York: G. K. Hall and Co., 1995.
Prosser, Eleanor. Hamlet and Revenge. London: Oxford Press,
1967.
Shakespeare, William. The Arden Shakespeare: Hamlet.
Ed. Harold Jenkins. London: Thomson Learning, 2001.
Shakespeare, William. Hamlet. Eds. Yasunari Takahashi and
Shoichiro Kawai. Tokyo: Taishukanshoten, 2001.
Skakespeare, William. Hamlet. Ed. J. Dover Wison. Cambridge:
Cambridge University Press, 1978.
Wilson, J. Dover. What Happens in Hamlet. London: The Syndics
of the Cambridge University Press, 1935.
Notes
[i] Harold Jenkins concluded that ‘the date of Hamlet is that as it has come down to us it belongs to 1601; but that nevertheless the essential Hamlet, minus the passage on the troubles of the actors, it is true, but otherwise differing little if at all from it, was being acted on the stage just possibly even before the end of 1599 and certainly in the course of 1600’ (Jenkins 13).
[ii] There are many descriptions about Richard Burbage’s date of birth. I found a reliable piece of evidence. William Ingram says ‘In a series of lawsuits in 1590 and 1591 concerning the Theatre, published over half a century ago by C. W. Wallace, we learn from the depositions of John Alleyn and others that Richard Burbage was James Burbage’s youngest son, perhaps nineteen or so in 1590, and that Cuthbert, by his own testimony, was twenty-four in 1591’ (Ingram 102). I hypothesize Burbage was born in 1571 in this thesis.
[iii] Eleanor Prosser says ‘I join with those who doubt that Shakespeare intended Hamlet to leap into the grave, even though Burbage probably did so. As Granville-Barker suggests, Burbage must have been carried away, for the action is contradicted by the lines (Prosser 224). She also suggests “oft have I seene him, leap into the Grave” is ‘indicating that the direction in Q1 accurately reflects contemporary stage’ (Prosser 224n).
[iv] Yasunari Takahashi argues that Hamlet should be 19 years old in the Second Quarto (Takahashi 9). But I couldn’t find the specific fact.
[v] This chapter’s discussion about comparison Q2 with F is mainly based on Takahashi 7-15. I want to improve this chapter more originally.
[vi] There is another explanation for this omission. Harold Jenkins argues that ‘This passage must therefore have been part of the original text and is usually thought to have been suppressed, on account of the derogatory references to Denmark, out of deference to Anne of Denmark, James ・’s queen’. (Jenkins 467)
[vii] After Burbage’s death Joseph Taylor took over his part. He was 33 years old at the time. Harold Child argues ‘Richard Burbage . . . died on March 13, 1619; and someone else must have played the part when the tragedy was performed at Court in the winter of 1619-20; almost certainly Joseph Taylor, who joined the company in May, 1619, and acted Hamlet ‘incomparably well.’ It was probably he also who acted the part at Hampton Court on January 24,1637; and his influence seems to have lasted on into the succeeding era’. (Wilson 1978, lxxi)
[viii] Wilson argues that ‘Elizabethan audiences saw Shakespeare’ Hamlet as a younger man than the text strictly allows (as most later audiences have)[?], for the thirty years indicated by the text would have been old by Elizabethan standards. The elegy on Burbage seems to support this in its reference to ‘young Hamlet’.’ (Wilson xvi)
[ix] ‘Numerous attempts have been made to reconstruct the old play [Ur-Hamlet] and to establish its relationship not only to the Shakespearean play as it is now known but to the “bad quarto” (Q1) of Hamlet and to the German version, Der Bestrafte Bruder-mord’. (Campbell 926)
2008/05/02/21:05
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
Shakespeare’s Sonnets
with a Focus on Sonnet 15
Takuo Yoneda
Introduction
Shakespeare’s Sonnets consists of two parts. The first part is dedicated to a young man who seems to be a lover of the poet (sonnet 1-126). The second part is dedicated to a woman known as Dark Lady. I want to deal with the first part in this paper. At first, I want to see descriptions about ‘time’ in those sonnets. Then I want to discuss Shakespeare’s attitude toward ‘time,’ focusing on sonnet 15.
Chapter 1. Descriptions of ‘time’ in The Sonnets
Shakespeare treated ‘time’ as a bad thing in The Sonnets. He describes ‘time’ as a destroyer of beauty as follows.
Devouring Time, blunt thou the lion’s paws,
And make the earth devour her own sweet brood;
Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws,
And burn the long-lived phoenix in her blood;
(19.1-4)
In this sonnet Shakespeare calls ‘time’ ‘Devouring Time’ and emphasizes its cruelty. Shakespeare always juxtaposes beauty of the young man and the brutality of ‘time’ that deprives beauty of him. He expresses his idea that beauty will be lost over and over again. Shakespeare recognizes all beautiful things will be destroyed by ‘time’ as follows:
Then of thy beauty do I question make,
That thou among the wastes of time must go,
Since sweets and beauties do themselves forsake
And die as fast as they see others grow;
(12.9-12)
On the contrary, Edmund Waller (1606-87) describes ‘time’ as positive thing in his “Old Age.”
The soul’s dark cottage, battered and decayed,
Lets in new light through chinks that Time has made:
Stronger by weakness, wiser men become
As they draw near to their eternal home.
(7-10)
Waller observes that the older people grow, the wiser they become. Contrary to Waller, Shakespeare never mentions positive side of ‘time’ in The Sonnets. Though actually Shakespeare refers growth of human beings in his sonnets, it is always a counterpart of old age. Shakespeare taunts the ferocity of ‘time’ in the next sonnet.
Those hours, that with gentle work did frame
The lovely gaze where every eye doth dwell,
Will play the tyrants to the very same
And that unfair which fairly doth excel:
(5.1-4)
Shakespeare says ‘time’ will destroy the beauty by the same hands created it. It’s a peculiarity of description of ‘time’ in his sonnets that Shakespeare always treats ‘time’ as thoroughly negative thing.
Chapter 2. Shakespeare’s attitude toward ‘time’ and sonnet 15
Shakespeare describes ‘time’ as absolute evil thing. He consistently stands against ‘time.’ To counter with ‘time’ means, for Shakespeare, to preserve beauty of beautiful things. The first means against ‘time’ is to leave offspring of the beauty. The second means is to leave his beauty in poetry.
Shakespeare’s The Sonnets begins with the following lines.
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty’s rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
(1.1-4)
In these lines the poet recommends a young man to try to marry someone and have a child. From sonnet 1 to 17 the poet consistently praises his beauty and, at the same time, proposes him to get married. In sonnet 12 he shows his feelings of competition toward ‘time.’ And he persuades the young man that procreation is the only countermine.
And nothing ‘gainst Time’s scythe can make defence
Save breed, to brave him when he takes thee hence.
(12.13-14)
Similarly, he says procreation is more effective than writing poetry to fight against ‘time’ in sonnet 14, 16 and 17.
Shakespeare firstly offers poetry as a countermine against ‘time’ in sonnet 15.
And all in war with Time for love of you,
As he takes from you, I engraft you new.
(15.13-14)
The last phrase ‘I engraft you new’ (l.14) means ‘I plant you anew,’ that is to say ‘I renew your life.’ The primary image is built on by ‘men as plants’ (l.5). These lines imply that the poet makes the youth live afresh in his sonnets. In this couplet Shakespeare proposed firstly another strategy to fight against time instead of procreation. That is verbal wit, the power of art. Actually, there is an ingenious pun in this sonnet. The poet repeated the sound ‘you’ in 10 to14 (you…youth…youth…you…you…you). At last, ‘you’ are converted, by the additional ‘n’, into the sound ‘new’.
Sets you, most rich in youth, before my sight,
Where wasteful time debateth with decay
To change your day of youth to sullied night:
And all in war with time for love of you
As he takes from you, I engraft you new.
(10-14) (Emphasis added.)
He tries to renew his love’s beauty by means of verbal wit. This pun is a proper example of the verbal wit.
Chapter 3. After sonnet 15
The poet gains further confidence in his art after sonnet 15.
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.
(18.13-14)
Yet, do thy worst, old Time: despite thy wrong,
My love shall in my verse ever live young.
(19.13-14)
Sonnet 55 is a kind of proclamation of victory of poetry over ‘time.’
Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall outlive this powerful rhyme;
(55.1-2)
In sonnet 100 and 101 the poet calls out to Muse, the Goddess of poetry, as well as Time, the God of time.
Then do thy office, Muse; I teach thee how
To make him seem long hence as he shows now.
(101.13-14)
After sonnet 18 he never proposes the young man procreation but devotedly praises his beauty like a servant of the beauty.
And yet to times in hope my verse shall stand,
Praising thy worth, despite his cruel hand.
(60.13-14)
His beauty shall in these black lines be seen,
And they shall live, and he in them still green.
(63.13-14)
You still shall live–such virtue hath my pen–
Where breath most breathes, even in the mouths of men.
(81.13-14)
The poet attempts to preserve the young man’s beauty in his art. Nevertheless, these sonnets don’t tell us anything about the young man. The poet never describes his concrete profile. Through these sonnets I can see the poet himself facing with the youth rather than his love. He seems to try to compensate difference in age with devotion to art.
Conclusion
Shakespeare regards ‘time’ as an enemy. He insists that ‘time’ will destroy beauty in his sonnets over and over again. And he proposes two strategies to fight against time. The one is procreation, and another is to preserve beauty in his art. I think sonnet 15 is the first turning point in the whole of sonnets because in the sonnet Shakespeare firstly proposes new strategy to fight against time. That was verbal wit, the power of art. You can take the sonnet as a kind of the declaration of war against time.
Bibliography
Hirai, Masao, ed. Igirisu-meisisen. Tokyo: Iwanamishoten,
1990.
Shakespeare, William. The Arden Shakespeare:
Shakespeare’s Sonnets. Ed. Katherine Duncan-Jones.
London: Thomson Learning, 1997.
Shakespeare, William. Shakespeare’s Sonnets. Ed. Stephen
Booth. London: Yale University Press, 1977.
Shakespeare, William. The Sonnets. Ed. G. Blakemore Evans.
Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Shakespeare, William. Shakespeare’s Sonnets. Ed. W. G.
Ingram. London: University of London Press, 1964.
Shakespeare, William. Sonetto-shuu. Trans. Yuuichi
Takamatsu. Tokyo: Iwanamishoten, 1986.
2008/05/02/21:04
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
Bottom’s Dream
—夢と想像力—
米田 拓男
Introduction
William Shakespeare (1564-1616)のA Midsummer-Night’s Dream (1595-96)の中で、私は特にボトムに注目したい。ボトムはこの喜劇作品の中でも最も喜劇的な人物であり、職人から、ロバ、ピラマスと3回も変身する変化の多い派手なキャラクターだ。またボトムは作中、妖精を見ることが出来る唯一の人間でもある。本論ではボトムを中心に夢と想像力の関係について論じる。
Chapter 1
A Midsummer-Night’s Dreamに登場するボトムは、1661年の段階で『機屋ボトムの愉快な奇行』(The Merry Connceited Humours of Bottom the Weaver)と題するボトムを中心にした改作が出たほど、(玉泉 129) 当時から観客を惹き付けてきた魅力ある登場人物である。彼はアテネの職人仲間の人気者で、[i] 公爵の結婚祝いの席で披露するための芝居の主演に抜擢される。彼は気取り屋であり、それは、自分達のことを当時はまだあまり使われていなかった ‘actors’と呼んでみたりするところからも伺える。[ii](1.2.9, 14, 4.2.37) 彼は自己顕示欲が旺盛で、役振りの時から、どの役もやりたがり、口を出す。[iii] しかし、彼が憎めないのは、いくら気取ってみたところで、次から次へとボロを出してしまうところにある。
Shakespeare作品のコミック・キャラクターがしばしば言葉を言い誤るように、彼は非常に頻繁に言い間違いをするのだ。‘moderate’と言うべきところを ‘aggravate’と言ったり、(1.2.75)‘severally’や‘individually’が相応しいところで‘generally’というくらいならまだ良い。(1.2.2) 中には ‘I will roar you as gently as any sucking dove’と、‘sucking lamb’と‘sitting dove’を混用したと思われる、赤面ものの言い間違いもある。(1.2.76)僕が数えたところ、彼は全部で35回の言い間違いをしている。[iv]
その中でも知覚動詞の誤用が多く、都合8回言い間違えている。
○ ×
seen →heard (4.1.208)
heard →seen (4.1.209)
conceive →taste (4.1.209)
taste →conceive (4.1.209-210)
hear →see (5.1.191)
see →hear (5.1.192)
hear →see (5.1.347)
see →hear (5.1.348)
具体的に台詞を引用してみたい。
The eye of man hath not heard, the ear of man hath not seen, man’s hand is not able to taste, his tongue to conceive, not heart to report what my dream was. (4.1.208-210)
人間の目が聞いたこともない、人間の耳が見たこともない、人間の手が味わったこともない、舌が考えたこともない、心臓が言い伝えたこともない、あれは前代未聞のとんでもない夢だった。
この台詞は聖書の『コリント前書』からの一節であり、[v]ボトムはその知覚動詞をあべこべにして使用している。その他にもA Midsummer-Night’s Dreamの中には知覚に関する言及が多い。
Hermia. I would my father look’d but with my eyes.
Theseus. Rather your eyes must with his judgment look. (1.1.56-57)
ハーミア 父が私の目で見てくれればいいのですが。
シーシアス それよりもお前の目に父の分別を持たせなさい。
この台詞では視覚について言及している。次のヘレナの台詞は視覚と聴覚について述べている。
My ear should catch your voice, my eye your eye,
My tongue should catch your tongue’s sweet melody. (1.1.188-189)
私の耳にあなたの声を、私の目にあなたの目を
私の舌にはあなたの甘い調べをうつしてちょうだい。
そしてヘレナは森に入り、彼女の知覚に生じた変化に気付く。
Hermia. Dark night, that from the eye his function takes,
The ear more quick of apprehension makes;
Where it doth impair the seeing sense,
It pays the hearing double recompense.
Thou art not by mine eye, Lysander, found;
Mine ear, I thank it, brought me to thy sound. (MND 3.2.177-182)
ハーミア 暗い夜、人の目からその働きを奪ってしまう。
そのぶん耳はいっそう鋭敏になる。
見る力を駄目にしたかわりに
聴く力を二倍にしてくれる。
ライサンダー、あなたを見つけたのは目じゃない、
感謝しなくては、耳があなたの声のところへ導いてくれたの。
恋人たちは夜の森に入り、まず確かな視覚を奪われた。彼らの知覚の変調はそれだけにとどまらない。オーベロンとパックのいたずらによって、彼ら恋人たちと、ティターニア、職人たちの知覚はさらなる変調を来していく、[vi]ボトムの言い間違いのように。そして、知覚が奪われ、混乱していくうちに彼らのうちで、想像力が視覚や聴覚といった知覚よりも確かな拠り所となっていくのだ。[vii]
Chapter 2
次の台詞は、魔法にかけられたティターニアがボトムに出会う場面のものだ。
Titania. I pray thee, gentle mortal, sing again.
Mine ear is much enamoured of thy note;
So is mine eye enthralled to thy shape;
And thy fair virtue’s force perforce doth move me,
On the first view, to say, to swear, I love thee. (3.1.29-33)
ティターニア お願い、優しい方、もう一度歌って。
この耳はあなたの歌声にうっとり聞き惚れ
この目はあなたの姿かたちに見とれている。
あなたの美しさにこもる力は私の心を揺さぶり
一目見ただけで誓わずにいられない、愛しています。
ティターニアの目には、ロバ頭のボトムの姿が美しく映っている。愛を打ち明けるティターニアにボトムは冷静に言い返す。
Bottom. Methinks, mistress, you should have little reason for that. And yet, to say the truth, reason and love keep little company together now-a days. The more the pity that some honest neighbours will not make them friends. Nay, I can gleek upon occasion. (3.1.134-138)
ボトム 奥さん、そうまでおっしゃるとは、相当理性に欠けておいでだね。もっとも、正直な話、このところ理性と恋とはまるっきりそっぽを向き合ってる。ご近所の正直者があいだに入り仲直りさせないのは残念至極。てなわけで、たまには俺だって気のきいた冗談のひとつも言えるんだ。
この台詞の中で、ボトムは ‘reason and love keep little company together now-a days.’と言っているが、A Midsummer Night’s Dreamの中には、この台詞と共鳴する台詞がいくつかある。次の台詞は森に向かう前に、ヘレナがハーミアを羨んで語る独白の一部である。
Things base and vile, holding no quantity,
Love can transpose to form and dignity.
Love looks not with the eyes, but with the mind;
And therefore is wing’d Cupid painted blind. (1.1.232-235)
恋は程を知らないから、卑しく醜いものも
並はずれた立派なものに変えてしまう。
目で見るのではなく心が見たいように見る。
だから、絵に描かれたキューピッドはいつも目隠しをしてるんだわ。
ヘレナは、人は恋に落ちると想像力が視覚を補って、相手を実際以上に美しく見せてしまうと言う。以下のシーシアスの台詞も同様のことを述べている。
Lovers and madman have such seething brains,
Such shaping fantasies, that apprehend
More than cool reason ever comprehends.
The lunatic, the lover, and the poet,
Are of imagination all compact. (5.1.4-8)
恋する者、気の狂った者は頭のなかが煮えたぎり
ありもしないものを空想する。だから
冷静な理性では理解できないことを思いつく。
狂人、恋人、そして詩人は
想像力で出来ている。
この台詞では、上記の台詞をさらに発展させて、恋人に、狂人と詩人を並列して並べている。[viii]そして彼らは皆、想像力‘imagination’の産物であると述べている。
それでは、森をさまよう恋人たちの‘imagination’ は、どのような性質のものなのだろうか。アテネ郊外の森でティターニアがボトムに出会った時、つまり妖精が人間に遭遇した時、人間が妖精に驚くのではなく妖精が人間に驚いている。ティターニアにとっては、ロバ頭のボトムは類まれなほど優雅で美しい。ボトムにとっては、妖精の女王はたまたま出会った女性にすぎない。この時、ボトムもタイターニアも相手に対する評価を誤っている。二人のコミュニケーションは、誤解に基づいて成立している。二人とも非常に個人的な想像力の範疇で相手を評価していて、客観性を失っている。[ix]ボトムに限っては自分がロバに変身したことすら、ついぞ知らないままなのだ。[x]ティターニアも、自分が魔法にかかっていることなど知る由もない。アレグザンダー・レガットは次のように述べる。
劇全編を通して四つの異なったグループが認められる。恋人たち、道化たち、年齢が少し上のアテネの人たち、そして妖精たちである。どのグループも自分たちにしかかかわらない問題に熱中していて、他グループの問題にはほとんど気付いていない。 (レガット 122)
つまり、彼らは知覚を失い、自らの想像力の中をたゆたうようになる。森にいる彼らの想像力は主観的なもので、[xi]非常に個人的な範囲に限定されたものになるのだ、まさに夢のように。
Chapter 3
次の台詞は、魔法が解けてボトムが目覚める時にかたられる台詞である。
I will get Peter Quince to write a ballad of this dream. It shall be call’d ‘Bottom’s dream’, because it hath no bottom; (4.1.210-212)
ひとつピーター・クウィンスに頼んで、俺の夢を歌にしてもらおう。題は「ボトムの夢」がいい。ボーッとむなしい夢だからな。
ボトムは目覚めると、妖精の女王と出会った体験を、夢であると決めつけて、それを「ボトムの夢」と命名する。[xii]しかし、ライサンダーが ‘by the way let us recount our dreams’「歩きながら、ゆうべの夢の話をしよう」と言うのとは対照的に、(4.1.197) ボトムは夢の話はできないと言う。
I have had a most rare vision. I have had a dream past the wit of man to say what dream it was. Man is but an ass if he go about to expound this dream. (4.1.202-204)
なんともけったいな夢を見たもんだ。確かに夢だ、だがどんな夢かは人間の知恵じゃ言えないな。この夢を説明しようとするやつは、とんまなロバだ。
その後、職人仲間のところへ戻った時にも、ボトムは夢の話をしようとして言い淀む。(4.2) ボトムは何故、夢の話をしないのだろうか。
ノースロップ・フライは次のように述べる。
夢では、人は誰も自分自身のロゴスであるといったヘラクリトスから、どの夢にも理解不可能の部分があって、それが未知との橋わたしになるというフロイトに至るまで、夢は、夢見る者の個人的世界の核をなしており、それゆえに他人への伝達は不可能であると考えられている。しかし夢を見る力は、伝達力としての想像力と密接な関係をもっている。そしてこれがボトムを悩ますパラドックスなのである。 (『シェイクスピア喜劇の世界』 149-150)
このパラドックスとはどういうことなのだろうか。まず、夢を見るのには想像力が必要である。ここでいう「夢を見る力」とは、想像力を指す。そして、人にものを伝えるのにも想像力が必要である。従って、夢を見る人間には、人にものを伝える想像力を持っている。しかし、夢は個人的なものなので、本質的に他人に伝えることができない。つまり、夢を見た人間は誰しも、その夢を人に伝えたいけど、伝えられないというパラドックスに悩まされることになる。ボトムはそのことを本能的に瞬時に察知したのだろう。ライサンダーは、周りの人たちに自分が経験した夢のような体験を語って聞かせるだろう。しかし、結局それを理解させることは永遠にできないのだ。[xiii]
詩人はそれをつたえようと悪戦苦闘するのだろう。ボトムは詩人ではないが、役者であった。レガットは役者ボトムを次のように評する。
役者ボトムは劇中最大の馬鹿者であるが、ある意味ではもっとも広い想像力を持った人物である。妖精を目にするだけでなく、彼らに気安く挨拶までするのだ。どんな役でも演じられる(し、いくらかでもチャンスがあれば実際に演じてしまう)彼の役者としての多芸多才ぶりは、シェイクスピア自身の想像力の喜劇的写しではないか。「雛鳩みたいに優しい声で唸ってみせるぞ」(1幕2場73行)と約束するボトムには、現実を調整し直す芸術家の特権が感じられる。 (レガット 150)
しかし、レガットのこのような好評価に反して、5幕1場での「ピラマスとシスビーの悲恋物語」上演の席では、からかいの対象になり、シーシアスに次のように言われてしまう。
Theseus. The best in this kind are but shadows; and the worst are no worse, if imagination amend them.
Hippolyta. It must be your imagination then, and not theirs. (5.1.210-213)
シーシアス 芝居というものは最高の出来でも所詮は影、そのかわり最低のものでも影以下ということはない。想像力で補えばいいのだ。
ヒポリタ でもそれはあなたの想像力でしょう、あの人たちには欠けている。
このシーシアスの発言は正しい。そもそもボトムは、観客の想像力を信頼していた。ボトムたちは芝居の稽古の最中、あれほど夫人方のライオンへの反応を気にしていたではないか。(1.2, 3.1.) 観客の想像力を過剰に信頼した結果、あのような芝居になったのだ。シーシアスは、想像力が時として大きな力を持つことになることを理解しているようだ。
Such tricks hath strong imagination
That, if it would but apprehend some joy,
It comprehends some bringer of that joy;
Or in the night, imagining some fear,
How easy is a bush suppos’d a bear? (5.1.18-22)
強い想像力にはそんな魔力がそなわっている。
だから何か歓びを感じたいと思うだけで
その歓びをもたらすものを頭のなかでこしらえ上げる。
また逆に、闇夜に恐怖を感じれば
ただの繁みも簡単に熊と思えてくるのだ。
しかし、シーシアスの想像力は、[xiv]若者たちの話を理解するところまではいかなかった。
A Midsummer-Night’s Dreamは最後、パックが1人舞台に登場し、納め口上を述べるが、その中に次のような一節がある。
Puck. If we shadows have offended,
Think but this, and all is mended,
That you have but slumb’red here
While these visions did appear.
And this weak and idle theme,
No more yielding but a dream, (5.1.417-422)
パック 影にすぎない私ども、もしご機嫌を損ねたなら
お口直しに、こう思っていただきましょう。
ここでご覧になったのは
うたた寝の一場のまぼろし。
たわいない物語は
根も葉もない束の間の夢。
この口上でパックは、A Midsummer-Night’s Dreamという芝居それ自体を夢のようなものだと言う。それは、Shakespeareの想像力の産物、つまり、夢ということだ。森の中で夢のような体験をしたボトムは、劇中の舞台上で、芝居というひとつの夢を演じる。その芝居を見ている公爵たち、を見ている妖精たち、を見ている我々、を見ている神々… 夢の入れ子構造がバームクーヘン状に広がっていく。その中心に、ボトムの夢が、ぽっかりと口を開けている。
Conclusion
Chapter 1では、ボトムの言い間違いに注目し、言い間違いの中には特に知覚動詞の誤用が目立つことと、作品中にも知覚に関する記述が多いことについて言及した。そして登場人物たちが森に入り、知覚が奪われ、混乱していくうちに、彼らのうちで、想像力が知覚よりも確かな拠り所となっていくということについて論じた。
Chapter 2では、恋人たちは想像力の産物であるという考えに触れ、彼らの想像力は主観的で限定された、夢のようなものだということを述べた。
Chapter 3では、夢について語ろうとするが、語れない、ボトムのパラドックスと、夢と想像力の関係について論じた。
後注
ボトムの言い間違いについて。全部で35回の言い間違いをしている。
副詞 2回
○ ×
severally, individually → generally (1.2.2) 矛盾する、反対の意味
seemly, fitly → obscenely (1.2.98) 卑猥な間違い
名前の訛り 7回
Hercules → Ercles (1.2.24)
Phoebus → Phibbus (1.2.30)
Hercules → Ercles (1.2.35)
Thisby → Thisne (1.2.46)
Leander → Limander (5.1.195)
Cephalus → Shafalus (5.1.197) 引用自体も不適当
Procris → Procrus (5.1.197) 引用自体も不適当
接続詞 1回
make or mar → make and mar (1.2.33) 慣用的言い回しの言い間違い
形容詞 5回
a monstrous little (1.2.46) oxymoron的な変な言い回し、矛盾する、反対の意味
moderate → aggravate (1.2.75) 反対の意味
sucking dove (1.2.76) sucking lambとsitting doveの混用、卑猥な間違い
odours → odious (3.1.75) 香りの形容詞形を言い間違えた、卑猥な間違い
lamentable tragedy → sweet comedy (4.2.39) 反対の意味
名詞 8回
tragedy → comedy (3.1.8) 反対の意味
wild-beast → wild-fowl (3.1.29) イメージ的に反対
effect → defect (3.1.35) 反対の意味
nor his heart to report (4.1.210) 主語と動詞がちぐはぐ、身体の部位
lamentable tragedy → sweet comedy (4.2.39) 反対の意味
Hero → Helen (5.1.196) 思い違い
Ninus → Ninny (5.1.201)
Eye → Tongue? (5.1.299) 身体の部位
数詞 1回
eight and eight (3.1.24) 思い違い
文法 2回
yourselves → yourself (3.1.27) シェイクスピアのミスの可能性も
odorous → odours (3.1.77) 名詞形と形容詞形の間違い
冠詞 1回
the play → a play (4.1.213) 石井正之助氏の注では「タイテイニアとの情事が念頭にある」とあるが、本当か?
動詞 8回
(知覚動詞の誤用)
seen → heard (4.1.208)
heard → seen (4.1.209)
conceive → taste (4.1.209)
taste → conceive (4.1.209-210)
hear → see (5.1.191)
see → hear (5.1.192)
hear → see (5.1.347)
see → hear (5.1.348)
他にも誤解、勘違い多数あり
参考文献
ハンス・ビーダーマン 『図説 世界シンボル辞典』 訳者 藤代 幸一・
宮本 絢子・伊藤 直子・宮内 伸子 東京: 八坂書房 2000.
ヤン・コット 『シェイクスピア・カーニヴァル』 訳者 高山 宏 東京: 平凡社
1989.
テリー・イーグルトン 『シェイクスピア—-言語・欲望・貨幣—-』 訳者
大橋 洋一 東京: 平凡社 1992.
ノースロップ・フライ 『シェイクスピア喜劇の世界』 訳者 石原 考哉・市川 仁
東京: 三修社 2001.
ノースロップ・フライ 『シェイクスピアを読む—-ノースロップ・フライのシ
ェイクスピア講議』 訳者 石原 考哉・市川 仁・林 明人 東京: 三修社 2001.
アレグザンダー・レガット 『シェイクスピア、愛の喜劇』 訳者 川口 清泰
東京: 透土社 1995.
Schmidt, Alexander. Shakespeare lexicon and Quotation Dictionary. Rev.
Gregor Sarranzin. New York: Dover Publications, 1971.
Shakespeare, William. A Midsummer-Night’s Dream. 編注者 石井 正之助
東京: 大修館書店 1987.
ウィリアム・シェイクスピア 『夏の夜の夢 間違いの喜劇』 訳者 松岡 和子
東京: 筑摩書房 1997.
柴田 稔彦 『シェイクスピアを読み直す』 東京: 研究者 2001.
玉泉 八州男 ほか 『シェイクスピア全作品論』 東京: 研究者出版 1992.
Notes
[i] 4幕2場で、‘he hath simply the best wit of any handicraft’などと、職人仲間から大変に高く評価されている。
[ii] 「このころまでは劇を演じる人間のことをまだ「役者」(player)というアングロサクソン系のことばで表すのが普通であったのに、ボトムなどは自分のことをもったいぶって、ラテン系の語である「俳優」(actor)と称している」 (柴田 123)
[iii] 彼は ‘ethical dative’の ‘you’ や ‘your’を良く使うが、そんなところからも彼の自己顕示欲の強さを読み取れる。
[iv] 後注のボトムの言い間違いの一覧表参照。
[v] 「「神、彼を愛する者たちのために備えたまいしことどもを、人の目は見ず、人の耳は聞かず、人の心は入れざるなり。されど神、その聖霊によりてこれらのことどもを我れらに啓示したまえり。聖霊はあらゆるものを、然り、神の深きにあることどもをよくたずね得るものなれば」と、その聖句にはある。」 (コット 48)
[vi] パックは、ティターニアとライサンダー、ディミートリアスの目に惚れ薬を塗り、ボトムをロバに変身させ、ライサンダーとディミートリアスを、二人の声色をまねて誘導する。それらのいたずらが、彼らの知覚を混乱に陥れる。
[vii] SchmidtのShakespeare lexiconの ‘imagination’の項に次のような記述があった。 ‘the faculty of the mind by which it conceives and forms ideas of things not present to the eye’
[viii] 狂人は原文では ‘the lunatic’となっている。 ‘luna’は古来、狂気を意味する語だが、作品中の月の記述には狂いがあり、矛盾しているという。
「本文に言及されている部分から判断すると、森の場面の晩は月の出ない夜でなくてはならない。ところが実際は、雲に隠れてよく見えないのかもしれないが、月が依然としてそこにあることを示すような言及がたくさんある。」 (『シェイクスピアを読む』 82)
[ix] 「二人とも本性から逸脱して変容を来したのに、自分たちは正常であると思い込んでいるのだ。(中略)ひとりびとりが自分の認識の中に留まり、自己満足に浸り、内にこもっていて、根は無邪気と言える。」 (レガット 121)
[x] 「ボトムの頭がロバの頭になるとき、他人が彼をどうみるかと、彼自身が彼自身をどうみるかとのあいだに、自分の顔をみることのできないがゆえの亀裂が生ずるだろう。」 (イーグルトン 64)
[xi] シンボル辞典の「森」の項に次のような記述があった。「夢にあらわれる「暗い森」は、アイデンティティーの確立以前の段階、あるいは意識が正常に働いている状態ではおずおずとしか足を踏み入れることのできない「無意識」の領域をあらわす。」 (ビーダーマン 439)
[xii] コンコーダンスによれば、A Midsummer-Night’s Dreamでは‘dream’という単語は、‘dream’と ‘dreams’合わせて計16回使用されている。そのうち、一番多く使っているのがボトムで6回である。
[xiii] Hippolyta. ’Tis strange, my Theseus, that these lovers speak of.
Theseus. More strange than true. I never may believe
These antique fables, nor these fairy toys. (5.1.1-3)
ヒポリタ シーシアス、不思議ね、あの恋人たちの話は。
シーシアス 不思議だ、とても本当とは思えない。ああいう荒唐無稽な昔話や
たわいないおとぎ話のたぐいはどうも信じる気になれない。
[xiv] 「シーシュースがここで使っている‘imagination’という言葉は、ごくありふれたエリザベス朝の用法で、今日では、実在しないという意味の‘imaginary’という言葉で表される。シーシュース自身はともかく、この言葉は今日われわれのいう ‘imaginative’よりは積極的な意味、つまり後にブレイクやコウルリッジによって発展させられた創造力という意味をもっているのである。私が『オックスフォード大英語辞典』で調べた限りでは、英語におけるこの言葉の積極的な意味はここから始まっている。」 (『シェイクスピアを読む』 89)
2008/05/02/21:02
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)