道化、英雄、人 —ミルトン『失楽園』のサタンについて—
道化、英雄、人
—ミルトン『失楽園』のサタンについて—
米田 拓男
はじめに
ミルトンの『失楽園』に登場するサタンは、様々な受け取られ方をされてきた。サタンこそが『失楽園』における真の英雄であるという主張から、サタンは一種の道化に過ぎないという見解まで、その幅は極端なまでに広い。私自身は、『失楽園』を読み、サタンが持つ人間らしさに惹かれる。そして何故ミルトンはサタンに人間らしさを賦与したのかが気にかかる。そこで私は、本論において、今までなされてきた様々なサタンの解釈について考察し、サタンに人間らしさが賦与された理由を探ってみることにしたい。章構成は以下のようになっている。
第一章 道化か英雄か&mdash様々なサタン像—
第二章 ミルトンの分身としてのサタン
第三章 物語における悪役としてのサタン
第四章 堕落した人間の原型としてのサタン
第一章では、道化から、英雄までの幅広いサタン像について紹介する。第二章では、サタンとミルトンの主張が重なっている箇所があることから、ミルトンとサタンを同一視するサタニストの主張について考察したい。第三章では、物語においての悪の必要性について考え、サタンに崇高さが賦与された理由を探る。第四章では、サタンを堕落した人間の原型として考え、アダムとイヴと比較し、サタンの人間らしさの源泉を探り、サタンをサタンたらしめている問題について指摘する。
本論は、サタンについての様々な解釈を考察することを通じて、サタンに見られる人間らしさの理由を解明することを目的とする。
第一章 道化か英雄か&mdash様々なサタン像&mdash
ミルトンの『失楽園』に登場するサタンは、受け取り手に様々な解釈をされてきた。サタンこそが『失楽園』における真の英雄であるという主張から、サタンは一種の道化に過ぎないという見解まで、その幅は広い。これほど受け取られ方に幅があるキャラクターも珍しい。ここでは、様々な人々のサタンの解釈を見たい。
まず、サタンを英雄視する意見から見る。ウィリアム・ブレイクは、『天国と地獄との結婚』において次のように記す。
これミルトンが天使達及び神のことを叙する時活気なき理由である。
そして悪魔及び地獄の叙述の躍如たるは彼が真の詩人であり、しらず
しらず悪魔の仲間入りをしていたためである。
(ブレイク 128)[1]
ブレイクにとっては『失楽園』における天使達の描写は、退屈なものであったようだ。そして、それに反してサタンの描写は、大変に魅力的なものに映っていたらしい。ブレイクの他にも十九世紀の詩人や作家たちの中には、コールリッジやバイロン、ハズリット、シェリーなど、ミルトンのサタンを英雄視する者が多かった。パーシー・ビッシュ・シェリーにおいては、ミルトンのサタンは、道徳的にも神より優れた存在だった。
一道徳存在としてミルトンのセイタンは神より遥かに秀れている。敵
対し、苦しみながらも自らが良しと見る何らかの目的にじっと耐える
存在が、確実不動の勝利に安穏とあぐらをかきながら、敵にこの上な
く暴虐な復讐を企てる存在より秀れていて当然なのだ。この復讐は、
よく誤解されるように敵を悔い改めさせようとする意図とは無縁にし
て……敵を追いつめ、更なる苦悶を蒙らせようという公然たる意図の
もとに行われるのである。(リンク 296)
パリでは、詩人ボードレールが日記に次のように書き綴った。
私は美の、私の美の定義を発見した。それは激しく、そして悲哀に満
ちたものである。……敵対なきところに、この美は考えられない。…
…男性的なこの美の完全この上ない典型は、ミルトンが表現しようと
した魔王セイタンだと、考えざるをえないのだ。(リンク 297)
これらの記述から、ミルトンが描いたサタンに心酔する、若き詩人たちの姿を垣間見ることができる。
このようにサタンを英雄視する主張がある一方で、サタンを道化として考える見解もある。野呂有子氏は論文「道化としてのサタン、サルマシウスそしてチャールズ一世」の中で、サタンがイヴを誘惑する際、蛇に変身する前に一度、蛙になっていることに着目し、ミルトンはアリストパネスの喜劇『蛙』から道化的なイメージを継承しているのだと論じている(新井2003 60-5)。
何故、サタンの受け止められ方にはこれ程の差異が生じるのだろうか。ロマン派の詩人たちはサタンを英雄的だと言ったが、それは具体的にどの辺りを指しているのだろうか。それは、恐らく次のような箇所だ。第二巻において天上での戦いに破れた堕天使たちは、サタンを囲んで神への復讐策を模索する。そして神が造った、人間という新しい種族を堕落させることで、神に復讐を果そうということに決める。渾沌界を通って人間のいる楽園に赴くことには危険が伴う。だがサタンは、自分ひとりでやってのけようと言うのである。
わが戦友諸君、
全体にかかわる一大事として提案され決定されたことを、それが
単に困難であり危険だという理由だけで、もしわたしが敢えて
自ら引き受けないとするならば、わたしは、栄光に包まれ
武威に輝くこの王座を、そしてこの帝王としての権威を、
全く虚しくするものといわなければならぬ! (中略)
ことわっておくが、わたしは、この度のこの遠征に、余人の参加を
許さない」。こう言って、地獄の王は立ち上がり、一同に返事の
余裕を与えなかった。(第二巻 444-9、465-6)
サタンのこのような態度は、ルネサンス期に一般的であった「高い身分には義務がともなう」という考え方、’noblesse oblige’に基づいたものと見る事ができるという。(新井1980 259)そして、サタンはただ一人で旅立つ。この場面に見るサタンは確かに英雄的と言える。
サタンはつねに未来のことを考え、計画を立て、自ら率先して行動していく。神がその子に油を注いだ日に反乱を計画し、夜中に反乱軍を集結させ、神の軍勢に戦いを挑む。一日目には戦いに破れた後すぐに会議を開き大砲を作ることを提案し、彼の部下たちにすぐに仕事にかからせる。最終的に天上における戦いでは敗北し地獄に落とされることになるが、意識を回復するとすぐに神への復讐策を模索し、人間を堕落させるために楽園へと赴くのだ。藤井治彦氏は次のように記す。
セイタンは、つねに計画し、つねにその計画を行動に移す者である。
彼はつねに目標に向かって急いでいる。その姿は、それだけ切り離し
て眺めるならば、美徳を備えているように見える。セイタンは、ある
意味では、真面目なのであり、勤勉なのである。
(平井1974 280-1)
確かにサタンは、行動力に溢れ英雄的な魅力を備えている。
しかしミルトンは、果たして本当にサタンを英雄として描いたのだろうか。私はそう言い切ることに戸惑いを覚える。私がそう言い切ることができない理由は、第六巻と第十巻におけるサタンの相次ぐ敗北の描写にある。ここでのサタンの扱いは、英雄というよりは道化のそれと言った方が適切であるように思える。例えば、第六巻で描かれる天上での戦いで、サタンは、一日目には堕天使の軍勢から寝返ったアブデルを相手に強気に勝利を宣言するが、その後すぐに打ち負かされる。二日目には、ミカエルに威勢よく啖呵をきって立ち向かうが、結局、自分の方が傷付き味方の天使たちに運び去られていく。そして三日目には、神が御子を戦場へ遣わし、御子が堕天使の軍勢をもろとも地獄へと突き落とすが、この時サタンは登場さえしない。第十巻でサタンがイヴを誘惑する場面では、サタンがイヴを誘惑した後、サタンは巨竜に、堕天使たちは蛇に変身させられる。サタンの最後を描写する次の箇所は特に滑稽である。
そう言ったあと、恐らく自分の耳を聾するばかりの満堂の
喝采と賞賛の声が忽ちあがるものと思い、期待に胸をふくらませ、
暫時佇立していた。ところが、意外にも、四方八方から彼の耳を
襲ってきたものは、無数の舌、舌、舌から洩れてくる不気味な
しゅっしゅっという声であった!(第十巻 504-8)
確かにサタンは、第一巻と第二巻においては英雄的と呼ぶことはできる。しかし、『失楽園』に英雄的に登場したサタンは、最終的に道化的な扱いにまで貶められる。第六巻、十巻でのサタンの退場は、サタンの視点に立つ読者にとっては、アンチ・クライマックス的であると言わざるを得ない。もしミルトンが本当にサタンを英雄として描いていたとするなら、サタンの幕引きはこのようなものにならなかったはずだ。だが、そうかと言って、サタンが道化のバリエーションであると言い切ることも私にはできない。私はサタンを道化とも、英雄とも考えない。その両方の性質を合わせ持った、アンビバレントな存在であると考えたい。
第二章 ミルトンの分身としてのサタン
前章で、私は、サタンが道化的な要素と英雄的な要素を合わせ持ったアンビバレントな存在であると結論付けたが、私にはサタンの描写が、悪魔というにはあまりに人間的であると感じられる。それは、第六巻で傷付いたサタンが仲間に盾に乗せて運ばれていくところや、楽園にいる人間たちを羨む次のような台詞の中で強く感じる。
なんという憎むべき光景だ! なんという他人の心を
苛む光景だ! こうやって、この二人は、幸多きエデンの園の
中にありながらさらに幸多き園ともいえる、その固い抱擁の
世界に沈湎し、祝福につぐ祝福を心ゆくばかり味わうことができる。
しかるに、わたしは地獄に投げ込まれている–そこには喜悦も
愛もなく、永劫に充たされない恐ろしい欲望の苦しみが(それも
それに劣らぬ多くの責苦の一つにすぎないのだが)あるだけだ。
(第四巻 505-11)
ミルトンの描くサタンには、何故このような人間らしさが賦与されているのだろう。
サタンの人間らしさは、ことによれば、ミルトン自身に起因するのかもしれない。前章で、ブレイクが「悪魔及び地獄の叙述の躍如たるは彼が真の詩人であり、しらずしらず悪魔の仲間入りをしていたためである」と書いたことについて触れたが、ミルトンがサタンの仲間入りをしていたというのみならず、ミルトン自身とサタンを同一視する議論が存在する。つまり、サタンはミルトンの分身であるとする解釈である。だからこそ、サタンをいきいきと描写することができたのであるという訳だ。そのようにミルトンとサタンの類似に異常な関心と興味を寄せる者のことを「サタニスト」(Satanists)と呼び、その意見に反発する者を「アンティサタニスト」(anti-Satanist)と呼ぶこともあるという。(田中 100)
事実、サタンの語りの中には、ミルトンの主張と重なるように思える箇所がある。それは例えば次のような箇所だ。
座天使よ、主天使よ、権天使よ、力天使よ、しかして
能天使よ!わたしはお前たちにこのように呼びかける、ただし、
この厳めしい称号がただ単なる空しい肩書きでないとしての
話だ!というのは、神の命によって、今や或る者が
すべての権力を我が物顔に独占し、油を注がれし王という
名の下に、われわれの光彩を尽く奪い去ってしまったからだ。
(中略)我々が未だかつて
行ったこともない跪座の礼、つまり平身低頭して拝むという
あの醜悪な礼を、われわれから受けようとここへやって来る
彼を迎えるのには、どんな新しい恭啓の礼を工夫すべきかを
相談するためなのだ!一人の者に対してさえ過分の礼なのに、
況やその者と、今広く宣示されているその姿であるもう一人とに
対し、二重に拝礼するなどとはもっての他だ!
(第五巻 772-7、780-4)
William Kolbrenerは、論文’Milton’s Warring Angels’の中で、この語りでサタンは、ミルトン自身がReadie and Easie Wayで王政批判を行ったのと同じレトリックを使って、御子が天上において首位についたことを批判していると記す(Kolbrener 148)。一六六〇年に、イギリスではチャールズ二世が王位につき、十一年振りに王政が回復した。ミルトンは、キリスト教的共和国の実現を夢見ており、王政の回復には批判的な立場に立っていた。Readie and Easie Wayというのは王政批判のパンフレットであり、そのパンフレットの中の王政批判と同じレトリックをサタンが使っているというのだ。
だが、ミルトンの反君主制主義を主張する言葉と、サタンの御子に対する言葉の間には相違がある。ミルトンが提唱していたキリスト教的共和国というものは、人が人の上に立つことなどできない、ということだと理解する。つまり、人の上に立つ者は神一人で十分であると。サタンも御子の首位を批判するが、サタンの場合は、御子を引きずり降ろした後、自分が自らその座に座ろうと企んでいる。ここにサタンとミルトンの主張の決定的な相違がある。サタンはミルトンが使用したのと同じレトリックを用いているが、その本質は全く異なっている。だから私には、ミルトンとサタンの主張を同一視することはできないと思う。
それに、次のような見解もある。
『偶像破壊者』、『第一弁護論』、及び『第二弁護論』におけるミル
トンの敵対者たちの多様なイメージが『楽園の喪失』における大いな
る敵対者サタンの像に収斂している (新井2003 55)
ここで説明されていることは、先に述べたことと全く逆のことである。つまり、サタンは王政を批判するミルトン自身を反映しているのではなく、ミルトンと政治的に敵対していた相手側を反映しているというのである。こうしてみると、サタンとミルトンを同一視するのはいささか性急な議論のような気がして来る。
だが、次の主張は、一面の真実を含んでいるように思う。
この作品中のサタンや人祖の苦悩は同時にそのままこの作品執筆当時
のミルトン自身の苦悩であったと考えてよいと思う。つまりサタンや
人祖の追放を聖書の物語に則って詩化しようとした時、ミルトンはそ
の時の自分自身のエグザイル感をサタンや人祖のエグザイルの苦悩に
仮託して表現しようとした(長澤 73)
ミルトンは一六五二年に失明し、一六五八年には、結婚生活わずか十五ヶ月の妻と生後間もない女児を失うという立て続けの不幸に見舞われた。そして、一六六〇年に望んでいなかった王政が回復した。『失楽園』の出版は一六六七年だが、一六六〇年には、ミルトンはすでに口述を開始していたという。それを考えると、サタンにミルトン自身の感情が反映されているのは当然と言えば当然である。また、サタンのみならず追放の身となるアダムやイヴにも、ミルトンが心情的に託したものがあったとしてもおかしくはない。
だが、たとえミルトンがサタンに何らかの心情を仮託していたとしても、サタンは敗北する運命にあった。そして、ミルトンは実際にサタンを敗北させた。もしミルトンがサタンに自分の心情を託していたとしたら、そこには深いアイロニーが伴っていることになる。そのようなアイロニーを込めて、ミルトンはサタンを彼自身と重ね合わせていたのかも知れない。真相は知る由もないので、ここではサタンに弱さや嫉妬、苦悩といった人間的な性格が賦与されているということだけを確認して、議論を次に進めたいと思う。
第三章 物語における悪役としてのサタン
Neil ForsythはThe Satanic Epicの中で、叙事詩の古典やキリスト教の神話、プロテスタントの神学者や聖書を除けば、ミルトンのサタンに最も大きな影響を与えているものは演劇の伝統であると述べている。[2] 『失楽園』はもともと、叙事詩ではなく五幕構成の劇作品として構想されていた。それは正義、慈悲、勤勉、無知といった、寓意的な登場人物が出てくる中世の道徳劇を意識した作品だったようだ。[3] 中世の道徳劇には悪魔も頻繁に登場したようだが、その悪魔というのは「毛むくじゃらの悪魔が口に爆竹をくわえて、舞台を吠えまわる」といったようなもので、クリストファー・マーロウの『フォースタス博士』に登場する悪魔も当時、そのように演出されていたようだ。(村上 28)『失楽園』には『フォースタス博士』からの影響が指摘されている詩行がいくつかあるが、殊に悪魔の造形に限っては影響されていないようである。ミルトンは『失楽園』において、独自の悪魔像を追求したといえそうだ。『失楽園』は構想上、叙事詩となる前に一篇の劇作品であった訳だが、芝居には悪役というものが必要不可欠なものだ。『オセロー』にはイアーゴーが、『ハムレット』にはクローディアスという悪役が必要であった。悪役がその劇の成否を決めることも多い。ミルトンの創造したサタンは、劇場で観客の要求に応えることも十分にできうる、魅力を持った悪役である。
ミルトンは、そのような悪を描くことで何を伝えようとしたのだろう。その答えは第一巻の冒頭にある。
願わくば、このいと高き大いなる主題にふさわしく、
永遠の摂理を説き、神の配慮の正しきを、人々に
証明することを、私に得させ給わらんことを!(第一巻 24-6)
ミルトンはこの叙事詩で、神の配慮の正しさを描き出そうとしたのだ。だが、善を伝えるための物語にどうしてサタンが必要だったのだろうか。それは、悪が無いところでは善を描くことはできないからであるし、悪がいなければ、また、物語も生まれ得ないからである。つまり、サタンは、神の正しさを描くための必要悪だったのだ。
善という概念それ自体を、単独で表象するのは非常に困難である。何故なら、神に匹敵するような、最高の位にある善を表わすことのできる言葉を、人間は持ち合わせていないからである。そのため、善を描くためには比較対象となる悪が必要不可欠なのだ。悪によって善が知られる。もっと言えば、悪が善を規定する、と言うこともできよう。ミルトンは、善なる神を表象する必要上、サタンを表象しなくてはならなかった。神を描くためには悪魔が必要だったのである。そして、ミルトンが描き出さんとした善なる神は、人間にとって量り知れない大きさと深さを持つ、最高の位に位置する概念であった。だから、そのような大きな力を持つ神を描くためには、大きな力を持つサタンが必要だったのだ。『失楽園』におけるサタンの存在意義はそこにある。ミルトンは『失楽園』で巨大な善と悪を描こうとした。そしてその結果、善も悪も崇高な性質を帯びてしまったのだ。つまり、物語の要請で巨大な悪を描こうとしたら、悪もまた崇高なものとなってしまった。田中勉氏は、次のように記す。
(ミルトンは)人間精神に宿る絶対者、最高存在者としての神の観念
が包含する属性のことごとくに対立する邪悪をセイタンに表現しよう
としたが、あらゆる邪悪を邪悪たらしめる自己原因としての悪の実体
は、余りに大きく深くて、それを表徴するに足る概念は一つだにミル
トンの精神に存在しなかったのである。(中略)要するに、ミルトン
はキリスト者としてあらゆる悪の自己原因である悪の本体という、人
間の表徴力を越えた実体の描写を試みたために失敗したと言ってよ
い。(田中 106)
ミルトンが描くサタンに、私はそれ程邪悪な印象を受けない。確かに、田中氏が言うように、ミルトンが巨大で邪悪な悪を描くつもりでサタンを造型したのだとすれば、その試みは失敗に終わったのかもしれない。しかし、ミルトンのサタンは、悪の中に崇高さという善なる要素を兼ね備えることによって、『失楽園』という物語における一つの魅力的な登場人物となり得た。性格描写が複雑なものとなり、悪役として奥行きを備えることになった。
例えば、次のような箇所に、サタンの悪役としての複雑さが認められる。
ああ、それにしてもなぜあのようなことを? 神はあのような
仕返しをわたしから受ける謂われはなかった。わたしをあれほど
輝ける者として造り、恩恵を施しこそすれ、いささかも咎める
ことをされなかった。求められた奉仕にしろ辛くはなかった。
神に賛美を捧げることは、辛いどころか全く易々たる恩返し
であり、感謝を捧げることも全く当然なことであった!
(第四巻 43-8行)
サタンは楽園に到達し、いざ人間を堕落させて神への復讐を果たそうとする段になって、自分の行いを後悔し、このように逡巡する。サタンは、神に恩恵を与えられたことを正しく認識している。サタンは自分の過ちを認め、神に反逆したことを後悔しながらも悪を選ぶ。そして、アダムとイヴに哀れみを感じながらも、復讐のために彼らを滅ぼす決意を固める。
この二人を見ていると、
わたしの心は驚嘆の念に充たされ、ともすれば愛情さえ覚える。
それほど、神の姿が彼らの姿のうちに生き生きと輝いている、
それほど、彼らに形を与え給うた者の手がその形に美しさを
注ぎ込んでいる! ああ、気高き二人よ!(第四巻 363-7行)
これらの台詞は、悪の化身のものというには、あまりに人間的な響きを持っている。
サタンにこのような台詞を語らせることで、ミルトンのサタンは複雑さを増す。『ハムレット』のクローディアスにも自分の犯した罪を認め、自分の邪悪さを認識していることを示す独白があるが、そのような多面性を賦与することは、登場人物に奥行きを与えることになる。悪の中に善なる要素を描きこむことは、受け手に混乱や誤解を与えることにもなりかねない。だが、そのキャラクターだけに留まらず、作品自体に複雑さと奥行きを与える結果をもたらす。そして、受け手に、そのキャラクターに感情移入する余地をも与える。サタンに、崇高さや人間臭い感情が賦与されているからこそ、ブレイクやシェリー、ボードレールといった詩人たちは、サタンに感情移入したのである。
ブレイクは、西欧の絵画の伝統では獣的で醜悪な者として表現されることの多い悪魔を、どこからどう見ても人間にしか見えないような、一糸纏わぬ姿で両手を高く揚げるサタンの水彩画を描いている(図版1参照)。この絵は、ブレイクが、ミルトンが描いたサタンの本質を、さすがにサタンに共鳴したものであるだけあって、上手く捉えてみせたものであると思う。

図版1 ウィリアム・ブレイク『サタンが反逆天使に呼びかける』
ミルトンの『失楽園』のための版画下絵の水彩。(リンク 91)
第四章 堕落した人間の原型としてのサタン
これまでの章で、サタンの造形に見られる人間らしさについて様々触れてきたが、何故、サタンにそのような人間らしさが賦与されねばならなかったのだろうか。
一つには、善や悪というのは、観念だけではあまりに大きすぎて手にあまるので、人間の姿を借りて表現するのが、受け取り手とイメージを共有するのにもっとも有効であったということが言えるだろう。ラファエルは第六巻で次のように語っている。
わたしは今言語に絶する云々と言ったが、天使の
言葉をもってしてもそれを語るのは難しく、地上で見られる
いかなるものに譬えたら、このような神の如き力と力との極限に
近い激突を、人間の想像力に訴えたらよいのか分からないからだ。
(第六巻 297-300行)
ラファエルはアダムに向かって天上の戦闘の激しさを語っているが、天上界を知らぬ者にそれをそのまま伝えることはできないので、地上のものに置き換えて話をしているのだと言う。だから、他の箇所でも話の合間で、「壮大無比な事象を卑近な事象に譬えて表わすとしての話だが」と断ったりしている(第四巻 310-1行)。
作者ミルトンもまたラファエルと同じように、サタンを描くに当たって、巨大な悪を表現するために人間らしい性格を与えたとは言えまいか。読者に伝わりやすいように、人間らしい姿を借りてきたのではないか。人間が持つ想像力というのは、見たことのないものに対しては、なかなか有効に働かないものである。ギリシア神話やローマ神話には、多くの異形の者たちが登場するが、『失楽園』をそのようなものとして描いた場合、「神の配慮の正しさ」を伝えるという当初の目的を達成するためには障害となったことだろう。人間に善という概念を分かりやすく伝えるために、聖書にキリストが必要であったのも同様であるかも知れない。そしてその人物の思考に、第二章で述べたように、人間の一つのモデルとして一番勝手知ったる自分自身の考えが流れ込んでいたとしても、つまり、サタンにミルトン自身の思考が反映されていたとしても、何ら不思議は無い。
だが私は、ミルトンがサタンを人間的に描かなくてはならなかった最大の理由は、ミルトンがサタンを、堕落した人間の原型として描いたことにあると思っている。人間とサタンは、両者とも神によって造られた被造物で、共に罪を犯し、追放の憂き目に会う。
両者にはそのように重要な共通点があるが、最初に挙げておきたいのが、両者ともに、神によって自由意志を与えられているということである。自由意志とは、神が被造物に対して与えた、その者に自分自身の選択で自由に振る舞うことを許す特権である。その権利があるからこそ、被造物は、己の裁量で自由に振る舞うことができるのだ。つまり、一言で言えば、それは、堕落する権利である。サタンも人間も、この自由意志を誕生した瞬間から与えられていた。そして両者ともその権利を行使し、堕落に至るのである。第四巻で、サタンは自分自身に呼びかける。
お前こそ
呪わるべきだ。神の意志に反して、お前は今当然悔いているものを
自分の意志で選んだからだ。(第四巻 71-73行)
サタンは、自分が罪を犯したことを後悔しており、自分など呪われて当然であると考えている。この語りから、サタンは自分の意志で、罪を犯したことを理解していることが分かる。つまり、サタンは、神に与えられた自由意志を理解しているのだ。そして、その上で罪を犯した。
サタンも人間も罪を犯すが、両者が犯す罪は同じ性質のものである。それはどのような罪なのか。彼らの犯した罪は、七つの大罪のうち、傲慢である。それは、被造物が、創造主である神を、創造主であると認めるのを止める事である。神がサタン(正確に言えば、サタンと呼ばれる前のルシファー)と人間を創造した。そしてサタンは神に反逆し、人間は、神の言い付けを破り、知恵の木の実を食べた。被造物が、創造主を創造主であると認めることを止める、そのことがキリスト教的な罪の始まり、つまり原罪なのである。[4]
両者が罪を犯すことになった、その動機にも共通点がある。サタンが神に反逆した理由は、御子に対する嫉妬であった。そして、人間の堕落に関しては、イヴが堕落したのはサタンにそそのかされたからだが、アダムが果実を口にしたのは、己の欲望に負けたからだ。下の箇所がそれを説明している。
彼は狐疑逡巡することなく、かねて持っていた己の善き知識に
逆らってその果実を食べた、—-惑わされたからでなく彼女の女と
しての魅力に愚かにも負けたからに他ならなかった。
(第九巻 997-9行)
アダムは、イヴの魅力に抗うことができず、罪を犯した。サタンも人間も、それを悪だと判断する能力を有していたにも拘らず、己のうちの欲望に打ち勝つことができずに罪を犯したのだ。
平井正穂氏は、アダムとイヴが罪を犯したことが「堕落 (The Fall)」であるのに対して、サタンが罪を犯したことは「原堕落 (Ur-Fall)」であると記している(平井1998 26)。この指摘は正鵜を得ていると思う。サタンと人間にはこれだけの共通項がある。サタンは、堕落した人間の原型と言えるのではないか。つまり、原罪を背負った人間の原型であると。私は、ミルトンは、サタンをそのように描いていると思う。そのため、サタンに人間的な性質が備わることとなったのだ。
さて、サタンと人間は、罪を犯した後、サタンは天上界から、人間は楽園から、共に放逐される。以下に挙げるのは『失楽園』最後の詩行である。
彼らは、ふりかえり、ほんの今先まで
自分たち二人の幸福な住処の地であった楽園の東にあたる
あたりをじっと見つめた。(中略)彼らの目からはおのずから
涙があふれ落ちた。しかし、すぐにそれを拭った。
世界が、—-そうだ、安住の地を求め選ぶべき世界が、今や
彼らの眼前に広々と横たわっていた。そして、摂理が彼らの
導き手であった。二人は手に手をとって、漂泊の足どりも
緩やかに、エデンを通って二人だけの寂しい路を辿っていった。
(第十二巻 640-9行)
こうしてアダムとイヴは、楽園を追放されて旅立っていく。ここでも、サタンと二人を重ね合わせることができる。アダムとイヴの旅立ちは、第一章で取り上げた、天上での戦いに敗れたサタンが単身、人間を陥れるために楽園へと赴く姿と重なる。新井明氏は次のように述べる。
アダムの旅立ちを描写するときに、作品の最後まで読みきたった読者
としては、第二巻において感じたと同様のヒロイックな雰囲気を、こ
こに感じないわけにはいかない。ミルトンはおそらく、アダムのヒロ
イズムを主張するという目的からだけでも、旅ゆくサタンの英雄性を
強調しないわけにはいかなかったのである。
(新井1980 259)
両者のヒロイズムには確かに共通した雰囲気を感じ取ることができる。
長澤順治氏は以下に挙げるように、ミルトンは、サタンと人間の追放を似たように描いており、そのため、サタンの追放には人間らしい苦悩がもたらされ、読者もその苦悩に共感することができると述べる。
ミルトンはサタンを始めとする堕天使の群れを人間と同じような次元
で扱っている。つまり良心や選択の自由がずっとのこされているもの
のように描いている。だからそのための堕天使の人間臭に満ちたエグ
ザイルの苦悩は、そのまま人間的に共感できるものがある。
(長澤 76)
だが、実際は異なるのだ。人間は神によって見放されてはいない。第三巻で、神は、人間たちはサタンにたぶらかされて堕落したのであるから、恩寵を与える意向であることを宣言する。第六巻において、アブデルがサタンに告げる言葉が示唆的である。
隷属とは、今汝の部下が汝に仕えているように、
愚かなる者に仕える、或は己より価値高き者に叛逆した者に
仕える、ということだ。しかも、汝自身、自由な身どころか
自分自身の奴隷になっているではないか。(強調筆者)
(第六巻 178-81行)
アブデルは、サタンに告げる。お前はもはや「自由」ではなく、「自分自身の奴隷」に過ぎないと。ここでいう「自由」とは自由意志に他ならない。つまり、堕落する自由である。サタンは自由を失った。何故なら、すでに堕落してしまったからである。一度神の恩寵から離れたものには、もはや原罪を犯す自由、つまり、神の意志に逆らう自由は無いのだ。サタンは、堕ちる自由を失った。そして、「自分自身の奴隷」となった。サタンは自分自身の「内なる地獄」に捕われたのだ。
恐怖と疑惑が千々に乱れた思いを翻弄し、彼の
内なる地獄を底の底から揺り動かした。彼は自分の内部に、
自分の身の周辺に、常に地獄を持っており、たとえ
場所が変っても自分自身から抜け出せないのと同じく、
地獄からは一歩も抜け出せないからだ。(強調筆者)
(第四巻 19-23行)
この詩行は、クリストファー・マーロウ『フォースタス博士』の次の台詞と共鳴している。
地獄に境界はなく、一定の場所に限られてはいない。
われらのおるところすなわち地獄、
地獄あるところすなわちわれらの永劫の住まいなのだ。(二幕一場)
地獄とはサタンの外部にあるものではなく、サタンがいる所が地獄なのである。つまり、サタンは、永久に「内なる地獄」から逃れることはできない。サタン自身、空間としての地獄がそれを認識する内面と関係していることを理解している。次の引用は、サタンが天上での戦闘に敗れた後、地獄で語るものである。
心というものは、それ自身
一つの独自の世界なのだ、—-地獄を天国に変え、天国を地獄に
変えうるものなのだ。 [5] (第一巻 253-255行)
サタンは堕天使たちを前にして、今、彼らは地獄にいるが、気持ち次第で、その地獄は天国に変るのだと、彼らを鼓舞する。しかし、彼は地獄から逃れることはできない。楽園へと向かうサタンはそのことに気付く。
どこへ逃げようが、そこに地獄がある!
いや、わたし自身が地獄だ! (第四巻 75-6行)
ここに堕落後のサタンと人間との大きな差異がある。人間たちは堕落した後も、第三巻で神が語っているように、神の恩寵の下にいる。何故なら、人間たちはサタンにそそのかされて堕落したからである。しかしサタンは神の恩寵の下にいない。何故ならサタンは自分の心に芽生えたラファエルへの嫉妬によって、自ら堕落したからである。「内なる地獄」とはそのことを表わしている。つまり、「地獄」とは、神の恩寵の届かない場所のことを意味しているのだ。この「内なる地獄」、つまり神の恩寵の下にいないことが、サタンを、道化や英雄、ミルトン自身、アダム、イヴ等と分かち、サタンをサタンたらしめている。
結び
私は、本論において、今までなされてきて様々なサタンの解釈について考察し、サタンに人間らしさが賦与された理由を探ってきた。
第一章では、道化から、英雄までの幅広いサタン像について紹介した。サタンには確かに英雄的な側面があるが、第六巻、十巻でのサタンの退場を考えると、ミルトンが本当にサタンを英雄として描いていたかどうかは疑わしい。私は、サタンが道化的な要素と英雄的な要素を合わせ持ったアンビバレントな存在であると結論付けた。
第二章では、サタンとミルトンの主張が重なっている箇所があることから、ミルトンとサタンを同一視するサタニストの主張について考察した。サタンは、ミルトンが使用したのと同じレトリックを用いているが、その本質は全く異なっている。そのため私は、ミルトンとサタンの主張を同一視することはできないと考えた。だがサタンには、ミルトンと共有したかもしれない、弱さや嫉妬、苦悩といった、人間的な性格が賦与されているということを確認した。
第三章では、物語においての悪の必要性について考え、サタンに崇高さが賦与された理由を探った。ミルトンは、『失楽園』で、神の配慮の正しさを描き出そうとしたが、善を描くためには、サタンという悪役が必要だった。そして、ミルトンが、巨大な善と悪を描こうとした結果、善も悪も崇高な性質を帯びることになった。サタンは、悪の中に崇高さという善なる要素を兼ね備えており、複雑で奥行きのある悪役となった。
第四章では、サタンを、堕落した人間の原型として考え、アダムとイーヴと比較し、サタンの人間らしさの源泉を探った。人間とサタンは、両者とも神によって造られた被造物で、共に罪を犯し、追放の憂き目に会う。私は、サタンは、原罪を背負った人間の原型であると結論付けた。そのため、サタンに人間的な性質が備わることとなったのだ。しかし、サタンには堕落したアダムやイヴと異なる決定的な違いがある。サタンは、ラファエルへの嫉妬にかられ、自ら堕落する。そうしてサタンは、神の恩寵から離れ、「内なる地獄」に捕われることになるが、この「内なる地獄」こそが、サタンをサタンたらしめている要素であると論じた。
私は本論において、サタンに人間らしさが賦与された理由を探って来た。その理由は、従来論じられて来たように、サタンが道化として描かれているからでも、英雄として描かれているからでもない。あるいは、ミルトンが自分を投影してサタンの性格を造形したからでもない。私は、その理由は、サタンが堕落した人間の原型として描かれていることにあるのだと考える。そして、ミルトンにとってサタンとは、中世道徳劇に登場したよな爆竹を加えた毛むくじゃらの化け物といったような、異形のものを指すのではなく、「内なる地獄」に捕われているもの、つまり神の恩寵を離れ、永久に地獄に捕われ続けるものを指すのである。
引用文献
新井 明 『ミルトンの世界—-叙事詩性の軌跡』 東京: 研究社 1980.
新井 明・野呂 有子 編 『摂理をしるべとしてムミルトン研究会記念論文集』
東京: リーベル出版 2003.
Blake, William. Blake’s Poetry and Designs. Ed. Mary Lynn Johnson and
John E. Grant. New York and London: W. W. Norton & Company,
1979.
ウィリアム・ブレイク 『ブレイク詩集』 土居 光知 訳 東京: 平凡社 1995. Forsyth, Neil. The Satanic Epic. New Jersey: Princeton University Press,
2003.
平井 正穂 編 『ミルトンとその時代』 東京: 研究社 1974.
—– 『イギリス文学論集』 東京: 研究者 1998.
Kolbrener, William. Milton’s Warring Angels. Cambridge: Cambridge
University Press, 1997.
ルーサー・リンク 『悪魔』 高山 宏 訳 東京: 研究社 1995.
ミルトン 『失楽園』 平井 正穂 訳 東京: 岩波書店 1981.
長澤 順治 『ミルトンと急進思想 英国革命期の正統と異端』 東京: 沖積舎
1997.
村上 淑郎 著者代表 『エリザベス朝演劇—-小津次郎先生追悼論文集—-』 東京:
英宝社 1991.
小津 次郎・小田島 雄志 編著 『エリザベス朝演劇集』 東京: 筑摩書房
1974.
田中 勉 『ミルトン新考』 東京: 松柏社 1971.
辻 裕子・佐野 弘子 編 『神、男、そして女 ミルトンの『失楽園』を読
む』東京: 英宝社 1997.
参考文献
新井 明 『ミルトン論考』 東京: 中教出版 1979.
—- 編 『ミルトンとその光芒』 東京: 金星堂 1992.
—- 『ミルトンとその周辺』 東京: 彩流社 1995.
—- 『ミルトン 人と思想134』 東京: 清水書院 1997.
圓月 勝博 他 『挑発するミルトン—-『パラダイス・ロスト』と現代批評』
東京: 彩流社 1995.
Jasper, David. and Stephen Prickett. ed. The Bible and Literature;
A Reader. Oxford and Massachusetts; Blackwell Publishers, 1999,
越智文雄博士喜寿記念論文集編集委員会 『ミルトンム詩と思想』 東京:
山口書店 1986.
Milton, John. Paradise Lost. 2nd ed. Ed. Fowler, Alastair. London:
Addison Wesley Longman Limited, 1998.
ミルトン 『ミルトン詩集』 才野 重雄 編注 東京: 篠崎書林 1976.
才野 重雄 『ミルトンの生涯』 東京: 研究社 1982.
武村 早苗 『ミルトン研究』 東京: リーベル出版 2003.
註
[1] The reason Milton wrote in fetters when he wrote of Angels & God, and at liberty when of Devils & Hell, is because he was a true Poet and of the Devil’s party without knowing it. (Blake 88)
[2] Apart from classical epic and Christian myth, apart from Reformation theologians and their biblical proof-texts, the most important influence on Milton’s Satan was the dramatic tradition. (Forsyth 60)
[3] The early sketches in the Trinity Manuscript for what became Paradise Lost, when he was still thinking of it as a tragedy not an epic, show Milton thinking along the lines of the medieval morality plays (which, unlike the mysteries, continued to lead a half-life well into the seventeeth century): he peoples his draft with allegorical characters like Justice, Mercie, Labour, Ignorance. These jottings, which are also reminiscent of Greek tragedy in their use of the chorus and their five-act structure, are usually dated to 1640-42 According to Edward Phillips Milton’s nephew, he was still thinking of a tragedy a few years later (”several Years before the Poem was begun”), and Phillips even quotes the first ten lines of Satan’s Niphates speech as having been ”designed for the very beginning of the said Tragedy.” (Forsyth 60)
[4] メアリ・シェリーは、失楽園を意識して『フランケンシュタイン』を書いた。(辻 170)この物語に登場する怪物は、『失楽園』のサタンのように、創造主である科学者の意志に抗して世界を彷徨うことになる。
[5] 平井正穂氏は訳注に次のように記す。「天国と地獄のいわば外在性ともいえるものを否定し、内在性を強調する考えは、十七世紀の無神論者の主張したところであった。この考えは勿論ストア派の思想まで遡ることができる。しかし、ルネサンスの人々にとっては魅力的なものと思われたことは間違いない。」(ミルトン 333)


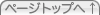
Comments & Trackbacks
Trackback URL http://shakeweb.co.uk/spear/thesis/29.html/trackback