ガートルードとアルカージナ
ガートルードとアルカージナ
—シェイクスピア『ハムレット』とチェーホフ『かもめ』の比較—
米田 拓男
Introduction
本論では、シェイクスピアの『ハムレット』とチェーホフの『かもめ』の二作品を比較する。『ハムレット』と『かもめ』には、多くの共通点がある。両作品とも、主人公は新しい恋人(夫)を持った母親に対して愛情と憤りの入り交じった複雑な感情を抱き、恋に思い悩み、決意を持って行動を起こすことができない。二作品とも中断される劇中劇を含み、主人公の死によって幕を閉じる。作中でチェーホフは『ハムレット』からの台詞を引用してさえいる。『かもめ』の劇構造が『ハムレット』に似通っているとは、しばしば指摘されるところである。(佐々木 一八〇頁)
そのように多くの共通点を持つ二作品だが、その作品の形式には大きな相違がある。その相違は、対照的であると言ってもいいほどのものである。本論では、『ハムレット』のガートルードと『かもめ』のアルカージナという二人の登場人物を比較したい。Chapter 1では、ガートルードとアルカージナの性格を比較して論じながら、チェーホフとシェイクスピアの相違を、リアリズムと非リアリズムという点に求める。Chapter 2では、リアリズムと非リアリズムという観点からさらに前進して、作者と作中人物における主観性と客観性について議論を展開する。本論は、ガートルードとアルカージナという二人の作中人物を通して、最終的にシェイクスピアとチェーホフという二人の作家の違いを浮き彫りにすることを目的とする。
Chapter 1 リアリズムと非リアリズム
『ハムレット』においても『かもめ』においても、主人公とその母親との関係が、物語の展開の上で、主人公の内面における葛藤の焦点となっている。本論では、特にアルカージナとガートルードの台詞に注目し、シェイクスピアとチェーホフという二人の劇作家それぞれの特徴について論じたいと思う。そのための手続きとして、母親と息子が二人きりになって話を交わす、それぞれの作品にとって唯一の場面を比較することにしたい。『ハムレット』第三幕第四場の居室の場と、『かもめ』第三幕でトレープレフが母親に自分の頭に包帯を巻いてくれとせがむ場面である。
まず、『ハムレット』の方から見てみたい。王の御前での劇中劇の上演後、ハムレットはガートルードの部屋に来るように言われ、母親の部屋に赴く。そしてハムレットは部屋に入るなり、母親に対して強い調子で当たる。身の危険を感じたガートルードは人の助けを求め、それに応じて壁掛けの後ろに隠れていたポローニアスも助けを求める。ハムレットは彼を刺し殺す。その後、ハムレットはさらに母親に強い口調で言いつのる。そしてガートルードが答える。
王妃 私がなにをしたというのです、
おまえにそのような口のきき方をされるとは?
ハムレット あなたがしたことは、女のつつしみ深さに泥をぬり、
貞淑の美徳を偽善者呼ばわりすることだ、
汚れない愛の額からバラの冠を奪いとり、
そのかわりに売笑婦の烙印を押すことだ、
結婚の誓いを踏みにじり、博打うちの
空約束にすることだ、ああ、あなたがしたことは、
夫婦の約束からその魂を抜き去り、神に誓ったことばを
たわごとの羅列にすることだ。そのために、
天も憤りに顔を赤らめ、堅い大地も悲しみに
ふるえおののいているのです。
王妃 なんのことです、いったい、
のっけからそのようにどなりつけるようなこととは?
ハムレット ごらんなさい、この絵を、それから
これを、二人の兄弟の絵姿だ。
どうです、このお顔に宿る気品は、
太陽神アポロの巻き毛、主神ジュピターの額、
三軍を叱咤激励する軍神マルスのまなざし、
天を摩する山頂におり立ったばかりの
使神マーキュリーの立ち姿、
神々が天下にむかって、これこそ
人間のなかの人間、男のなかの男と
知らしむるために印を押した契約書、母上、
これがあなたの夫であった人だ。
(『ハムレット』第三幕第四場四一〜六四行)
ここでハムレットは、語気を荒げて、母親に対して挑むような強い口調で言いつのっていく。その語りかけには、一方的で、母親に意見を差し挟ませないような、断固とした調子がある。ガートルードは、ハムレットが一方的にたたみかける合間に、一言、二言、口を挟むだけである。ガートルードはハムレットに対して強く出ることができない。ここに見られる二人の関係は、一方が、もう一方の不正を容赦なく糾弾するというものだ。
続いて、『かもめ』のトレープレフとアルカージナの対話を見てみたい。第二幕が幕を閉じた後、トレープレフは拳銃で自殺を謀る。そして、第三幕が幕を開けた時、トレープレフは、自殺に失敗し、頭に傷を受け、包帯を巻いて登場する。この場面でトレープレフは、先のハムレットと同様に、自分の母親に向かって、母親の恋人がいかに彼女にとって相応しくないかを説いてみせる。
トレープレフ 包帯かえてくれる、ママ? ママは上手だから。
アルカージナ (薬品棚からヨードホルムと包帯を取り出す)それは
そうと、ドクターは遅いわね。
トレープレフ 十時にくるって約束したのに、もう十二時だ。
アルカージナ おすわり。(彼の頭の包帯をとる)まるでターバンを巻
いた人みたい。昨日勝手口にきただれかが聞いてたよ。おまえはど
この国の人かって。でも、もうほとんどなおったわ。あとほんのち
ょっと。(彼の頭にキスする)私がいなくなってからまたピストルを
おもちゃにしたりしないわね?
トレープレフ しないよ、ママ。あのときはぼく、とてつもなく絶
望して、自分をおさえきれなくなったんだ。もう二度とあんなまね
はしない。(彼女の手にキスする)
(中略)
ここ何日か、ぼくは子供のころみたいにママが好きで好きでたまら
なかった。僕にはママしかいないんだ。それなのにどうして、どう
してあんな男がぼくたちの間に入りこむんだい?
アルカージナ コンスタンチン、おまえにはあの人のことがわかっ
てないんだよ。あの人は最高の人格者で……。
トレープレフ その最高の人格者がぼくに決闘を申しこまれそうだ
と知ると卑怯者の正体をあらわしたじゃないか。逃げ出すんだから
な。恥っさらしめが、こそこそと!
アルカージナ なにをばかな! 私があの人に頼んで発つことにし
たんだよ。そりゃあおまえは私たちの関係を不愉快に思うかもしれ
ない。でもおまえだってもう一人前の知性はもっているだろう、だ
ったら私の自由を尊重してほしいわ。
(『かもめ』第三幕九七〜九九頁)
ハムレットもトレープレフも、母親に対してエディプス・コンプレックス的な屈折した愛情を抱いているといえるが、1ここでのトレープレフの振る舞いは、エディプス・コンプレックスというより、むしろ幼児返りといった方が相応しい。トレープレフは二十五歳という設定になっているが、とてもそうは思えない。彼は母親の前で、だだをこねる子供と化している。そのようなトレープレフと比べれば、ハムレットの方が遥かに理性的である。例えば次のような場面。ハムレットは自分の母親に会いに行く直前に、次のように決意を表明する。
だが待て、まず母上のもとへ。
ああ、それには人の心を失ってはならぬ、けっして
この固い胸に母親殺しのネロの魂を入りこませてはならぬ。
きびしくはあっても、子としての情愛は忘れないぞ。
短剣のようなことばは用いても、用いるのはことばだけだ、
その点、舌と心はおたがいに裏切りあってほしい。
舌がどのように激しく母上を責め立てようと、心よ、
そのことばを実行に移す責めだけは負うなよ。
(『ハムレット』第三幕第二場三八七〜三九四行)
「子としての情愛」。ハムレットは、母親の自分に対する愛情を問う前に、自分の母親に対する愛情を問う。トレープレフは決してそのような認識に至ることはない。『ハムレット』の例では、その場のイニシアティヴをハムレットがとっているが、『かもめ』では、場のイニシアティヴは母親のアルカージナに握られている。トレープレフは、母親に断固たる調子で語ることができず、到底母親を説得できそうにない。この二つの場面を比べてみると、『ハムレット』では、息子の方が母親よりキャラクターが強く、『かもめ』では、息子より母親の方がキャラクターが強い。言い換えれば、ガートルードの方がより受動的で、アルカージナの方がより能動的であるといえる。
この二作品における母親像は、その性格描写において、赴きがだいぶ違うのが判るだろう。そして、この二人の性格において、決定的に違うことがある。先の場面で、アルカージナは、トレープレフの批判に対してきつく言い返す。そもそもアルカージナは口が悪く、息子に対してもあけすけに批判し、露骨に冷淡な態度をとったりする。それに比べて、ガートルードはハムレットに対して、冷淡な態度をとったり、罵倒するようなことはない。一見すると、ガートルードの方が息子に対して理解がありそうに見える。しかし、実際は、アルカージナの方が息子の気持を理解していて、ガートルードの方が息子の気持を理解していない。
先の引用の中で、ガートルードは、言いつのるハムレットに対して、「私がなにをしたというのです、おまえにそのような口のきき方をされるとは?」であるとか、「なんのことです、いったい、のっけからそのようにどなりつけるようなこととは?」と疑問を呈する。どうやら、ガートルードは、ハムレットが何を言わんとしているのか、この段階で分かっていないようなのだ。先に引用した引用の直前には、もっとひどいことを言っている。
ハムレット まあ、まあ、おすわりなさい、動いてはなりませぬ。
いま、鏡を見せてあげましょう、あなたの心の奥底を
とくとごらんになるのです、それまではどこへも行かせませぬ。
王妃 なにをするのです? まさか私を殺すつもりでは?
だれか、だれか、助けて。
(『ハムレット』第三幕第四場十八〜二二行)
ガートルードは、ハムレットの母親に対する愛情を察していないどころか、実の息子に殺されるのではないかと思っているのだ。この誤解は、あまりに酷すぎると思う。この場面の息子に対する理解のなさから判断すると、ガートルードはとても聡明な人物とはいい難い。そもそも彼女は、自分の夫が不審な死を遂げ、それから間もない内に、夫を殺した男と少しも怪しむことなく結婚したのである。ハムレットの母親に対する憤りも判るような気がしてくる。ハムレットはガートルードの鈍感さをなじっているのだ。次の引用でガートルードは、そうやって言いつのられて、やっとのことでハムレットの言わんとしていることを飲み込む。
王妃 ああ、ハムレット、もうなにも言わないで。
おまえは私の目を心の奥底にむけさせる、
そしてそこに見えるのは、どす黒いしみ、
洗っても落ちはしまい。
ハムレット ああ、落ちるものですか。
脂ぎった汗くさい寝床のなかで、欲情にただれた
日々を送っている以上。抱いて抱かれる
その相手は汚らわしい豚—-
王妃 お願い、もうやめて。
おまえのことばは短剣のようにこの耳を刺す。
もうなにも言わないで、ハムレット。
(『ハムレット』第三幕第四場九〇〜九九行)
ガートルードのこのような鈍感さが、ハムレットの悲劇の源泉になったと言うことも可能だろう。そして、ガートルードが自らの内に邪な心が宿っていることを認識するこの言葉が、『かもめ』の中で引用されているのである。『かもめ』は、トレープレフが書いた戯曲を、母親とその愛人の前で上演する劇中劇の場面から始まる。そしてその場面のトレープレフとアルカージナの対話は、『ハムレット』の今の場面からの引用で始まる。
アルカージナ (トレープレフに)「ここへおいで、ハムレット、母の
そばへ」ねえ、いつはじまるの?
トレープレフ もうすぐだよ。辛抱して。
アルカージナ 「ああ、ハムレット、もうなにも言わないで。
おまえは私の目を心の奥底に向けさせる、
そしてそこに見えるのは、どす黒いしみ、
洗っても落ちはしまい」
トレープレフ 「ああ、落ちるものですか。
脂ぎった汗くさい寝床の中で、欲情にただれた
日々を送っている以上。抱いて抱かれる
その相手は汚らわしい豚……」
(『かもめ』二七〜二八頁)
この二つの台詞は、言っている言葉は同じだが、その意味合いは全く違うものになっている。ガートルードが言う時、この台詞はガートルードの鈍感さを暴露する。しかし、アルカージナが言う場合には、それとは全く逆のものを示す結果となる。この場面で先に『ハムレット』の台詞を引用してみせるのは、アルカージナの方だ。アルカージナは自分の息子をハムレットに見立てる。ということはつまり、アルカージナは、トレープレフが自分と愛人の関係に嫉妬していることを理解しているのだ。だからこそ『ハムレット』を引き合いに出しているのだ。そして、母親が始めた『ハムレット』ごっこに付き合うトレープレフもまた、母親が自分の気持を分かっている、ということを理解するだろう。実は、アルカージナは、ガートルードに比べて遥かに敏感であり、聡明である。アルカージナの感性が豊であることは、トレープレフによっても語られている。
まぎれもなく才能があって、頭もよくて、小説を読んで泣くことも
できる。ネクラーソフの詩を全部暗誦することだってできる。病人
の世話をさせたらまさに天使だ。
(『かもめ』十四頁)
トレープレフは、母親の感受性を評価している。彼は、感性の鋭い母親の自作への評価を恐れてさえいる。アルカージナは決して鈍感な母親ではない。しかし、だからこそ余計に厄介であると言うこともできる。アルカージナは、「おまえは私の目を心の奥底に向けさせる、そしてそこに見えるのは、どす黒いしみ、洗っても落ちはしまい」というハムレットの台詞を、ユーモアを持って言っている。実にしたたかな母親、ずぶとい神経の持ち主である。彼女が本当に自分の心にどす黒いしみがあると思っているのかといえば、露にも思っていない。全くの冗談として言っている。むしろ、トレープレフがそう思っているのだろうと悟って、自らガートルードを演じてやっている訳だ。それに対してトレープレフの「ああ、落ちるものですか。脂ぎった汗くさい寝床の中で、欲情にただれた日々を送っている以上。抱いて抱かれるその相手は汚らわしい豚……」という台詞の返答には、彼の本音が込められているように思える。アルカージナの方が、トレープレフよりも一枚も二枚も上手である。アルカージナは、ガートルードより遥かにトレープレフの気持を理解しているといえる。しかし、それだからこそ、ガートルードより質の悪い母親であると言うこともできる。アルカージナは、息子の気持を分かっていると思いこんでいたが、しかし、息子の絶望が、自らを死に追いやるほど強烈なものだとは思っていない。だから、息子に思っていることをそのまま言ってしまう。女優でまわりからちやほやされているから、人に気を使い慣れていないということもあるかもしれないが、息子のことを想っているのに、きつく当たってしまう。以下に挙げる引用は、先に挙げた、トレープレフが、頭に包帯を巻いてもらいながら、母親の愛人トリゴーリンのことを批判する引用に続く場面である。息子の愛人への批判に対して母親が答える。
アルカージナ じゃあおまえはなんなのよ? このデカダン!
トレープレフ さっさとあんたの大事な劇場にもどってくだらない三
流芝居に出るがいい!
アルカージナ そんな芝居に出たことなんて一度もないわよ! 私の
ことに口出ししないで! くだらないコント一つ書けないくせに!
この小売り商人! そう——キエフの商人! 居候!
トレープレフ けちんぼ!
アルカージナ ボロッかす!
トレープレフは腰をおろし、静かに泣く。
人間の屑! (興奮して少し歩きまわる)泣かないで。泣くことは
ないよ……。(泣く)泣いちゃだめ……。(彼の額、頬、頭にキスす
る)ね、おまえ、許して……いけない母さんを。ふしあわせな母さ
んを。
トレープレフ これだけはわかって! ぼくはなにもかもなくしてし
まった。あの人はぼくを愛していない、ぼくはもうなにも書けない
……ぼくの希望はみんなこわれた……。
アルカージナ そんなに気を落とさないで……なにもかもうまくいく
わ。あの人を連れて行くから——そしたらあの子もまたおまえを愛
してくれるでしょう。(彼の涙をふいてやる)さ、もうおしまい。こ
れで仲なおりよ。
トレープレフ (母の両手にキスする)うん、ママ。
(『かもめ』一〇〇〜一〇二頁)
アルカージナは、つい一時の感情に流されて息子にきつく当たるが、息子が泣き始めると、情愛のこもった態度をとるようになる。そして、自分はトリゴーリンを連れて立ち去るから、再びニーナの愛を取り戻せるようになるだろうと言う。アルカージナは、トレープレフの恋人のニーナが、アルカージナの愛人トリゴーリンに好意を抱いているのを感じ取っており、トレープレフがそのことを気にしているということまで気付いている。なんという感受性の豊かさだろう。それゆえにこの物語の結末は悲壮なものとなる。ことによると、アルカージナがあまりに感受性が豊かであるがゆえに、息子をあまやかしてしまったのかもしれない。
このように見てくると、アルカージナの性格描写の方がガートルードより遥かに生々しくて多彩であるように思える。それに比べると、ガートルードの性格描写が、平面的で、奥行きのないものに感じられてしまうことは否めない。2居室の場においても、ガートルードはハムレットの非難に対して、ただの一言も自己を弁護しようとしない。ガートルードは終始受け身の姿勢で、ハムレットの非難を受け入れるのである。『ハムレット』作中全体においてもガートルードは一貫して受け身である。自己を主張することがない。ハムレットに、いつまでも亡き父を憐んでいるのをやめるように言うのも、ウィッテンベルク大学に行かずデンマークに滞在するよう頼むのも、クローディアスの意向に追従して言っているように読むこともできる。
『ハムレット』の第四幕第七場に、ガートルードが、川で溺れるオフィーリアの情景を語る場面がある。この場面は、何故ガートルードは溺れているオフィーリアを見ていながら、助けようとしなかったのかと、議論のかまびすしい箇所であるが、あの語りを成立させているのは、ガートルードの受動性だ。実際に彼女がオフィーリアが溺れて行くところを見ていたとは思わないが、彼女の語りに観客が違和感を抱かずに済むのは、ガートルードの受動的な性格に負うところが大きい。アルカージナが同じように語るところを想像できるだろうか? 否、できない。アルカージナが同じ台詞を吐くとき、観客はそれこそ何故助けなかったのかと、違和感を抱くことになるだろう。アルカージナは、その台詞を語るには、あまりに地に足がつきすぎている。その台詞を語るには、彼女の性格描写は現実的すぎる。シェイクスピアが描いたガートルードは、あまり現実的に描くと成立しなくなるタイプのキャラクターなのだ。リアリズムと非リアリズム。この対照がチェーホフとシェイクスピアを比較した時に見えてくる最大の特色といえるだろう。
Chapter 2 客観と主観
そして、そのリアリズムと非リアリズムという区別は、客観と主観という区別に置き換えることができると思う。チェーホフは、客観的に、主観的に行動する人物たちを描き、シェイクスピアは、主観的に、客観的に行動する人物たちを描いている。どういうことか詳しく説明したい。まず、チェーホフは、今見てきたように現実主義的なスタイルで執筆をする。アルカージナがあたかもそこに実在しているかのように描く。その現実らしさは、チェーホフによる冷静な観察眼によってもたらされる。チェーホフは、人間の対話の複雑さをそのまま舞台上に再現しようとする。登場人物たちは、時に、言い淀んだり、言いやめたり、言い換えたりしながら自分の言葉を語っていく。そのためチェーホフの登場人物は、主観的に行動しているように見える。チェーホフは、客観的な観察に基づいて、主観的に行動しているように見える人物を作り出しているのだ。それに対して、シェイクスピアは、もう少し観客に分かりやすいように様式化する。ブランク・ヴァースを使用して、その人物の身分を表わしたり、会話の量を調整して、重要な人物には長い台詞を与え、その人物に観客の意識を集中させるように工夫する。そしてそのことは時に、登場人物の現実らしさを害うことにもなる。先のガートルードの語りがよい例である。あの場面でのガートルードは、本来の役を離れて、観客へオフィーリアの最後を伝えるための語り手として機能している。シェイクスピアは、主観的に人工の手も加えつつ、客観的に行動する人物たちを描いている。つまり、シェイクスピアの作品に出て来る登場人物たちは、皆、役者なのだ。シェイクスピア作品の登場人物たちは、観客に見られていることを意識して行動している。
俳優にとっては、チェーホフの自然主義的な芝居の方が、必然的に負担が大きくなる。シェイクスピア劇では、私は、悲しい、といえばそれは本当に悲しいことなのだ。しかし、チェーホフの芝居ではそうはいかない。チェーホフ劇の登場人物が、私は悲しい、と言っても、それが本当に悲しいという保証はないのだ。彼はもしかしたら、実はとても嬉しいのかもしれないし、あるいは楽しそうに振る舞っていても、本当に楽しいのかどうかわからない。私たちの日常生活と同じように。シェイクスピアの登場人物の感情の動きは、チェーホフに比べれば直線的であるといえる。チェーホフの場合は、感情が、さまよい、立ち止まり、たゆたう。チェーホフ劇の登場人物たちの台詞は、本当の感情を覆い隠したり遠回しに表現したりしている。役者たちは、表面的に台本にある台詞を頼りに、その人物が本当はどう思っているのかを読み取らなくてはならない。そして舞台上でその感情を辿り、追体験しなくてはならないのだ。私は悲しいと言って、大声で泣き叫べば、知らず感情移入して、涙を流せる。それはそれほど大変な作業ではない。しかし、楽しい風を装って、心で泣くというのは至難のわざである。チェーホフの方が、このように二重三重に屈折している。それは、私たちの日常の反映でもある。私たちもそのように屈折して生きているのである。
しかし、チェーホフが書いたその後の作品に比べれば、『かもめ』はまだシェイクスピアのような従来的な劇作に近い。『かもめ』の中には、拳銃が発射されるという非日常的な場面が二度もあり、主人公の死が描かれ、またリアリズム演劇には馴染まない、伝統的な演劇手法である独白や傍白も、何箇所かで使われている。独白や傍白と言うのは、それぞれのキャラクターが各々の主観的な考えを述べるものだ。しかし、日常に生きる私たちは独白や傍白を語ることはない。独白や傍白と言うのは、その人物が自分の考えを主観的に語っているようでありながら、実は、極めて客観的に自分を認識しながら語る、自意識の強い語りなのだ。
『かもめ』に出て来る傍白を見てみよう。アルカージナが、トリゴーリンが自分のもとを去るのを思い留まらせようとする場面である。アルカージナが言う。
あなたの価値を理解できるのは私だけ、あなたに真実を語る
のも私だけなのよ、私の大事な、すばらしい人……いっしょに発つ
わね? ね? 私を棄てたりしないわね……?
トリゴーリン おれには自分の意志というものがない……一度だっ
て自分の意志を通したことがない……(中略)一瞬たりともきみの
目の届かないところに行かせるんじゃないよ。
アルカージナ (ひとりごと)これでこの人も私のもの。(なにご
ともなかったかのように、けろっとして)残りたいなら残ってもい
いのよ。
(『かもめ』一〇七〜一〇八頁)
この傍白は、彼女が心の内で思っていることであるわけだが、チェーホフのような自然主義的な作風の中では特に、内面を自ら語るという行為は、観客にアルカージナの自意識を強く感じさせる結果をもたらす。それは、女優であるアルカージナというキャラクターには相応しいかもしれない。しかし、役者が傍白を語った段階で、観客は自分達が芝居を見ているのだという現実に引き戻されてしまう。このような、明らかに独り言とは言えない独白や傍白は、その芝居の虚構性を強調する結果となり、チェーホフのような自然主義的な作風の中では明らかに浮く。そのため、チェーホフは『かもめ』以降の作品では独白や傍白をほとんど使用しなくなるである。
チェーホフはこの作品以降、より写実主義的、現実主義的な方向性を深めていく。シェイクスピアは、ハムレットに「芝居というものは、昔もいまも、いわば自然にたいして鏡をかかげ、善はその美点を、悪はその愚かさを示し、時代の様相をあるがままにくっきりとうつし出すことを目指しているのだ」と言わせているが、(『ハムレット』第三幕第二場十九〜二三行)チェーホフの執筆方法は、まさに「自然に鏡をかかげる」ような方法であり、ハムレットが語る理想的な演劇手法に当てはまるのではないか。
一方シェイクスピアは、ハムレットにそのように語らせておきながら、後期ロマンス劇に至って、それとは反対の方向へ向かっていった。否、シェイクスピアの自然観が変化した、と言った方が正しいのかもしれない。シェイクスピアは『冬物語』を執筆するにあたって、「時」のコーラスや、熊を舞台上に登場させたり、彫像が動き出すといった自然主義的な演劇から遠ざからざるをえないような趣向を凝らしたが、恐らくシェイクスピアは、作為を持って、作為的な改変を行っていた。シェイクスピアが自らそのことを表明しているととれる台詞がある。
ポリクシニーズ 娘さん、どういうわけで
あの花をさげすむのだな?
パーディタ あの赤と白とのまだら模様は、
偉大な造化の自然に人工の手が加わってできたもの、
と聞いておりますので。
ポリクシニーズ それはそうかもしれぬ。だが、
なんらかの手を加えて自然がよりよくなるとすれば、
その手を生み出すのも自然なのだ。したがって、
自然にたいして加えたとあなたの言うその人工の手も、
実は自然の生み出す手に支配されているのだ。いいかな、
野育ちの幹に育ちのいい若枝を嫁入らせることによって、
卑しい木に高貴な子を宿らせることがあるだろう、
これは自然のたりないところを補う、と言うより、
すっかり変えてしまう人工の手だ、しかし実は
その人工の手そのものが自然なのだ。
(『冬物語』第四幕第四場八五〜九七行)
シェイクスピアはこの時点では、自然に人工の手を加えることも、大きな目で見れば自然の一部であると考えていたかのようである。ここに僕は、シェイクスピアの達観した演劇/芸術観を見る。彼の中では、もはや自然と人工は相対するものではなくなっていたのだろう。
これまで見てきたように、シェイクスピアの『ハムレット』と、チェーホフの『かもめ』は多くの接点を持っているが、両者の指向する方向には大きな違いがあった。シェイクスピアとチェーホフは、それぞれ『ハムレット』と『かもめ』を執筆した後、それぞれの劇作手法を突き詰めていき、全く逆の方向へと進んでいったのである。『ハムレット』と『かもめ』はそのような、対極的な志向を持った二人の作家の創作の軌跡が、一瞬だけ交わった交点となっている作品と捉えることができるだろう。
Conclusion
本論では、ガートルードとアルカージナを比較しつつ、シェイクスピアとチェーホフの作家性の違いについて論じた。
Chapter 1では、それぞれの戯曲中、唯一母親と息子が語り合う場面である、『ハムレット』の居室の場と『かもめ』の第三幕に焦点を合わせた。そして二人を比較していく内に、一見子供のことなんか何も考えていないように見えたアルカージナが、思いの外、トレープレフのことを思い遣っていることが明らかになった。また、アルカージナに対してガートルードはあまりに受動的であるが、その受動性は、ガートルードが溺れるオフィーリアについて語る場面では有効に働いていることについて論じた。また、ガートルードはアルカージナのように現実的に描くと成立しなくなる可能性があることについて言及した。そして、チェーホフとシェイクスピアの劇作術はリアリズムと非リアリズムという対照的な特色に負っていると結論づけた。
Chapter 2では、リアリズムと非リアリズムという観点からさらに前進して、作者と作中人物における主観性と客観性について議論を展開した。チェーホフは、客観的に、主観的に行動する登場人物を描き、シェイクスピアは、主観的に、客観的に行動する登場人物を描いているのである。そしてそのキャラクターの特質の違いが、実際に俳優が演じる時にどのような違いとなって表れるのか考察した。そしてシェイクスピアとチェーホフがそれぞれ『ハムレット』と『かもめ』を書き上げた後、各々、全く逆の方向へと進んでいき、自分の劇作手法を突き詰めていったと論じた。
自分の専門はイギリス演劇ということもあり、英米以外の国の劇作品を丁寧に読み込んだことがなかったが、今回レポートを書くにあたって『かもめ』を何度もじっくりと読んでみて、新鮮な感動があった。そして夢中になってメモをとり続けるうち、いつしかそのメモが膨大な量になり、まとめるのに苦労した。実は、もう一本レポートが書けるほどの材料があり、本レポートのChapter 3としてそれを展開したかったのだが、今回そこまで行くことができずに非常に残念だ。いつか、そのメモを活用して、チェーホフとシェイクスピアで悲劇/喜劇論を書きたい。
今回、シェイクスピアの比較対象としてチェーホフを選んで正解だった。シェイクスピアに関して、いくつかいままで思いもよらなかったようなアイデアを思いついた。ガートルードの溺れゆくオフィーリアについての語りを成立させるためには、現実主義的な人物造形が不適切であるという点や、シェイクスピアは主観的に、客観的に行動する人物を描いているという点などがそれだ。それ以外の思わぬ副作用としては、今回アルカージナとガートルードを比較したことで、ガートルードがなんとも人間味を欠いた人物に見えてきてしまったことだ。これならハムレットが憤るのも無理はない、そう実感してしまった。しかし、そう結論を下すのはまだ早い。何故なら、ジョン・アップダイクの小説を一年以上前に読んだ時に、人間的で魅力的なガートルード像に触れた気がしたからだ。ガートルードに関しては、いずれ再び考察したいと思う。
引用文献
佐々木 基一 『私のチェーホフ』 東京: 講談社 1990.
ウィリアム・シェイクスピア 『ハムレット』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1983.
ウィリアム・シェイクスピア 『冬物語』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1983.
アントン・チェーホフ 『かもめ』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1998.
※『ハムレット』と『冬物語』の行数は、それぞれArden版とOxford版によっている。
参考文献
ジョン・アップダイク 『ガートルードとクローディアス』 訳者 河合 祥一郎
東京: 白水社 2002.
アントン・チェーホフ 『桜の園』 訳者 小野 理子
東京: 岩波書店 1998.
アントン・チェーホフ 『三人姉妹』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1999.
アントン・チェーホフ 『ワーニャ伯父さん』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1999.
G・J・ワトソン 『演劇概論』 訳者 佐久間 康夫
東京: 北星堂書店 1990.
Notes
1 『かもめ』の第三幕に、医師のメドヴェジェンコが、「こんな謎々がありましたね—-朝は四本足、昼は二本足、夕方は三本足……」と言う場面がある。(『かもめ』九五頁)これは、ソポクレスの『オイディプス王』でスフィンクスがオイディプスに出す謎かけである。チェーホフはフロイトのエディプス・コンプレックスを踏まえてこの台詞を書いたのだろうか? しかし、フロイトがエディプス・コンプレックスについて論じた『夢判断』の出版は一九〇〇年であり、チェーホフが『かもめ』を執筆したのは一八九五年である。単なる偶然に過ぎないのか、それとも時代の最先端を行く精神分析に言及したのだろうか。医師であったチェーホフには、精神分析に興味を抱いていた可能性も十分あり得ると思う。
2 ジョン・アップダイクは、『ガートルードとクローディアス』という小説を書き、ガートルードが、犯罪のことなどなにも知らないまま、従順に、懸命に、目の前にいる人を愛する女性であるという解釈を豊かに肉付けしてみせている。


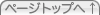
Comments & Trackbacks
Trackback URL http://shakeweb.co.uk/spear/thesis/28.html/trackback