『冬物語』の「時」の勝利
『冬物語』の「時」の勝利
—ロバート・グリーン『パンドスト』との比較—
米田拓男
Introduction
シェイクスピアの『冬物語』は、シェイクスピアと同時代の作家ロバート・グリーン (Robert Greene, 1560?-1592) の小説『パンドスト』 (Pandosto, 1588) を下敷きにして書かれている。シェイクスピアが用いたのは、言葉遣いなどの共通点からみて、一五八八年版、あるいは一五九二年版のうちいずれかだろうと考えられている。(『冬物語』 217)『冬物語』には、プロットのみならず、グリーンの表現をそのまま使っている箇所もあり、グリーンの『パンドスト』に負うところは大きい。
本レポートでは、『冬物語』と『パンドスト』の比較を行う。材源比較をしてみたいと思ったそもそものきっかけは、この両作品の副題が、共に『時の勝利』 (The Triumph of Time) であることによる。私は以前から、シェイクスピアが、『パンドスト』を元に戯曲を執筆するにあたって、結末を大きく変えたことを知っていた。シェイクスピアのリオンティーズに相当する人物は、『パンドスト』では自ら命を絶ち、悲劇的な末路を辿ることになる。一方、シェイクスピアのリオンティーズは、自分が死に追いやったと信じていたハーマイオニが生きて目の前に蘇り、過去の罪を許される。何故、副題を同じくしながらこうも結末が変わるのか。その理由を知りたいと思った。
二作品には舞台となっているシチリアとボヘミアが入れ替わっているなど、[i]多くの相違点があるが、以下のSection で、具体的な例を挙げていくつかの相違点について論じたい。そして、二作品を比較することにより、シェイクスピアの『冬物語』の執筆の狙いはどこにあるのか、二作品に共通する主要テーマである「時」の性質の違いはどのようなものなのかを明確にすることを目的とする。
Section1 リオンティーズの嫉妬
シェイクスピアの『冬物語』のリオンティーズは、物語の冒頭で、全く突然に激しい嫉妬にかられるように見える。Sir Arthur Quiller-Couch氏は、「これは常に、当然のように、批評家たちの眉をひそめさせてきた」と書いている。[ii]以下は、リオンティーズが初めてその嫉妬心を表明する独白である。
リオンティーズ (傍白)あれの熱心さは
度がすぎる。友情の交換も度がすぎると情欲の交換となる。
この胸騒ぎはなんだ、心臓が踊り騒いでいるが、それは
喜びのためではない、喜びではない。あの歓待ぶりはどうだ、
無邪気な顔をよそおうのも、無遠慮にふるまうのも、
やさしい心からの、ゆたかな胸のうちからのものであって、
女主人にふさわしいことかもしれぬ、それは認めよう。
だが、ほら、あのように手のひらにふれ、指をつねるのは、
そして鏡にでもむかうように作り笑いを浮かべ、獲物を追う
角笛のような溜息をつくのは、ああ、あのような歓待ぶりは
気に入らぬ、寝とられ亭主のしるしである角をはやすのは
まっぴらだ。(『冬物語』 1.2.107-118)
この独白の前に描かれている、ハーマイオニがポリクシニーズに滞在を延期してもらうように頼む場面だけをリオンティーズの嫉妬の根拠とすると、リオンティーズの嫉妬は確かにあまりに唐突なものに思える。それに対して、『パンドスト』では、ハーマイオニ(『パンドスト』作中ではベラリア)とポリクシニーズ(同じくイギスツス)の仲がことさらに親密であることが説明されている。
ベラリア[ハーマイオニ]は、イギスツス[ポリクシニーズ]のなかにもろもろのすぐれた性質に飾られた王者らしい豊かな精神を認め、イギスツスは、彼女のなかに淑やかで親切な性質を見出したので、ふたりの愛情はいつとはなく結ばれ、お互いはなれていることができないほどになった。で、パンドストが緊急の国務にたずさわっていて、イギスツスと席を同じくすることができないときには、ベラリアが彼といっしょに庭園を散歩したり、またそこで、ふたりだけの雅びたたのしいもてないごとのうちに時を過しては、ふたりとも満足するのであった。両者のあいだにこういう習慣がつづいているとき、パンドストの胸には、ある暗い感情が入りこんで、さまざまな疑念に彼を駆り立てたのである。(『パンドスト』 25-6)
この描写を見ると、『パンドスト』でのリオンティーズの嫉妬は、十分根拠があるように思える。シェイクスピアは、『パンドスト』に見られる、このようなリオンティーズが疑念をつのらせていく過程をばっさりと切り捨てた。その理由として、Hallett Smith氏は、「彼(シェイクスピア)は、『オセロー』で嫉妬が心に芽生える過程を描き切ったので、他の芝居でそれを芝居にする必要がなかったのだ」と書いている。[iii]『オセロー』では、嫉妬が人の心にいかに形成されていくかということを描くのに、まるまる一本の戯曲を必要とした。レオンティーズの嫉妬が物語の発端に過ぎない『冬物語』で、嫉妬をつのらせていく過程を描いたとしても、『オセロー』には及ぶまい。それでカットしたのだ。シェイクスピアの関心は他のところにあった。
Nevill Coghill氏は、「レオンティーズは、シェイクスピアが参照している材源の話のように、長い期間に渡り嫉妬して」いたのであって、ここで突然嫉妬心を燃え上がらせたのではないと書く。[iv]私もNevill氏の意見に賛同したい。リオンティーズは、物語が始まる前からポリクシニーズとハーマイオニの関係を怪しんでいたのだ。私は、リオンティーズは二人の関係を確かめたくて、ポリクシニーズの滞在を引き延ばそうとしているのだと思う。だからハーマイオニに故意にポリクシニーズに滞在を引き延ばしてもらうように頼むのだ。
しかし、残念なことに、先に引用したリオンティーズの独白をそのような文脈で読むことはできない。リオンティーズは独白の中で「この胸騒ぎはなんだ」と言う。まるで、今初めて二人の仲を怪しみ始めたような口ぶりなのだ。この齟齬をどのように理解したらよいのだろう。私はここで、『ハムレット』の第三独白を引き合いに出して考えたい。第二幕第二場でハムレットは旅回りの役者たちと話を交わす。そして別れ際に、明日の晩に『ゴンザーゴー殺し』を、台詞を追加して上演してもらいたい旨を伝える。ハムレットは、その直後に第三独白を語る。その独白の中で、ハムレットは、芝居をうってクローディアスが本当に父を殺したのか確認しようと、今まさに思いついたかのように語る。
そうだ、よく聞く話だが、罪を犯したものが
芝居を見ているうちに、舞台の真実に魂をうたれ、
たちまち悪事いっさいを白状することがあるという。
(中略)
あの役者たちには、
叔父の前で、父上の殺害に似た話を
演じさせよう。(『ハムレット』 2.2.584-592)
これを一体どう考えたら良いのか。アーデン版の編者Harold Jenkins氏は、それだけでは説明がつかないとしながらも、Dover Wilson氏の、ハムレットの独白は、彼の心の中にすでに感じたことを表現しているのだとする理論を紹介している。(Jenkins 273)高橋康也氏と河合祥一郎氏による大修館シェイクスピア双書の註では、「役者を見たとき閃いた考えがここでようやく表現されたと解釈すべきであろう。独白の占める想像的な時空間は、リアリズムあるいは古典主義的な時計の針の動きから自由である」と記されている。(高橋 209)
リオンティーズの独白も、この『ハムレット』の第三独白と同じように考えれば良いのではないか。リオンティーズの独白は、彼がリアルタイムで考えていることだけを述べているものではなく、ポリクシニーズが滞在していた九ヶ月の月日の間に思っていたことをも内在しているのだ。シェイクスピアは観客にリオンティーズの心情の変化を理解してもらうために、ここで一度整理して独白によって語らせているのだ。
Section2 時間の省略
シェイクスピアが、リオンティーズが嫉妬心をつのらせていく過程を切り捨てたもう一つの理由として、時間の短縮ということが挙げられる。シェイクスピアは材源の物語を芝居にするにあたって、大胆といえるほどの時間の圧縮を行うことがよくある。『ロミオとジュリエット』の場合は、材源であるアーサー・ブルックの長篇詩で九ヶ月に渡る物語を四日間に圧縮した。『オセロー』では、オセローとデズデモーナの長期に渡る結婚生活を一昼夜半に凝縮した。『冬物語』でも、リオンティーズの嫉妬の過程以外に、多くの時間の省略が行われている。
シェイクスピアの『冬物語』では、ハーマイオニは登場した時から妊娠している。
侍女1 ねえ、王子様、
お母様のおなかは日一日と丸くおなりでしょう、
私たちが新しい王子様にお仕えすることになるのも
もうすぐです。(『冬物語』 2.1.15-16)
それに対して、『パンドスト』ではハーマイオニ(ベラリア)は、リオンティーズに貞節を疑われ投獄された後、獄中で妊娠していることに気付く。そして獄中で出産するのだ。そのため原作では、獄中で数カ月経過しているはずである。ポリクシニーズ(イギスツス)が何ヶ月滞在していたのかは判らないが、九ヶ月である必要は無い。『冬物語』では、ポリクシニーズはシチリアに九ヶ月滞在していることになっているが、私には、一国の王が親睦のために滞在する期間としてはいささか長すぎるように感じられる。シェイクスピアの作意が感じられる部分である。
シェイクスピアは、パーディタの成長の過程も切り捨てた。『パンドスト』では、幼少のパーディタ(フォーニア)が、七歳、十歳と成長していく過程が描かれている。
夫婦ともその子が大好きになったが、子どもは年を重ねるにつれていよいよ美しくなっていった。羊飼いは毎晩帰宅すると、その子を膝にのせ、歌を聞かせたり、踊らせたり、おしゃべりをしたりで、子どもも物を言うようになり、彼を父(とう)、彼女を母(まあ)、と呼びはじめた。(『パンドスト』 56)
それに対して、シェイクスピアは擬人化した語り手としての「時」を登場させ、十六年の時を一挙に経過させてしまう。
また、『冬物語』のパーディタとフロリゼルは、登場した時から相思相愛の仲である。
フロリゼル このような草花を身につけていると、きみのからだは
どこもかしこも生き生きと見える。羊飼いの娘ではない、
四月のはじめに姿を見せる花の女神フローラだ、きみは。
この毛刈り祭りというのはかわいらしい神々の饗宴のようだ、
そしてきみはその女王なのだ。
パーディタ まあ、王子様ったら。(『冬物語』 4.4.1-5)
しかし、『パンドスト』では、二人が初めて出逢う場面が描かれている。パーディタ(フォーニア)を初めて見たフロリゼル(ドラスツス)は、心ではパーディタの美しさに惹かれながらも、その気持を自ら否定しようとする。
非の打ちようのないフォーニアが、彼の愛情をはげしく燃え立たせたために、気持も大きくかわり、感情も改まったように感じて、こんな変化を生んだ恋を呪い、こんな選択をしたがるわが心の卑しさを咎めるのであった。が、こうした思いも、とるに足りない感情にすぎないものであって、自分の好き勝手に抛り出せるものだと考え、自分を魅惑した魔女を避けようと、彼は乗馬に拍車を当てると、この美しい羊飼い女に別れを告げた。(『パンドスト』 63)
シェイクスピアはこのような、十分劇的な場面となりうる箇所をあっさりと棄てている。
これらの改変からは、「時」のコーラスの導入がその最もたる例であるが、シェイクスピアの作意が感じられる。シェイクスピアは、「人間なんて、十六から二十三までの年がなきゃあいいんだ」(3.3.58 -9)と言って登場する羊飼いのように、気に入らない場面を片っ端から切り落としてしまったのだろうか。否。これらの改変により、余分なものが削ぎ落とされている分、リオンティーズの嫉妬や、フロリゼルとパーディタの愛といったものが、純化されていると考えることができるのではないか。シェイクスピアは、作為を持って、作為的な改変を行ったのだ。シェイクスピアが自らそのことを表明しているととれる台詞がある。
ポリクシニーズ 娘さん、どういうわけで
あの花をさげすむのだな?
パーディタ あの赤と白とのまだら模様は、
偉大な造化の自然に人工の手が加わってできたもの、
と聞いておりますので。
ポリクシニーズ それはそうかもしれぬ。だが、
なんらかの手を加えて自然がよりよくなるとすれば、
その手を生み出すのも自然なのだ。したがって、
自然にたいして加えたとあなたの言うその人工の手も、
実は自然の生み出す手に支配されているのだ。いいかな、
野育ちの幹に育ちのいい若枝を嫁入らせることによって、
卑しい木に高貴な子を宿らせることがあるだろう、
これは自然のたりないところを補う、と言うより、
すっかり変えてしまう人工の手だ、しかし実は
その人工の手そのものが自然なのだ。(『冬物語』 4.4.85-97)
かつてシェイクスピアは、ハムレットに「芝居というものは、昔もいまも、いわば自然にたいして鏡をかかげ、善はその美点を、悪はその愚かさを示し、時代の様相をあるがままにくっきりとうつし出すことを目指しているのだ」と言わせた。(『ハムレット』 3.2.19-23)シェイクスピアは今では、自然に人工の手を加えることも、大きな目で見れば自然の一部であると考えているかのようである。[v]ここに私は、シェイクスピアの達観した演劇/芸術観を見る。彼の中では、もはや自然と人工は相対するものではなくなっていたのだろう。
Section3 彫像の場
シェイクスピアによる『パンドスト』からの改変の最大のもの、それは物語の結末の付け方にある。『パンドスト』も『冬物語』と同じようにパーディタ(フォーニア)とフロリゼル(ドラスツス)の結婚によって幕を閉じるが、リオンティーズ(パンドスト)が自殺することによって苦い後味を残す。
イギスツス[ポリクシニーズ]はこのめでたい出来ごとを聞くと、息子[フロリゼル]の幸運を大いによろこび、ふたりの若い恋人たちには絶え間ないよろこびであったが、時を移さず結婚の賀宴を張ったのであった。終わるやいなや、パンドスト[リオンティーズ]は、彼が最初に朋友イギスツスを裏切った次第、彼の嫉妬がベラリア [ハーマイオニ]の死因となった経緯、また自然の掟にそむいて彼がわが娘に欲情を抱いた経過を思い出して絶対絶命の想いに駆られ、鬱病におち入り、この喜劇を悲劇の大団円で締めくくろうと、われとわが身を滅ぼしたのであった。(『パンドスト』 105)
それに対して『冬物語』では、リオンティーズの目の前で自分が死に追いやったと思っていたハーマイオニが彫像から蘇る。
ロバート・グリーンの『パンドスト』は、当時、大変人気のあった作品だったという。(『冬物語』 217)ということは、『パンドスト』と同じ結末を予測しながら観ていた観客が沢山いたということを意味する。そうであるならば、シェイクスピアによるエンディングの改変は、大きな衝撃だったはずだ。Nevill Coghill氏は、彫像の場で観客にハーマイオニの死を信じさせるために、シェイクスピアがそのステージ・クラフトに独自の工夫を施したことを論じているが(Coghill 39-40)、『パンドスト』の話が一般に流布していた当時の観客にとっては、それはより有効に働いたことだろう。
現実的に考えれば、ポーライナがハーマイオニを十六年間も匿っておき、その間、葬儀も済ませることはちょっとあり得そうにない。最後にハーマイオニが復活する場面が、それまでの展開から一見つながらないように思えるのは、シェイクスピアが原作の最後を改変していることに起因しているのではないか。だが、現実らしさを犠牲にし、観客に多少の違和感を感じさせてしまったとしても、シェイクスピアは最後をハッピー・エンドに書き換えたかったのだ。
思えば、シェイクスピアによる『パンドスト』からの改変箇所には明るく、喜劇的で、ポジティヴな要素が多い。威勢のいいおばさんといった風情のポーライナや、劇に喜劇的な要素を加味しているオートリカス、羊飼いの息子の道化は、シェイクスピアの創作である。シェイクスピアは『ロミオとジュリエット』を書く際にも、乳母とマキューシオという喜劇的な人物を大きく書き換えている。さらには、熊や時を舞台上に登場させるといった趣向も、前半の悲劇的な展開から喜劇へ転換する際の、蝶番の役割を担っていると考えることができる。原作へのこれらポジティヴな要素の追加は、物語の印象を大きく変えることになった。その際たるものがエンディングの変更である。しかし、エンディングの変更は、物語の印象を大きく変えたというにとどまらない。『パンドスト』も『冬物語』も、副題は共に『時の勝利』である。エンディングの変更は、この「時の勝利」の意味をも変えることになった。
『パンドスト』における「時の勝利」とは、パンドストに対する「時の勝利」を意味する。つまり、悪いものは「時」によって、結局裁かれる、ということ。『パンドスト』の物語を読み終えた読者は、因果応報、というありがたい教訓を頂戴して本を閉じることになる。しかし、シェイクスピアの「時の勝利」に、そのような教訓めいたニュアンスはない。では、シェイクスピアの『冬物語』における「時の勝利」とは、どのようなものか。シェイクスピアは、自分の妻や子供たちを死に追いやろうとしたリオンティーズに対して、許しを与える。「時」が人の罪を許す。『冬物語』の「時」は、そのようなものとして描かれている。人の弱さをも受け入れる「時」。この「時」寛容さは、前のSectionで述べた、人工をも受け入れる自然、という自然の寛容さに符合しているように思える。
観客は、いつの時代も、娯楽に教訓など求めない。一体、誰が、説教を聞きに劇場に足を運んで金を払うだろう。説教を聞きたいのなら教会にでも行った方がましである。シェイクスピアはそのことを良く知っていた。『パンドスト』の教訓めいた物語から許しの物語へ。シェイクスピアは『ロミオとジュリエット』でも、材源の長篇詩が持っていた説教臭さを見事に抜き取り、ロミオとジュリエットの悲劇を、情熱的な恋の物語として昇華させた。
『冬物語』の副題としての『時の勝利』とは、なんとも心憎いタイトルだ。『冬物語』の「時」は、悪をも許す。そしてその寛容さにおいて「時」は勝利しているのだ。『パンドスト』よりも懐の大きい「時」。より寛容な「時」。『冬物語』の「時」は、『パンドスト』の「時」に勝利している。
引用文献
Adelman, Janet. ‘Masculine Authority and the Maternal Body in The Winter’s Tale.’
Coghill, Nevil. ‘Six Points of Stage-Craft in the Winter’s Tale.’
ロバート・グリーン 『パンドスト王・いかさま案内他』 訳者 多田 幸蔵
東京: 北星堂書店 1972.
Shakespeare, William. The Arden Shakespeare Hamlet. Ed. Harold Jenkins. California: Methuen And Co. Ltd, 1982.
ウィリアム・シェイクスピア 『ハムレット』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1983.
ウィリアム・シェイクスピア 『ハムレット』 編者 高橋康成・河合祥一郎
東京: 大修館書店 2001.
ウィリアム・シェイクスピア 『冬物語』 訳者 小田島 雄志
東京: 白水社 1983.
Smith, Hallett. Shakespeare’s Romances. California: The Huntington Library, 1972.
※『ハムレット』と『冬物語』の行数は、それぞれArden版とOxford版によっている。
参考文献
Bloom, Harold. ed. Modern Critical Interpretations The Winter’s Tale. New York: Chelsea House, 1987.
Sanders, Wilbur. Harvester New Critical Introductions to Shakespeare The Winter’s Tale. Sussex: The Harvester Press Limited, 1987.
Shakespeare, William. The Oxford Shakespeare The Winter’s Tale. Ed. Stephen Orgel. New York: Oxford University Press, 1996.
Notes
[i] ここでしばしば、ボヘミアには海岸が無いということが問題となる。蒲池美鶴氏は、白水Uブックスの解説にシェイクスピアは「原作のボヘミアとシチリアをわざわざ入れ替え、「ボヘミアの海岸」などという実際にはありえない場所をつくり出した」(『冬物語』 217)と、書いているが、原作中にもボヘミアの海岸はしっかり登場する。
市の裏門からこっそり、すばやく出て行ったので、誰にも疑われず海岸についたからである。そこでは、さかんにののしりながらボヘミヤに別れを告げて上船した。(『パンドスト』 34)
船員たちは、ボヘミヤの海岸を発見すると、かくも恐ろしい嵐から逃れおおせたよろこびに、祝砲をうち出すのであった。(『パンドスト』 90)
港が、パンドストの宮廷のあるボヘミアの首都にあるものだ、と船員に聞くと、ドラスツスは悲しくなりはじめた。(『パンドスト』 90)
[ii] ‘This has always and rightly offended the critics.’ (Coghill 31)
[iii] ‘Shakespeare changed all this, because he had fully portrayed the growth of jealousy in Othello and had no need to dramatize it in another play.’ (Smith 102)
[iv] ‘It is clear that Leontes, as in the source-story which Shakespeare was following, has long since been jealous and is angling now (as he admits later) with his sardonic amphibologies, to catch Polixenes in the trap of invitation to prolong his stay, before he can escape to Bohemia and be safe.’ (Coghill 33)
[v] フェミニズム批評のJanet Adelman女史は、論文 ‘Masculine Authority and the Maternal Body in The Winter’s Tale’ の中で、『冬物語』の中で「造化の神を欺く」という言葉が使われていることを根拠に、この芝居は芸術家ジュリオ・ロマーノの「人工的な作品を決定的に否定」していると書いているが、(Adelman )私にはそうは思えない。語り手「紳士3」のただの強調に思える。以下、その箇所からの引用。
紳士3 いや、姫君がポーリーナ様ご所蔵の母上の彫像のことをお聞きになり——それはイタリアの巨匠ジューリオ・ロマーノが長い歳月をかけて製作し、やっとこのほど完成したものだが、ロマーノ自身、自分の作品に息を吹きこむ永遠の力が与えられていたら、造化の神を欺いてそのまねをしたいと言っているほど、ハーマイオニ様そっくりのハーマイオニ様の像だという。(『冬物語』 5.2.92-98)(下線筆者)


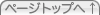
Comments & Trackbacks
Trackback URL http://shakeweb.co.uk/spear/thesis/27.html/trackback