ラファエルが語り、ダーウィンが読む天地創造
ラファエルが語り、ダーウィンが読んだ天地創造
—『失楽園』第7巻をめぐって—
米田 拓男
Introduction
本論では、ミルトン『失楽園』第7巻を扱う。第7巻では、旧約聖書の「創世記」の冒頭にあたる天地創造が、ミルトンらしい壮大な筆致で綴られている。ミルトンはこの『失楽園』書くにあたって、聖書のauthorized versionを使用しているのは間違いのないところである。ミルトンは聖書という材源をどのように扱かっているのだろうか。私はその点に関心がある。本論では、ラファエルの語りに注目したい。
Chapter 1「ミルトンとシェイクスピア、その材源の差異」では、グリーンブラットの7つの「否認宣言」を手掛かりに、グリーンブラットの言うところの「社会エネルギー」という観点から、ミルトンとシェイクスピアの材源を比較し、両者の作品がどのような人々を対象として書かれたのかということについて考察する。
Chapter 2「ラファエルの語りについて」では、『失楽園』がラファエルの語りによって成立しているという点に焦点を当てて、第7巻の語りの構造について分析する。
Chapter 3「ダーウィンが読んだ『失楽園』」では、第7巻の天地創造の記述が、何故ダーウィン以降の私たちにとって読むに耐えるものとなっているのかという点について、ラファエルの語りを手掛かりに考察する。
Chapter 4「教育者としてのラファエル」では、第7巻に登場するラファエルが人間存在を賛美する台詞を、「存在の大きな鎖」、「雅量」、「高邁」といった言葉をキーワードに、ミルトンの『教育論』と絡めて論じる。
Chapter 1 ミルトンとシェイクスピア、その材源の差異
スティーブン・グリーンブラットは、文学作品は社会的エネルギーの磁場の中に存在するものであると説く。彼によると、一つの文学作品は、常に社会的エネルギーの影響を受けて成立し、そしてその作品自体が持つエネルギーが、今度は社会に影響を与えるのである。彼は、「文化的実践(つまりは文学作品)に内在する社会的エネルギーがいかに交渉され交換されるのか」という問いに答えるための第一段階として、次のような7つの「否認宣言」を行っている。
1 偉大な芸術のエネルギーの唯一の源泉として天才を持ち出すこと
はしない。
2 動機なき創造はあり得ない。
3 超越的、無時間的、不変的表現はあり得ない。
4 自立的な芸術作品はあり得ない。
5 源泉(〜から)と対象(〜のため)のない表現はあり得ない。
6 社会的エネルギーを持たない芸術はあり得ない。
7 社会的エネルギーの自然発生はあり得ない。
(グリーンブラット 22-23)
グリーンブラットは、シェイクスピアについて論じる過程においてこの7つの否認を行っているのだが、このことは『失楽園』にも当てはまる。一つずつ検証してみたい。(1)ミルトンは、『失楽園』という作品をある社会的背景のもとで(社会的エネルギーを受けて)書いた。イギリスでは1660年に、チャールズ二世が王位に就き、彼が望んでいなかった王政が11年振りに回復した。ミルトンは王政批判のためのパンフレットを多く書いたが、『失楽園』には、その反響と取れる詩行が散見される。(2)ミルトンは1652年に失明し、1658年には結婚生活わずか15ヶ月の妻と生後間もない女児を失うという立て続けの不幸に見舞われた。彼の個人的不幸は、『失楽園』の執筆と無縁ではあるまい。(3)『失楽園』という作品には、書いている当時の政治的見解、個人的な思いが込められているはずである。(4)ミルトンは『失楽園』を書くにあたって、材源として聖書の「創世記」を使用している。そのため彼は『失楽園』を、彼の内的想像力のみに頼って執筆した訳ではない。(5)ミルトンは『失楽園』を、ある程度読者を想定して執筆したはずである。第7巻には ‘fit audience find, though few’(31行)という一節があるが、これはミルトンが『失楽園』を執筆する時に想定していた読者像と重なるかも知れない。(6)ミルトンは1660年頃には『失楽園』をすでに口述を開始しており、1667年に出版した。『失楽園』には、永年に渡る執筆によって蓄積された、グリーンブラットが言うところの「エネルギー」が凝集しているはずである。(7)『失楽園』という作品が持つ「社会的エネルギー」は、政治的、個人的背景の影響を受けており、ある程度は「創世記」という材源から継承しているはずである。
ここでグリーンブラットを引用して私が確認しておきたかったことは、『失楽園』には材源がある、ということと、ミルトンは、何らかの読者を想定して『失楽園』を書いたはずだ、ということの2点である。ここで、シェイクスピア作品と『失楽園』を比較してみたい。まずは第1点目の、材源の違いについて考察する。シェイクスピアは、そのほとんどの作品で材源を用いている。私は過去に『ロミオとジュリエット』と『冬物語』の材源比較を試みたことがあるが、シェイクスピアの材源の扱いについて、その時私は両作品に共通性を見出だした。シェイクスピアは、アーサー・ブルックの物語詩『ロウミアスとジューリエット』(Tragical historye of Romeus and Juliet, 1562)を劇化するにあたって、様々な改変を施しているが、その時私が注目したのは、二人の喜劇的人物、乳母とマキューシオであった。ブルックの詩には、巻頭に ‘To Readers’ として、ここに描かれている恋人たちのように、後先考えずに行動すると身を破滅することになると、読者に対して警告している。そのことが象徴するように、ブルックの詩には全体的に若者たちへの戒めめいた説教臭が充満している。シェイクスピアは、二人の喜劇的人物に、多くの活躍の場を与え、猥雑な冗談を言わせることによって、材源にあった説教臭さを取り除いた。
『冬物語』は、シェイクスピアと同時代の作家ロバート・グリーン (Robert Greene, 1560?-1592) の『パンドスト』 (Pandosto, 1588) を下敷きにして書かれている。シェイクスピアによる『パンドスト』からの改変の最大のもの、それは物語の結末の付け方にある。『パンドスト』は『冬物語』と同じように、パーディタ(『パンドスト』ではフォーニア)とフロリゼル(ドラスツス)の結婚によって幕を閉じるが、リオンティーズ(パンドスト)が自殺することによって苦い後味を残す。ところがシェイクスピアは、『冬物語』においてリオンティーズを殺さず、かつその妻ハーマイオニも生きていたことにして、彫像を装って彼の前に現れる彫像の場を創作し、作品に救いを与えた。材源には、嫉妬深く自分勝手な男に罰が下されるという説教臭が残るのである。『パンドスト』の物語を読み終えた読者は、因果応報、というありがたい教訓を頂戴して本を閉じることになる。しかし、シェイクスピアの『冬物語』に、そのような教訓物語めいたニュアンスはない。
グリーンブラットは、「5 源泉(〜から)と対象(〜のため)のない表現はあり得ない」と言うが、シェイクスピアの作品を受容したのは、劇場の観客であった。観客は、いつの時代も、娯楽に教訓など求めない。一体、誰が、説教を聞きに劇場に足を運んで金を払うだろう。説教を聞きたいのなら教会にでも行った方がましである。シェイクスピアはそのことを良く知っていた。シェイクスピアは『ロミオとジュリエット』で、材源の長篇詩が持っていた説教臭さを見事に抜き取り、ロミオとジュリエットの悲劇を、情熱的な恋の物語として昇華させた。そして『冬物語』では、教訓めいた物語を許しの物語へと書き換えた。シェイクスピアが行ったことは、材源を対象のために書き換える作業だったと言える。
では、ミルトンはどのような材源をどのような対象のために書き換えたのか。ミルトンは聖書を材源として選んだ。当時のイギリスにおいて知らない人はいないアダムとイヴの楽園追放の物語を、である。ミルトンとシェイクスピアの場合とで大きく異なるのは、『失楽園』の読者は、予め材源を知っていることを想定して書かれている点である。シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』や『冬物語』は、その材源を観客が知っているものとして書かれてはいない。ミルトンは聖書を材源として選んだことで、シェイクスピアとは比べ物にならないくらい大きな制約を迫られることになったはずだ。『失楽園』は、読者に馴染みの深い物語を扱っているので、読者と作品の間に、シェイクスピアの場合には無い軋轢が生じることになる。第7巻は、殊にそれが強い巻である。ミルトンは、天地創造を聖書からあまりにもかけ離れたように書くことはできない。何故なら、読者は聖書の一番始めに出てくる天地創造の記述をいやと言うほど頭に刷り込まれているだろうからである。そこからあまりかけ離れれば、そのようなものは私が知っている天地創造ではないとして、読者が離れてしまうだろう。それでは、予め知っている物語を読むことによって、読者がミルトンに期待したものとは何であろうか。自分が知っている天地創造を読みたいのであれば、聖書を紐解けばよいだけの話だ。聖書の天地創造を知った上で、尚、天地創造の物語をミルトンに求めるものがあるとすれば、それは、自分が良く知っている、あのお馴染みの場面が、詩人の力によってどのように再現されているのかという興味に尽きる。そしてミルトンは、そのような読者の期待に見事に答えて見せている。例えば、次のような描写はその格好の例である。
Be gathered now ye waters under heaven
Into one place, and let dry land appear.
Immediately the mountains huge appear
Emergent, and their broad bare backs upheave
Into the clouds, their tops ascend the sky:
So high as heaved the tumid hills, so low
Down sunk a hollow bottom broad and deep,
Capacious bed of waters:
神はさらに言われた、
『汝ら、天の下なる滄海よ、一処に集れ、しかして、
乾ける土をして出現せしめよ!』と。すると巨大な山々が
忽然として姿を現わし、その広々とした裸の背を高く
雲の中にまで擡げた。頂上は屹然として大空に聳え立った。
盛り上がる山々が高くそそり立つにつれ、広く深く
窪んだ谷間が、下へ下へと沈んでゆき、滄海をたたえるのに
ふさわしい広漠たる海底となった。(283-289)
(以下、引用は平井訳を参照)
さすが詩人だと思うような、スケールの大きなSF的と言っても良い描写だ。この箇所は聖書では次のように書かれている。
神は言われた。
「天の下の水は一つ所に集れ。乾いた所が現れよ。」
そのようになった。(「創世記」 1章9節)
このような簡潔な描写を、ミルトンは聖書の中のわずかな記述を詩人の想像力で大きく膨らませているのである。だが、ミルトンの詩的修辞にはこれ以上深入りしない。本論では、この天地創造の場面がラファエルによる語りとして描かれていることに注目したい。次章以降では、ミルトンが聖書の物語を、聖書を熟知している読者のために書き換える際に行った改変のうち、このラファエルの語りについて具体的に論じていくことにする。
Chapter 2 ラファエルの語りについて
第7巻は、ミルトン自身の詩神への呼びかけ(invocation)によって幕をあける。それはホメロスやヴェルギリウスの叙事詩の形式を意識してのことであろう。invocationの中でミルトンは次のように言う。
Standing on earth, not rapt above the pole,
More safe I sing with mortal voice, unchanged
To hoarse or mute, though fallen on evil days,
On evil days though fallen, and evil tongues;
In darkness, and with dangers compassed round,
And solitude;
目も眩むような宇宙の極の上に立ってではなく、この
地上に立ってさらに安らかに、人間らしい声で歌いたいのだ。
たとえ悪しき日々に沈淪していても、—-たとえ悪しき日々と、
悪しき罵詈雑言の中に沈淪し、暗黒の中にあって危険に囲まれ
孤独に苛まれていようとも、声だけは荒立てることなく、また
黙することなく歌いたいのだ! (第7巻 25-28)
このように、ミルトンは闇の中で創作をしていくことを宣言しているが、それはさながら、渾沌の中で神が行う天地創造のようである。第7巻は全12巻に及ぶ『失楽園』の後半の最初の巻であり、invocationによって始まる。そして『失楽園』の後半は、旧約聖書の冒頭に相当する天地創造の描写から始まるのだ。新たな始まりを感じさせる巻である。新井氏は、この箇所が最初に書かれた可能性を示唆する。
ミルトンが『楽園の喪失』のどの部分から口述を開始したかというこ
とは、わかっていない。叙事詩は詩神への呼びかけで始るのが通例で
あるから、この作品のなかでなん度かあらわれるその種の呼びかけの
ひとつが、ミルトンの最初の口述部分となったかもしれない。
(中略)
第七巻の冒頭は王政復古前後の、かれじしんの逆境に言及しているこ
とからみて、個人的色彩のきわめて濃い詩行であるといえる。そして
この個人的色彩は、これらの部分が、あるいは全体の歌い出しの部分
(のひとつ)となっていたのかもしれないという推測をゆるすのであ
る。(新井 126-7)
第7巻は、このように、ミルトン自身の詩神への呼びかけで始まるが、ミルトンが直接天地創造を語る訳ではない。その役割はラファエルへ引き継がれる。アダムはラファエルに、自分たちがどのように誕生したのか、世界がどのように造られたのか知りたいと思い、ラファエルに話すようにせがむ。「神聖なる解説者よ (Devine interpreter)」とアダムはラファエルに語りかける(72行)。平井氏は、『アエネーイス』でメルクリウス(マーキュリ)がそう呼ばれているのを借りたらしいと述べている(平井 312)。この願いに答えて、ラファエルはアダムに語り始める。
This also thy request with caution asked
Obtain: though to recount almighty works
What words or tongue of seraph can suffice,
Or heart of man suffice to comprehend?
Yet what thou canst attain, which best may serve
To glorify the maker, and infer
Thee also happier, shall not be withheld
Thy hearing,
用心深くお前はわたしに頼んだが、その願いを聞き届けて
あげよう。それにしても、わたしのような熾天使のいかなる言葉、
いかなる舌が、全能の神の御業をよく語りえようか? また、
人間のいかなる心がよく理解しえようか? だが、それにも
かかわらず、もしお前が創造主を誉め讃えるのに役立ち、
お前をさらに幸多き者にするのに役立つのであれば、お前に
理解できる限り、そのことについて答えることを控えるべき
ではなかろうとわたしは思う。(第7巻 111-8)
こうしてラファエルは天地創造の場面をアダムに語り始める。
このように天地創造をラファエルの口からアダムに向かって語らせたということは、非常に重要な点であると思う。そしてラファエルの語る天地創造は、聖書のそれと異なる箇所が多くある。聖書における天地創造は次のように始まる。
初めに、神は天地を創造された。地は渾沌であって、闇が深淵の面に
あり、神の霊が水の面を動いていた。神は言われた。
「光あれ。」(「創世記」 1章1-3節)
このように「創世記」では、神自らが天地を創造する。それに対して、ラファエルが語る天地創造では、神の代わりに御子が天地創造に赴くことになる。御子は戦車に乗って渾沌へと向かう。
meanwhile the Son
On his great expedition now appeared,
Girt with omnipotence, with radiance crowned
Of majesty divine, sapience and love
Immense, and all his Rather in him shone.
About his chariot numberless were poured
Cherub and seraph, potentates and thrones,
And virtues, winged spirits, and chariots winged,
御子は大いなる遠征の途につこうとして、その姿を現わされた。
その腰には全能の力を帯び、その頭には神々しい威儀と
広大無辺の知恵と愛との輝きを、冠として着けておられた。
そして、父なる神のすべての光が御子のうちに輝いていた。
彼の乗られた戦車の周囲には、智天使、熾天使、能天使、
座天使、力天使その他の翼をもった夥しい数の天使たちと、
これまた翼をもった多くの戦車の群れが屯していた。
(第7巻 193-9)
このように、ミルトンは聖書には登場しない御子を天地創造の場面に登場させ、御子が渾沌へ向かって行く過程を詩人の想像力で余す所なく壮大に描いて行く。聖書の単純な記述をここまで膨らませるその描写に、ミルトンの詩才をはっきりと見て取ることができる。あるいは、この場合、ラファエルが詩人であると言うべきか。いずれにせよミルトンはこのように、聖書には登場しない御子を天地創造の場面に登場させた。『失楽園』の神にとって、御子は「言(ことば)」と同義であるようだ。
And thou my Word, begotten Son, by thee
This I perform, speak thou, and be it done:
My overshadowing spirit and might with thee
I send along, ride forth, and bid the deep
Within appointed bounds be heaven and earth,
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
So spake the almighty, and to what he spake
His Word, the filial Godhead, gave effect.
だが、汝わが子よ、わが「言」よ、わたしは汝によって
今言ったことを行いたい。言え、汝、さらばことは成就しよう!
すべてを覆う聖霊と能力とを、わたしは、汝につけて送る。
直ちに戦車を駆って行き、「渾沌」に命ずるがよい、定められた
境界内において天と地とをあらしめよ、と!
(中略)
全能者はそんな風に語られた。そして、その語られたことを、
彼の『言』である聖なる御子が実現し給うたのだ。
(第7巻 163-75)
「言」である御子が天地創造を行う。これは聖書の、ヨハネによる福音書の冒頭の記述を受けてのことだろう。
初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言
は、初めに神と共にあった。万物は言によって成った。成ったもの
で、言によらずに成ったものは何一つなかった。(1章1-3節)
神と共にあり、神そのものでもある「言」。一体それは何を意味しているのだろうか。ミルトンはそれを御子と解釈した。ギャラガーは、 ‘Creation in Genesis and in Paradise Lost’ で、ミルトンが聖書にある矛盾に対して論理的辻褄を合わせようと試みた可能性について論じている(Gallagher 197-9)。[1] ギャラガーは次のように言う。
Milton may have been more consumed with the lust of logic than
smit with the love of sacred song
ミルトンは、神聖な詩の情熱に取りつかれていたというよりも、論理
への欲望に心を奪われていたのかも知れない(Gallagher 199)
「言」である御子による天地創造も、ギャラガーが言うような、ミルトンによる聖書の論理的辻褄を合わせるための試みの一つだったのではないか。第7巻の天地創造の件で御子が天地創造を行うのは、最初の方だけである。ラファエルの語りにはすぐに御子は登場しなくなり、代わりに神が自ら天地創造を行う。御子の記述が最初だけですぐになくなってしまうのは、言と神と御子が一体であることを示しているのかも知れない。
ギャラガーは、同じ論文の中で、聖書のテキストが過去に改変されたことについて論じている。聖書に見られる矛盾を解消するために、聖書が改変されたことがあったのだ。ミルトンの『失楽園』は、ギャラガーが言うように、それらの矛盾を解消する、ミルトン版の「創世記」の校訂本であると言えるのかも知れない。しかしミルトンは、新しい聖書を作り出そうとした訳では無かったと思う。私は、ミルトンは聖書に書かれていることを尊重しながら『失楽園』の執筆に取り組んでいたと考える。ラファエルの語りという大枠を導入したことがそのことを示している。どういうことか。ここで一度、語りの枠組みを整理しておきたい。『失楽園』第7巻の複雑な語りの構造は、聖書の「創世記」のそれと比べれば一目瞭然である。以下は聖書の語りの構造である。
神による天地創造(Act)
↓
執筆者(Narrate)
↓
読者(Read)
聖書では天地創造の描写を、執筆者が読者に向けてそのまま記述する。次に揚げるのは、それに対する『失楽園』第7巻の語りの構造である。
神(Order)
↓
御子(Act)
↓
ラファエル(Narrate)
↓
アダム(Listen)
↓
ミルトン(Narrate)
↓
娘たち(Write)
↓
読者(Read)
神は「言」である御子に命じて天地創造を行った。ラファエルはその光景を見ていた。 [2] そしてラファエルは、自分が見たことをアダムに語る。そのラファエルの語りを、作者ミルトンは読者に向かって語りかけている訳だが、実際には口述筆記として、実の娘に語りかけることによって作品化したのである。さらには第7巻には、invocationとしてミルトン自身が語り手として登場する。語りの構造の中に、ラファエルとミルトンという二人の語り手がいるのだ。何故、ミルトンはこのような構造を用いたのか。
『失楽園』第7巻が語りの入れ子構造になっているのは、聖書という材源の性質にあるのではないか。「創世記」の天地創造の描写は、聖書の中でも広く人口に膾炙した箇所である。そのためミルトンにとっては、聖書からの改変に特に慎重にならざるを得ない箇所だったのではないだろうか。ミルトンは天地創造の過程をラファエルの語りを通して描くことによって、「これは私が知っている天地創造ではない」という予想される読者からの批判に対して、「これはラファエルが語る天地創造ですよ」と予めエクスキューズしているのだ。だがそれ以上に、自分の手で聖書を書き換えるという行為が、ミルトン自身にとって恐れ多いことだったからなのではないか。ミルトンがミルトン自身の声で「創世記」を語るのでは、はなはだ不遜な行為であると思われかねない。天地創造をする神をも創造してしまうことになるのだから。私は、ミルトンがこのような語りの入れ子構造を採用したことに、ミルトンの聖書に対する畏怖の念を感じる。聖書の冒頭を飾る天地創造の記述を、『失楽園』では第7巻目に持ってきたということも、叙述を「事件の中心から(in medias res)」始めるという叙事詩の慣例に従ったということもあるだろうが、一方で、ミルトンの聖書に対する控えめな態度を示しているようにも思える。第7巻に見られる複雑な語りの入れ子構造。聖書の中の広く知られた物語を叙事詩として語り直すためには、このような構造が必要だったのである。
Chapter 3 ダーウィンが読んだ『失楽園』
『失楽園』第7巻で、ラファエルはアダムに天地創造について語る。アダムを通じて、ラファエル、そしてミルトンは、私たちに天地創造について語ってくれる。ところが残念なことに、ダーウィニズムに犯されている私たち(少なくとも私)は、このような天地創造が実際に行われたとは考えない。アメリカでは、進化論を教えない学校もあるようだが、根本主義者(fundamentalist)でもない限り、現代を生きる者がここに書かれているような天地創造を、実在の出来事として受け取ることはないだろう。ミルトン自身は、果たして本当に天地創造を信じていたのだろうか。もちろんダーウィンは、ヴィクトリア朝時代の人間であるので、ミルトンの時代の人々は進化論のことなど知る由もなかった。『種の起原』の出版は1859年である。17世紀の人間ならいざ知らず、ダーウィン以後の現代を生きる私たちは、天地創造の記述をフィクションとしてしか読むことはできない。だが、ラファエルの語りが、ここでも有効に機能している。本章でも前章に引き続き、ラファエルの語りの機能について考察する。
聖書には多くの矛盾点があるが、「創世記」に二つの天地創造が描かれていることもその一つである。ヘブライ語で書かれた原典では、「神」は1章ではエローヒーム、2章ではヤーウェと記されている。そのため、「創世記」は1章と2章で作者が異なるのではないかという説がある。神学者のアームストロングは、「創世記」に二つの天地創造が描かれていることには意味があると考えている。彼女は次のように述べる。
編集者たちは、最初に二つの明らかに矛盾する創造物語を提示するこ
とによって、およそ一人の人間が神的心理の全体を包括することなど
できないのだという基本的な宗教的原理を例示していたのである。
(アームストロング 30)
また、アームストロングは次のようにも述べる。(エロヒストとは「創世記」の1章の執筆者、ヤーウィストは、2章の執筆者を指す。)
聖書の編集者たちは、二つの矛盾する創造物語を提供することによっ
て、J[エロヒスト]もP[ヤーウィスト]も虚構を書いたのだということ
を指摘していたのである。彼らは、新しい宇宙論的発見によって時代
遅れのものとされえないような、時代を超えた真理を提供したのであ
る。([]は筆者による)(アームストロング 31)
アームストロングは、聖書の編集者たちが二つの矛盾する創造物語を並列したことによって、聖書の天地創造の記述が普遍性を獲得したということを述べているが、ラファエルがアダムに語る次の台詞にも同じ効果がある。
Immediate are the acts of God, more swift
Than time or motion, but to human ears
Cannot without process of speech be told,
So told as earthly notion can receive.
そもそも、
神の御業というものは瞬時にして成るもので、時間や運動の
速さを凌ぐものなのだ。しかし、そのことは、諄々と
言葉をつらねて地上の者に分かるように説かないかぎり、
到底人間の耳に伝えることはできない。(第7巻 176-9)
ラファエルが言うことが正しければ、天地創造は7日間かかったのではなく、全てが一瞬のうちに行われたことになる。ラファエルはアダムが理解できるように人間界の事例に置き換えて、分かりやすく説明しているのだ。ラファエルは、第6巻で天上の戦争について説明する時にも同じことを言っている。
Thus measuring things in heavユn by things on earth
At thy request,
わたしは、お前の求めに応じて、地上の事柄を物差しにして、
天上の事柄を測りながら今まで話してきた
(第6巻 893-4行)
ギャラガーは、神が人間の創造を第6日目の最後に行うように、ミルトンが創造の順序を入れ替えたことについて論じているが(198)、このような台詞の前では、そのような議論は全て水泡に帰する他ない。このような台詞は、聖書に書いてあることは全てフィクションだという考え方に導きかねないが、実際、ミルトンはそのように考えていたのではないか。これらの台詞はさりげなく挿入されているように見えながら、実はミルトンの聖書批判であり、聖書解釈を表わしているのである。聖書には多くの矛盾点が存在するが、ラファエルがアダムに告げているこのような考え方—-つまり、聖書に書かれていることは全て、読者のために分かりやすく書き換えられたフィクションであるという考え方—-は、そのような矛盾に対する解釈の問題を一挙に解決することだろう。ミルトンが聖書をフィクションとして捉えていた可能性を示唆するこのラファエルの台詞は、とりもなおさず『失楽園』という作品のフィクション性を強調する。ミルトンは『失楽園』を紛うかたなきフィクションとして書いた。だからこそ、ダーウィン以降の私たちも楽しめるのだ。そして実は、当のダーウィンその人も、『失楽園』を楽しんだのである。ミルトン詩集は彼の愛読書の一つだった。
ここで重要となってくるのが、ビーグル号航海におともした二冊の本
を思い出すことである。このとき彼の想像力は最も敏感な時期にあっ
た。一冊はライエルの『地質学原理』。もう一冊、彼が『自伝』のな
かで、肌身離さずビーグル号からの長い陸地探検のあいだも持ち歩い
たと言っているその本が、ミルトン詩集であった。(ビア 56)
そして、ミルトンの『失楽園』は、ダーウィンの進化論の着想に貢献していたのである。
ダーウィンは、ミルトンのうちだす人間中心的宇宙観を転覆すること
に喜びを見出だすようになるのだが、それでもミルトンの言葉の世界
は、それが豊富や、密集や、特定の種の形成に対する、ダーウィン自
身の感覚と一致していたために、どれくらいが生き残りうるか、どれ
くらいが過去との共通性と連続性を保ちうるかを、ダーウィンにはっ
きり示した。ミルトンがダーウィンに深い想像の喜びを与え、それが
ダーウィンにとっては理解につながる手立てとなった。
(ビア 61)
ダーウィンによる進化論以後の私たちがミルトンの『失楽園』を楽しむことができるのは、ミルトン自身がそのフィクション性に自覚的だからである。ミルトンは、「創世記」というフィクションに書かれている天地創造の描写を、同じく「創世記」というフィクションに登場するアダムに、ラファエルの口からフィクションとして語らせる。『失楽園』で二重の語りの構造を用いたことは、作品のフィクション性を強める作用をもたらした。そしてそのことによって、『失楽園』は普遍性を獲得したのだ。叙事詩が持つこのような語りの形式は、グリーンブラット流に言うなら、作品が保存しているエネルギーを、時代を超えて伝達することに有効なのである。
Chapter 4 教育者としてのラファエル
『失楽園』第7巻511行に次のような記述がある。ラファエルは、天地創造をアダムに語る過程で、人間存在のことを次のように賛美する。
There wanted yet the master-work, the end
Of all yet done; a creature who not prone
And brute as other creatures, but endued
With sanctity of reason, might erect
His stature, and upright with front serene
Govern the rest, self-knowing, and from thence
Magnanimous to correspond with heaven,
But grateful to acknowledge whence his good
Descends, thither with heart and voice and eyes
Directed in devotion to adore
And worship God supreme, who made him chief
Of all his works:
既に造られた
すべてのものの目標である、最も重要なものが未だ造られては
いなかった、—-つまり、他の生きもののように常に下を見、
道理を弁えないのと違い、聖なる理性を与えられ、背を
のばして直立し、穏やかな額を真っ直ぐに保って他のものを
支配し、自らを知り、そして自らを知るがゆえに神と交わるに
ふさわしい高邁な心を持ち、しかも同時に自分のもつ一切の
善きものがどこから下賜されているのかを知り、感謝し、
しかして、慎んでその心と声と眼を天に向けてそそぎ、
自分を万物の長として造り給うたいと高き神を崇め、拝む
ところの者、—-これがまだ造られてはいなかったのだ。
(第7巻 505-516行)
この台詞の中で、ラファエルは人間のことを ‘master-work’、’Magnanimous to correspond with heaven’、’chief / Of all his works’と賛美する。このような人間を賛美する記述は、聖書における天地創造の記述には出て来ない。このような記述を、ミルトンは人間の創造の場面に書き加えたのである。何故、ミルトンはこの台詞を追加したのか。この台詞から、ラファエルの語りが持つもう一つの性質を明らかにしたい。
ラファエルはこの台詞の中で、人間存在を貴いものとして謳い上げているが、この台詞は私に『ハムレット』の’What a piece of work is a man’という台詞を即座に連想させる (2幕2場286行)。前後を含めて引用してみる。
近頃、どういうわけか何をやっても楽しくない。日課にしていた武術
などの稽古も全部やめてしまった。やけに気が滅入って、この地球と
いう見事な建造物も、海に突き出た崖っぷちにしか見えない。大空と
いう類いまれなあの天蓋、見ろ、あの素晴らしい頭上の広がり、燃え
立つ黄金をちりばめた絢爛豪華な天井、ああ、あの空でさえ濁った毒
気の集まりとしか思えないのだ。人間は造化の神の傑作だ、気高い理
性、無限の機能、形の素晴らしさ、動きの敏捷さ、天使のような行動
力、神さながらの理解力。世界の美の精髄、生きとし生けるものの鑑
—-だが、それが何だ、俺にとっては塵のかたまり。人間を見ても楽
しくない—-女だって同じだ。(強調筆者)
(松岡訳 2幕2場280-91)
ハムレットの人間賛美は、前後の文脈の中で読むと、そう簡単に喜ばしいものでないことはすぐに分かる。この台詞をどのように理解したらよいのだろう。高橋氏は次のように記す。
ルネサンスの人間賛歌の思想に基づいて人間を神に例える一方で、
「死を想え」(memento mori)の思想に捉えられ、ジレンマに陥る
ハムレット。(高橋 187)
高橋氏によると、この台詞はルネサンスの人間賛歌の思想に基づいていることになる。しかし、人間存在がいくら素晴らしいものであっても、ハムレットには人間が「塵の塊」に見える。それは、人間がいずれ死すべき存在であるからである。人間は素晴らしい。しかし、いつかは塵に帰る。素晴らしいが完璧なものではない。この議論に対してティリヤードは次のように書く。
この台詞は従来、ルネサンス・ヒューマニズムの偉大な英国的一例、
すなわち中世の厭世的禁欲主義に対する人間の尊厳の主張として取り
扱われてきた。だが実は、これはまったく純粋に中世的伝統の中にあ
る。つまり神の姿に似せて造られた人間の堕落以前の状態への、そし
て観念的にはまだ人間が取り戻しうるような状態への正統的賛歌を
シェイクスピア流に書いたものなのである。これはまたシェイクスピ
アが人間を、天使と動物の中間という伝統的な宇宙観に従った位置に
据えているという事実をも示している。(ティリヤード 4)
ティリヤードによれば、この台詞はルネサンス以前の中世的伝統の中にあるという。そして、まだ人間が取り戻しうる堕落以前の状態への正統的賛歌を。そのことを踏まえると、ハムレットは高橋氏が言うように人間が死すべき存在であることを嘆いているのではなく、人間の堕落を嘆いているのかも知れない。堕落以前の人間は貴いものだったが、堕落によって、人間存在は地に落ちた。男も女も、本来貴いものであったはずが、堕落している。「人間は造化の神の傑作だ」という時、ハムレットは、そのことを嘆いているのかも知れない。
ここでティリヤードが触れている、この人間を天使と動物の中間に位置する存在として秩序付けているのはthe Great Chain of Beingの考え方に基づく。ティリヤードによれば、十五世紀の法学者ジョン・フォーテスキューは、自然法に関するラテン語の著作の中で次のように記しているという。
「この秩序においては、熱いものが冷たいものと、乾いたものが湿っ
たものと、重いものが軽いものと、大きなものが小さなものと、高い
ものが低いものと、それぞれ調和している。この秩序においてはま
た、天上の王国では、ある天使が別な天使の上にという具合に次々と
序列をつけて配され、地上と空と海とでも、人間は人間同士、獣は
獣、はたまた鳥は鳥、魚は魚と、それぞれがそれぞれのあいだで序列
をつけられている。したがって、地上を這ういかなる虫でも、空高く
飛ぶいかなる魚でも、この秩序の鎖によって妙なる協和音のハーモ
ニーのうちに縛られないものはないのだ。罪人ばかりのすむ地獄だけ
がこの秩序に抱擁されることを拒み……。神は被造物の数と同じ数だ
けその区別を設けた。したがっていかなる被造物であっても、他のあ
らゆる被造物となんらかの点で異なり、そしてそれゆえに他のすべて
となんらかの点で上下の差別を持たないようなものは存在しない。こ
のようなわけで、最高位の天使から最下位の天使に至るまで、自分よ
りも上と下に天使がいないような者は絶対に存在しないし、人間から
最も下等な虫に至るまで、なんらかの点で別の被造物にまさり、かつ
なんらかの点で別の被造物に劣ることのないようなものも存在しな
い。すなわち、秩序の絆に包み込まれないようなものはないのであ
る。」(ティリヤード 49-50)
フォーテスキューは、全ての存在は序列によって秩序付けられているという。このような序列の中で、人間は、動物と天使の中間に位置すると考えられていた。ポウプ『人間論』の中にも同様の考え方が見られる。
まず最初に、天なる神と地上の人間とについて、我らの知っているも
のから判断する以外に、我らは何を判断し得るだろうか。
人間について我らが判断し参照するよすがは、この地上の彼の状態を
除いて何があるだろうか。たとい神が無数の世界に知られているとし
ても、我らは我らの世界に神をあとづける以外にないではないか。
茫漠たる空間を貫いて眺め、
数多の世界が重なり合って、一個の宇宙を形づくるのを見、
組織が組織の中に連なり、
いかなる惑星がいかなる太陽をめぐり、
いかに様々な存在が恒星の一つ一つに住むかを観察し得る者は、
神がなぜ我らをこのように造ったかを語り得るかも知れない。
然しこの世界を支え、結ぶものを始め、
強固な連絡、微妙な依存、正しい位置の関係などを、
広く行き渡る汝の魂は、果して見ぬいたことがあるだろうか。
部分が全体を包むことがあり得るだろうか。
すべてのものを一つに引き寄せ、引かれて支える偉大な鎖は、
神と汝とのいずれが、支えているのだろうか。(強調筆者)
(ポウプ 上田訳 154)
この中で、「すべてのものを一つに引き寄せ、引かれて支える偉大な鎖」というのは、同じことを指している。
ここで再び、本章の冒頭に揚げたラファエルの台詞に戻りたい。新井氏は、この台詞には、雅量(Magnanimity)の考えを見て取ることができると言う。
アダムは「きよき理性」[sanctity of reason]をさずかり、「寛やか
なる心」[Magnanimous]—-つまり「雅量」をもって神と交わり、節
制を尊びつつ、他を治める。これらの美徳は、[・・・・]明らかに
「貴族とおもだったジェントリー」にミルトンが求めた理想的人間像
である。つまり創造されたアダムの姿には、ミルトンの考える指導者
層の典型が見い出されるのである(この理想たるアダムが堕落し、悔
い改め、神に従順を誓うにいたる過程が、『楽園の喪失』のそのもの
のドラマである)。(新井 116)
第7巻の次にみる箇所にも、Magnanimityの考え方を見ることができると、新井氏は言う(108-116)。ミルトンは1659年に『教会問題における世俗権力』や『教会浄化の方法』といった冊子を公刊している。そのうち『自由共和国樹立の要諦』を、ミルトンは改訂し、三箇所に大きな加筆を行ったという。そのうちの第二の加筆部分で、ミルトンは、王政支持派を、神のみわざと人間の努力を評価しない怠けものとこきおろしている。彼は旧約聖書の「箴言」第6章6節以下の、「怠けものよ、アリのところへ行き、そのなすところを見て、知恵を得よ。アリは君侯なく、支持者なく、主人もないが、夏のうちに食物をそなえ、刈り入れのときに食糧を集める」ということばを引用している。ミルトンはその引用の後、さらに次のように付け加える。
アリは無分別、無制限の人びとにたいして、倹しき自制の民主政、あ
るいは共和国の範例となり、一人の専制君主による一支配体制下より
も、多くの勤勉にして平等なる人びとが未来をのぞみ、協議しあいつ
つ、安全に繁栄してゆく型となる
この加筆を行った一六六〇年の二月、三月頃、ミルトンは『失楽園』の口述を進めていた。ミルトンはこの改訂版『自由共和国樹立の要諦』に見られる主張を、詩的なかたちで『失楽園』のテキストの中に嵌め込んでいるかもしれないのである。第7巻の次の箇所が、アリ社会の部分に相対すると考えられる詩行である。
First crept
The parsimonious emmet, provident
Of future, in small room large heart enclosed,
Pattern of just equality perhaps
Hereafter, joined in her popular tribes
Of commonalty:
最初に匍い出したのは、用心深く
将来のことを考える、なりこそ小さいが大きな知恵を
内に秘めた、節約ずきの蟻であった。蟻は、恐らく今後、
やがては公正な平等の手本となるであろうが、この時も
種族全員をあげての共同体を営んでいた。(第7巻 484-8)
共和政の象徴とされたアリ社会の諸特徴の一切が、ここに出揃っていると新井氏は述べる。この箇所では ‘large heart’ という言葉が使われているが、この語は、ラファエルの人間賛美の台詞に出てくる ‘magnanimous’という語同様、「雅量(マグナニミティ)」の変形であると言える。このアリの創造は第6日目に行われた。そしてこの第6日目の最後の仕事として、神は人間を造るのである。そしてその際に、本章冒頭の一節が記されるのだ。
新井氏は、この雅量という概念はアリストテレスの『ニコマコス倫理学』以来、「王者の条件とされていた美徳」であると言う(新井 133)。『ニコマコス倫理学』を実際に見てみよう。第四巻、第三章「高邁、うぬぼれ、卑下」で、アリストテレスは次のように述べる。高邁(メガロプシューキアー)という言葉で表わされているのが、雅量に相当する概念であろう。
高邁な人とは、自分自身のことを大きな事柄に値すると見なしてお
り、また現に値する人だと考えられる。なぜなら、自分にその価値が
ないのにそんなふうに思っているのは愚かな人であるが、徳をそなえ
ている者で愚かな人や、無分別な人というのは、だれもいないからで
ある。だから、高邁な人とは、今述べられた人を指している。という
のは、自分が小さな事柄に値し、しかも自分自身のことをそのような
ものにしか値しないと見なしているような人は、節制のある人では
あっても、高邁な人ではないからである。すなわち、高邁とは偉大さ
に存するのであって、それはちょうどまた美しさが、大きな身体に認
められれるのに対し、小さな人たちというのは、上品で均整がとれて
いても、美しいとは言えないのと同様である。
(アリストテレス 164-5)
アリストテレスは、「高邁とは偉大さに存する」と言う。高邁、つまり雅量は、偉大さと結びついている。
神は人間を偉大なものとして造ったのである。ラファエルはアダムに向かって、人間、つまり目の前にいるアダムの偉大さを謳い上げる。何故、ミルトンはラファエルにそのようなことをさせたのだろうか。その理由は、この作品が叙事詩であることに求められるかも知れない。英雄的人物が主人公であることは、叙事詩の特徴の一つだからだ。新井氏は次のように述べる。
第一に、叙事詩はそもそも民族の苦難と栄光を語るものであるから、
それは集団的な性格をもつ。第二に、民族の統一精神を象徴する人格
を「範例(モデル)」としてうたいあげる。だからことばも(ラテン
語ではなく)各地方、各国々のことばを用いることが多く、内容もナ
ショナリズムの色彩がつよい。第三に詩人と聴衆とは過去の歴史を共
通に想起することができる関係にある。第四に民族の美徳を代表する
「範例」的人物がうたわれるいじょう、作品は教育的目的をになっ
た。第五として、主人公が苦難の旅路をへて目的地に達するという、
いわば「探究」の形式をもつ。これが「誘惑とたたかう霊魂の巡礼」
の主題をかたちづくることが多かった。第六に、叙事詩は時間的・空
間的知識の「要約」でなければならなかった。さいごに、叙事詩人は
みずからが倫理的高潔を主張できる人物であることが求められた。
(強調筆者)(新井 124-5)
2番目に揚げられている「民族の統一精神を象徴する人格」とは、アダムとイヴをおいて他にない。『失楽園』が叙事詩である以上、ミルトンはアダムとイヴの人格を「範例(モデル)」として歌い上げなくてはならない。ラファエルの人間賛美の台詞は、そのような叙事詩というジャンルの要請によるものなのかも知れない。そして4番目に揚げられているように、アダムとイヴという「範例」的人物が謳われることによって、『失楽園』は「教育的目的」を担うことにもなった。
ミルトンは『教育論』の中で次のように記す。
学問の目的は、神を正しく知ることができるようになって、わたした
ちの最初の親が犯した堕罪を回復することである。その知識によっ
て、神を愛し神にならい、できうるかぎり神に近いものとなるため
に、わたしたちの魂に真の美徳を有せしめて、それが信仰という天か
らの恵みと結合して最高の完全を形成することである。ところが、わ
たしたちの理解力というものは、この肉体にあっては目に見えるもの
にしか及ばない。したがって、目に見える、より程度の低い被造物を
順序正しく研究することで得られるほど明らかには、神と目に見えな
い事がらを知る知識には到達できないのであるから、賢明なる教育に
おいても、必然的にこれと同じ方法がとられるべきである。
(ミルトン 11-12)
ミルトンは、学問の目的を「神を正しく知ることができるようになって、わたしたちの最初の親が犯した堕罪を回復すること」にあると述べる。「目に見える、より程度の低い被造物を順序正しく研究する」という記述からは、ミルトンが明らかに ‘the Great Chain of Being’の概念を意識していることを表している。ミルトンにとっての学問とは、「神を正しく知」り、「神を愛し」、「できうる限り神に近いものとなる」こと、つまり、「存在の大きな鎖」の序列をできるだけ上に上って行き、神に近づくことなのである。そしてここでも雅量の概念が表れる。ミルトンは、教育を次のように定義する。
わたしは、平時にも戦時にも、私的であれ公的であれ、すべての職務
を正しく、巧みに、気高くやりとげるように人を訓練するところのも
のを、完全至高の教育であると呼ぶ。(強調筆者)
(ミルトン 16)
「すべての職務を正しく、巧みに、気高くやりとげる」ような人とはアリストテレスが言う「高邁(メガロプシューキアー)」に通じる人をも指すのであろう。しかし、新井氏は、アリストテレスの雅量と。ミルトンの雅量には違いがあると言う。
アリストテレスのいう雅量は人間そのものの偉大性の概念であって、
政治指導者に求められる資質である。それにたいしてミルトンのいう
雅量は、具体的に旧新約聖書に出る、アブラハム、サムエル、ヨブ、
キリスト、パウロなど神への信従をとおした諸人物にたいして、神の
側からあたえられた尊厳をさしていうことばである。アリストテレス
のいう「雅量」が人間中心的概念であるとすれば、ミルトンのそれは
いわば神中心的概念であるということができるであろう。
(新井 72)
ここに至って、ミルトンが考える雅量、ミルトンが認識していた ‘the Great Chain of Being’のイメージが具体的に見えてくるような気がする。ミルトンは地球上の全ての生き物の頂点に君臨する者としてではなく、神、そして天使の下位に存在する者として人間を捉えていたのである。
ミルトンは、人間を神の下で気高く教育したいという意識があった。そしてそのような試みの成果として、私たちは『失楽園』という書物を持っている。ラファエルは第7巻において、アダムに天地創造について語るが、ラファエルはアダムの教育者なのだ。ラファエルはアダムに向かって次のように言う。
such commission from above
I have received, to answer thy desire
Of knowledge within bounds:
一定の限界内での知識を
えたいというお前の欲望に応ずるのが、わたしが天から
受けてきた使命でもある。(118-20)
そしてラファエルは、アダムが「すべての職務を正しく、巧みに、気高くやりとげるように」教育を施す。その過程で、人間賛美の台詞が出てくるのである。しかし私は、ラファエルのその言葉に、ハムレットが人間を賛美する時と同様、アイロニカルな響きを聞き取らざるを得ない。何故ならラファエルは、アダムがこの後ラファエルを裏切り、サタン扮する蛇によって堕落させられるのを知っているからだ。ラファエルは、アダムが堕落することになるのを神から聞いてすでに知っているのだ。全てが徒労に帰すのを知った上で、なおかつラファエルはアダムに教育を施す。となれば、ラファエルのこの言葉には、アダムに対して、人間は貴いものなのだから、誘惑に負けてくれるなという思いが込められていると考えるべきであろう。ミルトンがこのような語りを書いた背景には、そのような思いが込められているのではないか。ミルトン自身が口述筆記をしている時、ミルトンはラファエルがアダムに言い聞かせるようにして語ったのだ。
ここで再び、グリーンブラットの7つの「否認宣言」を思い出したい。ここに来て明確になったことがある。それは、(5)ミルトンは「創世記」を材源として、聖書を予め知っている人々、つまりアダムがやがて堕落することを知っている人々に対して『失楽園』の第6巻を書いた。(2)そしてその動機は読者を教育することにあったのだ。
最後に、先に引用した『教育論』からの一節を、再び引用する愚をお許しいただきたい。
学問の目的は、神を正しく知ることができるようになって、わたし
たちの最初の親が犯した堕罪を回復することである。その知識によっ
て、神を愛し神にならい、できうるかぎり神に近いものとなるため
に、わたしたちの魂に真の美徳を有せしめて、それが信仰という天か
らの恵みと結合して最高の完全を形成することである。ところが、わ
たしたちの理解力というものは、この肉体にあっては目に見えるもの
にしか及ばない。したがって、目に見える、より程度の低い被造物を
順序正しく研究することで得られるほど明らかには、神と目に見えな
い事がらを知る知識には到達できないのであるから、賢明なる教育に
おいても、必然的にこれと同じ方法がとられるべきである。
(ミルトン 11-12)
ラファエルは「わたしたちの最初の親」たるアダムに教育を施す。ミルトンは「私たちの理解力と言うものは、この肉体にあっては目に見えるものにしか及ばない」という。そのためミルトンは、天地創造を人間にも分かるような形で語り直した。ミルトンは第7巻で「目に見える、より程度の低い被造物を順序正しく」描写している。ミルトンは、それが、「神と目に見えない事がらを知る知識」に到達するために有効な教育法であると記す。まさにこの通りの方法で、ラファエルはアダムに教育を施す。しかし、それは失敗することが運命付けられている。神は天使たちの教育に、サタンという存在を生み出すことにより失敗した。その天使たちの一人、ラファエルは、アダムに対する教育に堕落を阻止することができず失敗することになる。そしてミルトンは『失楽園』という一冊の書物を通じて私たちに教育を施す。それは果たして成功しているのだろうか。だが、それが成功するかしないかが問題なのではない。ラファエルは、アダムが堕落することを承知の上で、アダムを教育する。ミルトンも、人間が「最初の親が犯した堕罪を回復する」ことができないと分かっていても教育を辞めなかっただろうからだ。
Conclusion
本論では、ミルトン『失楽園』第7巻について、ラファエルの語りに注目して論じた。第7巻では、旧約聖書の「創世記」の冒頭にあたる天地創造が、ミルトンらしい壮大な筆致で綴られている。ミルトンは聖書という材源をどのように扱かっているのか。私はその点に関心があった。
Chapter 1「ミルトンとシェイクスピア、その材源の差異」では、グリーンブラットの7つの「否認宣言」を手掛かりに、グリーンブラットの言うところの「社会エネルギー」という観点から、『失楽園』とシェイクスピア『ロミオとジュリエット』、『冬物語』の材源を比較した。ミルトンとシェイクスピアの場合とで大きく異なるのは、『失楽園』の読者は、予め材源を知っていることを想定して書かれている点である。天地創造をラファエルの語りによって描いたことは、ミルトンが聖書の物語を、聖書を熟知している読者のために書き換える際に行った改変の中で特に重要なものであることを指摘した。
Chapter 2「ラファエルの語りについて」では、『失楽園』がラファエルの語りによって成立しているという点に焦点を当てて、第7巻の語りの構造について分析した。ミルトンがミルトン自身の声で「創世記」を語るのでは、はなはだ不遜な行為であると思われかねない。何故なら、天地創造をする神をも創造してしまうことになるからである。聖書の中の広く知られた物語を叙事詩として語り直すためには、ラファエルの語りによる入れ子構造が必要だったのである。
Chapter 3「ダーウィンが読んだ『失楽園』」では、第7巻の天地創造の記述が、何故ダーウィン以降の私たちにとって読むに耐えるものとなっているのかという点について、ラファエルの語りを手掛かりに考察した。ラファエルはアダムが理解できるように、天上界の出来事を人間界の事例に置き換えて、分かりやすく説明しているのだと言う。ミルトンは、「創世記」というフィクションに書かれている天地創造の描写を、同じく「創世記」というフィクションに登場するアダムに、ラファエルの口からフィクションとして語らせる。『失楽園』で二重の語りの構造を用いたことは、作品のフィクション性を強める作用をもたらした。ダーウィンの進化論以後の私たちがミルトンの『失楽園』を楽しむことができるのは、ミルトン自身がそのフィクション性に自覚的だからである。
Chapter 4「教育者としてのラファエル」では、第7巻に登場するラファエルが人間存在を賛美する台詞を、「存在の大きな鎖」、「雅量」、「高邁」といった言葉をキーワードに、ミルトンの『教育論』と絡めて論じた。ラファエルは、天地創造をアダムに語る過程で、人間存在のことを’master -work’、’Magnanimous to correspond with heaven’、’chief / Of all his works’と賛美する。この台詞は、Great Chain of Beingや雅量(Magnanimity)、さらにはアリストテレスが『ニコマコス倫理学』の中で論じている高邁(メガロプシューキアー)といった考え方と結びつく。
ミルトンは『教育論』の中で、学問の目的を「神を正しく知」り、「神を愛し」、「できうる限り神に近いものとなる」ことにあると述べる。つまり、ミルトンにとっての学問とは、「存在の大きな鎖」の序列をできるだけ上に上って行き、神に近づくことなのである。ミルトンは「私たちの理解力と言うものは、この肉体にあっては目に見えるものにしか及ばない」という。そのためミルトンは、天地創造を人間にも分かるような形で語り直した。ミルトンは「目に見える、より程度の低い被造物を順序正しく研究する」ことが、「神と目に見えない事がらを知る知識」に到達するために有効な教育法であると記す。第7巻におけるラファエルは、まさにこの通りの方法で「わたしたちの最初の親」たるアダムに教育を施す。そしてミルトンは『失楽園』という一冊の書物を通じて、同時に私たち読者にも教育を施しているのだ。
Afterward
本論執筆中に、入院していた祖父の容態が悪化し、亡くなった。僕はお通夜、そして告別式に出席している間、ずっとある違和感を抱き続けていた。それは一昨年に亡くなられた倉本先生の告別式の時にも感じたことである。例えばそれは、斎場で流れているシンセサイザーの電子的な音楽に、段取り然とした斎場の係員に、テレビのワイドショーで芸能人の死が報じられる際に耳にするような女性アナウンスに感じた。そしてコンピューター制御の火葬場。火葬場の内装がひんやりと冷たい。冷たく光る御影石の床、蛍光灯の白い光。床にはゴミ一つ落ちていない。ガラス張りの自動ドアからは外の駐車場が目に入る。何の装飾も施されていないのは、宗教的に無色でありたいという思惑があってのことなのかも知れない。そして最後、駅員のようないでたちの係員の手によって祖父の遺骨は骨壷の中に収められた。僕にはこれらの光景が、悪趣味な儀式の一部に思われる瞬間がいくつもあった。システマティックに管理された、悪趣味な儀式。日本人の行き着く先がこのような光景であるとは、僕には哀しすぎる。
日本に必要なのは、ミルトン的教育だ。日本は宗教的基盤が脆弱に過ぎる。しかし近ごろでは、宗教というと、イメージが悪い。日本で宗教というと、オウムやアルカイダといった狂信的な宗教集団と結びつきやすい。そのような日本の宗教的な基盤の薄さが、葬儀に露呈している。
僕は以前、カトリックの葬儀にも参列したことがある。僕はどこの宗教にも属していないが、小中学校、高校と、ボーイスカウトに入っており、10年間カトリックの教会に通っていた。だからミサにも数えきれないほど参加したし、クリスマス・パーティにも毎年参加していた。その頃、スカウトの仲間の一人が、病気で亡くなるということがあった。葬儀は教会で執り行われ、僕は仲間のスカウトと共に礼拝に参列した。礼拝は教会の礼拝堂で執り行われ、オルガンの音が静かな流れる礼拝堂で、僕は敬虔な気持になった。
何も西洋の宗教が、日本の宗教より優れていると言いたいのではない。明治の近代化以降、さらには敗戦後のGHQによる統治を経て、日本人は日本の文化、伝統の多くを捨ててきた。それが問題だと言いたいのだ。それは言葉にも言えることである。明治以降、あるいは特に敗戦以降、日本語はそのボキャブラリーが物凄く少なくなった。日本語の語彙の貧しさは、文部科学省が認定している人名に使用できる漢字に、昨年まで「林檎」という漢字が含まれていなかったことが示している。
日本人は伝統を全て切り捨ててきてしまったのだ。それが無機質な火葬場と、告別式にかかるシンセサイザーの音楽が象徴している。無機質な斎場でのシンセサイザーの音楽と、礼拝堂でのオルガンの音。全ては高度成長のため。経済的発展のため。経済的発展のために多くのものを犠牲にしてきたのだ。
物質的に豊かになっていく過程では、無機質な火葬場は、近未来的なテクノロジーの反映として、豊かさとして人々の目に映ったのかもしれない。だが、そのような経済的発展を謳歌していない今の日本では、寒々しく映るばかりである。
日本において現在『失楽園』がそれほど読まれていないとしたら、『失楽園』が、読者が聖書を読んでいることを想定して書かれているからではないか。ミルトンは第7巻31行で、’fit audience (find,) though few’と書いている。日本ではまさに少ない読者になってしまっているのかも知れないが、僕はミルトンが『失楽園』を少ない読者に向かって書いたとは思わない。日本で『失楽園』が読まれないとするなら、それは恐らく日本の宗教的貧しさに根ざしているのである。問題は根深い。
このような日本が宗教的な深みに到達する時が果たしてくるだろうか。そう考える時、僕は、堕落するアダムに説教するラファエルの気持が少しだけ分かったような気になる。僕が今後行っていく活動、例えばいま大学院で文学を研究しているようなことによって、そのような日本の文化的土壌を少しでも豊かなものとすることに貢献できたら、と切に願う。
Notes
[1] ミルトンのテキストも改訂されてきた。中にはリチャード・ベントリー(Richard Bentry, 1662-1742)といったような古典学者が、ミルトンが没して五十年後に、主観的な解釈によって改訂するような事態も起きた。それは次の箇所に表れているという。
彼は思索と勇気を表わすために、
彼女は柔和と魅惑的な優美を表わすために、
彼は神のみのために、彼女は彼の内なる神のために造られた。
(第4巻 297-99)
佐野氏は次のように述べる。
とりわけ299行(He for God only, she for God in him)について、
古典学者リチャード・ベントリーは一七三二年に編んだ『失楽園』の
注釈で、「どの版でも見過ごされてきた誤り。作者は[彼は神のみの
ために、彼女は神と彼のために造られた He for God only, she for
God AND him]と書いていた」と主張した。ベントリーの大胆な改訂
は、女性の男性への依存・従属感を取り除こうとするもので、ミルト
ン批判というよりは、ミルトンを批判から救おうとしたものなのかも
しれない。(佐野 4)
[2] しかし、どうやら、ラファエルは6日目は、天地創造に付き合っていないようだ。
実を言うと、わたしは
あの日には偶々留守をしていた。大部隊で方形の陣を固め
(これがわれわれに課せられた命令だった)、暗澹たる未知の
旅に出、はるか彼方の地獄の門に向かって遠征していた。
神が御業を行っておられる間に、スパイや敵が一人でも
そこから抜け出さないように監視するのが、われわれの任務で
あった。(第8巻 229-35)
ということは、ラファエルは6日目に関しては他の天使、あるいは神から聞いたことになる。
Works Cited
新井 明 『人と思想134 ミルトン』 東京: 清水書院, 1997.
アリストテレス 『ニコマコス倫理学』 朴 一功 訳 京都: 京都大学学術
出版者, 2002.
カレン・アームストロング 『楽園を遠く離れて 「創世記」を読みなお
す』 高尾 利数 訳 東京: 柏書房, 1997.
ジリアン・ビア 『ダーウィンの衝撃』 渡部 ちあき・松井 優子 訳 東
京: 工作舎, 1998.
Gallagher, Philip J. ‘Creation in Genesis and in Paradise Lost.’ Milton
Studies. 163-204.
スティーブン・グリーンブラット 『シェイクスピアにおける交渉』 酒
井 正志 訳 東京: 法政大学出版局, 1995.
The Holy Bible: A Reprint of the Edition of 1611. Oxford: Oxford UP,
1985.
共同訳聖書実行委員会 『聖書 新共同訳』 東京: 日本聖書教会,
1987.
Milton, John. Paradise Lost. 2nd ed. Ed. Alastair Fowler. London:
Addison Wesley Longman, 1998.
—–. 『教育論』 私市 元宏・黒田 健二郎 訳 東京: 未来社, 1984.
—–. 『失楽園(下)』 平井 正穂 訳 東京:岩波書店, 1981.
アレグザンダー・ポウプ 『人間論』 上田 勤 訳 『世界名詩集大成9
イギリス篇 I 』 加納 秀夫 訳者代表 東京: 平凡社, 1959.
佐野 弘子 「ミルトンの女性観・結婚観をめぐる批評」 『神、男、そ
して女 ミルトンの『失楽園』を読む』 辻 裕子・佐野 弘子 編 東
京: 英宝社, 1997. 3-18.
Shakespeare, William. Hamlet, Prince of Denmark Updated Edition. Ed.
Philip Edwards. Cambridge: Cambridge UP, 2003.
—–. 『ハムレット』 松岡 和子 訳 東京: 筑摩書房, 1996.
高橋 康也・河合 祥一郎 註 シェイクスピア 著 『大修館シェイクスピ
ア双書 ハムレット』 東京: 大修館書店, 2001. 84-387.
E・M・W・ティリヤード 『エリザベス朝の世界像』 磯田 光一・玉泉
八州男・清水 徹朗 訳 東京: 筑摩書房, 1992.
Works Consulted
新井 明 『ミルトンとその周辺』 東京: 彩流社, 1995.
新井 明・野呂 有子 編 『摂理をしるべとしてムミルトン研究会記念論文
集』 東京: リ−ベル出版, 2003.
圓月 勝博・小野 功生・中山 理・箭川 修 『挑発するミルトンム『パラダ
イス・ロスト』と現代批評』 東京: 彩流社, 1995.
ヴィクター・ローランド・ゴールド 他 編 『聖書から差別表現をなくす
試行版 新訳聖書・詩編(英語・日本語)』 上沢 伸子 他 訳 東京:
DHC,1999.
平井 正穂 『イギリス文学論集』 東京: 研究者出版,1998.
白鳥 正孝 『ミルトンの思想-『失楽園』を中心に』 東京: 鷹書房弓プ
レス, 2001.
武村 早苗 『ミルトン研究』 東京: リ−ベル出版, 2003.
宇都宮 秀和 『文学と神学の間—ミルトン・言語・聖書解釈をめぐって
—』 東京: 近代文芸社, 2000.


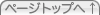
Comments & Trackbacks
Trackback URL http://shakeweb.co.uk/spear/thesis/31.html/trackback