エリザベス朝時代の復讐劇
エリザベス朝時代の復讐劇
シェイクスピア『ハムレット』とトマス・キッド『スペインの悲劇』の比較
Elizabethan Revenge Plays
A Critical Comparison of Hamlet and The Spanish Tragedy
米田 拓男
序
本論で私は、イギリス演劇史における特に復讐劇という視点から、シェイクスピア(William Shakespeare, 1564-1616)の『ハムレット』(Hamlet, ca.1600)という作品がどのような状況の下で書かれたのかを、トマス・キッド(Thomas Kyd, 1558-1594)の『スペインの悲劇』(The Spanish Tragedy, 1587)と比較することによって考察してみたいと思う。そもそも何故、当時多くの復讐劇が書かれた中で、『ハムレット』だけがこれほどまでに上演されることになったのだろう。もちろん、『ハムレット』が優れた作品であることは言うまでもない。そうでなければ、『ハムレット』がグローブ座で初演されてから優に400年以上が経過している現在においてなお、これほど上演され、かつ読まれ続けているはずはない。『ハムレット』が優れた作品であると口にするのは容易い。だが、何故『ハムレット』だけが、という疑問を解くためには、当時のイギリス演劇の状況を考えなくてはならない。同時代の他の作品と比較してみなければ、『ハムレット』という作品が持つ真の価値というものは分からないだろう。
『ハムレット』という作品は、シェイクスピアの想像力によってのみ純粋培養されてこの世に生み落とされた訳ではない。『ハムレット』には材源が存在し、物語の筋の大部分をそれに負っている。なるほど確かにシェイクスピアは、材源であるサクソやベルフォレにはない亡霊や劇中劇といった要素を劇中に新たに導入してはいる。しかしそれらは、『ハムレット』が書かれる以前に、すでにトマス・キッドが『スペインの悲劇』で使用したモチーフだった。『ハムレット』という作品が、歴史から隔絶した真空状態で書かれた訳ではない以上、『ハムレット』がどのような先行作品の遺産を有効利用して書かれているのかということを考察するのには意味があるはずだ。それなくしては、『ハムレット』の価値を本当に理解したことにはならない。シェイクスピアはどのような素材をどのように料理したのか。本論における私の最大の関心はそこにある。
第一章では、エリザベス朝で復讐劇が誕生する過程について論じ、『スペインの悲劇』や『ハムレット』が書かれるに至った背景を説明する。第二章では、『スペインの悲劇』と『ハムレット』の共通点を列挙し、その影響関係について考察する。第三章から以下の三章では、第二章で指摘した、『スペインの悲劇』と『ハムレット』に見られる共通点のうち、「亡霊」(第三章)、「劇中劇」(第四章)、「狂気」(第五章)の三つの要素に焦点を当て、それぞれ一つずつ取り上げて論じたいと思う。果たして『ハムレット』は、『スペインの悲劇』から何ものかを継承しているのだろうか。また、継承しているとしたら『ハムレット』の独自性はどこにあるのか。本論は、その影響関係を、イギリス演劇史における復讐劇の系譜という視点から考察するものである。
第一章 イギリスにおける復讐劇の誕生
本章では、イギリスに復讐劇が現れ、『スペインの悲劇』と『ハムレット』が書かれるに到った背景について見たい。両作に直接的な影響関係はあったのだろうか。つまり、シェイクスピアの『ハムレット』は『スペインの悲劇』の影響下に書かれたと言うことはできるのだろうか。
16 世紀後半のエリザベス朝から、続くジェイムズ一世の時代に、イギリスでは復讐劇が大流行した。それは、ジャスパー・ヘイウッド(Jasper Heywood, 1535-1598)がセネカ(Seneca, ca.4 BC-65 AD)の悲劇を英訳したのを機に始まった。ラテン語から英訳されたセネカの戯曲は、人々に広く読まれるようになり、この時期に書かれた悲劇はその影響を受けることになった。そのため必然的に、この時代の悲劇には復讐がモチーフとして多く取り入れられた。例えば、1558-61年には、セネカの『テュエステス』(Thyestes)が翻訳された。これは、自分の女房を誘惑したとして、その男(実弟)の子供を殺し、その肉を料理して男に食べさせるという、アトレウス一家の悲劇を描いた話で、シェイクスピアの『タイタス・アンドロニカス』(Titus Andronicus, ca.1589)の種本のひとつと看做されている。[1] それと前後してセネカの『トロアス』(Troades)と『怒れるヘラクレス』(Hercules furens)が出版された。1561年には、セネカの影響色濃い、親子間の復讐を扱った、一般に英語による最初の悲劇と看做されている『ゴーボダック』(Gorboduc)が書かれた。[2] 1566年には、セネカの『アガメムノンの悲劇』(Agamemnon)が英訳され、ジョン・ピカリング(John Pickering, 1544-96)はそれを種本として『ホレステス』(Horestes)(1567年)を書いた。[3] 他にトマス・プレストン(Thomas Preston, 1537-98)『カンビュセス』(Cambises, 1569)と恐らくリチャード・バウワー(Richard Bower, d.1561)によって書かれた『アピウスとヴァージニア』(Appius and Virginia, ca.1567)も、『ホレステス』と同様に寓意を用いた道徳的インタールードであり、セネカの流血悲劇を思わせる題材を扱っている(中村 125)。そして、1581年には、『セネカの悲劇十篇』(Seneca’s Tragedies)が『ゴーボダック』の作者の一人であるトマス・ノートンの編集によって出版された。
だが、これらセネカの、あるいは、セネカ風の悲劇と、『スペインの悲劇』との間には、大きな差異があった。セネカの劇は、恐らく朗読用、あるいは読書の目的ために書かれている。『ゴーボダック』や『ホレステス』なども、いわゆる書斎劇(closet drama)として書かれた。こういった作品では、残酷な場面がすべて登場人物の台詞によって語られ、決して舞台上で展開されることはない。だが、キッドは、そういった場面を実際に舞台の上に再現してみせた。『スペインの悲劇』は、イギリスにおいて、初めて舞台上で殺人が描かれた作品なのだ。それは、当時、とても斬新なものだった。
『スペインの悲劇』の初演がいつだったか、はっきりしたことはわかっていないが、1587年頃とする説が有力である。[4] また、その年かあくる年にはクリストファー・マーロウ(Christopher Marlowe, 1564-1593)の『タンバレイン大王』(Tamburlaine the Great, 1590)が初演されたようだ。[5] 『スペインの悲劇』は、1592年の四つ折り版から、1633年の四つ折り版に至るまで、現存するテキストだけでも十版を重ねた(佐野 3)。そのことから、当時大変な人気を獲得していたことがうかがえる。
エリザベス朝の人々は、血の気の多い享楽を求めていた。熊いじめ、牡牛いじめなどといった見せ物は、いつも大変に人気があったし、絞首刑、斬首刑、八裂きの刑などの処刑には、たくさんの見物人が群がった。そのような背景も、『スペインの悲劇』に続く復讐劇の流行と無縁ではないだろう。ロンドン市当局は、市内に公開劇場を建設することを許さなかったが、この時期の演劇を、ピューリタンが支配していた市当局が気に入らなかったのも、当然だったと言えるかもしれない。結局、1642年に、ロンドン市郊外にあった全ての劇場は、議会によって閉鎖されてしまう。
『スペインの悲劇』の成功を受けて、その後クリストファー・マーロウが『マルタ島のユダヤ人』(The Famous Tragedy of the Rich Jew of Malta, 1589)を書く。そして、それと同じ頃、シェイクスピアは『タイタス・アンドロニカス』を書いた。[6] シェイクスピアは、『タイタス・アンドロニカス』を書くにあたって、セネカの劇に影響を受けながらも、キッドが『スペインの悲劇』でそうしたように、セネカでは描かれなかった残酷な場面を、実際に舞台上に再現した。1600年頃、『ハムレット』とほぼ同時期には、ジョン・マーストン(John Marston, 1576-1634)が、『アントニオの復讐』(Antonio’s Revenge)を書いた。[7] 『アントニオの復讐』は、『スペインの悲劇』が切り開いた復讐劇を、さらに残酷化したと言える作品である。そして、1601年に、シェイクスピアの『ハムレット』が登場する。[8]
以上が、イギリスに復讐劇が誕生してから『ハムレット』が書かれるまでのおおよその過程である。消失した作品もあるだろうが、数としてそれほど多くはない。そのことから言えるのは、『ハムレット』がイギリスにおける「復讐劇の伝統」に基づいて書かれたというのが、誤解であるということだ。『ハムレット』が当時流行していた復讐劇の伝統を利用していたという記述をしばしば目にすることがある。[9] しかし『ハムレット』は、イギリスの復讐劇の伝統の中から生み出されたものではない。河合祥一郎が次のように指摘しているように、むしろ、その後に続く復讐劇の伝統を作り出した作品なのである。
フレッドソン・バワーズは名著『エリザベス朝の復讐悲劇』の中で、真に「復讐悲劇」と呼べる一連の人気エリザベス朝悲劇の流れはキッドの『スペインの悲劇』から始まると言明しているが、『スペインの悲劇』上演の1589 年頃から『ハムレット』上演の1601年頃までに書かれた復讐劇の数が少ないことを鑑みても、『ハムレット』が「復讐劇の伝統」の中で書かれたものではないことがわかる。むしろ『ハムレット』はその後に続々と書かれた復讐悲劇の原型なのであって、「復讐劇の伝統」とはむしろ『スペインの悲劇』や『ハムレット』を嚆矢として生まれ始めたものなのだ(河合 148)。
『ハムレット』以前に書かれた復讐をモチーフとした作品、つまり「復讐劇」は、先に挙げた通りであるが、舞台用に書かれた「復讐悲劇」ということになると、『スペインの悲劇』と『タイタス・アンドロニカス』くらいしかない。『スペインの悲劇』以降に書かれた「復讐劇」には『タンバレイン大王』や『アントニオの復讐』があるが、主人公が生き残るので悲劇には当てはまらない。『ハムレット』以前に書かれた「復讐悲劇」の数がそれほど多くなかったという事実は、両作品の近似をより強く印象づける。次章で述べるように、両作品には偶然とは言えないほどの多くの類似点があるのだ。
トマス・キッドはセネカの影響下に、『スペインの悲劇』という独自の復讐劇を生み出した。そしてシェイクスピアは恐らく当時、画期的に目新しい芝居だった『スペインの悲劇』の影響の下に、『ハムレット』を書いた。その『スペインの悲劇』初演から『ハムレット』初演に至る十数年間に作られた復讐劇の型が、その後、シリル・ターナー(Cyril Tourneur, ca.1575-1626)や、ジョン・ウェブスター(John Webster, 1580-1630)といった劇作家たちの作品に受け継がれていったのである。
第二章 『スペインの悲劇』と『ハムレット』に見られる共通点
『ハムレット』には、『スペインの悲劇』の影響を受けて書かれたことを伺わせるような、多くの類似点がある。[10] 以下にその共通点と、差異を列挙してみたいと思う。
1、復讐劇である、ということ。そしてその復讐は、復讐者よりも身分の高い者に対して果たされるということ。『ハムレット』と『アントニオの復讐』は、王子から王への、『スペインの悲劇』と『タイタス・アンドロニカス』は、家臣から王への復讐であり、いずれにおいても、国王に対して復讐が果たされる。
2、肉親の情に基づく復讐。子の死に対する父親の復讐(『スペインの悲劇』、『タイタス・アンドロニカス』)、あるいは、父の死に対する子の復讐(『アントニオの復讐』、『ハムレット』)。
3、亡霊が登場する(『スペインの悲劇』、『マルタ島のユダヤ人』、『アントニオの復讐』、『ハムレット』)。
4、殺人が秘密にされていること(『スペインの悲劇』、『ハムレット』)。
5、狂気。復讐へと向かう過程で、復讐者は、狂気を装おう(『スペインの悲劇』、『タイタス・アンドロニカス』、『アントニオの復讐』、『ハムレット』)。
6、ホレイショという名前の主要人物が登場する(『スペインの悲劇』、『ハムレット』)
7、禁じられた恋のモチーフ。『スペインの悲劇』では、プリンセス(ベル=インペリア)と家臣の息子(ホレイショ)の恋であるのに対して、『ハムレット』では、プリンス(ハムレット)と家臣の娘(オフィーリア)の恋。
8、芝居好きな主人公(『スペインの悲劇』、『ハムレット』)。
9、劇中劇を伴う(『スペインの悲劇』、『ハムレット』)。
10、復讐を果たした直後に主人公が死ぬこと(『スペインの悲劇』、『タイタス・アンドロニカス』、『ハムレット』)。[11]
両作品にはこのように多くの共通点があるが、『ハムレット』と『スペインの悲劇』の繋がりは、ここに揚げたような作中の諸要素に留まらない。『スペインの悲劇』の作者トマス・キッドは、シェイクスピアの『ハムレット』の種本であると考えられている、『原ハムレット』(Ur-Hamlet)の作者であるとも言われているのだ。『原ハムレット』とは、シェイクスピアの『ハムレット』が初演されたと推定されている1600-1年以前に上演されていたらしい『ハムレット』と呼ばれる作品で、いくつかの記録以外、その存在は確認されていない。ハロルド・ブルーム(Harold Bloom)は、『原ハムレット』はシェイクスピア自身が書いたものであると論じており、[12] イアン・ウィルソン(Ian Wilson)も同様の考えを示唆している。ウィルソンは次のように記す。
一般的な見方としては、この『原ハムレット』の作者はトマス・キッドで、彼の最大のヒット作、『スペインの悲劇』と同種の劇と考えられているが、シェイクスピアの同僚の役者ケンプ、ブライアンなどの一座が、かつて1586 年、ハムレットのエルシノア城を訪れたことを想起すれば、この古い劇を書いたのは若いシェイクスピア自身で(この旧作は存在しないが)1599年から 1600年になって全面的に改訂し、この時期の彼にふさわしい成熟した作品に仕上げたということも、キッド説と同様、十分ありうることではないだろうか。
(ウィルソン 619)
シェイクスピアは1585年の段階で、息子をHamnetと名付けている。そのことも考え合わせると、シェイクスピアがその頃から劇作品としての『ハムレット』を構想しており、『スペインの悲劇』の成功に影響されつつ劇の構想を発展させていったという可能性もあり得なくはない。[13] 一方、ウィリアム・エンプソン(William Empson)は『原ハムレット』をもとにキッドが書き上げたのが『スペインの悲劇』だったと考えている(Empson 69)。ハロルド・ジェンキンズ(Harold Jenkins)も同意見である(Jenkins 97-101)。
『原ハムレット』を書いたのが誰か、今となっては知る由もないが、いずれにせよ、『ハムレット』が、12世紀末のデンマークの歴史家で詩人のサクソ=グラマティカス(Saxo Grammaticus)が書いた年代記『デンマーク史』(Historiae Danicae)を材源としているのは間違い無い。サクソの年代記は1514年に初めて印刷され、その後フランスで、ベルフォレ(Francois de Belleforest)がフランス語に翻訳した。そのフランスでの出版が、1570年である。そしてそれが英訳されたのは、1608年なので、英訳をシェイクスピアが参照したことはあり得ない。[14] しかし、シェイクスピアが、間接的にせよ、サクソに材源を負っていることは確かだ。何故なら『ハムレット』は、その物語の大筋をサクソと共有しているからだ。言うまでもなく、『ハムレット』の材源は、『スペインの悲劇』ではなく、サクソの年代記である。そして、シェイクスピアはその年代記に、いくつかの大きな変更を加えている。以下に揚げたのは、New Cambridge版『ハムレット』の編者フィリップ・エドワーズによる、サクソの年代記から『ハムレット』に加えられた変更点のリストである。そのまま書き出してみる。
『ハムレット』に見られる最も重要な変更点は、以下の通りである。
1、殺人が秘密のものとなった。
2、亡霊がハムレットに、殺人があったことを告げ、復讐するように言う。
3、レアティーズとフォーティンブラスが登場する。
4、オフィーリアの役が大きくなり、重要なものとなった。
5、役者たちと、彼らが上演する劇が登場する。
6、ハムレットは、王を殺す時に死ぬ。(Edwards 2)
これらの改変箇所を、『スペインの悲劇』と比べてみたい。このうち、3番目と4番目は、『ハムレット』の登場人物に関するものなので除外するが、[15] それ以外の、1、2、5、6番は、全て、『スペインの悲劇』と共通する要素である。『スペインの悲劇』では、ホレイショの殺人は隠されており(1)、亡霊が登場し復讐の神に復讐を懇願し(2)、ヒエロニモやベル=インペリアたちによって演じられる劇中劇が導入され(5)、復讐者は復讐を遂げる時に死ぬ(6)。この四つの要素は、サクソの材源に加えられた改変であるが、このように全て『スペインの悲劇』に含まれている。このことを鑑みると、サクソの年代記に、『スペインの悲劇』に見られるいくつかの重要な要素が加えられたものが『ハムレット』であると、ひとまず言うことが可能だろう。
次章からの三章では、本章で指摘した、『スペインの悲劇』と『ハムレット』に見られる共通点について、「亡霊」(第三章)、「劇中劇」(第四章)、「狂気」(第五章)にそれぞれ焦点を当てて、具体的に論じたいと思う。『スペインの悲劇』と共通する要素が、『ハムレット』ではどのように扱われているのだろうか。それを比較することによって、『ハムレット』の独自性を明らかにしていきたい。
第三章 亡霊
この章では、「亡霊」に焦点を当てて、『スペインの悲劇』と『ハムレット』を具体的に比較する。『スペインの悲劇』でも『ハムレット』でも、劇の冒頭に亡霊が登場する。今幕を開けたばかりの劇は、彼ら亡霊のために果たされる復讐の過程を描いていくこととなる。つまり、物語が始まる以前に肝心な殺人行為は行われているのだ。しかし、両作品では、その復讐の性質に差異がある。『ハムレット』の場合は、ハムレットは劇の冒頭に登場する亡霊に促され、復讐に赴くことになる。しかし、『スペインの悲劇』の場合はそうではない。『スペインの悲劇』では、冒頭に登場するアンドレアの亡霊は、物語の主人公であるヒエロニモに直接働きかけることはできない。アンドレアは、自分の命を奪ったバルサザーに対する復讐を誓うが、彼は、ギリシア悲劇のコロスのように、ヒエロニモが息子ホレイショのために復讐を遂げるのを、ただ傍観していることしかできないのである。[16] 『スペインの悲劇』では、バルサザーへの二重の復讐が描かれている。アンドレアの、自らを殺害されたことに対する復讐と、ヒエロニモの、息子が殺されたことに対する復讐である。そして物語は後者の復讐を軸に進展し、前者の復讐が、物語の本筋に影響を与えることはない。アンドレアの復讐は、ヒエロニモの復讐が果たされる時に、副次的に果たされることになる。
シェイクスピアは、『ハムレット』にサクソの年代記にない亡霊を登場させたが、物語が始まる以前のこの殺人について、ある改変を行っている。前章で揚げたフィリップ・エドワーズのリストの1 番目にあるように、殺人を秘密のものにしたのである。復讐劇における復讐は、遅延させられねばならない。何故なら、復讐こそが究極的な目的である復讐劇においては、復讐が果たされれば、劇が終わってしまうからである。そのため作者は、復讐をいかに遅らせるか、ということに知恵を絞ることになる。シェイクスピアが前王ハムレットの殺害を秘密のものとしたことは、サクソの復讐物語に、ミステリーの要素を加味することとなった。『スペインの悲劇』でも、ホレイショの殺害の真相は、隠されている。これは、復讐の遅延のための知恵なのである。観客は、主人公と共に事件の真相に近づいていく。『スペインの悲劇』と『ハムレット』で、作者は、現代の推理小説と同じテクニックを用いているのだ。
そのテクニックを見てみよう。『スペインの悲劇』では、ホレイショの殺害の真相は、ヒエロニモのもとに、まず、ベル=インペリアの手紙によって告げられる。殺害されたホレイショの恋人であったベル=インペリアが、肉親の情に背いて、兄とポルトガル王子を告発し、ヒエロニモに復讐を促す。『ハムレット』においては、隠された殺人に関する最初の情報は、亡霊によってもたらされる。ハムレットは、目の前で実の父親の亡霊に事の真相を明かされ、クローディアスに復讐を果たすよう請われるのだ。しかし、用心深いヒエロニモとハムレットは、にわかにそれ(ヒエロニモはベル=インペリアからの手紙、ハムレットは亡霊の言葉)を信じることができない。そのため両者は、しばらく様子を伺うことになる。
『スペインの悲劇』において、隠された殺人が真実であったことの確信をヒエロニモにもたらすのは、ホレイショ殺害を手伝った手下ペドリンガーノが、主人のロレンゾーに宛てて書いた手紙である。手紙によって真相を知ったヒエロニモは、ベル=インペリアからの手紙が真実を告げていたことを知る。ヒエロニモは、物語の中盤を過ぎたところで、初めて復讐を心に誓うことになる。『ハムレット』の場合はどうだろうか。『ハムレット』では、ミステリーが解きあかされていく段階で、これよりももっと複雑な手続きが踏まれている。『スペインの悲劇』においてヒエロニモは、事件の真相を、手紙を受け取ることによって偶然知ることになる。それに対してハムレットは、亡霊の言っていることが正しいのか確かめるために、自ら積極的に行動に出ることになる。王の面前で、その罪を告発するような内容の劇を上演しようと試みるのである。『スペインの悲劇』では、ホレイショの殺人は、舞台上で描かれているので観客はそれを目撃しているが、『ハムレット』においては、前王の殺害は亡霊の台詞の中でしか描かれない。そのため、『ハムレット』の観客は、『スペインの悲劇』の観客と異なり、事件の真相を知ることができない。観客は、ハムレットと一緒になって、謎を解きあかしていくことになるのだ。
ヒエロニモは、ベル=インペリアからの手紙を信じることができなかったが、それは、その手紙は直接ベル=インペリアから貰ったものではなかったので、ヒエロニモを陥れるための罠である可能性があったからだ。それでは、『ハムレット』ではどうか。ハムレットが亡霊の言葉を信じることができないのは、キリスト教の教義に関わる問題である。カトリック信仰においては、幽霊は煉獄からやってくる死者の霊であると考えられる。それに対して、プロテスタントでは、幽霊は悪魔の手先と考えられる。『ハムレット』が書かれた当時のイギリスは、宗教的に不安定な時期にあった。カトリックを信奉したヘンリー七世によって開かれたテューダー朝のイギリスは、次代のヘンリー八世に到り、離婚問題をきっかけにイギリス国教会が作られ、王室はプロテスタントを奉じるようになる。しかし次代メアリ一世によって、一転、カトリックへの反動政策が急進的に押し進められ、エリザベス一世の時代に、再びプロテスタントが国教となった。『ハムレット』は、イギリスがこのような一連の宗教的な混乱を、ようやくくぐり抜けた時代に書かれた作品である。もちろん、『ハムレット』の物語の舞台は12 世紀のデンマークであると設定されてはいる。しかし、12世紀には存在しなかったはずのウィッテンバーグ大学(1502年創立)が作中に登場したり、 1600年頃のロンドンの劇場の状況を反映した台詞があったりと、シェイクスピアが具体的に頭の中に思い描いていたのは彼が生きていたイギリスに近い。『ハムレット』が上演された当時のイギリスの観客にとっては、亡霊を死者の霊と見るか、悪魔の手先と見るかといった判断は、デリケートな問題を孕んでいた。そのような時代にあって、ハムレットは、亡霊が本物の父親の霊であるのか、ハムレットを陥れようとする悪魔の手先なのか、見極めることができない。この点において、『ハムレット』は、ミステリーとして高度なクオリティを誇ることになる。『アントニオの復讐』にも、ハムレットと同様に、父親の亡霊が息子を復讐へと駆り立てるために姿を現すが、アントニオは、亡霊の言うことをつゆにも疑わず、復讐へと赴く。そこでは『ハムレット』にあるようなミステリーが生成することはない。
さらに、ハムレット自身は、クローディアスが前王を殺害したという客観的な証拠を、結局、最後まで手に入れることができないのだ。『スペインの悲劇』では、亡霊が最後に登場し、復讐が果たされたことを観客の前で確認する。しかし『ハムレット』では、亡霊は居室の場以降登場しない。観客は、クローディアスが自らの罪を告白するのを聞いているので、クローディアスの罪を疑うことはないが、ハムレット自身は、「ねずみ取り」の上演の際、クローディアスが慌ただしく席を立ったという事以外、クローディアスの罪を確信する客観的な証拠を得ることはない。『ハムレット』の最後に亡霊が登場しないことは、『ハムレット』が持つ、ミステリーとしての効果を高めることに貢献している。
シェイクスピアは、『スペインの悲劇』でコロス的な役割を演じていたに過ぎなかった亡霊を直接物語に絡ませて、高度なミステリーをつくり出した。その結果、『スペインの悲劇』のヒエロニモに比べて、ハムレットの逡巡が、遥かにスリリングなものになったと言えるだろう。
第四章 劇中劇
本章では「劇中劇」を中心に、引き続き両作品の比較を試みたい。『スペインの悲劇』と『ハムレット』に登場する二人の復讐者、ヒエロニモとハムレットは、ともに芝居好きな人物として描かれている。ヒエロニモは、若い時分に劇を書いていたと言う。「私は若いころ一所懸命、ものにもならない詩劇を書きましてね。」(キッド 49)ハムレットは、旅回りの役者たちの前で、演劇論をぶってみたり台詞を暗唱してみせたりする(第2幕第2場、第3幕第2場)。そして二人とも、復讐の目的のために芝居の上演を企画する。ただ上演するだけではない。二人とも、芝居の台本の作成に関わっているのだ。ヒエロニモが上演する劇は、昔、ヒエロニモ自身が書いた悲劇であり、ハムレットは、上演する芝居「ねずみ取り」に、自分が考えた台詞を十五、六行、付け加えるように言う(第2幕第2場531行)。このような劇中劇の導入は、この二つの作品に、複雑な劇構造をもたらすこととなった。
その構造を『スペインの悲劇』から見ていきたい。『スペインの悲劇』では、冒頭に亡霊のコロスが登場し、劇中で展開されていく出来事を、亡霊が観客と共に見守っていくというフレームが示される。これから物語の中で展開される出来事を、亡霊たちが見、さらにそれを観客が見ることになる。そして、劇の最後にも亡霊たちが登場し、彼らが物語の幕を引く。『スペインの悲劇』は、劇全体が、亡霊のコロスの視点という大枠の中に、すっぽりと収まっている。亡霊たちは、最初と最後だけでなく、劇の合間にも度々登場し、そのフレームを確認する。
そのような入れ子構造の中に、終幕、ヒエロニモが劇を上演することによって、さらにもう一つの入れ子構造が加えられる。劇中劇の登場人物たち(パシャ、パーシダ、エラスタス、ソリマン)がいて、それをヒエロニモたちが演じている。そしてその演技を、スペイン王たちが見ていて、その光景を見守る亡霊たちがいて、さらに私たち観客がそれを観ているのである。
劇中劇の登場人物(パシャ、パーシダ、エラスタス、ソリマン)
↑
ヒエロニモ、ベル=インペリア、ロレンゾー、バルサザー (act)
↑
スペイン王、ポルトガル王たち (see)
↑
アンドレアの亡霊、復讐の霊 (see)
↑
観客 (see)
劇中劇の中で復讐を遂げたヒエロニモは、最後、観客であるスペイン王たちに向かって語りかける。
皆さん方はたぶん、いまの芝居はただの絵空ごとだ、俳優たちもふつうの悲劇役者と同じことをしただけだと、お考えでしょう。(中略)すぐまた息を吹き返して立ち上がり、あすの観客を楽しませるのだ、と。でもいま、それはあてはまらないのです。ちがうのです、王様方。
(キッド 48)
確かに、劇中劇の芝居を演じる、バルサザーやロレンゾーやベル=インペリアという役の人物たちは、物語の中では本当に死ぬ。しかし、もちろん、彼らは俳優によって演じられているのである。そして当然ながら、これらの人物を演じる俳優たちは、本当に死ぬわけではない。つまり、ヒエロニモたちが使う剣は、彼らが属する劇の次元では本物の剣であるが、観客が属している現実世界の次元では、舞台上の小道具に過ぎない。喜志哲雄は以下のように記す。
よほど血のめぐりの悪い観客でなければ、ハイエローニモーの台詞は芝居の嘘にわざと観客の注意を引きつける効果をもっていることを悟るに違いない。これは、あることを語りながら、同時にそれが虚偽であることを認めている台詞なのである。(喜志 24)
氏は、『スペインの悲劇』にこのような劇構造が取り入れられたことによって、芝居の嘘が強調される結果になったと指摘する。このことは、これが、舞台上で初めて殺人が描かれた劇であることと、関係があるように思える。『スペインの悲劇』は、ローレンス・スターン(Laurence Sterne, 1713-68)の『トリストラム・シャンディ』(The Life and Opinions of Tristram Shandy, 1759 -67)のように、それが語られているメディアそのものに強く意識的な芝居である。スターンが『トリストラム・シャンディ』を書いたのは、イギリスの近代小説がようやく完成した頃である。『スペインの悲劇』は、イギリス中世の聖史劇、道徳劇の時代を経て、ようやく演劇が大衆のものとなった時期に書かれた。ある表現手段の黎明期にそのメディアに自覚的な作品が登場するということは興味深い。いずれにせよ、この劇は舞台上で殺人を描く初めての作品だったため、キッドは、芝居というメディアに対して、極度に意識的にならざるを得なかったのではないだろうか。
では、『ハムレット』でシェイクスピアは、どのように劇中劇を使用しているのだろう。もうキッドと同じ手は使えまい。シェイクスピアは『ハムレット』で、『スペインの悲劇』の応用/発展型ともいえる劇中劇の使い方をしている。だが、『ハムレット』の劇中劇の場面を見る前に、ここで『ハムレット』第2 幕第2場443-509行の、旅回りの役者たちがトロイ落城の台詞を語る場面を見たい。役者たちがエルシノア城に到着して、ハムレットの前にやってくる。ハムレットは、彼が気に入っているアイネーアスがダイドーに語る、トロイア陥落の場面の台詞を暗唱し始める。そしてその途中で、台詞は役者1に引き継がれる。ハリー・レヴィン(Harry Levin)は、The Question of Hamletの中の一章で、このハムレットと役者が語る台詞を細かく分析している(Levin 138-164)。その中でレヴィンは、この語りが持つ、複雑な入れ子構造について触れている。『ハムレット』では、劇中劇の場だけでなく、ここでも複雑な入れ子構造が使用されている。順番に見ていきたい。まず、父アキレウスの仇を討とうと、トロイア王プライアムに斬り掛かる復讐者ピラスがいる。そしてその戦いをプライアムの妻ヘキュバが見ている。さらに、それを天上から神々が見下ろしている。そのことをアイネーアスがダイドーに語っているのである。そして、その語りを、ハムレットと役者が語っており、その光景を、ポローニアスをはじめとした周りにいる者たちが見ている。そして最後に、それを私たち観客が見ているのだ。図にすると以下のようになる。
ピラス→プライアム(kill)
↑
ヘキュバ(see)
↑
神々(see)
↑
アイネーアス→ダイドー(narrate)
↑
ハムレットと役者1(act)
↑
ポローニアスたち(see)
↑
観客(see)
このように、この語りは複雑な入れ子構造を持っているが、それは、次に見る劇中劇の場面にも当てはまる。同様に、順を追って説明したい。まず、劇中劇の中の登場人物たち、王と王妃、ルシアーナスがいる。そして、その役を演じている旅回りの役者たちがいる。そしてこの場に招かれ、観劇しているクローディアスとガートルードがおり、ハムレットは、その二人が芝居を観る様を観察している。そして、それだけに留まらず、後ろの陰で、ハムレットに頼まれたホレイショが、それを見張っている。さらには、この場面には登場しないが、プライアムに斬り掛かるピラスを神々が見ていたのと同様に、ハムレットの父親の亡霊がこの場を煉獄から見ているかもしれない。そしてそれを、私たち観客が観ているのだ。まとめると以下のようになる。
劇中劇
↑
役者たち (act)
↑
王と王妃 (see)
↑
ハムレット (see)
↑
ホレイショ (see)
↑
亡霊 (see)
↑
観客 (see)
『ハムレット』の劇中劇は、入れ子構造としてはトロイ落城の語り(player’s speech)ほど複雑ではない。だが、この劇中劇をさらに複雑なものにしているもう一つの要素がある。それは、場面の焦点の問題である。『スペインの悲劇』の劇中劇の場では、場面の焦点、つまり、観客が一番意識を向けている場所は、ヒエロニモたちが演じている劇中劇の舞台上にあった。その光景を傍観しているスペイン王たちや、亡霊たちに観客の意識が集中することはない。また、先のplayer’s speechにおいても、途中、ポローニアスやハムレットが言葉を差し挟むことはあるが、場面の焦点は、あくまで台詞を語っているハムレットや、役者にある。この場面で観客は、台詞を語っているハムレットや役者に意識を集中しているはずだ。ところが、『ハムレット』の劇中劇の場では、場面の焦点は、実は劇中劇の舞台上にはない。観客の意識が集中するのは、演じられている劇中劇の舞台上ではなく、むしろ、それを観ている王と王妃であり、二人を観察しているハムレットの方である。シェイクスピアもそのための工夫をしているように思われる。ここで演じられている劇中劇の王と王妃の台詞では、観客の意識を強く引くような表現は、故意に避けられている。古めかしい擬古文で語られており、語られている内容には、特別、目を引くようなアクションもない。ここでは、明らかに劇中劇より、それを観ているハムレットたちの方に焦点がある。
キッドは『スペインの悲劇』のクライマックスにおいて、演劇というメディアそのものを吟味し直すような、先鋭的な劇中劇を使用した。シェイクスピアは物語の中盤で、観客の焦点を「ねずみ取り」の劇そのものから、それを観る登場人物たちへとずらすことによって、劇中劇を背景的に用いた。『ハムレット』におけるこのような劇中劇の使用は、『スペインの悲劇』がなかったら存在し得なかっただろう。シェイクスピアは『ハムレット』において、『スペインの悲劇』の劇中劇の場で学んだものを、応用/発展させたと言えるのではないか。前章と本章で扱った「亡霊」、「劇中劇」という二つの要素は、サクソの年代記には見られないものである。シェイクスピアは「亡霊」と「劇中劇」という二つの大きな道具立てを、『スペインの悲劇』から継承しながらも、大きく発展させて、独自のものとしたのである。
第五章 狂気
本章では『ハムレット』と『スペインの悲劇』の共通点のうち、「狂気」について考察したい。ヒエロニモとハムレットは共に復讐者であり、復讐に至る過程で狂気を装うことになる。だが何も復讐劇における狂気は『スペインの悲劇』と『ハムレット』に限った話ではない。『タイタス・アンドロニカス』のタイタスや『アントニオの復讐』のアントニオも、同様に狂気を装う。狂気には、悪の犠牲者としての、また同時に悪の告発者としてのイメージがある。主人公の怒りが狂気として発現するのだ。狂気は、セネカの劇にも見られる、古典的ともいえる復讐者のイメージである。『ハムレット』の材源となったサクソの物語でも、アムレスは、狂気を装う。
そして彼は偽りの愚かさを装い、知性が完全に欠けている振りをした。この狡猾な策略は、彼の知性を隠しただけでなく、彼の身の安全を確保することにもなった。(Saxo 103)
復讐劇の主人公たちは、何故、狂気を身に纏わなくてはならないのだろうか。もちろんそれは、復讐を達成するために相手を油断させるための一つの手段である。しかし、ハムレットとヒエロニモには、狂気を演じているという範囲を超えて、本物の狂気に取り付かれてしまったと思えるようなところがある。それは例えば、次のような箇所である。『スペインの悲劇』における、ヒエロニモが、息子を失った老人を失った息子ホレイショと間違える場面や(第3幕第13場)、『ハムレット』における居室の場で、ハムレットが、ガートルードに詰め寄り、ポローニアスを刺し殺し、亡霊を見るような箇所である(第3幕第4場)。
二人は何故、狂気の縁にまで向かわなくてはならなかったのだろうか。さらには何故、復讐者は伝統的に狂気を纏うことになるのか。そのことについて考えるにあたって、アリストテレスによる悲劇の定義について見ておきたい。アリストテレスは『詩学』の中で、悲劇を次のように定義している。
悲劇とは、一定の大きさをそなえ完結した高貴な行為、の再現(ミメーシス)であり、快い効果をあたえる言葉を使用し、しかも作品の部分部分によってそれぞれの媒体を別々に用い、叙述によってではなく、行為する人物たちによっておこなわれ、あわれみとおそれを通じて、そのような感情の浄化(カタルシス)を達成するものである。
(アリストテレース 34)
アリストテレスによれば、悲劇とは、一定の大きさをそなえ完結した「高貴な」行為の再現でなくてはならない。復讐劇においては、この「高貴な」という箇所が問題を孕むことになる。ハムレットは、そしてヒエロニモは、果たして高貴であるといえるのだろうか。
西欧において復讐者とは、本来的に犯罪者と同義である。何故なら、キリスト教では復讐は認められていないからだ。聖書「ローマの信徒への手紙」第12章第19節には、次のようにある。
愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。「『復讐はわたしのすること、わたしが報復する』と主は言われる」
復讐劇の主人公は、それをアリストテレスが言うような悲劇として成立させるためには、高貴な状態を保ったまま、復讐を成し遂げなければならないという、二律背反した課題を背負うことになるのだ。[17] シェイクスピアとキッドがアリストテレスを気にしていたと言うつもりはないが、復讐劇の主人公が伝統的に狂気を纏ってきたのは、ひとつには主人公である復讐者に、悲劇の主人公としての高貴さが必要だったからではないか。悲劇の主人公としての高貴さを幾分かでも保つためには、狂気が必要だったのだ。つまり、気が狂っていれば、それは本人の理性とは関係のない行為ということになるので、悪の行為が容認される素地を作ることになるのだ。もちろん、エリザベス朝演劇には、『リチャード三世』や、『タンバレイン大王』といった、悪人を悪人として描いて観客を楽しませる劇は存在した。しかし、復讐劇における悪人は、復讐される者としてすでに存在している(例えば、クローディアスや、ロレンゾー、バルサザーなど)。復讐者は、復讐を達成するまでは犯罪者ではない。悪に立ち向かう正義が、復讐を達成する瞬間に悪人になるのだ。その時に観客の共感を引き離さないためには、工夫が必要になる。
『ハムレット』にも、そのような、復讐者=犯罪者となるハムレットから、観客の共感を引き離さないようにする作者の意図を垣間見ることができる。『ハムレット』には、ハムレットが悪の側に近付く瞬間がいくつかある。それは例えば、次のような箇所である。ハムレットは第五独白で次のように言う。
夜もふけた、いまこそ魔女どもがうごめき出し、
墓が口を開いて地獄の毒気をこの世に吹きこむ時刻。
いまならおれも人の生き血をすすり、昼日中には
目にするだけでふるえおののくような残忍な所業を
やってのけることもできよう。(第3幕第2場349-353行)
もうひとつの例は、クローディアスが自らの罪を告白する祈りの場で語られる第六独白からのものである。その独白の中でハムレットは、クローディアスをきちんと地獄にたたき落とすために、今は復讐するのをやめておこうと言う。
やつが飲んだくれて
眠りほうけるときもあろう、怒りにわれを失うとき、
あるいは邪淫の床に快楽をむさぼるときもあろう、
賭博にふけるとき、ののしりあうとき、いつでもいい、
救いようのない罪業にうつつを抜かすときこそ
やつを突き落としてやる、その踵が天を蹴り、
その魂が地獄へとまっさかさま、たちまち地獄の
どす黒さに染まるように。(第3幕第3場89-95行)
この独白は、ジョンソン博士(Samuel Johnson, 1709-1784)をはじめとする18世紀の批評家たちに、「恐ろしすぎて、読むのも口にするのも憚られる」と、衝撃を与えたらしい(野島 191)。これら二つの独白は「ネズミ取り」の成功によって、ハムレットが強い興奮状態にある時に語られるものだ。ワトソンは、ここには「示唆に富むパターン」があるという。「ハムレットが自らを復讐者であると明確に認識する際には、シェイクスピアは彼を何らかの感情的な緊張状態に置いている」という(ワトソン 70)。ポローニアスの刺殺についても同様のことが言える。居室の場において、ハムレットは明らかに冷静さを失っている。シェイクスピアは、ハムレットの冷静さを失わせ狂気に近付けることによって、ハムレットから悲劇の主人公に足る高貴さを完全に失わせてしまわないように気を配っている。
このように狂気の縁に追い詰められながら、復讐劇における復讐者たちは、最終的に見事に復讐を果たす。復讐劇の主人公たちは復讐を遂げて、ついには犯罪者となる。そして、死を迎える。復讐劇が悲劇としての「高貴さ」を獲得するために、復讐者は、復讐が達成された暁には必然的に死ななければならないのだ。
ここで、ヒエロニモとハムレットの、復讐から死に至る過程を検証してみたい。ハムレットは、フェンシングの試合でレアティーズの毒を塗られた剣に傷ついた後、その剣でクローディアスを刺し、突発的に復讐を果たす。まさに激情にかられた形で。それに対しヒエロニモは、冷静に計画を練り、その計画通りに復讐を達成する。その計画は、狂気とは対極にある理性によって生み出されたものだ。そしてヒエロニモは、劇中劇によって復讐を遂げた後、カスティールを刺し殺し、その後、自らの手によって命を断つ。ヒエロニモはこのように、復讐を遂げた後にもさらに罪を重ねるのだ。カスティールは一見罪のないように見えるし、[18] 自殺もまた神に禁じられた行為である。二人を比較してみると、観客の目にはハムレットの方が高貴さをとどめているように映るはずだ。
『スペインの悲劇』以外の復讐劇における復讐者たちと比較してみても、ハムレットの方が、相対的に高貴さをとどめているといえる。『アントニオの復讐』や『タイタス・アンドロニカス』では、復讐者が、その復讐の一環として相手の子を殺している。特にアントニオは、罪の無い子供を亡霊に言われるがままに殺していて、その残虐な行為は高貴さとはほど遠い。おまけにアントニオは、復讐を遂げた後で死ぬこともない。突発的に復讐を果たした瞬間に死を遂げるハムレットの方が遥かに高貴に見え、その分、『ハムレット』は、アリストテレスが理想とする悲劇に近いと言える。
だがそれは、復讐者に限らない。『ハムレット』では、復讐される者にまでいくらかの「高貴さ」が付与されているのだ。復讐される者、つまりは悪人であるクローディアスは、自分の罪を罪として認識している。クローディアスは、自らが犯した罪が邪悪なものであることを傍白によって語る。
いまのことば、おれの良心をきびしく鞭うつわ!
きれいに化粧された娼婦の顔は、化粧がきれいなのであって
実は醜い、だがそれ以上だ、美しいことばで
飾り立てられたおれの行為の醜さは。
ああ、なんという重荷!(第3幕第1場50-54行)
また、祈りの場で、クローディアスは、自らの罪を語る。
おお、この罪の悪臭、天にも達しよう。
人類最初の罪、兄弟殺しを犯したこの身、
どうしていまさら祈ることができよう。
祈りたいと思う心はいくら強くとも、
それを上まわる罪の重さに押しつぶされる。(第3幕第3場36-40行)
無論、これは真の悔悛ではない。何故ならクローディアスは、ハムレットの独白の後、この場の最後で、自らの祈りが心を伴わないものであったことを告白しているからだ(第3 幕第3場97-8行)。だが紛れもなく、クローディアスは良心の呵責に苦しんでいる。このように『ハムレット』には、悪人の中にある善の側面までもが描かれているのだ。それに対して、『スペインの悲劇』のロレンゾーもバルサザーも、決して反省することはない。『タイタス・アンドロニカス』には、アーロンを筆頭に、タモーラやサターナイナス、残酷なタモーラの息子たちディミートリアスとカイロン等、悪の権化といった役柄が多数登場するが、彼らは決して自らの罪を省みることはない。さらに復讐者タイタスも、劇の冒頭でタモーラの子供を生け贄として殺し、自分に逆らった息子ミューシャスを自ら剣で刺し殺しているが、それに対する反省の色を見せることはない。『アントニオの復讐』におけるピエーロも同様である。彼は、全く同情の余地のない、悪の化身のように描かれている。そのような人間味のない悪党たちによる残虐な行為は、観客の感情移入を妨げることになり得る。もちろん打倒さるべき悪党に観客が感情移入する必要などないのかもしれないが、何はともあれ、『ハムレット』のクローディアスには観客が共感する幾許かの余地がある。クローディアスは間違いなく、他の復讐劇の悪役に比べて、遥かに人間的に描かれている。エリオット(Thomas Stearns Eliot, 1888-1965)は、クローディアスに見られるそのような人間性を評価している。[19] 『スペインの悲劇』におけるキッドの人間観察は、ここまでの深みには到達していない。『ハムレット』が『スペインの悲劇』に比べて圧倒的に上演されている最大の理由は、このような人間観察の複雑さにあるのだと思う。
結論
第一章では、『ハムレット』が書かれるに到るイギリス演劇史の流れを、復讐劇という視点から概観した。エリザベス朝時代のイギリスでは、16 世紀後半から、セネカの影響を受けて復讐劇が書かれるようになった。『スペインの悲劇』は、それまで舞台上で描かれることのなかった殺人を直接観客の目の前で描いた、当時としては画期的な芝居だった。『ハムレット』でも『スペインの悲劇』同様、殺人は舞台上で行われる。そのような芝居の先行作品の数が少ないことから、『ハムレット』は、恐らく『スペインの悲劇』の直接的な影響下にある。シェイクスピアは『ハムレット』で、『スペインの悲劇』で切り開かれた新しい芝居のスタイルを継承し、発展させた。1587年頃に『スペインの悲劇』が初演されてから、1600-1年に『ハムレット』が初演されるまでの16 世紀末の十数年の間に、その後17世紀に多く書かれることになる「復讐悲劇」の型が作られたのである。
第二章では、まず『ハムレット』と『スペインの悲劇』の共通点を列挙した。それから、『ハムレット』の材源であるサクソの年代記に、シェイクスピアが新たに付け足した要素を示した。材源には無い、シェイクスピアが新たに『ハムレット』に付け加えた、「劇中劇」、「亡霊」、「殺人が秘密にされていること」などといった要素は、その重要なものの多くが『スペインの悲劇』に含まれている。従って、サクソの年代記に、『スペインの悲劇』に含まれているいくつかの重要な要素を加えたものが『ハムレット』であると言うことが可能である。
第三章から第五章にかけては、『ハムレット』と『スペインの悲劇』を具体的に三つの共通点に焦点を当てて比較することにより、『ハムレット』の独自性を明らかにしようとした。第三章では、「亡霊」について考察した。シェイクスピアは『ハムレット』で、『スペインの悲劇』でコロス的な役割を演じていたに過ぎなかった亡霊を直接物語に絡ませることによって、より豊かな物語を作り出してみせた。また、サクソの年代記では先王の殺害は公のものとなっていたのに対して、『ハムレット』では先王ハムレットの殺害が隠されたものとなり、物語にミステリーの要素が加味されることになった。さらにそのミステリーは、亡霊に対するキリスト教の教義の問題と結びついたことによって、一層高度なものとなった。
第四章では、両作品で使用されている「劇中劇」の構造についてそれぞれ例を示し、分析した。キッドは『スペインの悲劇』で劇というメディアそのものを吟味し直すようなやり方で劇中劇を使用した。それに対して、シェイクスピアクスイクスピアは、『スペインの悲劇』で学んだについてそれぞれ分析は、観客の焦点を上演されている劇中劇からそれを観ている登場人物たちへずらすことによって、劇中劇を場面の背景として使用した。シェイクスピアは、『スペインの悲劇』があったからこそ、このような劇中劇の使い方ができたのではないか。『ハムレット』の劇中劇の場は、『スペインの悲劇』の応用/発展型と言えるだろう。第三章と第四章で扱った「亡霊」、「劇中劇」という二つの要素は、サクソの年代記には見られないものである。この二章による分析から、シェイクスピアは「亡霊」と「劇中劇」という二つの大きな道具立てを『スペインの悲劇』から継承しながらも、大きく発展させて、独自のものとしていることが分かる。
第五章で扱ったのは、「狂気」である。「狂気」は、サクソやベルフォレの材源に見られる要素であるのみならず、セネカの悲劇、さらに、同時代の他の復讐劇、『アントニオの復讐』、『タイタス・アンドロニカス』でも用いられている要素であり、復讐劇というジャンルと密接に結びついた問題である。本章では、復讐劇をアリストテレスが理想とする悲劇の必要条件であるミメーシス(一定の大きさをそなえ完結した高貴な行為の再現)に近付けるために、狂気が欠くべからざる要素であることについて考察した。そして、ヒエロニモよりもハムレットの方が、アリストテレスが理想としている悲劇の主人公に相応しいと論じた。さらにその「高貴さ」は、シェイクスピアの『ハムレット』では悪人にまで付与されており、その人間観察の複雑さによって、『ハムレット』は復讐劇という一ジャンルを超越し得たのだと結論づけた。
これら三つの視点からの分析により、私の中で、『ハムレット』という作品が他の復讐劇に比べて現在も広く上演され続けている理由がかなり鮮明になった。その最も重要な理由は、第五章で扱ったように、人間の描き方にある。『スペインの悲劇』を含め、同時代の復讐劇における人間観察は、『ハムレット』ほどの深みには到達していない。16世紀フランスの人文主義者モンテーニュ(Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592)は、その著作『随想録』(Essais, 1580-1588)の中で、人間は本来的に、様々の相反する要素を同時に抱えた存在で、刻々と変わり行く存在であるとくり返し説いているが、シェイクスピアは『ハムレット』の登場人物を、まさにそのような者として描いた。[20] そのことは、『ハムレット』という作品の全体像を捕らえ難いものにしたかもしれない。だが、それによって『ハムレット』は、以後作られることになるあまたある復讐劇を突き放し、イギリス演劇史のみならず、世界文学の中で、特別な地位を獲得するに至ったのだ。
『スペインの悲劇』から『ハムレット』に到る16 世紀最後の十数年間に確立した「復讐悲劇」の伝統は、この後シリル・ターナーやジョン・ウェブスターといった劇作家たちに受け継がれ、1642年にロンドンの全ての劇場が閉鎖されるまで、隆盛を誇ることになる。その中にあって『ハムレット』は、「復讐悲劇」というジャンルを切り開いた作品であったと同時に、ジャンルを越えた作品となった。
引用文献
アリストテレース・ホラーティウス 『詩学・詩論』 松本 仁助・岡道男 訳
東京: 岩波書店 1997.
Bloom, Harold. Shakespeare: The Invention of the Human. New York:
Riverhead Books, 1998.
Edwards, Philip. Introduction. The New Cambridge Shakespeare: Hamlet,
Prince of Denmark: Updated Edition. By William Shakespeare. Ed.
Philip Edwards. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 1-82.
Empson, William. ‘The Spanish Tragedy’ Elizabethan Drama. Ed. Ralph J.
Kaufmann. London: Oxford University Press, 1961.
Erne, Lukas. Beyond the Spanish Tragedy: A Study of the Works of
Thomas Kyd. Manchester and New York: Manchester University Press,
2001.
Farley-Hills, David, ed. Critical Responses to Hamlet 1600-1790. New
York: AMS Press, 1997.
Jenkins, Harold. Introduction. The Arden Edition of the Works of William
Shakespeare: Hamlet. By William Shakespeare. Ed.Harold Jenkins.
London: Thomson Learning, 1982. 1-159.
河合 祥一郎 「復讐」 『シェイクスピア・ハンドブック』 高橋康也 編
東京: 新書館 1994. 148.
喜志 哲雄 『英米演劇入門』 東京: 研究社 2003.
トマス・キッド 『スペインの悲劇』 村上 淑郎 訳 『エリザベス朝演劇集』
小津 次郎・小田島 雄志 編 東京: 筑摩書房 1974. 5-52.
共同訳聖書実行委員会 『聖書 新共同訳』 東京: 日本聖書教会 1987.
Levin, Harry. The Question of Hamlet. New York: Oxford University Press,
1959.
村上 淑郎 著者代表 『エリザベス朝演劇 —小津次郎先生追悼論文集—』
東京: 英宝社 1991.
中村 哲子 「総論2. インタールードの主題と特色」 『イギリス中世・
チューダー朝演劇事典』 松田 隆美 編 東京: 慶應義塾大学出版会
1998. 115-132
野崎 睦美 解説 『タイタス・アンドロニカス』 ウィリアム・シェイクス
ピア 作 小田島 雄志 訳 東京: 白水社 1983.181-194.
野島 秀勝 脚注 『ハムレット シェイクスピア作』 ウィリアム・シェイ
クスピア 作 野島 秀勝 訳 東京: 岩波書店 2002. 11-325.
奥田 宏子 「67. 『ホレステス』 Horestes」 『イギリス中世・チューダー
朝演劇事典』 松田 隆美 編 東京: 慶應義塾大学出版会 1998.
オウィディウス 『変身物語(上)』 中村 善也 訳 東京: 岩波書店 1981.
佐野 隆弥 「『スペインの悲劇』一五九二から一六〇二年へ」 『エリザベス
朝の復讐悲劇』 石田 久 著者代表 東京: 英宝社 1997. 3-27.
Saxo Gramaticus. “Hamlet from the Historia Dania.” Trans. Oliver Elton.
The Sources of Hamlet. Ed. Sir Israel Gollancz. London: Frank Cass
and Company Limited, 1967. 93-163.
高橋 康也・河合 祥一郎 解説 『大修館シェイクスピア双書 ハムレット』
ウィリアム・シェイクスピア 作 東京: 大修館書店 2001. 3-53.
G. J. ワトソン 『演劇概論—ソフォクレスからピンターまで』 佐久間 康夫
訳 東京: 北星堂書店 1990.
イアン・ウィルソン 『シェイクスピアの謎を解く』 安西 徹雄訳 東京:
河出書房 2000.
[1] 『タイタス・アンドロニカス』のもうひとつの種本として考えられているのが、オウィディウス(Ovidius, 43 BC-AD 17)の『変身物語』(Metamorphoses, AD 8)第六巻の中の、『テレウスとプロクネとピロメラ』である。これは、妹ピロメラを夫テレウスに陵辱されたプロクネが、その復讐として、自分と夫との間の子を殺害し、夫に食べさせるという話である。(オウィディウス 241-254)シェイクスピアは、『変身物語』の中の多くのエピソードを、自作の中でモチーフとして使っている。
[2] 作者はトマス・ノートン(Thomas Norton, 1532-84)とトマス・サックヴィル(Thomas Sackville, 1536-1608)。
[3] 『ホレステス』はセネカを種本としてはいるが、ローマを題材にした他のセネカ風の悲劇と異なり、ギリシャから素材をとっていて、喜劇仕立てとなっている(奥田 306)。
[4]ルーカス・アーン(Lukas Erne)は、最新の『スペインの悲劇』の研究書、Beyond the Spanish Tragedy (2001)の中で、『スペインの悲劇』の初演は、1587年が有力としている(Erne 58)。
[5]アーンはBeyond the Spanish Tragedyにおいて、マーロウの『タンバレイン大王』と、『マルタ島のユダヤ人』に、キッドの影響を見ることができると記している(Erne 58)。これは、二人が共同で生活していたということを考えると、当然であろう。
[6]『タイタス・アンドロニカス』の初演がいつかは分かっていない。1594 年に第1四つ折り本が出版されたが、1592年から94年にかけて、イギリスでは疫病が猛威を振るい、ロンドンの劇場は閉鎖された。そのため、初演はそれ以前の1590年前後と考えられる。この作品も『スペインの悲劇』同様、人気を博したようだ(野崎 182-185)。
[7] 『ハムレット』と『アントニオの復讐』は、どちらが先行作か、議論が分かれている。『アントニオの復讐』の影響下に『ハムレット』が書かれたとする説と、『ハムレット』影響下に『アントニオの復讐』が書かれたとする説がある。New Cambridge版の編者フィリップ・エドワーズ(Philip Edwards)は、『ハムレット』が先行すると考えている(Edwards 7)。
[8] 『ハムレット』の初演の年代については諸説ある。第2幕第2場にある劇場戦争への言及から、従来は1601年とする説が有力であったが、最近の研究では1600年とする説もある(高橋 21-26)。
[9] 例えばG・J・ワトソン(G. J. Watson)は、「当時極端に人気を博していたジャンルである復讐劇の伝統」とか、「『ハムレット』が復讐劇の慣行を利用しているのは事実だが」などと記している(ワトソン 68)。
[10]リチャード・バーベッジ(Richard Burbage, ca.1570-1619)の死に捧げられた哀歌から、ハムレットと『スペインの悲劇』の主役ヒエロニモは、バーベッジによって演じられたことが分かる(Farley-Hills 9)。そのことは、ハムレットとヒエロニモには、共通する要素があるということを示してはいまいか。
[11] 『アントニオの復讐』、『マルタ島のユダヤ人』は、復讐劇でありながらも、主人公は死なない。尚、ハムレットの材源であるサクソの物語でも、ハムレットは復讐を果たした後も長い間生き続ける。ここでは、「復讐劇」と「復讐悲劇」を分けて考えている。『ハムレット』以前に書かれた「復讐悲劇」ということになると、『スペインの悲劇』と『タイタス・アンドロニカス』くらいしかない。その後書かれた「復讐悲劇」としては、『復讐者の悲劇』(Revenger’s Tragedy)、『モルフィ公爵夫人』(The Duchess of Malfi, 1612-14)などがある。
[12] ハロルド・ブルームは次のように記す。「私は、シェイクスピアは、1587-89年頃の初期の版から、ストラトフォードに引退する頃まで、『ハムレット』を書き直し続けたのだと考えている」。(Bloom 391)
[13] 『原ハムレット』が、シェイクスピアが書いたものであるとすると、『ハムレット』について触れられている最も古い記録が1589年のものなので、シェイクスピアの劇作活動、最初期の習作であると考えられる。
[14] ハムレットの物語を収めたベルフォレの『悲話集』(Histoires Tragiques, 1570)が、1608年以前に英訳されていたと主張する研究者もいる。
[15] リストの4番目の、オフィーリアのキャラクターの拡大は、『スペインの悲劇』に見られる、ホレイショと、ベル=インペリアの禁じられた恋のモチーフの『ハムレット』への導入と言えないこともない。
[16]クリストファー・マーロウの『マルタ島のユダヤ人』でも、冒頭にマキャベリの亡霊が登場する。亡霊は、権謀術数を用いて金をかき集めているユダヤ人の悲劇をこれからお目にかけるという序詞を述べて退場する。亡霊は、以後、登場せず、物語には関わらない。
[17]後年のシリル・ターナーの『無神論者の悲劇』(The Atheist’s Tragedy, 1611)では、亡霊は主人公に復讐をしないように命じる。「フランスへ帰れ、お前の老いた父親は死に、お前は殺人により灰嫡されたのだ。忍耐を持ち事の成就を持て、復讐は王の王たる神に任せよ」『ハムレット』や、『アントニオの復讐』で描かれた亡霊のイメージを逆手に取った設定といえよう。
[18] 村上淑郎はカスティールを刺し殺すことは不自然ではないと、ヒエロニモの心情を擁護している(村上 21)。
[19]志賀直哉も、人間的なクローディアスに感情移入したからこそ、『クローディアスの日記』を書いたのだろう。
[20] シェイクスピアはモンテーニュの『随想録』の一節を、『テンペスト』の中で借用している。そのことから、シェイクスピアがモンテーニュを読んでいたことは、「まったく疑問の余地がない」(ウィルソン 499)。ジョン・フロリオ(John Florio, 1553-1625)の手になる英訳が出版されたのは、『ハムレット』のQ1が出版されたのと同じ1603年である。ジョン・フロリオは、シェイクスピアのパトロンであった第三代サウサンプトン伯ヘンリー・リズリー(Henry Riseley, 1573-1624)のイタリア語の家庭教師でもあり、シェイクスピアと親しかったのではないかという説もある。『ハムレット』にモンテーニュの影響があるのかどうかは謎である。


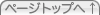
Comments & Trackbacks
Trackback URL http://shakeweb.co.uk/spear/thesis/30.html/trackback