意識変革の劇、Macbeth —Gunpowder Plotをめぐって—
意識変革の劇、Macbeth
—Gun Powder Plotをめぐって—
米田 拓男
Introduction
Macbethが執筆されたと考えられるのが1606年。今から遡ることちょうど400年前、ロンドンは、Gunpowder Plotの話題で持ち切りだった。そしてShakespeareは、事件を巡る一連の騒動を横目に見ながら、Macbethを執筆していた。
ある作品はそれが書かれた時代と無縁ではいられない。Macbethも例外ではない。Macbethという作品はどのような社会背景の下で書かれたのか、それを知ることで見えなかったものが見えてくるに違いない。本論では、Gunpowder PlotとShakespeareのMacbeth執筆の関係について探ってみる。
1. Gunpowder Plot
Gunpowder Plotは、1605年11月5日に起こった、カトリック教徒たちが弾圧を恐れて起こした、国会議事堂爆破未遂事件である。その時期は、ShakespeareがMacbethの構想を固めていた時期と、恐らく重なる。
この事件とMacbethの執筆ではどちらが早いか、様々な議論があるが、私見では、様々なテキストの内的要因から、Shakespeareは Macbethを、事件が最終的な決着を見たあとで完成したと思われる。例えば、Macbethの中には’equivocator’という言葉が何度か使われている。この言葉は、国会議事堂を爆破する陰謀のことを告白によって首謀者たちから知らされていながら、告白の内容を外に漏らすことは牧師という立場上許されないため、秘密にしておいたことを罪に問われたGarnet神父が、裁判の際に使った言葉だった。
「二枚舌」というテーマは、作品を構成する重要な要素のひとつである。PopeとColeridgeは、’equivocator’という言葉が現れる The Porter Sceneは後から書き加えられたのだと主張しているが、それは考えられないように思う。魔女が語る、劇冒頭の’foul and fair’というフレーズも、魔女がMacbethに「二枚舌」を使って騙すのも、’equivocation’というテーマと繋がる。このような作品の根幹に関わるテーマを後から付け足したとは考えづらい。Garnet神父の裁判が行われたのは1606年3月28日なので、初演はそれより確実に後だと思われる。事件の首謀者たちの中には、Shakespeareと同じWarwickshire出身の者もいたようだ。Shakespeareはことのほか、この事件に関心を寄せていたのではあるまいか。
個人的な印象からも、Macbethという劇は事件と繋がっているように思える。私がMacbethという芝居に抱く印象は、闇のイメージである。そのような印象は、次のような場面からもたらされる。Macbethは、Duncan殺害の前に、闇の中に短剣が浮かんでいるのを見る。Duncanは、闇の中で寝込みを襲われ殺害される。Banquoは暗い森の中で暗殺される。その時、ランタンが落ち、あたりが暗闇に包まれる。Macbeth夫人は夜の城内をさまよい歩く。そしてMacbethの独白には蝋燭が出てくる。
Out, out, brief candle,
Life’s but a walking shadow, (5.5.22-3)
消えろ、消えろ、束の間の灯火、
人生はたかが歩く影に過ぎない
深い闇を感じさせる独白である。
Macbethという劇の印象は、このような暗闇に包まれた、地下牢のようなものである。その暗闇は、Guy Fawkesたちが火薬をしかけた地下室の闇に通じるように思える。それは、Fawkesたちの闇の中の作業に通じる。独白に出てくる蝋燭は、火薬のイメージと結びつく。暗い想像力が働かされ、地下室で陰謀が企まれる。そのような暗い地下の思考から生み出されたと思えるような殺戮が、Macbethの舞台上でも展開される。
Fawkesたちの為したことは、明らかなテロ行為である。彼らはカトリック教徒の解放を求めてこのような手段に出たが、その思惑は裏目に出た。この事件以降、カトリックへの弾圧はいっそう激しいものとなったのだ。アメリカ社会で、9.11がイスラム教徒に対する差別意識を強めたように、当時のロンドンでも、カトリックに対する迫害がいっそう加速されたのは想像に難くない。この陰謀事件は、カトリックへの迫害を強めるために、プロテスタントの側が仕組んだのではないかと、陰謀説を主張する歴史家もいるくらいだ。
いずれにせよ、彼らの思惑は達成されず、Fawkesたちは逮捕され、処刑が決行されることになった。その処刑は凄惨を極めるものだった。事件の首謀者たちは、首をくくられ、内蔵を引き出され、馬で四裂きにされ、その首はロンドン・ブリッジにさらされた。
このような事件が起こり、それがこのような結末を迎えたことは、同時代の人々に強い衝撃をもたらしたはずだ。町に陰鬱な空気が漂ったのは間違いないだろう。Shakespeareは、血なまぐさい社会を背景に、血なまぐさい出来事を描いた。陰鬱な劇は、当時の陰鬱な社会状況の反映なのだ。
Shakespeareが事件に触発されて劇を書いているのは間違いないように思える。事件の詳細を知ると、劇中のいくつかの場面の印象がより鮮烈なものとなる。Henry N. PaulはThe Royal Play of Macbethの中で、Gunpowder Plotの主犯者たちの一人の青年について述べている。Paulは、1606年1月30日に処刑された一人の青年と、一幕で語られるCawdorの領主に関連があるという。
その青年、Everard Digbyは、清廉潔白な人物だった。James Iは地方を回っていた時に、この人物に出会った。そしてJamesは彼を高く評価し、騎士の称号を与えた。Digbyはそのような人物であったにも拘らず、事件の首謀者たちと接し、彼らに協力することを約束してしまう。Macbethの一幕四場に次のような台詞がある。Duncanは、Cawdorの領主に処刑の処分を下す。そして彼の死に様がそれに続く場面で語られる。
But I have spoke
With one that saw him die, who did report
That very frankly he confessed his treasons,
Implored your highness’ pardon, and set forth
A deep repentance. Nothing in his life
Became him like the leaving it. He died
As one that had been studied in his death,
To throw away the dearest thing he owed
As ’twere a careless trifle. (1.4.3-11)
しかし、
処刑を見た者には会いました。その話によれば、
彼は率直に反逆を認めて
陛下のお赦しを請い、
深い改悛の情を示したそうです。彼の生涯を通じ
その去り際ほど見事なものはなく、かねてから
死に方の稽古をしていた者のように
最も大切な物を
反古同然とばかり潔く投げ捨てたそうです。
Cawdorの領主は立派な最期を遂げる。Paulは、彼の死に際しての態度は、Digbyのものと重なるという。DigbyはCawdorの領主のように、自らの罪を悔い、祈り、死んでいった。PoulはShakespeareが彼の処刑を見た可能性を示唆する。このCawdorの領主のくだりは、モデルになった人物がいたことを想像すると、より生々しいものとして目に浮かんでくる。
事件と共鳴しているように感じられる箇所は他にもある。戦場から戻ってきたMacbethは、次のように言う。
So foul and fair a day I have not seen. (1.3.36)
ひどいのか良いのか、こんな日は初めてだ。
この台詞は何を意味しているのだろうか。何を指しているのか意味を取りにくい台詞である。’fair’は戦場における勝利であるだろうが、’foul’は戦場の残酷さを指しているのか、あるいは、天候を指しているのか、劇の中では意味が通りにくい。だが、これは、火薬陰謀事件が発覚した日を形容するのにまさに相応しいような言葉だ。つまり、あまりにおぞましい事件だったが、実現しなくて本当に幸運だった、と。
私がこの事件から連想してしまうのは、オウム真理教による地下鉄サリン事件からしばらく経って起きた、新宿で青酸カリの時限装置が発見された事件だ。事件そのものは未然に終わったが、あの出来事は人々を不安に陥れた。あれが成功していたらどうなっていただろうか。Shakespeareが私たちの同時代人だったら想像したに違いない。Shakespeareは、Macbethでまさにそれをやっているのだ。
Macbethは’nothing is, But what is not’「あるものはないものだけ」と言う(1.3.140-1)。実際には「何も」起こらなかった爆破事件。それは、Shakespeareの想像力を刺激し、彼に劇を書かせた。Fawkesたちがしかけた火薬は、実際には爆発しなかったが、Shakespeareの想像力の中では爆発したのだ。 Macbethは、実際には起こらなかった恐ろしい事件を、Shakespeareが想像力を使って具現化した劇なのである。
2. 犯行のシミュレーション
現実の地下室では不発に終わった火薬は、しかし、Shakespeareの想像力の中で爆発した。そして同時代の人々も、それが爆発していたらどのような恐ろしいことになったか想像せずにはいられなかったに違いない。実際には爆発しなかったが、それはShakespeareの、そして、ロンドンの人々の想像力の中では確実に爆発したのだ。現実世界では何も起こらなかったが、陰謀の発覚は社会に大きな不安をもたらした。事件は、人々の想像力の中に、何かを確実に胚胎させたのだ。
Macbethは次のように言う。
Present fears
Are less than horrible imaginings. (1.3.136-7)
現実に恐ろしいものを見るよりも
想像するほうがずっと恐ろしい。
想像力豊かなMacbethは、実際の恐怖よりもそれを想像する方が恐ろしいと言う。Shakespeareは正にその恐ろしいことをして、劇を書いている。爆発していたらどのようになったか、皆想像したと思う。実際に爆発してしまうよりも、それを想像する方が恐ろしい。Gunpowder Plotは、人々の想像力に訴えかける事件だったのだ。
事件で使用された火薬の量は、いったいどのくらいの威力のものだったのか。実際にそれが爆発していたら、どの程度の被害がもたらされたのだろうか。案外、本当に爆発していたら、それほど大きな被害がもたらされなかったかもしれない。地下室がひとつ吹き飛ぶだけで、事なきを得たかもしれない。爆発していた方が、実行犯たちの刑が軽くなっていた可能性だってあるかもしれない。政府がそこまで犯人探しに血眼になることもなかったかも知れない。人々が感じた恐怖が、彼らに残酷な処刑をもたらした。彼らは、市民の想像力が描き出した爆発の罪さえも背負わされてしまったのかもしれない。そして市民は、彼らが一般の人間とは根本的に異なる、悪魔的な人物たちだったのだと考え、処刑して胸を撫で下ろした。
しかし、ここで、市井の人々の想像力とShakespeareの想像力の間には、当然ながら、大きな開きがあった。Shakespeareは、決して Macbethを悪魔的な人物として描いていない。Macbethは悪党であるが、自分の悪事におののきながら悪を行う、Barbara Everettが言うところの、一種の’villain-hero’なのである(Everett 85)。
MacbethはDuncanを殺す前に、その行為の恐ろしさに恐れをなし、気持ちがくじけそうになる。
My thought, whose murder yet is but fantastical,
Shakes so my single state of man that function
Is smothered in surmise, (1.3.138-40)
心に浮かぶ殺人は、まだ空想に過ぎないのに
俺の五体を揺さぶり、
思っただけで体が利かなくなる。
Macbethはこれほど自分の行為に恐れを抱いている。そして悪事を重ねたあとになっても、その行為におののいている。
O, full of scorpions is my mind, dear wife! (3.2.36)
ああ、お前、俺の心はサソリでいっぱいだ!
Macbethは罪悪感に責めさいなまれている。そして彼は心の平安を求める。
To be thus is nothing,
But to be safely thus. (3.1.49-50)
こうしていても何にもならない、
心安らかにこうしているのでなければ。
Macbethは悪を自覚しているのだ。それはShakespeare作品の他の悪党とは大きく異なる点だ。Richard IIIのGlocesterは悪を自覚しているが、それを行うことに快感も覚えている。Macbethは快感を覚えていない。彼は自分の行為を恐れている。自分の行為を見たくないと言う。彼はDuncanの血に濡れた手を見て’they pluck out mine eyes’「この両手が俺の目玉をえぐり出す」と言う(2.2.62)。Macbethは苦しみながら悪を行うのだ。Macbethの残虐な行為を想像しながら執筆しているShakespeare自身、快感を感じていないだろう。この劇で描かれる犯罪は痛みを伴っており、重々しい。Duncanを殺す場面に悪を為す爽快感は微塵も無い。それは、IagoやEdmundとも全く異なる点である。
Macbethは自分がなそうとする行為を何度も想像してしまう。そして自らが為そうとしている行為に恐れを抱く。Harold Bloomは、Macbethは’a tragedy of the imagination’「想像力の悲劇」であると言っている(Bloom 517)。A. C. Bradleyも次のように言う。
Macbethのよい面は・・・道徳の理念や命令や禁止という率直な言
葉で 自らを語るというよりも、動揺や衝撃を与える映像の中に具体
化されている。ゆえに想像力が彼の最高の持ち味なのである。
この想像力は、Shakespeareの想像力にそのまま重なる。
Shakespeareは、MacbethによるDuncan殺害を、恐ろしいものとして描いている。Macbeth自身、その行為に恐ろしさを感じているが、それは執筆しているShakespeare自身が感じている恐怖心と同等のものだ。Macbethが、自分が為すことに恐れを抱きながら実行に移して行く過程は、Shakespeare自身が恐れを抱きながら、悪事を舞台上に描いていくそれと同等なのだ。つまり、Shakespeareは Macbethに感情移入しながら劇を執筆しているのだ。
Shakespeareは火薬陰謀事件を恐ろしいと思ったが、彼の想像力は自分がそのような犯罪を犯すことを想像せずにはいられなかった。事件の実行犯の中にShakespeareと同郷の者がいたことは、犯人の立場を想像する際の一助となったかもしれない。Paulは、次のように書く。
Clopton House, which was a rendezvous of the plotters, was
near Shakespeare’s land, and he had known several of these men
since childhood. (Paul 226)
Shakespeareが犯人たちの何人かを子供の頃から知っていたというのは、本当だろうか。それが真実であったのだとすれば、それは、Shakespeareが犯人たちに感情移入する大きな余地を与えたと言えるだろう。
Shakespeare自身はカトリックだったのか、プロテスタントだったのか。どちらであったとも、立場を表明していない。しかし、 Shakespeareの身近にカトリックがいた可能性はある。Shakespeareの父、John Shakespeareは、国教忌避者のリストに名前を連ねたことがある。さらには、彼はカトリックの信仰遺言書を残してもいる。それは18世紀に発見されて失われてしまったので、その真贋は今となっては判断するのは難しいが、Shakespeareの父がカトリックであった可能性はある。さらには Shakespeareの娘、Susannaも、Holy Trinity Churchの「不信心者」のリストに名前が載せられたことがある。Shakespeareの身内にカトリックがいた可能性があるのだ。
Shakespeareは反逆者Macbethを、ごく普通の道徳観を持つ、臆病な男として描いた。その男が魔女にたぶらかされる。Macbethの行いは残虐なものだが、観客はMacbethに感情移入せずにはいられない。そのように書かれている。Shakespeareが感情移入しながら、劇を書いている。Shakespeare自身、犯人たちがどのような心境で犯行に臨んだのか、作品の中でシミュレートしてみたかったのではないか。
次のMacbethの台詞からは、いかにもShakespeareらしい発想が垣間見られる。
To know my deed, ’twere best not know my self. (2.2.77)
やったことを思い出すくらいなら、自分を忘れている方がいい。
恐ろしい行為を行うには、別の人格が必要なのだ。Macbethは他人になりたいと願う。役者でもあったShakespeareらしい発想である。そして Shakespeare自身、劇を書いている時にはMacbethになりきっている。犯罪者になりきって台詞を書いている。自分自身では恐ろしくてできないようなことを別の人格を借りて、劇の中でやっているのである。
観客は、Macbethが悪事を働くに至る心情の変化を注意深く見守る。そして観ているうちに、Macbethの思考に巻き込まれていく。観客も Macbethとなって犯罪者の意識を体験する。恐ろしいと感じた事件を、主犯の側から想像する。Shakespeareによる反逆者の心境のシミュレーションを、追体験することになるのだ。
3. 御前公演
だが、このようにMacbethに共感を抱いてしまうような書き方をすることはある種の危険を伴う。何故なら、観客の中には、James Iがいたからである。そのような書き方をしては、Jamesを陥れようとした犯罪者を擁護することになりかねない。Macbethは御前公演として上演された可能性が高い。そのため、James Iが観客として想定されていた可能性がある。
Macbethの作中には、James Iへの胡麻すりと受け取られかねないような箇所が散見される。四幕一場では、Macbethが魔女たちと再会し、彼の前を八人の王の幻影が横切る。その際、八人目の王が鏡を掲げているが(F1のト書きではBanquoが鏡を持っていることになっているが、Macbethの台詞との間に矛盾が生じてしまうので、八人目の王に書き換えられるのが通例)、その鏡には、御前公演の際には、観劇しているJames Iの姿が映し出されたはずである。もう一つが四幕三場、Malcolmがイギリス王の奇跡を語る場面である。Malcolmは、王がその奇跡の力を子孫に伝えると聞いたと言う。
and ’tis spoken
To the succeeding royalty he leaves
The healing benediction. (4.3.156-8)
そして聞くところによると、
王はこの有難い治癒力をご子孫に
伝授なさるそうだ。
このイギリス王がどういった血筋の者なのか分からないが、Banquoの子孫として先の八人の王の幻影に名を連ねるJamesの血筋を、さらに讃えんとする意図が垣間見える。その血縁の誉れ高さを二重に持ち上げようとしているように感じられる。他にもMalcolmが軍勢を貸し出してくれるイギリス王を ‘Gracious England’と呼んで、ほめ讃える箇所がある。
Shakespeareは、さらに、材源の設定にも操作を加えている。Holinshedの『年代記』では、Macbethにも正当な王位継承権があり、見方によれば、Duncanこそ王位簒奪者ととれる。また、James Iの先祖であるBanquoも、王位への野心を持っていて、MacbethのDuncan殺しに加担したことになっている。Shakespeareはそれらの箇所を劇化にあたって割愛した。
これらの要素は、James Iのためのご機嫌取りと勘ぐられかねない。犯罪を悪人の側から描いた作品だから、慎重さを要したのだろうか。しかし、私には、ただひとりJamesが見ることを想定して、このような台詞を書いたのではないのではないかと思う。
私は当時のロンドンを、9.11以降のアメリカと重ねて想像してしまう。アメリカでは9.11以降、国民の間に国粋主義的な言動が目立つようになり、ブッシュの支持率が大きく上がった。Gunpowder Plot以降のロンドンでも同様のことが起こっていたのではないか。国教徒たちが、James Iのもとに結束を固めようとしていたのではないか。Macbethにこのような台詞が現れるのは、それが時代の空気を反映しているからなのではなかいか。観客もこのような台詞を喜んだからなのではないか。
当然、Macbethでは、最終的に悪は罰せられねばならない。Macbethは最期、Macduffに破れ、無惨な死を迎えることになる。ここではタンバレイン大王のように、悪を為して尚、生きながらえることは許されない。もしMacbethが死ななかったらどうなるか。Shakespeareはただでは済まなかっただろう。James Iの寵愛を失うことになったかもしれない。いや、それだけではなく、客席から石が飛んでくることにもなりかねなかった。9.11の事件を受けたヒステリックなアメリカ市民は、少しでもイスラムを擁護するようなことを発言したら、少しでもブッシュ政権に非があることを言おうものなら、その者に対して激しい非難を浴びせかけた。Macbethにこのような国威の高揚に繋がるような台詞が含まれているのは、Jamesの顔色を伺っているだけではなく、検閲を恐れていただけでもなく、社会的要請だったのではないか。
4. 観客との乖離
Macbethという劇は、後半に向かうに従って、だんだんと観客とMacbethの間に距離が出来て行く。Macbethは劇の中で殺戮を繰り返して行く。Duncanを殺した後は、Banquoを、そして次にはMacduffの夫人と息子を殺す。Shakespeare劇において、子殺しは重大な罪だ。それを犯した者は死を覚悟しなくてはならない。ここまで来ると、観客は、観客が生きるモラルの世界から、完全に別の次元へと連れて行かれる。罪の意識に責めさいなまれる以前のMacbethはもういない。彼は自分の恐怖の感覚が麻痺してきたと独白で語る。
I have almost forgot the taste of fears;
The time has been, my senses would have cooled
To hear a night-shriek and my fell of hair
Would at a dismal treatise rouse and stir
As life were in’t. I have supped full with horrors;
Direness familiar to my slaughterous thoughts
Cannot once start me. (5.5.9-15)
恐怖がどんな味なのか、ほとんど忘れてしまった。
かつては、闇を切り裂く悲鳴に
五感が凍り付き、凄まじい話には
髪の毛が根元から逆立って、生き物のように
うごめいたものだ。だが恐怖をしたたか舐めた今、
どんな恐ろしいことも人殺しの俺の胸には昔馴染みだ、
もうぎくりともしない。
Macduffが自分の妻と子供が殺されたことを告げられる四幕三場では、MalcolmとMacduffが、そしてMacduffに妻子の死を知らせに来たRossが加わって、Macbethに対する批判を繰り広げる。ここで観客は、それまで感情移入して付き合って来たMacbethを第三者の視点で眺めることになる。子供を殺してしまったMacbethに対して、観客はもはや以前ほど親近感を抱けなくなっている。
そしてMalcolmたちは、ここでMacbethに対して兵を挙げることを話し合う。Macbethに対して攻撃をしかける側から話が展開していく。 Macbethが何かに対してアクションをしかけるのではなく、しかけられる側に回る。能動から受動へと劇の中での立場が変わる。Macbethを攻める側に、観客の心情の重心が移行し始める。
そして彼らの奇襲は成功し、最後、Macbethは戦場で倒れる。しかし、その死は舞台上では描かれない。四大悲劇では、Hamlet、 Othello、Learの死は舞台上で描かれるが、Macbethの死は異なる。「女の腹から生まれた」Macduffに戦いを挑む決心を固めた Macbethは、二人で切り結び合いながら舞台から退場し、次の場面では、切り落とされた首として舞台に現れる(注1)。そしてその姿は事件首謀者たちの末路とも重なる。Macbethは逆臣の徒として、相応しい最期を遂げたのである。
ここに来てJames Iはほっと胸を撫で下ろしただろうか。スコットランドに失われていた秩序が回復して、劇は幕を閉じる。観客たちもその終わり方に納得するだろう。劇としては安定した終わり方だ。誰からも文句は出ないだろう。
Shakespeare作品には、問題を残しながら終わる劇は多いが(注2)、Macbethは何も問題を残さない。あまりに残らなさ過ぎるほどだ。誰の目にも明らかな逆臣の徒Macbethが打ち倒され、Malcolmが王位を継承して、全ての問題が解決して、劇は幕を閉じる。あまりにも完全な完結性。
Macbethが死んだ後は、何ももったいぶることなく、劇はあっさりと終わる。Shakespeareの中で、そして観客の中で、James Iの中で、この終わり方はあまりに当然のものだった。事件首謀者たちの末路がそうであったように、Macbethはここでこのような末路を辿らねばならなかったのであり、それは誰にとっても自明のものだったのだ。こうして事件へのルサンチマンを解消した観客は、気持ちよく劇場を後にすることができる訳だ。
5. Is the Time Free?
しかし、私は、Macduffが言う”The time is free”「世界は解放された」という言葉に違和感を覚える。
Hail, king, for so thou art. Behold where stands
Th’usurper’s cursed head. The time is free. (5.9.21-2)
国王万歳、もう、そうご挨拶できるのです。ご覧ください、
王位簒奪者の呪われた首です。世界は解放されました。
その劇の完結性にも拘らず、この台詞に感じる居心地の悪さは何だろうか。
観る者がこの台詞に違和感を感じるとすれば、それは、観客がMacbethに感情移入してきていることによる。Macbethの性格には残虐なことをしてもなお、感情移入を許すような余地がある。それはMacbeth自身が、自分が生きていては許されないことを理解しているからである。本人も死を避けられないと思っている。殺戮を繰り返し、戻ることのできない地点に到達してしまったMacbeth自身、それを自覚していて、川の比喩を使って心情を述べている。
I am in blood
Stepped in so far that should I wade no more,
Returning were as tedious as go o’er. (3.4.136-8)
血の川に
ここまで踏み込んだからには、たとえ渡りきれなくても
戻るのも億劫だ、先へいくしかない。
そして、愛情も友人も持てず、老いていく悲しさを語っている。
My way of life
Is fall’n into the sere, the yellow leaf,
And that which should accompany old age,
As honour, love, obedience, troops of friends,
I must not look to have; (5.3.22-6)
俺の人生は
黄ばんだ枯れ葉となって、散るのを待っている。
それなのに、老いの日々の伴侶、
例えば栄誉、愛、従順、それに多くの友など
何ひとつ持てる見込みはない。
ここまで来ると、Macbethはもう生きていても楽しくない。死だけが安らぎである。だから観客は最後、Macbethが、「女の腹から生まれた」Macduffに、自分が負けることを予感しながら挑んで行く気持ちをよく理解することができる。
Macbethに対峙したMacduffは言う。
Then yield thee coward,
And live to be the show and gaze o’the’time.
We’ll have thee, as our rarer monsters are,
Painted upon a pole and underwrit,
‘Here may you see the tyrant.’ (5.8.23-7)
それなら降参しろ、卑怯者、
生きながらえて世間のさらしものになれ。
世にも珍しい怪物なみに見世物にして、
柱に絵を描き、こう書いてやる、
「さあ、お立ち会い、暴君だよ」
ここでMacduffが言っていることは、Gunpowder Plotの実行犯たちが最後に受けた屈辱と同じものをMacbethに舐めさせるということである。実行犯たちの運命について、Paulは次のように書く。
Some were killed, and some were taken alive and sent up to London. The King’s Book (M2), explained that people wished to see them “as the rarest sort of monsters; fools to laugh at them; women and children to wonder, all the common people to gaze ” (Paul 230)
Macbethは、Gunpowder Plotの実行犯たちと同じ屈辱を味わいたくなかったのだ。そして勇敢な戦士として、勝ち目の無さそうな相手に立ち向かっていく。
Conclusion
Macbethを1606年に書くとはどのような行為だったのか。当時のロンドンは、Gunpowder Plotの話題で持ち切りだった。1606年1月30日には、本論でも触れたEverard Digbyら、事件の犯人たちの処刑が決行された。それからちょうど四百年。その時にレポートで彼らのことを取り上げているのもなんだか不思議な気がする。
ある作品は、それが生み出された時代と切り離すことはできない。その作品は、その時代に生み落とされたからこそ、価値があるのだ。作品が書かれた背景を知ると、作品の面白さが増す経験を味わうことができる。今回もそれは例外ではなかった。
Chapter 1 では事件の概要と、作品の成立時期について論じた。様々な内的要因から、テキストは事件が決着を見たあとで成立したと論じた。Macbethは、実際には起こらなかった恐ろしい事件を、Shakespeareが想像力を使って具現化した劇なのだと論じた。
Chapter 2 では、Shakespeareが描き出したMacbethの性格について論じた。Shakespeareは反逆者Macbethを、ごく普通の道徳観を持つ、臆病な男として描いた。Shakespeareはカトリックに親近感を抱いていた可能性があり、Macbethという作品は、Gunpowder Plotの主犯者たちがどのような心境で犯行に臨んだのかについての一種のシミュレーションだったのかも知れない。
Chapter 3 では、作中にJames Iへの胡麻すりと受け取られかねないような箇所が散見されることを指摘し、Gunpowder Plot以降のロンドンでも9.11以降のアメリカと同様のことが起こっていた可能性を指摘した。つまり、ロンドン市民の間に国粋主義的な言動が目立つようになり、James I を持ち上げているような台詞は、そのような時代の空気を反映しているのである。
Chapter 4 では、MacbethがMacduffの夫人と息子を殺す辺りから、Macbethと観客との間に距離ができていくことを指摘した。以降、観客は、それまで感情移入して付き合って来たMacbethを第三者の視点で眺めることになり、Macbethの切り落とされた首が舞台に登場するに及んで、その視点は事件首謀者たちの末路を眺める視点と重なるのだ。
Chapter 5 では、Macbethに感情移入してきた観客が”The time is free”という言葉に感じる違和感について論じた。劇の視点は、後半、Macbethから離れていくが、Macbethの性格には、残虐なことをしてもなお、観客に感情移入を許すような余地がある。Macbethが辿った、一人の反逆者としての末路は、当時の観客にとっては、つい最近見たのと良く似た光景だった。Macbethを観てしまった観客は、ロンドン・ブリッジに掲げられた首謀者たちの首を、以前と同じものとして眺めることは出来ない。 Macbethは、当時の観客に、意識変革をもたらす劇だったのだ。
このように見てくると、Shakespeareがいかに一人の劇作家として優れていたかが分かる。当時Macbethを書くのは、危険を伴う行為だった。もっと無難な題材ならいくらでもあった。しかし、Shakespeareはこの事件に関心を抱いた。事件に触発され、想像力が掻き立てられた。面白い劇が書けると思った。だから書きたいと思った。自然な欲求。作家なら誰しも、自分が面白いと思ったものを書きたいと思うはずだ。しかし、その表現者としての自然な欲求を、妨げる力もまた存在する。表現者は、時にそのような力と戦うことになる。時の権力に逆らうことなく、しかもおもねることなく、如何にして作家的欲求を充足させるか。ShakespeareがMacbethを執筆する際に選択した手法は、その二律背反する課題を達成するための最良の選択だったのである。
Notes
1. F1を見ると、ユExeunt fighting.ユというト書きによってMacbethとMacduffは一度舞台上から退場し、その次の行のト書きヤEnter Fighting, and Macbeth Slaine.ユで、二人が斬り結びながら舞台に再登場し、MacduffがMacbethを打ち倒すことになる。しかし、その後Macbethの亡骸を舞台から運び出さなくてはならなくなる。しかしそのことを示すト書きや台詞は存在しない。Macduffが引きずって行くのかも知れないし、 MacduffがMacbethに致命傷を負わせ、うめきながらMacbethが退場するのかも知れない。いずれにせよ、Macbethには Hamlet、Othello、Learに与えられていたような、死際の台詞は与えられていない。
2. 問題のある終わり方をする劇は、Shakespeare作品には多い。『冬物語』では、最期にハーマイオニが彫像の姿で現れ、生きていたことが発覚する。しかし、十六年間、宮廷のそばでポーライナに匿われていたというのは、現実的な話ではないし、そもそも、Shakespeareは、ポーライナがハーマイオニを匿うことにしたということを観客に告げていなかった。彼女たち、ハーマイオニとポーライナ、そしてShakespeareは、観客を、レオンティーズもろとも十六年間騙し続けるのである。話のあまりの唐突な展開についていけなくなる観客がいたかも知れない。『リア王』では、最期、リアがコーディリアの亡骸を抱きながら登場し、リアもその場で命を失う。その理不尽なコーディリアの死に観客が納得がいかないと思ったとしても無理は無い。『十二夜』では、シザーリオに恋いこがれていたオリヴィアが、セヴァスチャンと結婚することになるが、それで本当に良いのかといぶかる観客が出てもおかしくない。
参考文献
Bloom, Harold. Shakespeare: The Invention of the Human. New York:
Riverhead, 1998.
Coursen, Herbert R. Macbeth: A Guide to the Play.London: Greenwood,
1997.
Everett, Barbara. Young Hamlet: Essays on Shakespeare’s Tragedies.
Oxford: Clarendon, 1989.
今井 宏 編 『世界歴史大系 イギリス史 2 近世』 東京: 山川, 1990.
Ioppolo, Grace. Revising Shakespeare. London: Harvard UP, 1991.
川北 稔 編 『新版 世界各国史11 イギリス史』 東京: 山川, 1998.
森 護 『英国王室史話』 東京: 大修館, 1986.
Paul, Henry N. The Royal Play of Macbeth. New York: Octagon, 1971.
Shakesepare, William. The New Cambridge Shakespeare: Macbeth. Ed. A. R.
Braunmuller. Cambridge: Cambridge UP, 1997.
イアン・ウィルソン 『シェイクスピアの謎を解く』 訳: 安西 徹雄 東京: 河
出書房, 2000.


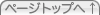
Comments & Trackbacks
Trackback URL http://shakeweb.co.uk/spear/thesis/32.html/trackback