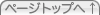Shakespeare作品に見られる’ethical dative’について
米田 拓男
Introduction
シェイクスピア作品の注釈にしばしば心性的与格‘ethical dative’という言葉を見かける。以前、ボトムの台詞に焦点を当ててA Midsummer-Night’s Dreamを読んでいた時にこの用法に出会った。以下がその台詞である。
but I will aggravate my voice so, that I will roar you as gently as any sucking dove; I will roar you an’ twere any nightingale. (A Midsummer-Night’s Dream 1.2.75-77)
だから俺は声を欲情させて、鳩がクークー鳴くみたいに優しく吠えてやる。ナイチンゲールみたいに吠えてやる。
この箇所の注に「このyouは聞き手の関心を引くために添えられた虚辞<心性的与格>」とある。 (石井 240) 僕はこの用法はボトムの自己顕示欲の強い性格を表していて大変に面白いと思った。今回のレポートではこのようなShakespeare作品に見られる ‘ethical dative’の用法について論じる。そして、それに関連して ‘ethical genitive’と、利害の与格 ‘dative of interest’についても言及する。
Chapter 1
OEDで ‘ethical dative’を引いてみたところ “the dative when used to imply that a person, other than the subject or object, has an indirect interest in the fact stated.”とあった。OEDによれば、’ethical dative’は話者の興味を反映するもののようだ。なるほどシェーラーの『シェイクスピアの英語』では、 ‘ethical dative’に「関心の与格」という訳語が与えられている。[i]しかし、それだけでは先に引用したボトムの台詞の説明としては不十分だ。ボトムの台詞は自分の関心というよりは聴者の注意を引こうとするものである。そのことを考慮すると、現代英語学辞典の記述の方が ‘ethical dative’の実際により近いように思われる。
叙述に生気を与えるために、話者が自己または聴者の関心を表すme、youを虚辞(EXPLETIVE)的に動詞に添えることをいい、古文、または、古文を模倣した文体に見いだされる。
そして、どうやら‘ethical dative’は叙述に生気を与えるものでもあるらしい。[ii]
具体例を挙げてみよう。
Casca. Marry, before he fell down, when he perceiv’d the common herd was glad he refus’d the crown, he pluckt me ope his doublet, and offer’d them his throat to cut. (Julius Caesar 1.2.263)
キャスカ それが、ぶっ倒れる前、王冠を拒絶したのが平民どもにうけたのを見て、どうしたと思う、こう胸をはだけてこの喉をかき切ってくれと言ったもんだ。
この箇所の注を見ると、「いわゆるethical dativeで、描写に生気を与えるためのもの。とくに意味はない」(大場 75)とあり、ここでも ‘ethical dative’は記述に生気を与えるものであることが述べられている。しかし、同時に大場氏はここで使われている ‘ethical dative’には特に意味はないとしている。本当に意味は無いのだろうか?
先に挙げてきたいくつかの‘ethical dative’の定義によれば ‘ethical dative’が用いられている箇所では、話者、あるいは聴者の関心が問題になっているはずである。Julius Caesarのこの場面では、シーザーが王冠を頂くことを快く思っていないキャスカが、大衆を前にしたシーザーの大袈裟な身振りを揶揄している。ここの ‘me’にはその大袈裟な身振りを軽蔑するような意味合いがあるのではないか。もう一つ例を見たい。次に挙げるのは、イアーゴーがその黒い胸の内をロダリーゴーに打ち明けるOthelloの一場面である。
Whip me such honest knaves. (Othello 1.1.49)
そんな馬鹿正直なやつはむちで打ってやれ
ここの注にも「me はいわゆるethical dativeで単に意味を強めるだけ」とある。(笹山 45)だが、ここでもやはり先と同じように正直者に対する侮蔑の感情が含まれているように思う。しかし、Introductionで触れたボトムの例はこれには当たらない。先のボトムの台詞には軽侮の感情の込められているはずもない。そのボトムの台詞に似た例を挙げる。Hamletの墓掘りの場の台詞である。
’a will last you some eight year or nine year. A tanner will last you nine year. (Hamlet 5.1.160-161)
ま、ふつうは八、九年ってとこかな。皮屋ならたっぷり九年はもちますがね。
墓掘りはハムレットに向かって、死体がどのくらいもつのか説いてみせる。ここでも注釈には「意味のないyou」とあるが、(高橋 347) 墓掘りは死体に関しては第一人者である。どことなく自慢げな響きがこもってはいないだろうか。このように ‘ethical dative’にはなんらかの話者の感情が込められているように思う。もう一つ例を挙げる。次の台詞はシャロー判事がフォルスタッフに学生時代の射撃競技会の思い出を語る場面である。
there was a little quiver fellow, and a’ would manage you his Piece thus; and a’ would about and about, and come you in and come you in: (The Second part of King Henry ・ 3.2.300-303)
その時に実に敏捷な小男がおりましてな、銃をこのようにかまえて、ここと思えばまたあちら、次々的を狙い撃ち、
この ‘you’は小男の敏捷さを強調しているが、同時にその敏捷さに対する感嘆の気持ちが混じってはいないだろうか。いずれにせよ、この‘you’が聞き手を注目させるためのマーカーとして機能していることは確かだ。ここの注には、「‘look you’くらいの気持ちを表わす」とある。(市河 213) 確かに、会話の中で突如として‘you’と呼びかけられれば、聴者は注意を向けないわけにはいかないだろう。
しかし、一方で、 ‘ethical dative’には ‘me’の用法もある。この二つの用法の違いはどこにあるのだろう。いくつか例を挙げる。以下の台詞はTwelfth Nightでサー・トービーがサー・アンドルーにヴァイオラに対して決闘をけしかける場面のものである。
Sir Toby. Go, Sir Andrew; scout me for him at the corner of the orchard, like a bum-baily; (Twelfth-Night 3.4.171-172)
ようし、行け、サー・アンドルー。庭の片隅で借金とりのように見張るんだ。
ここでは ‘me’は命令型の動詞の後に置かれているが、 ‘ethical dative’の ‘me’の用法には命令系で使われているものが多い。次の例もサー・トービーがサー・アンドルーに決闘をけしかける場面からのものだ。ここでも命令型が用いられている。
Sir Toby. Why, then, build me thy fortunes upon the basis of valour. Challenge me the Count’s youth to fight with him; hurt him in eleven places. (Twelfth-Night 3.2.30-32)
ようし、じゃあ勇気をもとでにひと旗あげろ。公爵の若造に決闘申しこんで、やつの体の十一箇所に傷を負わせるんだ。
これら二つの例はSchmidtのSHAKESPEARE LEXICONの ‘ethical dative’の用例から抜粋したものであるが、他の用例も命令型のものが多い。そのことは本レポートの他の箇所で取り上げた用例にもあてはまる。この箇所の注には「この“me”はいわゆるethical dativeで、相手に対する関心の強さを示す強意表現」と書かれている。(安西 173) このことから考えてみると、 ‘ethical dative’の ‘you’は相手の注意を自分に向ける働きを持つのに対して、 ‘me’は相手に行動を促す、あるいは相手の行動を強調する役割があるように思われる。
Chapter 2
前章まで心性的与格‘ethical dative’について論じてきたが、‘ethical dative’に準じたものに心性的属格 ‘ethical genitive’がある。Introductionで触れたボトムの台詞にもこの ‘ethical genitive’が使用されている箇所がある。
Bottom. I will discharge it in either your straw-cioour beard, your orange-tawny beard, your purple-in-grain beard, or your French-crown-colour beard, your perfect yellow. (A Midsummer-Night’s Dream 1.2.85-87)
麦藁色のでやるかな、みかん色がいいか、真っ赤がいいか、フランス金貨の真っ黄色がいいか。
この台詞にも、ボトムの自己顕示欲旺盛な性格があらわれていて面白い。注には「みなさんご存知の」とあるが、(石井 81) これはSchmidtのSHAKESPEARE LEXICONの ‘your’の項目の ‘ethical dative’の用例の冒頭にある ‘Used indefinitely, not with reference to the person addressed, but to what is known and common’という記述と一致する。目立ちたがり屋のボトムはやたらとこの ‘your’を使う。
for there is not a more fearful wild-fowl than your lion living; (A Midsummer-Night’s Dream 3.1.29-30)
生きたライオンくらいおっかない猛きん類はないからな。
I could munch your good dry oats. (A Midsummer-Night’s Dream 4.1.29-30)
極上のカラスムギをむしゃむしゃ食いたいもんだ。干し草ひと束なんてのも悪くない。
As You Like Itのタッチストーンの台詞にも ‘ethical genitive’が多く使われているようだ。
for all your writers do consent that ipse is he; (As You Like It 5.1.42)
あらゆる学者の一致した意見によれば、彼とはその男ということだ
as your pearl in your foul oyster. (As You Like It 5.4.59)
真珠が醜い牡蠣のなかにあるようにね。
Your If is the only peace-maker; (As You Like It 5.4.97)
「もしも」には偉大な力があるんだ。
これらも‘ethical dative’の‘you’同様、相手の関心を自分の話に向けるための注意のマーカーと考えていいだろう。
そして、これら ‘ethical genitive’の ‘your’にも‘ethical dative’同様に話者の感情が込められている場合がある。『新英語学辞典』よれば、‘ethical genitive’には「嘲弄・軽侮の気持ちが含まれることが多い」らしい。次に軽蔑的な意味合いで‘ethical genitive’が使用されている例を挙げる。次の例は父親の亡霊に出会った直後、ハムレットがホレーシオに言う台詞である。
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy. (Hamlet 1.5.166-167)
この天と地のあいだにはな、ホレーシオ、哲学などの思いもよらぬことがあるのだ。
この箇所の注には「“your”は懐疑論者ホレイシオを指すのではなく、「いわゆる」の意(Q2)。Fにはわかりやすく“our”とある」とあり、(高橋151) 文字どおりホレーシオを、あるいはホレーシオの学識を問うものではない。ハムレットは学問全般を問題としているのである。そしてその学問の限界に対して苛立っているのだ。ハムレットの苛立ちは自分に対しても向けられる。次の引用も同じくHamletからのものだ。両親に見せるための芝居の上演直前、ハムレットがオフィーリアを相手に語る台詞である。
Hamlet. O God, your only jig-maker! (Hamlet 3.2.122)
ハムレット しようがあるまい、おれは天下随一の道化役者だからな。
この ‘your’ からは、自分の運命が自分の思うようにいかないことへのもどかしさと、自分の本心を隠して狂気を演じ続けなくてはならないハムレットの、自嘲的な思いを読み取ることができる。もうひとつだけ例を挙げたい。ハムレットはポローニアスを殺した後で、クローディアスにポローニアスの居所を難詰される。そこでハムレットは、ポローニアスは晩餐の最中だと答える。しかし、その晩餐はポローニアスに群がる蛆虫たちの晩餐を指しているのだ。
Your worm is your only emperor for diet: we fat all creatures else to fat us, and we fat ourselves for maggots; your fat king and your lean beggar is but variable service—two dishes, but to one table. (Hamlet 4.3.21-25)
なにしろ蛆虫というやつ、食わせものですからね、食事にかけては王様だ。人間は自分を太らせるためにほかの動物たちを太らせて食う、そして太らせた自分を蛆虫に食わせる。太った王様もやせた乞食も、違った献立の二つの料理だが、食い手は一つだ。
ここで用いられている ‘ethical genitive’の ‘your’からは、ハムレットのクローディアスやポローニアスらに対する侮蔑の感情をありありと感じ取ることができる。
これらの例から、 ‘ethical genitive’の ‘your’は ‘ethical dative’の ‘you’と同様に、話者の関心を引くための注意のマーカーとしての役割を持ち、時に話者の感情を強く主張することもあることが分かる。
Chapter 3
前章までは、 ‘ethical dative’及び ‘ethical genitive’が会話中のある内容を強調する注意のマーカーであり、時に話者の感情を強く主張することについて論じてきたが、 ‘ethical dative’ はそれら以外により具体的な意味を持つ場合もあるようだ。次に挙げた例はHamletからの一節であり、ポローニアスが息子のレアティーズの安否を臣下のレナルドーに探りに行かせる場面のものである。
Enquire me first what Danskers are at Paris; (Hamlet 2.1.7)
先ずパリにはどんなデンマーク人がいるか調べてくれ
ここでも‘me’は命令型の動詞の後に置かれており、相手の行動に焦点を合わせる働きをしている。その言い方は、なにかにつけて大仰な言い方を好むポローニアスの性格にふさわしい。しかし、ここの注には「Sh.に頻出する「心性的与格」(ethical dative)の一例。意味は“for me”で、話者への関心をひくために虚辞的に動詞に添えるもの」とある。(高橋155) ここでの ‘me’は相手の行動を強調する以外にも ‘for me’という具体的な意味を持っているようだ。『新英語学辞典』の ‘ethical dative’の項に次のような記述がある。
心性的与格は利害の与格(DATIVE OF INTEREST)と似ていて区別が明確ではない場合もある。
上記のHamletからの一節はこの例に当てはまるものだろう。次に挙げるThe Taming of the Shrewの一場面でシェイクスピアは ‘ethical dative’のこのような性質を逆手にとって、一つのコミカルな場面を作り上げている。ペトルーキオが召使いに「ドアを叩け」と言う際にこの ‘me’を挿入し、「俺を叩け」と誤解されて騒動がもちあがる。[iii]
Grumio. Knock, sir? Whom should I knock? Is there any man has rebused your worship?
Petruchio. Villain, I say, knock me here soundly.
Grumio. Knock you here, sir? Why, sir, what am I, sir, that I should knock you here, sir?
Petruchio. Villain, I say, knock me at this gate,
And rap me well, or I’ll knock your knave’s pate.
(The Taming of the Shrew 1.2.6-12)
グルーミオ たたく! どいつをたたくんで、旦那様? だれか旦那様にヒツ礼なまねでもしたんですか?
ペトルーチオ ばか野郎、ここへきて力いっぱいたたけと言ってるんだ。
グルーミオ そこへ行ってですか、旦那様? たたくんですか、旦那様? 旦那様を? いやいや、あたしにはできませんや、旦那様、旦那様をたたくなんてことは!
ペトルーチオ ばか野郎、この門をたたけと言ってるんだ、能なしめ、しっかりたたかんときさまの脳なし頭をたたき割るぞ。
グルーミオはわざと曲解したのかもしれないが、当時の人々にとっても紛らわしい表現だったのではないか。次の例も ‘ethical dative’とも ‘dative of interest’とも、どちらとも取れそうだ。
Ariel. Is there more toil? Since thou dost give me pains,
Let me remember thee what thou hast promis’d,
Which is not yet perform’d me. (The Tempest 1.2.242-244)
エアリアル まだ仕事があるのですか? これ以上働かせるなら、お約束なさったことを思い出してくださいよ、まだそのままなのですから。
この箇所の注には「‘me’は話者の関心をはっきり示すために挿入された代名詞の目的格で、心性的与格(ethical dative)とよばれているもの」とあるが(藤田97) 利害の与格ともとれる。次の例も同様である。
In these times you stand on distance, your passes, stoccadoes, and I know not what. ’Tis the heart, Master Page, ’Tis here, ’Tis here. (The Merry Wives of Windsor 2.1.213-216)
近ごろは、やれ間合いがどうの、やれお突きやお胴がどうのと、うるさく言うことがはやっているようだが、問題は勇気ですよ、ページさん、ここですよ。
この例はSchmidtのSHAKESPEARE LEXICONでは ‘ethical dative’に分類されているが、注には “Almost equivalent to ‘for you’”とあり、(Oliver 1971, 49) 区別は難しい。次に挙げるSHAKESPEARE LEXICONからの二つの用例も同様である。
imagine me,
Gentle spectators, that I now may be
In fair Bohemia; (The Winter’s Tale 4.1.19-21)
どうかご観覧の皆様、私がいまおります舞台は一転して美しいボヘミアであるとご想像ください。
I’ll do you your master what good I can. (The Merry Wives of Windsor 1.4.87)
あんたの旦那のことは私に任せて、できるだけのことはするから。
このように場合によっては ‘ethical dative’と ‘dative of interest’の区別をつけることは難しい。そのため、『新英語学辞典』によると、 ‘ethical dative’を ‘dative of interest’の一種とみなす研究者もいるようだ。[iv]さらに、同じく『新英語学辞典』によれば、 ‘ethical dative’は「英語ではMEから用いられるようになり、初期ModEには口語(特に俗語)によく見られる」が、「ModEでは古風な表現になり、代わりにfor youなどが用いられる」ようになったとある。つまり、初期ModE時代に会話体で書かれたシェイクスピア作品に頻出する ‘ethical dative’は、強意の役割を次第に失っていき、 ‘dative of interest’としての役割が ‘for you’という形に吸収されていったと考えられる。
Conclusion
Chapter 1では、‘ethical dative’は単なる意味のない挿入語句ではなく、聞き手の注意を惹起するマーカーであり、話者の感情を反映したものであるということを論じた。また、‘ethical dative’の ‘you’は相手の注意を自分に向ける働きを持つのに対して、 ‘me’は相手の行動を強調する役割があるということについて述べた。
Chapter 2では、 ‘ethical dative’に関係の近い ‘ethical genitive’について言及し、‘ethical genitive’の ‘your’は ‘ethical dative’の ‘you’と同様に、話者の関心を引くための注意のマーカーとしての役割を持ち、時に話者の感情を強く主張することもあると論じた。
Chapter 3では、 ‘ethical dative’と ‘ethical genitive’との違いについて論じ、初期ModEで書かれたシェイクスピア作品に頻出する ‘ethical dative’は、注意のマーカーとしての役割を次第に失っていき、‘dative of interest’としての役割が、やがてModEの ‘for you’という形に吸収されていったのではないかという仮説を提示した。
参考文献
G. L. ブルック 『シェイクスピアの英語』 訳者 三輪 信春・佐藤 哲三・濱崎 孔一廊 東京: 松柏社 1998.
石橋 幸太郎 『現代英語学辞典』 東京: 成美堂 1973.
大塚 高信・中島 文雄 『新英語学辞典』 東京: 研究者 1882.
Schmidt, Alexander. Shakespeare Lexicon and Quotation Dictionary. Rev. Gregor Sarranzin. New York: Dover Publications, 1971.
Shakespeare, William. A Midsummer-Night’s Dream. 編注者 石井 正之助 東京: 大修館書店 1987.
Shakespeare, William. As You Like It. 編注者 柴田 稔彦 東京: 大修館書店 1989.
Shakespeare, William. British Library Cataloguing in Publication Data The Taming of the Shrew. Ed. Oliver, H. J. United States: Oxford University Press, 1982.
Shakespeare, William. Hamlet. 編注者 高橋 康也・河井 祥一郎 東京: 大修館書店 2001.
Shakespeare, William. Julius Caesar. 編注者 大場 建治 東京: 大修館書店 1989.
Shakespeare, William. Othello. 編注者 笹山 隆 東京: 大修館書店 1989.
Shakespeare, William. The Arden Edition of the Works of William Shakespeare The Merry Wives of Windsor. Ed. Oliver, H. J. United States: Muthuen & Co Ltd, 1971
Shakespeare, William. The Kenkyusha Shakespeare The Second Part of King Henry ・. 注釈者 市河 三喜・嶺 卓二 東京: 研究社出版 1963.
Shakespeare, William. The Tempest. 編注者 藤田 実 東京: 大修館書店 1990.
Shakespeare, William. The Winter’s Tale. Ed. Schanzer, Ernest. London: Penguin Books, 1986.
Shakespeare, William. Twelfth Night. 編注者 安西 徹雄 東京: 大修館書店 1987.
マンフレート・シェーラー 『シェイクスピアの英語—-言葉から入るシェイクスピア—-』 訳者 岩崎 春雄・宮下 啓三 東京: 英潮社新社 1990.
Simpson, J. A. The Oxford English Dictionary. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989.
Notes
[i] 「民衆的な「関心の与格」というのは今日方言では盛んに使われているとはいえ標準語では古風となっているが、シェイクスピアでは珍しいものではない。この与格は、話し手がその陳述に対して心の中で関心をもっていることを表わすものであり、くだけた会話に現れる」(シェーラー 33-34)
以下、引用文中の下線は筆者による。
[ii] ブルックの『シェイクスピアの英語』にも同様の記述がある。「前置詞を伴わない代名詞の特殊な用法のひとつに心性的与格(ethical dative)がある。その代名詞の指す人物が、表された出来事に特別な関心を持っていることを示すのに語りで用いられる。心性的与格は語りを一層生き生きとしたものにするのに用いられる口語表現手段である」(ブルック 117)
[iii] この箇所の注に次のような記述があった。
A regular Elizabethan use (Abbott 220) of the so-called ‘ethic dative’ – roughtly equivalent to ‘ knock here for me’ – but Grumio chooses to take ‘me’ as the grammatical object of ‘knock’. (Oliver 1982, 119)
つまり、グルーミオはわざと誤解した。
[iv] 次に挙げるのは『新英語学辞典』の ‘ethical dative’の項からの抜粋である。「心性的与格がこのように利害の与格に近いところからJespersen (MEG, Vol. 3 ∬14.4 2)は心性的与格を利害の与格の一種とする。また心性的与格は文の構造上は余分な目的語であるというので、Poutsma (Grammar, Vol. 1, ch. 3, ∬7-9)は過剰目的語(redundant object)と呼び、感情的要素を添え文体に生気を与えるところからJestersenは感情的間接目的語(emotional indirect object)と呼ことをすすめている。」
このように学者間の意見にも多少のばらつきがある。
2008/05/02/20:56
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
Shakespeareのソネットに見る「時」
米田拓男
Introduction
Shakespeareのソネット作品について論じる。場合に応じて同時代の他の詩人の作品にも触れたいと思う。Shakespeareのソネットには「時」についての記述が多い。ShakespeareのThe Sonnetsは、126番まではShakespeareの恋人と思われる青年に対する愛を描いたもので、127番以降は一般に「黒い女」と呼ばれている謎の婦人に捧げられている。ここではThe Sonnets前半の126番までを扱いたいと思う。詩を捧げられているその青年はだいぶ年若いようで、それらの詩の中には「時」や「老い」についての記述が多く見られる。127番以降には「時」ついての言及はあまり見られない。
本論では、ShakespeareのThe Sonnetsの成立経緯に簡単に触れた後、The Sonnetsで「時」がどのように表現されているか、Shakespeareがどのような姿勢で「時」に対峙していたかを見る。そして最終章では「時」とは切り離せないテーマであるカルペ・ディエムが、The Sonnetsの中でどのように表現されているのかを見たいと思う。
Chapter 1 ShakespeareのThe Sonnets
イタリアのルネサンス詩人Petrarchに始まる恋愛ソネットの伝統は、全ヨーロッパに広がり、イギリスではヘンリー八世時代にThomas WyattやHenry Howard、 Earl of Surreyらによって輸入された。エリザベス一世時代になるとPhilip Sidneyが‘Astrophel and Stella’を、Edmund Spenserが’Amoretti’をそれぞれ恋人にあてて書いた。そしてShakespeareはそれらの流れを引き継ぎ、恐らくRomeo and Julietを書いた頃に、The Sonnetsを書いていたと考えられている。その後ソネット形式は、ミルトンなどの後世の詩人たちに引き継がれていった。
ShakespeareのThe Sonnetsは謎に満ちている。ShakespeareがThe Sonnetsで愛を告白している、「黒い女」と青年は、今日では誰なのか分からない。Shakespeareと2人の関係も謎に包まれている。また、ここに描かれていることは、Shakespeareが実際に体験したことに基づいているのか、それとも全くの創作なのか、それも今日では確かめるすべが無い。
ShakespeareのThe Sonnetsには、当時流行していたらしいペトラルカ風恋愛ソネットの技巧的な愛の告白や誇張に満ちた修辞に対する批判が垣間見えるという。(岩崎 11)実際に、そういった過去の詩人や技法に対する批判的な姿勢は、ソネット21番に見ることができる。
So is it not with me as with that Muse
Stirr’d by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use
And every fair with his fair doth rehearse
Making a couplement of proud compare,
With sun and moon, with earth and sea’s rich gems,
With April’s first-born flowers, and all things rare
That heaven’s air in this huge rondure hems.
(21.1-8)
「当時輩出した恋愛ソネット連作の中で、男を対象にして愛を歌ったものは他にない」という。(高松 286)そうであるならば、上記の記述も考えあわせれば、The Sonnetsは当時においては非常に野心的、実験的な作品だったのでは無いだろうか。流行の恋愛詩に対する風刺的意味合いも強かっただろう。
Chapter 2 The Sonnetsにおける「時」の記述
The Sonnetsに出てくる「時」に関する描写を読む限りでは、Shakespeareにとって「時」はマイナス・イメージを伴うもののようだ。ほとんどの場合において「時」は美の破壊者として描かれている。例えば次の部分。
Devouring Time, blunt thou the lion’s paws,
And make the earth devour her own sweet brood;
Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws,
And burn the long-lived phoenix in her blood;
Make glad and sorry seasons as thou fleets,
And do whate’er thou wilt, swift-footed Time,
To the wide world and all her fading sweets;
But I forbid thee one most heinous crime:
(19.1-8)
このソネットでは「時」に「全てを食い尽くす時よ」と呼び掛け、その残忍さを強調している。ShakespeareのThe Sonnetsには青年の美しさと、それを奪う時の残虐さが常に並べて描かれている。美しいものもやがては失われるのだと。
Then of thy beauty do I question make,
That thou among the wastes of time must go,
Since sweets and beauties do themselves forsake
And die as fast as they see others grow;
(12.9-12)
Shakespeareは全ての美しいものが、いずれ必ず「時」によって破壊されるという認識を持っている。それを表す一つの例として、次の13番には「期限付きで借りている美しさ」という表現がある。
So should that beauty which you hold in lease
Find no determination:
(13.5-6)
「時」はShakespeareにとっては、いずれ誰のもとにもやって来る美の債務者なのだ。そのため「時」は死のイメージに直結する。
When I have seen such interchange of state,
Or state itself confounded to decay;
Ruin hath taught me thus to ruminate,
That Time will come and take my love away.
This thought is as a death, which cannot choose
But weep to have that which it fears to lose.
(64.9-14)
ShakespeareのThe Sonnetsには、例えばEdmund Wallerの’Old Age’ のように、成長して物事を見通す力を持てるようになったといったような、「時」に対する積極的な意義について書かれている箇所が無い。成長については書かれている箇所はいくつかあるが、必ず「老い」と対になっている。次の5番では、卓越した技術でせっかく作り上げた美を、その同じ手で破壊する「時」の残忍さをなじる。
Those hours, that with gentle work did frame
The lovely gaze where every eye doth dwell,
Will play the tyrants to the very same
And that unfair which fairly doth excel:
(5.1-4)
「時」について描かれている他の詩人の作品、例えばJohn Miltonのソネット形式で書かれた、初期の抒情詩’On His being Arrived at the Age of Twenty-Three’では、
How soon hath Time, the subtle thief of youth,
Stolen on his wing my three-and-twentieth year!
(1-2)
と、「時」を‘thief of youth’と否定的に表現している。しかし、同じ詩の後半では、「時」を自分自身を導いてくれるものとして肯定的に受け取っている。
Yet be it less or more, or soon or slow,
It shall be still in strictest measure even
To that same lot, however mean or high,
Toward which Time leads me, and the will of Heaven:
(9-12) (以下、下線筆者)
ShakespeareのThe Sonnetsにはこのような描写は見られない。総じてShakespeareのThe Sonnetsにおける「時」の表現の特徴は、徹底的にネガティブなものとして表現されているところにあるといえるだろう。
Chapter 3 The SonnetsにおけるShakespeareの「時」に対する姿勢
Shakespeareは「時」を完全なる悪として表現しており、The Sonnets中、一貫して「時」に対抗する姿勢を貫いている。Shakespeareにとって、「時」に対抗することは、即ち美を保存することである。その手段は、(1)美しい人の子孫を残すこと、(2)美しい人を詩に書いて、後世に残すことである。
ShakespeareのThe Sonnetsは次の一節で始まる。
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty’s rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
(1.1-4)
ここでShakespeareは、一人の青年の美しさを賛美し、彼に結婚をして子孫を残すことを奨めている。ソネット1〜17番目まで、Shakespeareは一貫して青年の美しさと説き、結婚を奨める。11番では、美しいものだけが子孫を残し、醜いものは滅べばいいとまで言う。
Let those whom Nature hath not made for store,
Harsh featureless and rude, barrenly perish:
Look, whom she best endow’d she gave the more;
Which bounteous gift thou shouldst in bounty cherish:
(11.9-12)
12番でShakespeareは「時」に対する対抗意識をはっきりと打ち出す。そしてその唯一の手段として子孫を残すことを説く。
And nothing ‘gainst Time’s scythe can make defence
Save breed, to brave him when he takes thee hence.
(12.13-14)
同様に、14、16、17番と、「時」に対抗するには、子孫を残すことの方が詩を書くことよりも有効であると説明している。しかし、17番以降、青年に結婚を奨めることは二度と無くなる。それ以降は時への対抗手段として、詩の力が強調されてくる。
最初に「時」に対する詩の力を高らかに歌い上げるのが15番である。このソネットは「時」に対する宣戦布告ととることができる。
And all in war with Time for love of you,
As he takes from you, I engraft you new.
(15.13-14)
以降、
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.
(18.13-14)
Yet, do thy worst, old Time: despite thy wrong,
My love shall in my verse ever live young.
(19.13-14)
と、自分の詩才に対する自信を深めていく様子を感じ取ることができる。さらに、
Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall outlive this powerful rhyme;
(55.1-2)
で始まる55番は、「時」に対する詩の高らかな勝利宣言だ。
100、101番のソネットには、時の神‘Time’に対して詩の女神‘Muse’への呼び掛けも出てくる。
Then do thy office, Muse; I teach thee how
To make him seem long hence as he shows now.
(101.13-14)
18番からを境に、Shakespeareの「時」への対抗手段が(1)子孫を残すことから、(2)詩を書くことへと移項したことが分かるだろう。一方で、Shakespeareの青年に対する態度も変化してくる。10番の、
Make thee another self, for love of me,
That beauty still may live in thine or thee.
(10.13-14)
という表現などを見ると、最初はどうやら相手の方から求愛してきたらしいことが伺える。最初の1〜17番までのShakespeareの青年に対する態度は、相手に結婚を奨めるなど、年上らしく冷静に振る舞って相手からの求愛を断るかのような態度をとり続けている。しかし、18番以降は、あたかも美の下僕となって青年の美しさを書きとどめようとしているかのようだ。
And yet to times in hope my verse shall stand,
Praising thy worth, despite his cruel hand.
(60.13-14)
His beauty shall in these black lines be seen,
And they shall live, and he in them still green.
(63.13-14)
You still shall live–such virtue hath my pen–
Where breath most breathes, even in the mouths of men.
(81.13-14)
Shakespeareは、「時」に打ち勝とうとして、相手の美しさを詩に保存しようとする。しかし、これらの詩から伝わってくるのは相手の美しさではない。実際、青年がどんな姿をしているのかについての具体的な描写は、全く書かれていないように思われる。The Sonnetsを読んでいて見えてくるのは、むしろ、年若い青年を前にしてのShakespeare自身の老い、そしてその年齢差を補うものとしての自分の詩才に賭けるShakespeare自身の姿である。
Chapter 4 The Sonnetsに見るカルペ・ディエム
カルペ・ディエムとは中世以来の「今日という日を楽しめ」という典型的なテーマの一つである。ShakespeareのThe Sonnetsにもカルペ・ディエム的テーマが散見される。例えば相手を薔薇の花に例えて、花の命は短いのだから盛りのうちに人生を謳歌せよ、と恋人に説くのはカルペ・ディエムの典型的な表現と言っていい。The Sonnetsにもそのような表現がある。
Then, were not summer’s distillation left,
A liquid prisoner pent in walls of glass,
Beauty’s effect with beauty were bereft,
Nor it nor no remembrance what it was:
But flowers distill’d though they with winter meet,
Leese but their show; their substance still lives sweet.
(5.9-14)
このソネットでは、花の命は短いからその香りを蒸留して残しておきなさいと説く。香りを蒸留して残しておくとは具体的に何を指しているのか。続く6番にその答えがある。
115、がしつのいらしいeaven:,
ven
ar!
Then let not winter’s ragged hand deface
In thee thy summer, ere thou be distill’d:
Make sweet some vial; treasure thou some place
With beauty’s treasure, ere it be self-kill’d.
(6.1-4)
ここで述べられているのは具体的には花の盛りのうちに子孫を残せ、ということである。しかし、先に述べたように時への対抗手段が(1)子孫を残すことから、(2)詩に残すことへ移行したのを受けて、54番のソネットでは自分の詩作の力によって蒸留するというように読み替えてある。
And so of you, beauteous and lovely youth,
When that shall fade, my verse distills your truth.
(54.13-14)
ここにきて思い至ったのだが、そういえばShakespeareのA Midsummer-Night’s Dreamにも同様の表現があった。
Thrice-blessed they that master so their blood,
To undergo such maiden pilgrimage;
But earthlier happy is the rose distill’d,
Than that which withering on the virgin thorn
Grows, lives and dies in single blessedness.
(1.1.74-78)
花を蒸留するというmetaphorはShakespeareが気に入っていた表現なのかも知れない。他にもカルペ・ディエムと重なるテーマを持つソネットがいくつかある。例えばソネット4番がそれだ。
Unthrifty loveliness, why dost thou spend
Upon thyself thy beauty’s legacy?
Nature’s bequest gives nothing but doth lend,
And being frank she lends to those are free.
Then, beauteous niggard, why dost thou abuse
The bounteous largess given thee to give?
Profitless usurer, why dost thou use
So great a sum of sums, yet canst not live?
(4.1-8)
ここでは、自分の美しさを一人占めせず、結婚しろと説いている。この表現もカルペ・ディエムの変奏のように思う。これと同様の表現がRomeo and Julietの中にある。ロミオが、ロザラインが貞潔の誓いをたてていることを、美の浪費だといって嘆く場面である。
ROMEO O, she is rich in beauty, only poor,
That when she dies with beauty dies her store.
BENVOLIO Then she hath sworn that she will still live chaste?
ROMEO She hath, and in that sparing makes huge waste,
For beauty starved with her severity
Cuts beauty off from all posterity.
(1.1.215-220)
Romeo and JulietもA Midsummer Night’s Dreamも、The Sonnetsが書かれたのと同時期に執筆されたと考えられているから、似たような表現が入り込んでいるのかも知れない。それはともかくとして、本レポートのChapter 1で、Shakespeareは恋愛詩の伝統に対して批判的な考えを持っているのではないかと書いたが、ここで見たように、カルペ・ディエムといった恋愛詩の伝統を引き継いでいることもまた確かなのだ。Shakespeareのソネット73番は、恋愛詩の伝統を踏まえた上で、実にShakespeareらしいカルペ・ディエムの表現になっているように思う。
That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin’d choirs, where late the sweet birds sang.
In me thou seest the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west,
Which by and by black night doth take away,
Death’s second self, that seals up all in rest.
In me thou see’st the glowing of such fire
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed whereon it must expire
Consumed with that which it was nourish’d by.
This thou perceivest, which makes thy love more strong,
To love that well which thou must leave ere long.
(73)
ここに描かれているのは老いを前にしたカルペ・ディエムである。カルペ・ディエムとはもちろん、自分、あるいは相手が老いることを前提とした考え方であるが、このソネットでは相手の目に映る自分の老いの描写が延々と12行目まで続く。そして最後のcoupletで、やがて別れが来るからこそ、君はいま私をより強く愛するのだと綴る。
カルペ・ディエムをテーマにした他の詩人たちの作品、例えば、Edmund Spenserの’The Song of the Rose‘であるとか、Robert Herrickの’To the Virgins, to Make Much of Time’、Andrew Marvellの’To His Coy Mistress’などに比べて、Shakespeareのソネット73番は悲愴感に包まれている。Edmund Spenserや、Robert Herrickらの作品は、もっと華やかで、開放感に満ちていて、時にユーモラスな印象をさえ受ける。
それに対して、このソネット73番にあるものは、開放感というよりも閉鎖感、ユーモアよりも苦渋である。Edmund Spenserらの伝統的なカルペ・ディエムをテーマにした作品と受ける印象が全く異なるので、ソネット73番はひょっとすると、カルペ・ディエムをテーマにした詩とは看做されないのかも知れない。しかし、ここに表現されている感情に僕はリアリティーを感じる。例えば、相手の視線から自分の老いを描いているところに、作者の屈折した感情を見るようでリアルに思える。
そのように作者が屈折せざるを得なかったのは相手が同性だったからだろうか。それとも、2人の間に年令差があったからだろうか。Shakespeareのソネットにはどこか影があるように感じる。ShakespeareのソネットがEdmund Spenserらの詩のように開放感に溢れたものになっていないのは、2人の間の障害が大きかったせいかもしれない。障害が大きかったからこそ、表現される感情は切実さを増したのではないか。ロミオとジュリエット、あるいは、ハーミアとライサンダーのように。いずれにせよ、年齢差のある相手に向かってソネットを書き、自らの老いと対峙することになったShakespeareが、「時」を敵視することになったのは必然であったろう。
Conclusion
The Sonnetsに見る「時」の表現は必ずマイナス・イメージを伴っている。Shakespeareは「時」を美の破壊者であると考えている。彼は、美を保存することが、「時」に対抗する手段であると考える。作中、彼は「時」に対する対抗策を二つ挙げている。それは(1)美しい人の子孫を残すこと、(2)美しい人を詩の中に残すこと、である。17番までのソネットでは、(1)の子孫を残すことを唱えているが、18番以降は(2)の考えに移行し、詩が持っている力を強調するようになり、「時」に対抗して美を保存することが、詩人の使命であるかのような姿勢を示すようになる。年齢差のあった青年にソネットを書くことによって、自分の老いと対峙したShakespeareが「時」を敵視したのは当然であった。
引用文献
神山 妙子 編著 『はじめて学ぶ イギリス文学史』 東京: ミネルヴァ書房, 1989.
ウィリアム・シェイクスピア 『大修館シェイクスピア双書 夏の夜の夢』 編者 石井 正之助 東京: 大修館書店, 1987.
ウィリアム・シェイクスピア 『夏の夜の夢 間違いの喜劇 シェイクスピア全集4』 訳者 松岡 和子 東京: 筑摩書房, 1996.
ウィリアム・シェイクスピア 『大修館シェイクスピア双書 ロミオとジュリエット』 編者 岩崎 宗治 東京: 大修館書店, 1988.
ウィリアム・シェイクスピア 『ロミオとジュリエット シェイクスピア全集2』 訳者 松岡 和子 東京: 筑摩書房, 1996.
Shakespeare, William. The Sonnets. ed. G. Blakemore Evans. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
ウィリアム・シェイクスピア 『ソネット集 シェイクスピア作』 訳者 高松 雄一 東京: 岩波書店, 1986.
平井 正穂 編 『イギリス名詩選』 東京: 岩波書店, 1990.
2008/05/02/20:55
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
『十二夜』の「音楽」
〜恋の三重奏〜
米田 拓男
『十二夜』はOrsinoの意味深長な台詞で幕を開ける。
If music be the food of love, play on,
Give me excess of it, that, surfeiting,
The appetite may sicken and so die.
(1.1.1-3)(下線筆者)
音楽が恋を育む食べ物なら、続けてくれ。
嫌というほど聴かせてくれ。そうすれば飽きがきて
食欲は衰え、やがて死に絶えるだろう。
この台詞は何を意味しているのだろうか。音楽が、恋の食べ物であるとはどういう事なのだろう。『十二夜』には音楽を奏でたり、歌を歌ったりする場面がたくさん出てくる。これだけ音楽が出てくるからには、シェイクスピアは音楽に何か特別な意味や効果を持たせようとしているはずだ。
そこで僕はコンコーダンスで ‘music’ を引いてみた。すると ‘music’という単語は、『十二夜』全編の中で計6回出てくる事がわかった。ここでその6つを挙げてみる。
1. ORSINOの (1.1.1-3) の台詞。上に記載。
2. Thou shalt present me as an eunuch to him;
It may be worth thy pains, for I can sing
And speak to him in many sorts of music,
That will allow me very worth his service. (1.2.56-59)
私をお小姓として推薦して。
お骨折りは無駄にしません。だって私、歌が歌えるし、
楽器もいろいろ弾いてお聴かせできるし、
おそばに仕えるには打ってつけでしょう。
3. Duke. Give me some music. Now, good morrow,
friends.
Now, good Cesario, but that piece of song,
That old and antique song we heard last night; ‘
Methought it did relieve my passion much,
More than light airs and recollected terms
Of these most brisk and giddy-paced times.
Come, but one verse.
(2.4.1-7)
公爵 何か音楽を。やあ、おはよう、諸君。
そうだ、シザーリオ、あの歌がいい、
ゆうべ聴いただろう、昔の古風な歌だ。
おかげで胸の苦しみがすっかりやわらいだ。
せかせかと目まぐるしい今の世の中、
それに合わせたわざとらしい歌詞の、軽い曲よりずっといい。
さあ、せめて一節。
4. Viola. Save thee, friend, and thy music! Dost thou live
by thy tabor ? (3.1.1-2)
ヴァイオラ やあ、ご機嫌よう、君の音楽もご機嫌だね! 君はその小太鼓のお蔭で暮らしてるんだ。
5. Olivia. O, by your leave, I pray you:
I bade you never speak again of him;
But, would you undertake another suit,
I had rather hear you to solicit that
Than music from the spheres.
(3.1.105-109)
オリヴィア ああ、悪いけど、お願い!
公爵のことは二度と口にしないで。
でも、それとは別の願い事がおありなら
喜んでうかがうわ、天の星々が奏でる音楽
を聴くより嬉しい。
6. Olivia. If it be aught to the old tune, my lord,
It is as fat and fulsome to mine ear
As howling after music.
(5.1.104-106)
オリヴィア ご用向きがいつもと同じ調べでしたら、
私の耳にはうとましくうるさいものでしかありません、
音楽のあとの犬の遠吠えのよう。
これらを見てみると、この6つの台詞は、1.と3.がOrsino、2.と4.がViola、5.と6.がOliviaのものである事が分かる。『十二夜』に描かれる主要人物たち、片思いの円環をなす3人がそれぞれ2回づつ ‘music’ という言葉を使っている、というのが面白い。
それぞれの人物における ‘music’ という言葉の使われ方を見てみると、Orsinoの場合は、2回とも音楽を聞かせてくれと求めるかけ声として用いられている。Oliviaは、音楽を別のものとの比較対象として用いている。5.では音楽を聞くよりViolaの望みを聞く方が嬉しいと言い、6.では公爵の求愛が音楽の後のうなり声のようにうんざりするものだと言っている。Violaは2.では自分の音楽の才能について言及し、4.では道化の音楽の才能を祝福している。
ここから、3人それぞれの音楽の捉え方が分かってくる。Orsino は音楽と食べ物の比喩に見られるように、音楽に対してロマンティックな思い入れを持っている。それに対してOliviaは音楽を心地よいものであるとは思いながらも、他の物と比較する冷静さを持っており、醒めた見方をしている。Violaは、上記2人が音楽の受け手(リスナー)であるのと異なり、実際に歌も歌い、楽器も弾くプレイヤーである。Violaが自分とFesteの音楽的才能について言及しているのは、それを反映しているのではないか。
この3者3様の音楽観は、3人の恋愛観にも結びついているように思う。Orsino は音楽に対してと同じように、恋愛に対してもロマンティックな捉え方をしていて、Oliviaは恋愛も音楽同様、現実的な醒めた見方をしている。 Violaは、自分の屋敷で相手の出方を伺っているOrsinoとOliviaという2人の恋の聞き手の間を、伝令役として行ったり来たりと駆け回る。
そして物語は最終局面を迎える。そこでは3人の片思いの環は解かれ、3組みのカップルが誕生する。そこでのOrsino とOliviaの心変わりはあまりに唐突な印象を受けるが、2人の音楽観、恋愛観を鑑みれば多少の納得は行く。音楽に酔っている自分に酔うタイプの Orsinoは、自己陶酔的なロマンティックな幻想を打ち壊され、あっさりとViolaに心変わりをする。計算高い冷静な目を持つOliviaは、相手が Cesarioでないと分かっても、相手の容姿と出自に不足がない事を見極めてか、すんなりと受け入れてしまう。そして、Violaだけが自分の望みを叶えるのだ。
物語は最後、冒頭のOrsinoの台詞に答える形で、Festeの歌う歌で終わる。その歌では、ありふれた人の一生が歌われている。私達はきっとこの歌のように、くり返される風と雨の中を、Sir TobyやFesteたちが歌を歌い浮かれ騒ぐように、年をとり一生を終えるのだ。恐らく、死ぬまで飽きることなく音楽を食べ続けながら、Orsinoのように恋の夢を見て生き続けるのだ。
参考文献
ウィリアム・シェイクスピア 『十二夜』 訳者 松岡 和子 東京: 筑摩書房 1998.
ウィリアム・シェイクスピア 『十二夜』 編者 安西 徹雄 東京: 大修館書店 1987.
Shakespeare Concordance.
2008/05/02/20:55
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
Bottom’s Dream
米田 拓男
Introduction
ShakespeareのA Midsummer-Night’s Dreamの中で、僕が特に注目したい登場人物はボトムである。ボトムはこの喜劇作品の中で最も喜劇的な人物であり、職人から、ロバ、ピラマスと3回も変身する変化の多い派手なキャラクターだ。またボトムは作中、妖精を見ることが出来る唯一の人間でもある。ボトムは、本作中とても重要な役割を担っていると思う。そこで今回、僕は、ボトムの登場場面を中心にテキストを精読していった。そして、1つの謎に行き当たった。それは、ボトムは、ロバに変身している間は言い間違えをしないということだった。一体、何故なのだろう。その謎を解こうとしているうちに2つの語の使われ方が気になった。’ass’と’wood’である。本レポートでは、ボトムがロバに変身している間は何故言い間違いをしないのか、という問いに答えようと試みつつ、ボトムの言い間違いのヴァリエーションと、’ass’の二重性、’wood’の特殊な用法に付いて言及する。
Chapter 1 ボトムは何故ロバに変身したのか?–‘ass’の二重性について–
物語の中盤で職人たちが森で芝居の稽古をしていると、パックがボトムの頭をロバの頭に変えてしまう。ロバに変身するところから、「ボトムの夢」が始まると言っていい。何故、Shakespeareはここでロバという動物を選んだのだろうか。
Alexander SchmidtのShakespeare Lexicon and Quotation Dictionaryには、’the animal Asinus’という記述しか無い。そこでOEDを引いてみた。すると、動物のロバの他の用法が出ていた。’ass’のsb.1の用法として、
2. Hence transf. as a term of reproach: An ignorant fellow, a perverse fool, a conceited dolt. Now disused in polite literature and speech.
とあり、’ass’には無知な人物や、鈍感な人物に対する侮蔑的な意味があることが記されている。さらに、
c. The ass has, since the time of the Greeks, figured in fables and proverbs as the type of clumsiness, ignorance, and stupidity; hence many phrases and proverbial expressions. (Chiefly since 1500; the early references to the animal being mostly Scriptural, with no depreciatory associations.)
という記述から、ギリシャ時代からロバには無知や鈍感といったイメージとのつながりがあったらしいことが分かった。A Midsummer-Night’s Dreamが書かれたのは、1595-96年頃と推定されているので、これはその頃には一般的に知られていた用法であると考えられる。
実際、OEDの
d. to make an ass of : to treat as an ass, stultify. to make an ass of oneself: to behave absurdly, stultify oneself.
という項にMNDの用例が出ていた。引用されていたのは次の箇所である。
This is to make an ass of me; to fright me, if they could.
(3.1.113-114)(下線筆者)
これはボトムの台詞であるが、’ass’ を侮蔑的な意味合いで使っているボトム自身が、実際にロバに変身させられていて面白い。これは、この用法の最も古い使用例になっている。assのこの用法は、ひょっとするとシェイクスピアがつくり出したものなのかも知れない。いずれにせよ、シェイクスピアがボトムをロバに変身させたのは、言い間違いをしょっちゅうしているような、ボトムの軽率な側面にかけてのことだろう。
Chapter 2 何故、森に行ったのか?–‘wood’と‘mad’の関係について—
A Midsummer-Night’s Dreamで、ボトムと恋人たちが不思議な経験をするのが森の中であるということは特に注目に値することなのではないだろうか。ボトムがassに変わったのと同様、そこには意味があるはずだ。
劇中、’wood’という語は16回使用されている。そのうちほとんどがforestの意味で使われている。しかし、その中で例外的な用法を2つ見つけた。その一つ目は、
DEMETRIUS I love thee not, therefore pursue me not.
Where is Lysander and fair Hermia?
The one I’ll slay, the other slayeth me.
Thou told’st me they were stolen unto this wood;
And here am I, and wode within this wood,
Because I cannot meet my Hermia.
Hence, get thee gone, and follow me no more.
(2.1.188-194)
である。ここでの表記は’wode’になっているが、OEDには’wood’の古い表記の一つの例として載っている。石井正之助氏の注には
and wood=and mad (frantic)「気が狂いそう」。次のwood(森)にかけたしゃれ。
とある。そこでShakespeare lexiconで’wood’を引いてみると、形容詞的用法として、madやfranticの意味があると出ていた。OEDには、方言、あるいは、廃れた語として、
wood, a. (sb.2, adv.) Obs. exc. dial. or rare arch.
1. Out of one’s mind, insane, lunatic: = MAD a. ・
とあった。ついでにmad a. ・を引いてみたところ、
Suffering from mental disease; beside oneself, out of one’ mind; insane, lunatic. In mod. use chiefly with a more restricted application, implying violent excitement or extravagant delusions: Maniacal, frenzied.
とあった。しかし、OEDでMNDに触れられていたのは、
b. Violently angry or irritated; enraged, furious.
という用法においてであった。
いずれにしても、’mad’という言葉は、’go mad’で怒ることを表現するように、冷静さを失った状態をさす言葉だ。
しかし、何故’wood’に’mad’の意味があるのだろう。イギリスの森は平坦であると聞く。日本の森では迷ったら下山すればよいが、平地の森ではそうはいかない。MNDの舞台はアテネだが、西欧には森へ入って気が狂うというイメージがあるのかもしれない。森に迷って正気を失う、そんなところから生まれた言葉なのではないか。だとすれば、夢の舞台に森を選んだのは理に適っている。
MNDには、もう一つ’wood’の特殊な用法がある。ボトムが森でタイテイニアと会う場面である。
BOTTOM Not so, neither: but if I had wit enough to get
out of this wood, I have enough to serve mine own turn.
TITANIA Out of this wood do not desire to go:
Thou shalt remain here, whether thou wilt or no.
(3.1.140-143)
石井正之助氏の注には、’go (be) out of the wood’には‘危機を脱する’意味があると出ている。そこでOEDを引いてみたところ、
5. Phrases and Proverbs. a. in a wood: in a difficulty, trouble, or perplexity; at a loss.
という用法が出ていた。ひょっとするとボトム自身、あたりのただならぬ様子に危機を感じていたのかもしれない。
Chapter 3 ボトムは何故、言い間違えなくなったのか?
ボトムはロバに変身するまでの間、ずっと言い間違いをし続ける。そしてロバに変身している間はただの一度も言い間違いをせず、森から戻ってきて職人仲間の元へ戻ったとたん、言い間違いが復活する。ボトムはロバから元の姿に戻って目覚める時、
I will get Peter Quince to write a ballad of this dream. it shall be called ‘Bottom’s Dream’, because it hath no bottom;
(4.2.210-212)
と言うが、まさに’Bottom’ Dream’の間は、一切言い間違いをしないのだ。恋人たちは森の中に入り、狂気に近づき、妖精たちのいたずらのせいで混乱に陥る。ところがボトムの場合は、ロバの頭で妖精たちに囲まれるという異常な状況の下で、かつてなく冷静に振る舞う。妖精たちを前にして終止一貫して落ち着きくつろいだ態度を崩さない。しかし、よくよく考えてみると、妖精たちに囲まれているのに動じないということの方が不自然だ。妖精たちに囲まれて慌てるのが普通の反応だろう。妖精たちを前にして落ち着いていることの方が間違っている。あるいは、ボトムはロバになり、間抜けな要素が表に出た。だから間違えなくなった、ということも言えるかも知れない。
だが僕はボトムが’Bottom’s Dream’と名付けた不思議な出来事が、森で起こったということに注目したい。この物語では都会にいる職人たちと恋人たちが森の中に入って行く。都会には理不尽な法律があり、恋人たちはそれを逃れるために森に逃げ込む。都会と森の対比は秩序と無秩序(=mad)の対比であり、意識と無意識の対比でもある。ボトムは森に入り、ロバになり、意識のbottomに行く。言い間違えとはすなわち、ある秩序に適っていないということである。秩序の存在しない森の中では間違いは存在しないのだ。
Conclusion
ボトムを中心に論じようと思い、ボトムの言い間違えにどのようなヴァリエーションがあるのか、ということに注目しながら精読していたところ、ボトムがロバになっている時には1回も言い間違えをしないことに気付き、その理由を考えてみた。結果的に、その一つの疑問から出発して、’ass’の軽蔑的意味が古くからあったということと、’wood’の思いもよらない用法を知ることが出来た。
シェイクスピアは’ass’ とか’wood’とかいった一つの言葉の中に言外のイメージを含ませている。’wood’を’mad’の意味で使うことは現在ではなくなってしまったが、他にもシェイクスピアの時代に使われていて、今では使われなくなったイメージがあるのだろう。今回調べたことにより、シェイクスピアの言語のイメージの豊かさを実感することができた。
参考文献
Schmidt, Alexander. Shakespeare lexicon and Quotation Dictionary. Rev. Gregor Sarranzin. New York: Dover Publications, 1971.
Shakespeare, William. A Midsummer-Night’s Dream. 編注者 石井 正之助 東京: 大修館書店 1987.
ウィリアム・シェイクスピア 『夏の夜の夢 間違いの喜劇』 訳者 松岡 和子 東京: 筑摩書房 1997.
Simpson, J. A. The Oxford English Dictionary. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989.
2008/05/02/20:54
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
『テンペスト』と植民地主義
あるいは、バイリンガルとしてのキャリバン
米田 拓男
「あんたは言葉を教えてくれたけど、それで俺が得したのは悪口を言うことぐらいだぜ。血の病気にとりつかれて死んじまいな、俺に言葉を教えた罰だ!」(一幕二場三六二−四行)
シェイクスピア『テンペスト』の中の、プロスペローがキャリバンを自分の召使いに仕立て上げていく過程は、植民活動の過程に照らし合わせて辿っていくことができる。
プロスペローは魔法によって、島での支配力を強めていくが、実際の植民地支配の現場では、それは銃であり、言語であり、法律であった。中でも、文明の基盤にある言語は、特に大きな役割を果たして来た。
プロスペローが、物語の舞台となる島を支配するのにも、言葉は大変に有効であった。事実、プロスペローがキャリバンに最初に行ったことは、言葉を教えることであった。
プロスペローとキャリバンの関係は、友好的なものとして始まるが、途中でそれが変化する。そのきっかけとなるのがミランダに対する、キャリバンの強姦未遂事件である。ことによると、それは通常の求愛行為であり、ミランダもキャリバンに対して好意を持っていたかもしれないのに、プロスペローは、とにかくそれを陵辱と名付けた。そして、それ以降、プロスペローは、言葉によってキャリバンを貶めていくことになる。ミランダをキャリバンに嫁がせるはめにならないように、プロスペローは、キャリバンを、悪魔と獣の領域に貶めておく必要があったのだ。プロスペローと言い争っても、キャリバンは手も足も出ない。プロスペローの話す言葉でプロスペローと論争しても、キャリバンに勝てる見込みが無いのは当然である。
しかし、キャリバンは反逆に出る。それは、アイルランド先住民やヴァージニアのインディアンが、イギリス支配に抵抗したのに似ている。キャリバンは、ステファノーとトリンキュローという味方を得て、プロスペローの殺害を企てるが、結果的にその目論みは裏目に出る。結果的に、キャリバンの「裏切り者」という本性が立証され、従属状態が正当化されてしまうのだ。そして、最後には、キャリバンは改心し、自らいっさいの権利を放棄するのである。
こうして、『テンペスト』は、プロスペローにとって満足すべき結末を迎える。キャリバンの、強姦未遂という罪には、奴隷になるという罰が下され、殺害未遂という罪には、使用人になるという罰が下される。これら二つの事件で起こった、キャリバンの立場の変化は、奴隷制度から封建制度への移行に重ねることができる。その関係は、穏健なものになったが、同時に、いっそう強固なものとなった。この結末は、プロスペローにとってというより、ヨーロッパ植民者の夢の成就といえる。
『テンペスト』は、プロスペローの視点から語られているが、もちろんそれが唯一の視点ではない。プロスペローはキャリバンやエアリアルを嘘つき呼ばわりし、過去の事件、例えばキャリバンの強姦未遂事件や、エアリアルを木の間から助け出したことなどを、自分の言葉で語り直す。しかし、私たちはそれを本当に信じていいものだろうか。プロスペローは、植民史を書く歴史家とは言えまいか。植民する側の人間の意見だけを鵜呑みにするのは危険である。プロスペローが島に漂着した当時のことは、ヨーロッパ人がカリブ海諸島に到着した時と同様、真相への手掛かりが無いのである。
さて、プロスペローは大きな目的を達成することができたが、キャリバンに残された遺産といえば、呪うための言語と、悲しみを紛らわすための酒だけであった。ヨーロッパの植民地主義の数えきれない犠牲者たち、被植民者は、搾取され、奴隷にされ、征服者の言語を学び、恐らくその価値観さえ、自分のものとしてきた。彼らは自分たちの土着の文化と、支配者によって上から押し付けられた文化との間で引き裂かれている。キャリバンも同様だ。
言語が彼の牢獄になったのである。言語を通じて、プロスペローはキャリバンの現在を支配し、その未来を制限する。そのことこそが、植民地化のプロセスの最初の重要な成果なのだ。
しかし、キャリバンは身体的にも文化的にも虐待されながら、言葉によって新たな抵抗の武器を得た。キャリバンは、ステファノが酒に酔っているのと同じくらい、自分の第二の言語に酔っているのだ。私たちは、作品中に、キャリバンの詩的な台詞を見ることができる。
結果的に、プロスペローの言語は、キャリバンに自分の文化を表現する手段をもたらしたということになる。プロスペローには、キャリバンが文化を持っているなどということは想像もついていない。しかし、キャリバンにはプロスペローが作り出した訳でもなく、コントロールすることもできない文化がある。そしてキャリバンは、それを自分自身のものだと認識している。
この認識のプロセスに於いて、言語は形を変えて、プロスペローが全く予期できない、それまでとは異なった意味を獲得する。キャリバンはまさに、バイリンガルとなるのだ。プロスペローと共有する言語と、そこからキャリバンが新たに編み出した言語とは同じものではない。こうしてキャリバンは、プロスペローの言語の牢獄を打ち破るのである。
参考文献
ウィリアム・シェイクスピア 『テンペスト』
小田島雄志 訳 東京 白水社
アルデン・T・ヴォーン、ヴァージニア・メーソン・
ヴォーン 共著 『キャリバンの文化史』
橋本哲也 訳 青土社
上野美子 編 『世界の文学 シェイクスピア、
ラシーヌほか』 東京 朝日新聞社 1999
2008/05/02/20:53
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
あなたにとって芸術鑑賞とは何か。
米田 拓男
遺伝子生物学の中に「利己的遺伝子」という理論がある。この理論に従うと、人間は遺伝子の乗り物にすぎず、何万年という時の中で遺伝子それ自身が進化してゆくことが重要なのであって、私たち人間の身体はそのために利用されているだけだということになる。そして、社会に適応できない人は子孫を残すことができないということ、さらにショッキングなことに、いじめによる自殺までもがこの遺伝子淘汰の文脈で説明されうるのである。つまり、遺伝子にとっては優れた能力や資質を持った情報だけが生き残ってゆけばいいのであって、社会の中で生き残れない虚弱体質の人間や、社会に適応する能力のない人間は死滅しても何の問題もないという訳である。
このようなロジックをつきつけられると、果たして自分は生き残るべき存在なのかと悩んでしまうが、このような過激な理論が仮説とはいえ存在するのだ。
激しい情熱をカンバスの上に表現し、短い人生を駆け抜けた画家ゴッホ。彼もまた淘汰されるべき遺伝子の持ち主だったのだろうか。彼はピストル自殺でその生涯を閉じる。彼の作品を見ると、そこには生の歓喜とはほど遠い、憂鬱、不安、恐怖、そして死の予感とも言うべきものが充溢している。自殺直前の「カラスのいる麦畑」はまさに死を象徴している。背後の空は紺青に彩られ、あくまでも暗い。その空の一角には、古くから死の象徴であるともいわれるカラスが群れ飛んで、ゴッホの死を見とり、かつ冥界への先導をつとめるかのようである。失恋の痛手、芸術的創造力喪失の不安、いつ襲われるともしれない精神運動発作の恐怖。それらに、彼の心は確実に蝕まれていった。確かに彼の極端な生真面目さや、憂鬱体質が遺伝子の進化にとって有益な特質だったとは擁護しがたい。競争に勝ち残った強い人間だけが生き延びることのできるこの世界では、ゴッホのような後ろ向きのDNAなど、死すべき弱者の脆弱な遺伝子でしかなかったのかもしれない。芸術の歴史の中には、このゴッホのように芸術に殉死したかのように見える作家がしばしば現れるが、芸術活動とはこの利己的遺伝子に逆らう、ゲリラ的な何物かであるのかもしれない。
芸術作品は観る者に生き方を教える。生活のやり方ではなくどうやって生き続けるのかを。ゴッホの「カラスのいる麦畑」に死が溢れていようと、その作品を見て死にたくはならないはずだ。むしろ逆説的に生を強く感じるだろう。僕は芸術を宗教の代わりにさえなりうるものとして考える。僕にとっての芸術鑑賞とはそういうものだ。
2008/05/02/20:52
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)
ヒエロニムス・ボス
『快楽の園』
米田 拓男
ルネサンス期の作品を一つ取り上げて論じよ、と言われた時、僕はヒエロニムス・ボスしかないな、と思った。それも、あの矢で射抜かれ、包丁を耳に挟み込んだ、巨大な耳が描かれている絵だ、と。それくらいのインパクトを、あの絵は有する。
ヒエロニムス・ボスは、以前から気になっている画家だった。僕が始めて彼の名前に出会ったのは、美術評論家滝本誠氏の著書『映画の乳首、絵画の腓』の中においてだった。氏はその著書の中の、映画監督デイヴィッド・リンチの『ブルー・ベルベット』を論じた文章の中に、ヒエロニムス・ボスの名前が登場するのである。
映画『ブルー・ベルベット』は、ピケット・フェンスのあるアメリカ郊外の住宅地で、主人公ジェフリーが空き地で人間の耳を拾うことから、一見平和に見える住宅地の暗部に足を踏み入れていく物語である。そしてその著書の中に、『ブルー・ベルベット』が「ノーマン・ロックウェル・ミーツ・ヒエロニムス・ボス」と評され、そのコピーをリンチはいたく気に入ったという逸話が載っているのである。
僕は、早速ノーマン・ロックウェルとヒエロニムス・ボスの画集を見た。ノーマン・ロックウェルの作品は、いかにもアメリカらしい、大衆の風俗をユーモラスに描いたものだった。それでは、ボスはというと……。
そこに描かれていたのは人間や動物、怪物が入り乱れた、時におどろおどろしく、ときに幻想的な世界だった。そして、その作品世界は、ボスの多用するピンクの色彩と共に、僕の中に強烈に印象づけられた。
最初に見たときから、ボスの作品世界は独特なものだと思っていたが、ルネサンス当時の他の画家の作品と比較してみると、その印象はいっそう強くなる。ルネサンス期の画家だけではなく、美術史的な流れから見ても、ボスの存在はどこか浮いた感じがするのだ。一体何が他のルネサンス期の画家と違うのだろう。
そのことについて考える前に、もう一人の「浮いた」存在として、僕はチェコの作家フランツ・カフカを思い浮かべることができる。ヒエロニムス・ボスの作品を見た時に感じる不可解さに似たものを、僕はカフカの小説を読む時に感じる。
具体的にボスの作品を見てみよう。そう、あの巨大な耳の描かれた、『快楽の園』の右翼画面だ。
そこに描かれているのは地獄の光景である。縦に長い画面の中いっぱいに、責め苦に苛まれる人々の姿が描かれている。まず、画面の上方の遠景には、黒い煙を上げて燃え盛る街が見える。その下には、軍隊に追われるようにして裸で逃げ回る人々がいる。そして、さらに例の巨大な耳が、その人々の一部を押し潰す。その左側には、火あぶりにかけられた者が、悪魔によって処刑台へと昇らされている。画面下方の近景にも、ハープやリュートに固定された者や、鎧を着た犬に喉元を噛み付かれる者、賭博の罪によってテーブルに磔にされる者が描かれている。そこで行われている行為は、残酷極まりないものだ。
しかし、それらの光景を目にしても、僕はあまり痛みを感じない。例えばゴヤのエッチング作品や、「黒い絵画」の作品群の中の一つ「我が子を食らうサトゥルヌス」の方がもっと痛々しく、陰惨である。ボスの『快楽の園』にも人を食らう鳥の顔をした悪魔が描かれているが、全く陰惨な感じがしない。ここに描かれている地獄の風景は、全てが夢の中の出来事のようで、現実感を伴わない。痛々しいというよりはむしろ、ユーモラスな印象さえ受ける。その感覚がフランツ・カフカに通じるのである。
僕はこの作品を見た時、まさに、カフカの『ある流刑地の話』という短編を思い出した。その物語の中には、異様な処刑機械が登場し、一人の男が針によって、犯した罪を体中に刻まれながら殺されていく様が描かれている。しかし、そのような残虐極まりない光景の中にも、ボスの作品に見られるようなユーモアの感覚が存在する。
もう一つ例を挙げたい。日本絵画の地獄の光景、例えば『地獄草紙』の、特に原家本の中にも同様のユーモア感覚を見出せる。そこに描かれている、鬼の口を開けて笑う顔や、苦しみに耐える目を細めた罪人の表情は、どことなくユーモラスである。同じ『地獄草紙』でも、安住院本や益田家本に較べると、明らかに原家本の方がおかしみが強い。
僕はそこに作家の特質を見る。ボスの絵画も、カフカの小説も、『地獄草紙』の原家本も、同じユーモアを共有している。僕はそのユーモアの出所は、作品の持つ幻想性にあると思っている。
ボスの作品に戻ろう。今まで触れなかったが、『快楽の園』の右翼画面の中で、僕にとって一番印象深いものは、実は画面の中央に描かれた、卵の殻のような胴体を持った巨人である。男には腕が無く、二本の足が、首のすぐ脇から生えている。そしてその足は、途中から樹木に変化しており、二艘の船にまるで靴を履いているかのように固定されている。胴体の中は空洞になっており、中ではどうやら酒宴が催されているようだ。おまけに、頭の上では罪人と悪魔が輪舞を踊っている。これは一体なんなのだろう。
この絵を見たものは、誰もがこの人物に面食らうに違いない。ボスは何を想ってこの絵を描いたのか。この人物には何の意味が込められているのだろうか、と。しかし僕には、この奇妙な人物の造形から意味を読み取ろうとしても、無駄に思える。例えばフェルメールの『絵画の寓意』には、描かれているモチーフの一つ一つに、絵画を定義づけるための意味が込められているが、この人物に明確な意味が込められているとは、どうしても考えられないのだ。しかし意味が分からなくとも、僕はボスの作品に惹かれてしまう。思えば、その不可解さこそが、僕を魅き付けている理由なのかもしれない。
ボスにとってこの人物が重要な存在であったことは疑いない。ボスはこの人物の草案と思えるスケッチをいくつか残している。僕は想像してみる。ボスがこの人物を思いついた所を。もしかしたらボスの口元には、笑みさえ浮かんでいたかもしれない。スケッチに描かれた巨人の背景は、のどかな水辺だった。巨人の表情も笑みを含んだ穏やかなものだ。きっとボスは、楽しんでその素描を描いていたに違いない。
『快楽の園』の地獄の場面に感じたおかしみの質は、きっとその種のものなのだ。地獄を創造することに淫するボスの「快楽」に起因しているのだ。ボスは、絵を描くにあたって、リアリズムより想像力に重きを置いていたのは明らかだ。だから、ボスの作品に描かれている光景は、夢の世界の出来事のようであり、どんなに残酷な場面が描かれていたとしても、それはどことなくユーモラスなものに見えるのだ。
思えば、『ブルー・ベルベット』は、主人公が耳を拾うことで、白昼夢のような悪夢の現実に足を踏み入れる物語であった。ノーマン・ロックウェル的日常から、ヒエロニムス・ボス的悪夢の世界へ。悪夢は恐ろしいが、しかし甘美である。ボスの作品は、甘美な悪夢のように僕を魅きつけてやまない。
2008/05/01/09:14
| Thesis
| コメント & トラックバック (0)