ヒエロニムス・ボス『快楽の園』
ヒエロニムス・ボス
『快楽の園』
米田 拓男
ルネサンス期の作品を一つ取り上げて論じよ、と言われた時、僕はヒエロニムス・ボスしかないな、と思った。それも、あの矢で射抜かれ、包丁を耳に挟み込んだ、巨大な耳が描かれている絵だ、と。それくらいのインパクトを、あの絵は有する。
ヒエロニムス・ボスは、以前から気になっている画家だった。僕が始めて彼の名前に出会ったのは、美術評論家滝本誠氏の著書『映画の乳首、絵画の腓』の中においてだった。氏はその著書の中の、映画監督デイヴィッド・リンチの『ブルー・ベルベット』を論じた文章の中に、ヒエロニムス・ボスの名前が登場するのである。
映画『ブルー・ベルベット』は、ピケット・フェンスのあるアメリカ郊外の住宅地で、主人公ジェフリーが空き地で人間の耳を拾うことから、一見平和に見える住宅地の暗部に足を踏み入れていく物語である。そしてその著書の中に、『ブルー・ベルベット』が「ノーマン・ロックウェル・ミーツ・ヒエロニムス・ボス」と評され、そのコピーをリンチはいたく気に入ったという逸話が載っているのである。
僕は、早速ノーマン・ロックウェルとヒエロニムス・ボスの画集を見た。ノーマン・ロックウェルの作品は、いかにもアメリカらしい、大衆の風俗をユーモラスに描いたものだった。それでは、ボスはというと……。
そこに描かれていたのは人間や動物、怪物が入り乱れた、時におどろおどろしく、ときに幻想的な世界だった。そして、その作品世界は、ボスの多用するピンクの色彩と共に、僕の中に強烈に印象づけられた。
最初に見たときから、ボスの作品世界は独特なものだと思っていたが、ルネサンス当時の他の画家の作品と比較してみると、その印象はいっそう強くなる。ルネサンス期の画家だけではなく、美術史的な流れから見ても、ボスの存在はどこか浮いた感じがするのだ。一体何が他のルネサンス期の画家と違うのだろう。
そのことについて考える前に、もう一人の「浮いた」存在として、僕はチェコの作家フランツ・カフカを思い浮かべることができる。ヒエロニムス・ボスの作品を見た時に感じる不可解さに似たものを、僕はカフカの小説を読む時に感じる。
具体的にボスの作品を見てみよう。そう、あの巨大な耳の描かれた、『快楽の園』の右翼画面だ。
そこに描かれているのは地獄の光景である。縦に長い画面の中いっぱいに、責め苦に苛まれる人々の姿が描かれている。まず、画面の上方の遠景には、黒い煙を上げて燃え盛る街が見える。その下には、軍隊に追われるようにして裸で逃げ回る人々がいる。そして、さらに例の巨大な耳が、その人々の一部を押し潰す。その左側には、火あぶりにかけられた者が、悪魔によって処刑台へと昇らされている。画面下方の近景にも、ハープやリュートに固定された者や、鎧を着た犬に喉元を噛み付かれる者、賭博の罪によってテーブルに磔にされる者が描かれている。そこで行われている行為は、残酷極まりないものだ。
しかし、それらの光景を目にしても、僕はあまり痛みを感じない。例えばゴヤのエッチング作品や、「黒い絵画」の作品群の中の一つ「我が子を食らうサトゥルヌス」の方がもっと痛々しく、陰惨である。ボスの『快楽の園』にも人を食らう鳥の顔をした悪魔が描かれているが、全く陰惨な感じがしない。ここに描かれている地獄の風景は、全てが夢の中の出来事のようで、現実感を伴わない。痛々しいというよりはむしろ、ユーモラスな印象さえ受ける。その感覚がフランツ・カフカに通じるのである。
僕はこの作品を見た時、まさに、カフカの『ある流刑地の話』という短編を思い出した。その物語の中には、異様な処刑機械が登場し、一人の男が針によって、犯した罪を体中に刻まれながら殺されていく様が描かれている。しかし、そのような残虐極まりない光景の中にも、ボスの作品に見られるようなユーモアの感覚が存在する。
もう一つ例を挙げたい。日本絵画の地獄の光景、例えば『地獄草紙』の、特に原家本の中にも同様のユーモア感覚を見出せる。そこに描かれている、鬼の口を開けて笑う顔や、苦しみに耐える目を細めた罪人の表情は、どことなくユーモラスである。同じ『地獄草紙』でも、安住院本や益田家本に較べると、明らかに原家本の方がおかしみが強い。
僕はそこに作家の特質を見る。ボスの絵画も、カフカの小説も、『地獄草紙』の原家本も、同じユーモアを共有している。僕はそのユーモアの出所は、作品の持つ幻想性にあると思っている。
ボスの作品に戻ろう。今まで触れなかったが、『快楽の園』の右翼画面の中で、僕にとって一番印象深いものは、実は画面の中央に描かれた、卵の殻のような胴体を持った巨人である。男には腕が無く、二本の足が、首のすぐ脇から生えている。そしてその足は、途中から樹木に変化しており、二艘の船にまるで靴を履いているかのように固定されている。胴体の中は空洞になっており、中ではどうやら酒宴が催されているようだ。おまけに、頭の上では罪人と悪魔が輪舞を踊っている。これは一体なんなのだろう。
この絵を見たものは、誰もがこの人物に面食らうに違いない。ボスは何を想ってこの絵を描いたのか。この人物には何の意味が込められているのだろうか、と。しかし僕には、この奇妙な人物の造形から意味を読み取ろうとしても、無駄に思える。例えばフェルメールの『絵画の寓意』には、描かれているモチーフの一つ一つに、絵画を定義づけるための意味が込められているが、この人物に明確な意味が込められているとは、どうしても考えられないのだ。しかし意味が分からなくとも、僕はボスの作品に惹かれてしまう。思えば、その不可解さこそが、僕を魅き付けている理由なのかもしれない。
ボスにとってこの人物が重要な存在であったことは疑いない。ボスはこの人物の草案と思えるスケッチをいくつか残している。僕は想像してみる。ボスがこの人物を思いついた所を。もしかしたらボスの口元には、笑みさえ浮かんでいたかもしれない。スケッチに描かれた巨人の背景は、のどかな水辺だった。巨人の表情も笑みを含んだ穏やかなものだ。きっとボスは、楽しんでその素描を描いていたに違いない。
『快楽の園』の地獄の場面に感じたおかしみの質は、きっとその種のものなのだ。地獄を創造することに淫するボスの「快楽」に起因しているのだ。ボスは、絵を描くにあたって、リアリズムより想像力に重きを置いていたのは明らかだ。だから、ボスの作品に描かれている光景は、夢の世界の出来事のようであり、どんなに残酷な場面が描かれていたとしても、それはどことなくユーモラスなものに見えるのだ。
思えば、『ブルー・ベルベット』は、主人公が耳を拾うことで、白昼夢のような悪夢の現実に足を踏み入れる物語であった。ノーマン・ロックウェル的日常から、ヒエロニムス・ボス的悪夢の世界へ。悪夢は恐ろしいが、しかし甘美である。ボスの作品は、甘美な悪夢のように僕を魅きつけてやまない。


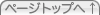
Comments & Trackbacks
Trackback URL http://shakeweb.co.uk/spear/thesis/52.html/trackback