Shakespeareのソネットに見る「時」
Shakespeareのソネットに見る「時」
米田拓男
Introduction
Shakespeareのソネット作品について論じる。場合に応じて同時代の他の詩人の作品にも触れたいと思う。Shakespeareのソネットには「時」についての記述が多い。ShakespeareのThe Sonnetsは、126番まではShakespeareの恋人と思われる青年に対する愛を描いたもので、127番以降は一般に「黒い女」と呼ばれている謎の婦人に捧げられている。ここではThe Sonnets前半の126番までを扱いたいと思う。詩を捧げられているその青年はだいぶ年若いようで、それらの詩の中には「時」や「老い」についての記述が多く見られる。127番以降には「時」ついての言及はあまり見られない。
本論では、ShakespeareのThe Sonnetsの成立経緯に簡単に触れた後、The Sonnetsで「時」がどのように表現されているか、Shakespeareがどのような姿勢で「時」に対峙していたかを見る。そして最終章では「時」とは切り離せないテーマであるカルペ・ディエムが、The Sonnetsの中でどのように表現されているのかを見たいと思う。
Chapter 1 ShakespeareのThe Sonnets
イタリアのルネサンス詩人Petrarchに始まる恋愛ソネットの伝統は、全ヨーロッパに広がり、イギリスではヘンリー八世時代にThomas WyattやHenry Howard、 Earl of Surreyらによって輸入された。エリザベス一世時代になるとPhilip Sidneyが‘Astrophel and Stella’を、Edmund Spenserが’Amoretti’をそれぞれ恋人にあてて書いた。そしてShakespeareはそれらの流れを引き継ぎ、恐らくRomeo and Julietを書いた頃に、The Sonnetsを書いていたと考えられている。その後ソネット形式は、ミルトンなどの後世の詩人たちに引き継がれていった。
ShakespeareのThe Sonnetsは謎に満ちている。ShakespeareがThe Sonnetsで愛を告白している、「黒い女」と青年は、今日では誰なのか分からない。Shakespeareと2人の関係も謎に包まれている。また、ここに描かれていることは、Shakespeareが実際に体験したことに基づいているのか、それとも全くの創作なのか、それも今日では確かめるすべが無い。
ShakespeareのThe Sonnetsには、当時流行していたらしいペトラルカ風恋愛ソネットの技巧的な愛の告白や誇張に満ちた修辞に対する批判が垣間見えるという。(岩崎 11)実際に、そういった過去の詩人や技法に対する批判的な姿勢は、ソネット21番に見ることができる。
So is it not with me as with that Muse
Stirr’d by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use
And every fair with his fair doth rehearse
Making a couplement of proud compare,
With sun and moon, with earth and sea’s rich gems,
With April’s first-born flowers, and all things rare
That heaven’s air in this huge rondure hems.
(21.1-8)
「当時輩出した恋愛ソネット連作の中で、男を対象にして愛を歌ったものは他にない」という。(高松 286)そうであるならば、上記の記述も考えあわせれば、The Sonnetsは当時においては非常に野心的、実験的な作品だったのでは無いだろうか。流行の恋愛詩に対する風刺的意味合いも強かっただろう。
Chapter 2 The Sonnetsにおける「時」の記述
The Sonnetsに出てくる「時」に関する描写を読む限りでは、Shakespeareにとって「時」はマイナス・イメージを伴うもののようだ。ほとんどの場合において「時」は美の破壊者として描かれている。例えば次の部分。
Devouring Time, blunt thou the lion’s paws,
And make the earth devour her own sweet brood;
Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws,
And burn the long-lived phoenix in her blood;
Make glad and sorry seasons as thou fleets,
And do whate’er thou wilt, swift-footed Time,
To the wide world and all her fading sweets;
But I forbid thee one most heinous crime:
(19.1-8)
このソネットでは「時」に「全てを食い尽くす時よ」と呼び掛け、その残忍さを強調している。ShakespeareのThe Sonnetsには青年の美しさと、それを奪う時の残虐さが常に並べて描かれている。美しいものもやがては失われるのだと。
Then of thy beauty do I question make,
That thou among the wastes of time must go,
Since sweets and beauties do themselves forsake
And die as fast as they see others grow;
(12.9-12)
Shakespeareは全ての美しいものが、いずれ必ず「時」によって破壊されるという認識を持っている。それを表す一つの例として、次の13番には「期限付きで借りている美しさ」という表現がある。
So should that beauty which you hold in lease
Find no determination:
(13.5-6)
「時」はShakespeareにとっては、いずれ誰のもとにもやって来る美の債務者なのだ。そのため「時」は死のイメージに直結する。
When I have seen such interchange of state,
Or state itself confounded to decay;
Ruin hath taught me thus to ruminate,
That Time will come and take my love away.
This thought is as a death, which cannot choose
But weep to have that which it fears to lose.
(64.9-14)
ShakespeareのThe Sonnetsには、例えばEdmund Wallerの’Old Age’ のように、成長して物事を見通す力を持てるようになったといったような、「時」に対する積極的な意義について書かれている箇所が無い。成長については書かれている箇所はいくつかあるが、必ず「老い」と対になっている。次の5番では、卓越した技術でせっかく作り上げた美を、その同じ手で破壊する「時」の残忍さをなじる。
Those hours, that with gentle work did frame
The lovely gaze where every eye doth dwell,
Will play the tyrants to the very same
And that unfair which fairly doth excel:
(5.1-4)
「時」について描かれている他の詩人の作品、例えばJohn Miltonのソネット形式で書かれた、初期の抒情詩’On His being Arrived at the Age of Twenty-Three’では、
How soon hath Time, the subtle thief of youth,
Stolen on his wing my three-and-twentieth year!
(1-2)
と、「時」を‘thief of youth’と否定的に表現している。しかし、同じ詩の後半では、「時」を自分自身を導いてくれるものとして肯定的に受け取っている。
Yet be it less or more, or soon or slow,
It shall be still in strictest measure even
To that same lot, however mean or high,
Toward which Time leads me, and the will of Heaven:
(9-12) (以下、下線筆者)
ShakespeareのThe Sonnetsにはこのような描写は見られない。総じてShakespeareのThe Sonnetsにおける「時」の表現の特徴は、徹底的にネガティブなものとして表現されているところにあるといえるだろう。
Chapter 3 The SonnetsにおけるShakespeareの「時」に対する姿勢
Shakespeareは「時」を完全なる悪として表現しており、The Sonnets中、一貫して「時」に対抗する姿勢を貫いている。Shakespeareにとって、「時」に対抗することは、即ち美を保存することである。その手段は、(1)美しい人の子孫を残すこと、(2)美しい人を詩に書いて、後世に残すことである。
ShakespeareのThe Sonnetsは次の一節で始まる。
From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty’s rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
(1.1-4)
ここでShakespeareは、一人の青年の美しさを賛美し、彼に結婚をして子孫を残すことを奨めている。ソネット1〜17番目まで、Shakespeareは一貫して青年の美しさと説き、結婚を奨める。11番では、美しいものだけが子孫を残し、醜いものは滅べばいいとまで言う。
Let those whom Nature hath not made for store,
Harsh featureless and rude, barrenly perish:
Look, whom she best endow’d she gave the more;
Which bounteous gift thou shouldst in bounty cherish:
(11.9-12)
12番でShakespeareは「時」に対する対抗意識をはっきりと打ち出す。そしてその唯一の手段として子孫を残すことを説く。
And nothing ‘gainst Time’s scythe can make defence
Save breed, to brave him when he takes thee hence.
(12.13-14)
同様に、14、16、17番と、「時」に対抗するには、子孫を残すことの方が詩を書くことよりも有効であると説明している。しかし、17番以降、青年に結婚を奨めることは二度と無くなる。それ以降は時への対抗手段として、詩の力が強調されてくる。
最初に「時」に対する詩の力を高らかに歌い上げるのが15番である。このソネットは「時」に対する宣戦布告ととることができる。
And all in war with Time for love of you,
As he takes from you, I engraft you new.
(15.13-14)
以降、
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.
(18.13-14)
Yet, do thy worst, old Time: despite thy wrong,
My love shall in my verse ever live young.
(19.13-14)
と、自分の詩才に対する自信を深めていく様子を感じ取ることができる。さらに、
Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall outlive this powerful rhyme;
(55.1-2)
で始まる55番は、「時」に対する詩の高らかな勝利宣言だ。
100、101番のソネットには、時の神‘Time’に対して詩の女神‘Muse’への呼び掛けも出てくる。
Then do thy office, Muse; I teach thee how
To make him seem long hence as he shows now.
(101.13-14)
18番からを境に、Shakespeareの「時」への対抗手段が(1)子孫を残すことから、(2)詩を書くことへと移項したことが分かるだろう。一方で、Shakespeareの青年に対する態度も変化してくる。10番の、
Make thee another self, for love of me,
That beauty still may live in thine or thee.
(10.13-14)
という表現などを見ると、最初はどうやら相手の方から求愛してきたらしいことが伺える。最初の1〜17番までのShakespeareの青年に対する態度は、相手に結婚を奨めるなど、年上らしく冷静に振る舞って相手からの求愛を断るかのような態度をとり続けている。しかし、18番以降は、あたかも美の下僕となって青年の美しさを書きとどめようとしているかのようだ。
And yet to times in hope my verse shall stand,
Praising thy worth, despite his cruel hand.
(60.13-14)
His beauty shall in these black lines be seen,
And they shall live, and he in them still green.
(63.13-14)
You still shall live–such virtue hath my pen–
Where breath most breathes, even in the mouths of men.
(81.13-14)
Shakespeareは、「時」に打ち勝とうとして、相手の美しさを詩に保存しようとする。しかし、これらの詩から伝わってくるのは相手の美しさではない。実際、青年がどんな姿をしているのかについての具体的な描写は、全く書かれていないように思われる。The Sonnetsを読んでいて見えてくるのは、むしろ、年若い青年を前にしてのShakespeare自身の老い、そしてその年齢差を補うものとしての自分の詩才に賭けるShakespeare自身の姿である。
Chapter 4 The Sonnetsに見るカルペ・ディエム
カルペ・ディエムとは中世以来の「今日という日を楽しめ」という典型的なテーマの一つである。ShakespeareのThe Sonnetsにもカルペ・ディエム的テーマが散見される。例えば相手を薔薇の花に例えて、花の命は短いのだから盛りのうちに人生を謳歌せよ、と恋人に説くのはカルペ・ディエムの典型的な表現と言っていい。The Sonnetsにもそのような表現がある。
Then, were not summer’s distillation left,
A liquid prisoner pent in walls of glass,
Beauty’s effect with beauty were bereft,
Nor it nor no remembrance what it was:
But flowers distill’d though they with winter meet,
Leese but their show; their substance still lives sweet.
(5.9-14)
このソネットでは、花の命は短いからその香りを蒸留して残しておきなさいと説く。香りを蒸留して残しておくとは具体的に何を指しているのか。続く6番にその答えがある。
115、がしつのいらしいeaven:,
ven
ar!
Then let not winter’s ragged hand deface
In thee thy summer, ere thou be distill’d:
Make sweet some vial; treasure thou some place
With beauty’s treasure, ere it be self-kill’d.
(6.1-4)
ここで述べられているのは具体的には花の盛りのうちに子孫を残せ、ということである。しかし、先に述べたように時への対抗手段が(1)子孫を残すことから、(2)詩に残すことへ移行したのを受けて、54番のソネットでは自分の詩作の力によって蒸留するというように読み替えてある。
And so of you, beauteous and lovely youth,
When that shall fade, my verse distills your truth.
(54.13-14)
ここにきて思い至ったのだが、そういえばShakespeareのA Midsummer-Night’s Dreamにも同様の表現があった。
Thrice-blessed they that master so their blood,
To undergo such maiden pilgrimage;
But earthlier happy is the rose distill’d,
Than that which withering on the virgin thorn
Grows, lives and dies in single blessedness.
(1.1.74-78)
花を蒸留するというmetaphorはShakespeareが気に入っていた表現なのかも知れない。他にもカルペ・ディエムと重なるテーマを持つソネットがいくつかある。例えばソネット4番がそれだ。
Unthrifty loveliness, why dost thou spend
Upon thyself thy beauty’s legacy?
Nature’s bequest gives nothing but doth lend,
And being frank she lends to those are free.
Then, beauteous niggard, why dost thou abuse
The bounteous largess given thee to give?
Profitless usurer, why dost thou use
So great a sum of sums, yet canst not live?
(4.1-8)
ここでは、自分の美しさを一人占めせず、結婚しろと説いている。この表現もカルペ・ディエムの変奏のように思う。これと同様の表現がRomeo and Julietの中にある。ロミオが、ロザラインが貞潔の誓いをたてていることを、美の浪費だといって嘆く場面である。
ROMEO O, she is rich in beauty, only poor,
That when she dies with beauty dies her store.
BENVOLIO Then she hath sworn that she will still live chaste?
ROMEO She hath, and in that sparing makes huge waste,
For beauty starved with her severity
Cuts beauty off from all posterity.
(1.1.215-220)
Romeo and JulietもA Midsummer Night’s Dreamも、The Sonnetsが書かれたのと同時期に執筆されたと考えられているから、似たような表現が入り込んでいるのかも知れない。それはともかくとして、本レポートのChapter 1で、Shakespeareは恋愛詩の伝統に対して批判的な考えを持っているのではないかと書いたが、ここで見たように、カルペ・ディエムといった恋愛詩の伝統を引き継いでいることもまた確かなのだ。Shakespeareのソネット73番は、恋愛詩の伝統を踏まえた上で、実にShakespeareらしいカルペ・ディエムの表現になっているように思う。
That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin’d choirs, where late the sweet birds sang.
In me thou seest the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west,
Which by and by black night doth take away,
Death’s second self, that seals up all in rest.
In me thou see’st the glowing of such fire
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed whereon it must expire
Consumed with that which it was nourish’d by.
This thou perceivest, which makes thy love more strong,
To love that well which thou must leave ere long.
(73)
ここに描かれているのは老いを前にしたカルペ・ディエムである。カルペ・ディエムとはもちろん、自分、あるいは相手が老いることを前提とした考え方であるが、このソネットでは相手の目に映る自分の老いの描写が延々と12行目まで続く。そして最後のcoupletで、やがて別れが来るからこそ、君はいま私をより強く愛するのだと綴る。
カルペ・ディエムをテーマにした他の詩人たちの作品、例えば、Edmund Spenserの’The Song of the Rose‘であるとか、Robert Herrickの’To the Virgins, to Make Much of Time’、Andrew Marvellの’To His Coy Mistress’などに比べて、Shakespeareのソネット73番は悲愴感に包まれている。Edmund Spenserや、Robert Herrickらの作品は、もっと華やかで、開放感に満ちていて、時にユーモラスな印象をさえ受ける。
それに対して、このソネット73番にあるものは、開放感というよりも閉鎖感、ユーモアよりも苦渋である。Edmund Spenserらの伝統的なカルペ・ディエムをテーマにした作品と受ける印象が全く異なるので、ソネット73番はひょっとすると、カルペ・ディエムをテーマにした詩とは看做されないのかも知れない。しかし、ここに表現されている感情に僕はリアリティーを感じる。例えば、相手の視線から自分の老いを描いているところに、作者の屈折した感情を見るようでリアルに思える。
そのように作者が屈折せざるを得なかったのは相手が同性だったからだろうか。それとも、2人の間に年令差があったからだろうか。Shakespeareのソネットにはどこか影があるように感じる。ShakespeareのソネットがEdmund Spenserらの詩のように開放感に溢れたものになっていないのは、2人の間の障害が大きかったせいかもしれない。障害が大きかったからこそ、表現される感情は切実さを増したのではないか。ロミオとジュリエット、あるいは、ハーミアとライサンダーのように。いずれにせよ、年齢差のある相手に向かってソネットを書き、自らの老いと対峙することになったShakespeareが、「時」を敵視することになったのは必然であったろう。
Conclusion
The Sonnetsに見る「時」の表現は必ずマイナス・イメージを伴っている。Shakespeareは「時」を美の破壊者であると考えている。彼は、美を保存することが、「時」に対抗する手段であると考える。作中、彼は「時」に対する対抗策を二つ挙げている。それは(1)美しい人の子孫を残すこと、(2)美しい人を詩の中に残すこと、である。17番までのソネットでは、(1)の子孫を残すことを唱えているが、18番以降は(2)の考えに移行し、詩が持っている力を強調するようになり、「時」に対抗して美を保存することが、詩人の使命であるかのような姿勢を示すようになる。年齢差のあった青年にソネットを書くことによって、自分の老いと対峙したShakespeareが「時」を敵視したのは当然であった。
引用文献
神山 妙子 編著 『はじめて学ぶ イギリス文学史』 東京: ミネルヴァ書房, 1989.
ウィリアム・シェイクスピア 『大修館シェイクスピア双書 夏の夜の夢』 編者 石井 正之助 東京: 大修館書店, 1987.
ウィリアム・シェイクスピア 『夏の夜の夢 間違いの喜劇 シェイクスピア全集4』 訳者 松岡 和子 東京: 筑摩書房, 1996.
ウィリアム・シェイクスピア 『大修館シェイクスピア双書 ロミオとジュリエット』 編者 岩崎 宗治 東京: 大修館書店, 1988.
ウィリアム・シェイクスピア 『ロミオとジュリエット シェイクスピア全集2』 訳者 松岡 和子 東京: 筑摩書房, 1996.
Shakespeare, William. The Sonnets. ed. G. Blakemore Evans. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
ウィリアム・シェイクスピア 『ソネット集 シェイクスピア作』 訳者 高松 雄一 東京: 岩波書店, 1986.
平井 正穂 編 『イギリス名詩選』 東京: 岩波書店, 1990.


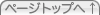
Comments & Trackbacks
Trackback URL http://shakeweb.co.uk/spear/thesis/20.html/trackback