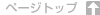The Economist の記事を訳出しました。
Defending Japan: Collective insecurity
原文はこちらから読めます。
記事の中では、安倍内閣が憲法解釈を集団的自衛にまで拡大させようとしていることについて肯定的に書かれていますが、靖国参拝のような「思慮にかけた」行動を見るにつけ、外交下手な日本が本当に近隣諸国に理解を求めながら改革を進めていけるのかどうか、多いに疑問が残ります。
防衛する日本
集団「不安」保障
首相が日本を平和主義から引き離そうとするのにも一理ある
2014年5月17日

日本の戦犯を祀る神社への彼の思慮に欠けた参拝を鑑みれば、近隣諸国が、日本の長年にわたる平和主義をこねくり回そうとする安倍晋三の計画を、深い疑念を持って見ていることは驚くに値しない。しかし、彼が今週発表した、日本が同盟国を防衛することを初めて許容しようとする提案は、日本を正しい方向へと導いている。その提案は、精力的な外交を伴うものである以上、地域を、不安にではなく、より安全にする必要がある。
『時代は変わる』
1945年の敗戦以来、日本は東アジアの平和と繁栄に貢献し、地球市民の模範となってきた。アメリカ人の占領者によって書かれた平和主義の戦後の憲法は、いくつかの点で賞賛に値する。その心髄である憲法九条には、日本は、国際紛争を解決するための武力行使を永遠に放棄するとある。この誓約は、日本の軍国主義が再びアジアにはびこることはないと近隣諸国を安心させる助けとなり、また、アメリカに西太平洋を見張らせることにもなった。その安全の保証が、今度は、日本人に、軍隊の制服を投げ捨てさせてサラリーマンのスーツを選ばせ、繁栄の道へと向かわせた。多くの日本人にとって、日本国憲法はプライドの源泉というだけではない。それは国の宝なのだ。
しかし、危険が高まりつつあり、日本の取り決めは時代遅れのものに見えてきつつある。脅威は、技術者たちが核爆弾を開発し終え、現在はそれを搭載するためのミサイル技術に取り組んでいる、北朝鮮から来る。そして中国は不満を溜め込み、軍事力を高め、東シナ海沖にある尖閣諸島の日本の長年にわたる支配に抗議している。
国内では、当惑しながら中国との衝突を避けようとしている超大国アメリカの、安全保障の不確かさに気を揉んでいる。疑念は、お互いが抱いている。一部のアメリカの戦略家は、日本がアメリカの安全保障にただ乗りしていることにうんざりしている。今日の憲法解釈では、日本は、カリフォルニアに向かって日本上空を飛んでいく北朝鮮のミサイルを撃墜することは許されない。朝鮮半島で戦争が起こっても、日本は、戦地に赴くアメリカの飛行機に燃料を補給することさえできない。アメリカの戦略家たちは、日本に、同盟の安全保障上、より大きな役割を果たしてもらうことを望んでいる。
最近の日本の指導者の誰よりも、安倍氏はこれらのことを理解している。自国の安全保障を強化するために、彼はすでに、同国初の国家安全保障局長を任命し、国家安全保障戦略を策定するなど、日本の慎重な基準に照らせば大胆な策を講じてきた。彼の最新の提案は、憲法を改正するのではなく、憲法が許容できること(特に、同盟国の援助に関わる集団的自衛の原則を指すが)を再解釈することだ。
中国は、自国の公共放送は行進する軍隊と鋭い音を立てて飛ぶジェット機で溢れているのに、日本の軍国主義を非難して、そのようなやり方は不正だと糾弾する。その誤解はほとんど故意に見える。平和維持活動以外の目的で、日本海域を越えて日本が軍隊を配備する筈がない。こういった比較的小さな変化を受け入れてもらうために、安倍氏が国内の人びとを苦心して説得していることが、日本が好き好んで戦争をしかけたいと望んでいる訳ではないことを示している。この新しい方針の主な効果は、日本が、アメリカ軍とより緊密に、兵站や諜報活動などについて連携しやすくなることだ。
他の点では、安倍氏の提案に取り立てて目を引くところはない。しかし、戦時中の日本が引き起こした大混乱や、現在、近隣諸国と不安定な関係にあることを考慮に入れると、改革は活発な外交と平行して進めていく必要がある。安全保障を、弱めるのではなく、強化しようとするのであれば、安倍氏は、日本の意図は、軍国主義復活の第一歩にあるのではなく、限定的で悪気のないものであると、地域を安心させる必要がある。
| 2014/05/18
| The Economist, Translation
|
The Economist の記事を訳出しました。
Video games: Pixel pressures
原文はこちらから読めます。
『グランド・セフト・オート V』の発売直後に掲載された、イギリスのゲーム産業に関する記事です。『GTA V』がアメリカのイギリス流のパロディであるという指摘が出てきます。この記事を読んで『GTA V』の購入を決めました。あまり遊べていないのですが。。最後は、携帯カジュアルゲーム市場への期待で締められています。
ビデオゲーム
ピクセルの重圧
大ヒット作のリリースが、イギリスのゲーム制作会社を延命させるかもしれない
2013年9月21日

9月17日にリリースされたビデオゲーム『グランド・セフト・オート V』は、一見した限りでは、まったくスコットランドらしくない。その舞台は架空のロサンゼルスだし、主人公である(アンチ)ヒーローは、アメリカのギャング3人組だ。しかし、しばらく遊ぶとイギリス独特のユーモアに気づくことになるだろう。ゲーム中の「ウィーゼル・ニュース」ネットワークは、文化闘争の最前線から終末的な報告を届ける。架空のソーシャル・メディア「ライフインベイダー」は、カリフォルニアの技術者をからかう。カジュアルな暴力表現はさておき、ゲームの美点は、それがアメリカの、特にイギリス流のパロディになっている点にある。
1億7000万ポンド(289億円)の予算がかけられたといわれるこのエジンバラで作られたゲームは、イギリスのビデオゲーム産業にとってのひとつの偉業だ。『GTA V』を開発した会社、ロックスター・ノース(Rockstar North)は、10億ポンド(1700億円)程の売り上げを達成することが期待されている。しかし悲しいことに、このような成功は、今日では稀だ。誇大広告の下、イギリスのビデオゲーム産業に、かつての威光はない。『GTA V』リリースの数日前、イギリス最古かつ最大のゲーム制作スタジオのひとつ、ブリッツ(Blitz)は、閉鎖することを発表した。ブリッツのトップ、フィリップ·オリバー氏は、契約のための熾烈な競争を原因の一端とした。
ゲーム産業におけるイギリスの弱体化は、グローバルなゲーム産業の状況を大きく反映している。 2大ゲーム機、Xbox 360とプレイステーション3は、両方ともそのライフサイクルの終焉を迎えようとしている。イギリスのゲームの売り上げ(アナログ・デジタルの両方を含む)は、2010年の20億ポンド(3400億円)から、2012年は16億ポンド(2720億円)に下落した。世界中で同様の傾向が見られる。ゲーム業界団体、TIGAが収集したデータによれば、そのことは、イギリスのスタジオで雇用されている制作スタッフが、2008年の9,900人から、2012年の9,224人に減少している理由の一端を説明する。
しかし、学校での質の高いコンピュータ・サイエンスの教育によって確立した、初期の優位性は失われている。資金調達の難しさは、例えばロックスター・ノースがアメリカ企業、テイクツー·インタラクティブ(Take-Two Interactive)に所有されているように、多くのスタジオが国外の制作会社に吸収されることを意味した。アメリカとカナダでは、州によっては、寛大な補助金を導入しており、企業は所得税さえも返還請求することができる。ゲーム開発者は、若く、流動的な傾向があるので、イギリスからスタッフが引き離されることになった。彼らを野心のある外国人と交換することは難しい。就労ビザは高価で、取得するのがますます困難になってきている。
TIGAのCEO、リチャード·ウィルソンによれば、時代の潮流がいま変わろうとしている。2012年、スタジオでの雇用の減少は横ばいだった。新しいゲーム機がまもなくリリースされるが、そのことは雇用の拡大を意味すると考えてよいだろう。2012年の予算において財務大臣ジョージ·オズボーンによって発表された補助金は、その必要性を受け入れていない欧州委員会により、遅らされている。しかし最終的には、補助金は可決されると思われる。制作費の25%に相当すると見込まれるその金額は、海外からの資金流入に歯止めをかけることになるだろう。
『GTA』のような大ヒット作は別にして、おそらく最大の希望は、小規模で柔軟なチームによって作られた、携帯電話や、タブレット、PC向けの、安価なカジュアルゲームにある。TIGAによれば、イギリスの開発会社の半分は、過去4年間に創業された。ニューヨークに拠点を置く開発会社、レボリューション・ソフトウェア(Revolution Software)の創設者、チャールズ・セシルは、彼の『ブロークン・ソード』シリーズの新しいバージョンをiPadユーザに販売できるようにしたアップルに感謝している。彼が指摘するように、イギリスのゲームが持つ皮肉なウィットには、未だ多くの需要がある。今こそ、それを生かす時だ。
| 2014/01/13
| The Economist, Translation
|
The Economist の記事を訳出しました。
Teaching and technology: E-ducation
原文はこちらから読めます。
教育工学(EdTech)の分野は、ソーシャルアプリ開発のノウハウを応用できる部分が大きいため、とても注目しています。
教育とテクノロジー
E-ducation
長らく停滞していた技術革命がついに進展を見せる
2013年6月29日

1913年、トーマス·エジソンは「映像で、人類の叡智すべての領域について教えることができる」と言い、教室では本はすぐに廃れるだろうと予測した。しかし実際には、映像は、教育にほとんど影響を与えなかった。最近まで、同じことがコンピュータでも言えた。1970年代以降、シリコンバレーの先見の明を持つ者たちが、自分たちの産業がオフィスと同じくらい教室を根本的に変えると主張し、それを根拠に学校へ多くのテクノロジーを売りつけてきた。子どもたちは、調査に、レポートのタイピングに、そしてカンニングに、コンピュータを使っている。しかし、教育システムの中核は、中世以来ほとんど変わっていない。つまり、「教壇に立つ賢人」たる教師が、居並ぶ学生に向かって「教え」を説く、というやり方である。トム·ブラウンやハックルベリー·フィンだったら、すぐにそれを見抜き、怖気をふるうだろう。
今になってようやく革命が進行している。その中心には、「画一的な」教育から、個人に向けた方法に移行するという考え方がある。テクノロジーは、各々の子供たちに、適応性のあるコンピュータ·プログラムによる講義や「著名人」による講義を、異なるスピードで教えることを可能にする。そして、担任教師の役割は、雄弁家からコーチへと移行する。つまり、特に助けが必要な場合に、装置が識別した子供に対して、個別の注意を向けるやり方だ。理論的には教室の役割が「変化」し、基礎的な知識が画面を通じて自宅に提供される一方、授業はその知識を定着させ、磨き上げ、テストする場になる。(今の宿題と同じ方法だが、より効果的だ。)政治家や教師がそれを受け入れさえすれば、多くの子供達へ、より低コストでより良質な教育が約束される。
なぜ今回の革命はこれまでと違うのか? その理由の大半は、いくつもの大きな変化が同時に起こっていることによる。それはつまり、高速モバイルネットワーク、安価なタブレット端末、低コストで大量のデータを処理する能力、洗練されたオンラインゲームと適応学習ソフトといったものを指す。例えば、継続的なパフォーマンス評価機能を持った新しいインタラクティブなデジタル教科書は、それを使用する生徒が何をどのように学習しているかに応じて、リアルタイムな変化が可能だ。(生徒自身がテストされていることに気づかないことだってあるだろう。)新しいデータ·マイニング·ソフトウェアは、特別な注意がない場合に、いつ生徒が読解や数学でミスするかを予測でき、手遅れになる前に、教師が介入することができる。
Yes we Khan
高等教育の方が、一歩進んでいる。立ち上げからようやく1年経ったばかりの「大規模なオンライン公開授業」を提供する草分けのひとつ、コーセラ(Coursera)は、現在、全世界で390万人以上の生徒数を誇り、83のパートナー機関によって提供される授業を使っている。大学は、テクノロジーを試すのに熱心だ。イギリスのテレビ講義形式のオープン・ユニバーシティ(Open University)は、現在、創業44年になる。しかし今回は、初等、中等教育がその後を追う。サルマン・カーン氏が、数学のビデオを作ることに集中するためにヘッジファンドの仕事を辞めてから4年後の現在、カーン・アカデミー(Khan Academy)には600万人の登録ユーザーがおり、彼らは毎日300万の問題を解答(または解答しようと)しており、そのカリキュラムは数学意外にも大きく拡大している。それはまた、アメリカの国境をも超えて広がっている。世界で最も裕福な男性のひとり、カルロス·スリム氏は、彼の母国メキシコの小学生のために開発されているカーン・アカデミーのカリキュラムのひとつに出資していると言われている。
教育工学は、これまで、他にも印象的な支持者を集めてきた。ビル·ゲイツ氏は、これを、教育における「歴史的瞬間」と呼んだ。民間資金も集まってきている。良い面だけを誇張する単なるハイテク好きとは違う、ルパート・マードック氏は、彼のデジタル教育事業、アンプリファイ(Amplify)に、今年、約18億ドルもの損失を許している。これは、アメリカだけでもすぐに440億ドルの価値になるだろうとニューズ・コーポレーションが試算している教育工学市場の覇権を握ることを期待してのことだ。ドバイを本拠地とする教育機関、ジェムズ(GEMS)は、遠隔地の子どもたちに手を差し伸ばすために、インドやガーナでテクノロジーの利用を拡大したいと考えている。
先行きが見通せない問題もある。多くの親はすでに、「ゆとり世代」を、ゲームをしてばかりいて、いつもコンピュータに向かって、文法のおかしな文章を書き込んでいると非難している。教師たちは教育工学のサービスを利用するかもしれないが、教師の労働組合は、学校がより少ない教師でやっていけることを示唆するものは何でも訝しく思うふしがあり、教育で金を儲けようとするマードック氏のニューズ・コーポレーションのような民間企業を嫌うものだ。プライバシーの心配もある。教育工学を扱う企業は、生徒の個人データの巨大な保管所となってしまう。
うまくいってはいるようだ
これらの懸念のほとんどは行き過ぎたものだ。営利企業は、長きに渡って、印刷された教科書を販売するビジネスをしてきているし、データ·プライバシー法の適用範囲を学生にまで拡大できない理由はない。しかし、大きな疑問は残る。子どもたちは果たして、より多くを学ぶことになるのだろうか? 今度は、それは、教師にかかっている。最高のテクノロジーでさえ、教師のサポートなくしてはどこにも到達しえないからだ。
教育工学の有効性は、主にアメリカで証明されている。ほとんどの場合において、教師がしっかり訓練されているとき、それは機能するようだ。教育工学を取り入れているカリフォルニア州サンノゼにあるチャーター・スクールのネットワーク、ロケットシップ(Rocketship)の低所得層の学生は、その州の最も裕福な地域に住んでいる学生の能力を上回っている。様々な試行プログラムで良い成果を出した、カーン・アカデミーの適応性のあるソフトウェア·プラットフォームは、現在、アメリカの最も裕福かつ最高の学力を誇る学区のひとつ、ロスアルトスで利用されている。
資金不足の公立校が、貧しい学生が学業に追いつくのを手助けするテクノロジーを導入するため資金繰りに苦しむ一方、豊な学校、特に私立校は、教育工学を最も熱心に取り込むので、短期的には格差が助長されることになるだろう。政府は、彼らが導入できるように投資する必要がある。いくらかの投資がされてはいる。韓国では、高速インターネットアクセスは学校では標準となっている。バラク·オバマは最近、アメリカがそれに続くことを約束した。法律は、生徒が、年齢に応じてグループ分けされるのではなく、同程度の学力の生徒と一緒に勉強できるように、改正される必要がある。しかし、多くの政治家にとって、強い力を持った教員組合との対決が、大きな試練となるだろう。
子を持つ親や納税者がそういった政治家を支えなくてはならない。教育は、テクノロジーが他の仕事にもたらした生産性の向上に、頑なまでに抗ってきた。しかし、この教育工学の波は、それを変えることを期待させる。テクノロジーは、おそらく一世紀以上の間、もう少しで教育を変革させるぎりぎりのところにあり続けてきた。今回こそは、それが実現しそうに見える。
| 2014/01/05
| The Economist, Translation
|
The Economist の記事を訳出しました。
Electricity in Japan: Power struggle
原文はこちらから読めます。
日本の電力
電力/権力闘争
福島 –チェルノブイリ以降、世界最悪の原子力災害– が、日本のエネルギーの未来に影を落とす
2013年9月21日
今週、日本で稼働する最後の原子炉が停止された。本州西岸に位置する大飯では、閉鎖は定期的なメンテナンスと安全確認のためのものだった。しかし、福島第一原発での3つのメルトダウンをきっかけに閉鎖された、大飯原発をはじめとする日本の50基の原子炉の再稼働予定日は、はっきりとは決まっていない。2011年3月の地震と津波が日本全土をひっくり返す前は、日本は、その電力の30%(世界でもっとも高い割合のひとつ)を原子力に依存していた。今では、1970年以降2度目の、完全に原子力なしの状態となっている。

昨年12月以来、官邸では、自民党が、閉鎖された原発の経済的コストについて発表している。経済産業省は、2013年末までに、非原子力の発電所を稼働させるために、余分な石油、ガス、石炭を輸入する必要があり、9兆2,000億円、余分に費用がかかることになると言う。急激な円安や原油高も向かい風となり、日本は現在、30年ぶりに貿易赤字となっている。日本の企業や消費者は、多くの国に比べてはるかに高い電力コストに直面している。
「原子力村」として日本で知られている、電力会社、官僚、学者、重工業のなれ合いのコミュニティが、原子炉を再稼働するように自民党をせき立てている。安倍晋三首相は、喜んで期待に応えようとするだろう。今年の初め、彼の政府は反原発のエネルギー政策委員会を追放した。福島の災害をきっかけに行われるようになった、原子力発電に反対する東京の街頭デモは減少していった。道は、原子炉を再稼働するために開かれているように見えた。
しかし、物事はそう簡単には運ばない。新しい、強化された原子力機関、原子力規制委員会は、原発を再稼働する前に、それが安全であると宣言しなくてはならないが、原発のいくつかは、活断層(世界の大地震の5分の1は日本で起きている)の上、または近くに位置している。また、法令により、近隣にある原発について町や村は意見を述べる機会が与えられているが、それによれば、ほとんどの日本人が恒久的な脱原発を望んでいる。挙げ句の果てに、被災地、福島での原発の混乱についてのニュースには改善の兆しが見られない。最近では、何百トンもの放射性の水が、太平洋に毎日流出していたことが発覚した。
だからこそ、安倍氏は慎重にことを進める必要がある。もしも原子力規制委員会が、日本でもっとも古く、もっともリスクの高い原発を再稼働しないと決めた場合、自民党はそれについて手出しできない。原子力規制委員会は、人員不足の上、政治的圧力の下にあるが、迅速に新たな安全規則を公布することを含め、活断層の上にある原子炉について基準を作っている。
また、首相は、簡単に大衆の反対を押さえ込むこともできないだろう。原子力発電所を抱えている地方の町は問題ではない。過去には、気前良く売り払ってもらえそうな、孤立し、経済的に恵まれない地域に発電所を設置するために、政府と電力会社は共謀していた。これらの町のいくつかは、原子炉を再稼働するように強く求めている。しかし、少し離れた場所では、反対意見が強くなる。本州北西岸に位置する新潟県の知事、泉田裕彦氏は、県民の約70%が、世界最大の原子力発電所、柏崎刈羽で原子炉を再稼働することに反対しているという。泉田氏は、 原子力規制委員会がゴーサインを出してしまえば、知事には再稼働を止める力がないと言う。しかし、影響力があり人気もある地方の政治家には、政府や電力会社の空威張りは通用しないだろう。
また、自民党は、2011年3月以前と比較して、原子力発電に批判的な多くの政治家を内包しており、経済大臣、甘利明氏のような原子力推進派の影響力に対抗している。彼らは、原子炉を再稼働すると、2016年に予定されている次の総選挙にマイナスになる可能性があると考えている。自民党の反原子力の連立パートナー、公明党もまた、いくらか政府を抑制している。一方、ビジネスが上向いていくという楽観主義が、景気回復は原子力発電に依存しているという問題の影を薄くしているように見える。原子炉が再稼働されるとしても、おそらく12〜15基がせいぜいだろうと、政府のエネルギー諮問委員会のメンバーでもある再生可能エネルギー専門家、植田和弘氏は言う。かつて日本の電力の少なくとも半分を供給することを期待していた原子力村にとって、それは大きな失望だろう。
その代わり、日本は、長期的な代替エネルギー供給のために準備を進めている。2011年以降、再生可能エネルギーのために新たに設けられた全量固定価格買取制度のおかげもあり、太陽光発電のような再生可能エネルギーを開発する独立系発電事業者の数は、3倍に増えた。水力発電を含む再生可能エネルギーは、いまや日本のエネルギーミックスの10%に及び、いつの日か、原子力発電がかつて誇ったシェアに置き換わるかもしれないという希望に導いている。
しかし、疑念は残る。電力網は、依然として大きな電力会社によって所有されており、彼らは、それをシェアしないための言い訳をいくらでも見つけてくる。それに、狭くて山の多い国で、必要なすべてのソーラーパネルや風力タービンをどこに設置しろと言うのか。東京大学のポール・スカリス氏は、風力発電に使われる土地、1平方メートルは、たった2ワットの電力しか生成しないと言う。太陽光発電の場合は、同等の面積で、20ワットが生成される。原子力発電は、1平方メートルで、約1,000ワット生成する。
したがって、これからの長い年月を、日本は、原子力の不足の大部分を補うために、石油、ガス、石炭でしのぐことになる。5月に、政府は、安価なシェールガスを輸入するための認可をアメリカから勝ち取った。それは、エネルギー輸入のコストを手軽に削減し、エネルギー安全保障についての懸念を軽減することができる。
福島の混乱の後、広範な地域に及ぶ停電が予測されなかったのは、ひとつには、化石燃料の発電所が出力を上げたことによる。2011年3月以前には、発電所の多くが最大出力以下で順調に稼働していた。しかし、もうひとつの理由は、省エネルギーの余地があったことだ。日本の自然エネルギー財団によると、東京だけでも、2011年以降、電力消費を10分の1削減した。こういった背景の下、省電力機器の需要が急増してきている。発光ダイオード(LED)が日本で販売されたすべての電球の売上に占める割合は、2009年の3%から、今日では、30%を超え、急上昇している。フィリップス エレクトロニクス ジャパン代表取締役、ダニー・リスバーグ氏は、2015年までに、白熱灯や蛍光灯の割合は以前のほぼ3分の1になるだろうと言う。
電力市場の自由化という積年の懸案は、エネルギー源の多様化と電気代の引き下げに大きく寄与するだろう。政府の計画(それは、福島での失態の取り繕いにより、最大の公益事業体、東京電力の地位が低くなったことで、通しやすくなった)は、発電と送電を分離し、住宅電力市場を新たな競争に開くことだ。改革が成功し、新しい非原子力プロバイダが顧客を獲得した時、日本のエネルギーミックスにおける原子力発電のシェアが下がることになるだろうと、東京にある富士通総研の高橋洋氏は言う。そのことは、ようやく、日本国民に、日本のエネルギーの選択について、いくらかの発言権をもたらすことになるだろう。
| 2013/09/22
| The Economist, Translation
|
The Economist の記事を訳出しました。
Japan and the 2020 Olympics: Party like it’s ’64
原文はこちらから読めます。
記事のタイトルは ‘Party like it’s ’64’。
これは、プリンスのヒット曲 ‘1999’ の歌詞 ‘So tonight I’m gonna party like it’s 1999’ のもじり。
世界が滅びると言われていた1999年にいるかのように、俺は明日のことなんか考えないでパーティーを楽しむぜ、という意味。
お先真っ暗な経済状況の下、後先のことを考えずに、オリンピックで盛り上がろうとしている日本を暗に揶揄した秀逸なタイトルです。
日本と2020年オリンピック
1964年の頃のようにパーティーしよう
東京が思いもかけない魔力を見せる
2013年9月14日
2016年のオリンピック招致が盛り上がらなかったのは当然だった。長期にわたる経済不安と財政赤字の拡大を経て、世界最大都市、東京の住民は、世界で最も金のかかるスポーツの見せ物に乗り気になれなかった。今回は、そのような問題はなかった。保守的な管理者会では、涙とハグは伝染しやすい。
2020年のオリンピック主催権利獲得のためにマドリッドとイスタンブールを打ち負かしていく過程で、東京都は、招致が都民の70%に支持されていることと、2011年3月に東北の沿岸地域を襲い、福島第一原発での原子力危機を引き起こした地震と津波以来、地域のサポートが大きく増加したことを、国際オリンピック委員会(IOC)に印象づけた。
東京のパッションに再び火を灯すのに災害を必要としたことは、奇妙なことに思えるかもしれない。しかし、東京都政は執拗にオリンピックが日本の復興の助けになるという考えを売り込んだ。終盤では、東京から230キロメートル離れた福島で変わらず続く一連の問題が、東京のオリンピック主催者たちを守勢に追い込み、最終的に、内閣総理大臣、安倍晋三が、放射能漏れは防ぐから選手たちは安全であるとIOCを安心させるために、470億円をかき集めることになった。
東京都は、1964年のオリンピックの中心施設だった国際オリンピックスタジアムを改修する一方、計画される37施設のうち、22の施設をゼロから建設しようとしている。日本政府はこれらすべてに4090億円かかり、それを3兆円のオリンピック需要で相殺できると見積もっている。しかし、巨大地震が2020年までに東京を襲うかも知れないことを考慮に入れなかったとしても(専門家たちはその可能性は高いと予測している)、その試算は荒っぽいほど楽観的に見える。
建設会社や不動産会社は、まだ気にしなくていい。1964年のオリンピックが、東京・大阪間の新幹線や首都圏の高速道路を含む、重要なインフラ整備の引き金となったのはよく知られるところだ。それより不吉なのは、累積していく財政赤字を補うために国債を発行しなくてはならない状況に日本が陥っていることだ。日本政府の負債の総額は、いまやGDPの200%を上回っているのだ。
これからの7年間に、コストの問題が大きく浮上してくるだろう。いまのうちは、総理大臣は、光輝く日本の首都を再び世界の表舞台に乗せたと胸を張って言うことができる。そして、東京という選択は、彼の成長戦略にとってカンフル剤として必要なのだろう。しかし、7年間に7回総理大臣が変わる国で、オリンピックにかかる費用が困難に直面している日本経済の最後の頼みの綱であったと判明する2020年に、非難を受けるべき安倍氏が総理大臣であることはありそうにもない。
| 2013/09/16
| The Economist, Translation
|