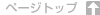大学教授の専門化
今週のThe Economistから書評を訳出しました。
原文はこちらから読めます。
The Economist Feb 25th 2010
University education in America
Professionalising the professor
アメリカの大学教育
大学教授の専門化
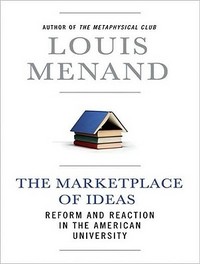
The Marketplace of Ideas: Reform and Resistance in the American University.
By Louis Menand.
この巧妙で知的な小品は、博士号を取得することを考えているすべての学生に読まれるべきである。そうすれば彼らは、他の道に進もうと決心するだろう。アメリカの大学で奇妙な事態が出来しているため、ハーバード大学の英文学教授ルイス・メナンドは、それをすばやく本にまとめた。
彼の関心は主に人文学-文学、語学、哲学など-にある。これらは、時代遅れになりつつある学問である。というのも、今や、アメリカの大学卒業者の22パーセントがビジネスを専攻しているのに対して、たった2パーセントが歴史学を、4パーセントが英文学を専攻しているに過ぎないからだ。しかし、アメリカの一流大学の多くは、学部生に、すべての教養人が持っていなくてはならない必要不可欠な考え方にまつわる規範から、基礎を習得して欲しいと望んでいる。しかし、そのほとんどの大学が、「普通教育」というものがどのようなものであるべきか、合意を得るのは難しいと気づいている。ハーバードでは、「偉大な本は読まれる。何故なら、それらは読まれているからである」と、メナン氏は記す。つまり、それらの書物は、社交上の接着剤のようなものとなっているのである。
そのような学科を構想し、教えることが難しい理由は、ひとつには、人文学教育と専門職教育は切り離され、別々の学校で教えられねばならないというアメリカのトップの大学による主張に、そのような学科は真っ向から対立するからである。しかし実際は、多くの学生は、両方を学ぶ。ハーバードの大学生の半分以上が、法学、薬学、あるいはビジネスに行き着くが、将来の医者や法律家は、専門家としての資格取得に乗り出す前に、専門外の人文学の課程を学ばなければならないのだ。
このように分離によってその専門課程を専門化することの他に、アメリカのトップの大学は、教授職をも専門化した。学問的研究への公費の増大はその進展を早めることになった。連邦政府の研究助成金は、1960年から1990にかけて4倍に増大した。しかし、研究の代償として、学部で教える時間は半分に減少した。専門化主義は、博士号の取得を、学問の世界での立身出世の必須条件にした。1969年に至っても、アメリカの大学教授の3分の1は、博士号を持っていなかったというのに。しかし、メナン氏の主張によれば、専門化主義の背後には、「ある種の専門化に必要な知識と技術は、伝達はできるが、譲渡することは出来ない」という、鍵となる考え方があるという。そのため学問は、知の生産だけではなく、知の生産者の生産をも牛耳っているのだ。
人文学ほど熱心に専門化主義に固執してきた学問はない。メナン氏が指摘するように、法律家には3年でなれるし、医者には4年でなれる。しかし、平均的に見て(平均!)、人文学の博士号を取得するのには9年かかる。(アメリカの学生への宣伝。あなたはイギリスのトップの大学で、4年未満で完全無欠の博士号を取得することができます。)英文学専攻の博士課程の学生の半分までもが、学位を取得する前にドロップアウトするのは、驚くに値しない。
同様に、学生のたったの半分しか、それを得るために大学院に入学した職、つまり終身在職権を与えられた教授職にありつけないという事実も、驚くには値しない。単純に、ポストがあまりに少なすぎるのだ。この原因の幾分かは、大学が博士号を、かつてないほど量産し続けていることにある。しかし、人文学系の科目を学ぼうとする学生は少なくなってきている。1970年から71年にかけて、英文科は、その20年後よりも多く学士号を授与していた。学生が減れば、教員も減る。だから、論文執筆の十年間の最後で、多くの人文学系の学生はその専門課程を去り、それまで訓練を受けて来なかったことをする羽目になるのだ。
高等教育を改革する鍵は、「知の生産者が生産される」方法を変えることにあると、メナン氏は結論づける。さもなければ大学人は皆、危険なまでに似通った思考を続け、彼らが研究、調査、批評する社会からますますかけ離れてしまう。「学問的探求は、少なくともいくつかの分野では、排他的な方向ではなく、より全体的な方向に向かう必要があるだろう。」しかし、一体どうしたらそれが実現できるのか、メナン氏は述べていない。実際には、お風呂のお湯と一緒に赤ん坊も流してしまうことにもなりかねない。つまり、学問的内向性に向けられた大衆のいらだちが、自由社会においてもっとも貴重な学問の権利である独立を、いくらか失わせることにだってなりかねないのだ。